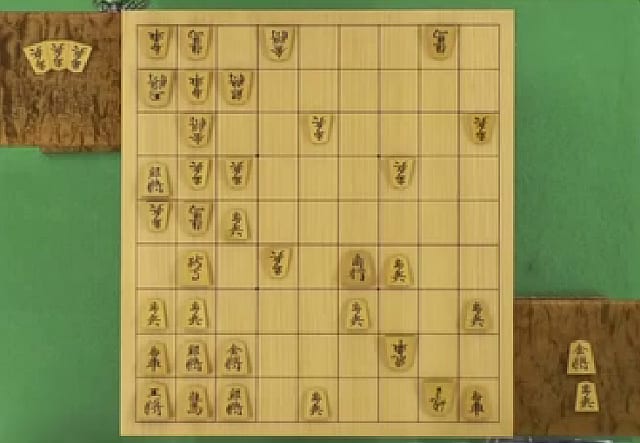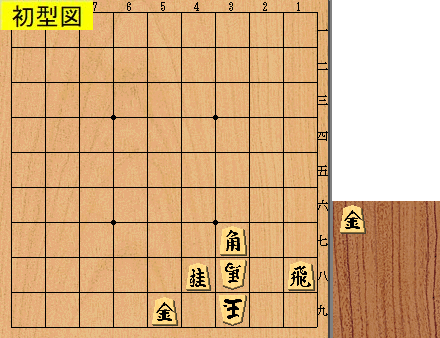横浜市鶴見区のサルビアホールで開催されていた『山内若菜予感展』を拝見。
『神々の草原』は3m×9mと大作。太古の人間が洞窟の壁に描いたような雰囲気が漂うが、あるいはシャガールの作品に度々登場する空想の動物群のような存在なのだろうか。
『賛歌 樹木』も同サイズ。広島の被爆地で生き残った樹木の中を象のような動物や幽霊たちが彷徨っている。

生きる者への讃歌なのだろうか、いや、生き残った者への讃歌というべきかな。
会場ですぐに感じたのは、数十年前に観た香川泰男展(練馬か埼玉か)。前の大戦でシベリアに抑留された経験を基に多くの作品を残されている。孫娘ではないかと思うほど同じような引力を感じた。
実は、彼女(山内氏)のプロフィールを読んでさらに驚いたのは、2009年から「シベリア抑留を忘れない文化交流」を始め、ハバロフスクの極東美術館で展覧会を開催されている。
今のロシアには、内心はまったくがっかりされていると想像。
2021年には東山魁夷日経日本画大賞入賞されているのだが、なぜ日本画と呼ばれるかといえば和紙におそらく日本画用の絵具で着色しているからだろう。
多くの方が思っているだろうが大きな公募型の展覧会(県展とか市展とか)は洋画の部屋と日本画の部屋と分かれているのだが、あまり意味はないと思うがたぶん審査員がなんらかの都合により分かれているのだろう。