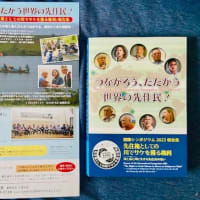社団法人北海道アイヌ協会主催の第28回「北海道大学アイヌ納骨堂におけるイチャルパ」が下記要領で開催されます。
【日時】8月5日(金)11:00~13:30
【会場】北大構内、アイヌ人骨納骨堂前
地図は、「さまよえる遺骨たち」blogにあります。http://hokudai-monjyo.cocolog-nifty.com/blog/
遺骨が正しくアイヌ民族に返還されることを祈りつつ参列したいと思います。
アイヌ文化振興・研究推進機構主催「アイヌ文化普及啓発セミナー」は都合が重なり、木村多栄子さん(イオル再生事業伝承者育成事業1期生)「私のなかのアイヌ文化」のみ受講となりました。ご自身のライフ・ストーリーと、アイヌとして生き文化伝承を継承して行きたいとの熱い思いを伺うことが出来ました。現在、旭川に住みながらご自分のフチから聞いたこと、白老で学んだこと、旭川アイヌの伝承の違いに興味を持たれて学びを続けておられるそうです。お若い方ですが、差別された体験もお話されました。
少し前になりますが、今年の3月6日に法政大学を会場に公開シンポジウム「今、アイヌであること―共に生きるための政策をめざして」が開催されたようです。案内チラシの「開催趣旨」には以下が記載されていました。
国会で採択された「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」(2008) 以来、アイヌ政策への取組が進められておりますが、この背景には「先住民族の権利に関する国際連合宣言」(2007) があります。現在、アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会による報告(2009) を受けて、アイヌが先住民族であるという認識に基づく政策展開や、民族共生の象徴となる空間の整備が計画されています。これらの政策が実現するためには、多様な文化と民族の共生が尊重されなければなりません。共に生きるための政策とは何か、どのようにすれば実現するのか、このシンポジウムはこれらの問題を考えます。多数のご来場を期待しております。
http://race.zinbun.kyoto-u.ac.jp/event_report/20110306.html
アイヌ政策推進会議のメンバーの多数が来られて話をされたようですが、そのメンバーのひとりでもある篠田謙一(国立科学博物館人類研究部人類史研究グループ長)さんの講演「要旨」には以下が書かれています。
明治期に始まる日本の人類学研究の中で、アイヌ民族の系統と由来は常に重要な研究課題として注目されてきた。その研究の基礎となる人骨の収集も明治から昭和にかけて継続的に行われ、現在では全国の大学研究機関に1500体以上のアイヌ人骨が収集されている。自然人類学は、古代人が残した人体そのものを扱うので、集団の成立や変遷に対して直接的な情報を提供する。アイヌ民族の成立の経緯、あるいは本土日本人を始めとする周辺集団との関係などは、人骨の研究なしには明らかにされることはなかった。本発表では、こうした研究の成果を紹介し、更にDNA分析など最新の自然人類学研究の動向について説明する。
一方、これらの研究に用いられてきた人骨の中にはアイヌの人たちの意向を無視して収集されたものも含まれている。自然人類学の研究者は、人骨を用いてして研究している以上、過去の行為に対する責任を負っており、信頼の回復のために努力をする責務がある。「民族共生の象徴となる空間」の議論が進む中で、人類学研究者としてこの問題をどのように解決すべきなのかということについて、現在の日本人類学会の取り組みを紹介する。
遺骨収集がアイヌ民族の「意向を無視して収集されたものも含まれている」という発言は以前にも目にしたことがありますが、全国の大学研究機関に1500体以上も「収集」されている遺骨がどこでどのようにして「収集」されたかの徹底的な調査、謝罪、返還への努力が全く見られない中で、どんな話をされたのでしょうか。
北大開示文書研究会の6月の「さまよえる遺骨たち」シンポの最中にフロアーからアイヌ民族のIさんが、上記のシンポジウムで、大きなスクリーンにアイヌの人骨の写真を映し出し、このアイヌは病気だった、そのせいで脊椎が固まってしまったんだと解説される場面があったと話されました。その後に電話で再確認をすると、「アイヌ人骨を実験材料のように扱って、脊椎の病気だ、梅毒だと言うものだから、思わず「この泥棒、ちゃんとアイヌのコタンにそれを返せ」と言った」と。
また、「今、アイヌであること」と題して、原田公久枝さんと丸子美記子さんが差別のことなどを話されたと言いますから、どんな流れになったのか、後日に参加者からお話を伺おうと思います。
朝日新聞に過日に案内した「総合的なアイヌ民族政策はどうなるのか」シンポの様子が報道されました。アイヌ政策推進会議の要になるお二人が参加し、関東で活躍しているアイヌ民族の方や市民外交センターの上村さんなどが議論すると聞いて、近ければ是非とも参加したかったですが、どうも総勢50人ほどの小規模なものとなったようで、とても残念です。
以下、記事を引用します。
道外のアイヌ民族政策 都内でシンポ(朝日新聞 2011年08月01日)
■「生活・教育支援進めて」
■「停滞」不満の声
「総合的なアイヌ民族政策はどうなるのか」と題するシンポジウムが31日、東京都内であった。アイヌ民族の政策を具体的に検討する政府の「アイヌ政策推進会議」が6月に作業部会報告をまとめたことを受けて開かれたが、道外に住むアイヌ民族の政策が進んでいないことへの不満を打ち明ける人もいた。
◇
主催したのは、「先住民族の10年市民連絡会」(事務局・東京都)などの市民団体。浦河町出身で、首都圏のアイヌ民族の団体や個人でつくるアイヌウタリ連絡会代表の宇梶静江さんをはじめ、道外のアイヌ民族や先住民族の専門家ら約50人が参加した。
推進会議は「民族共生の象徴空間を整備するための作業部会」と「道外アイヌの実態調査をするための作業部会」で議論し、6月に検討状況が報告された。
これを受けたシンポでは、宇梶さんが道外のアイヌ民族を代表する形で発言。作業部会の名称を挙げ、「『民族共生』と文字にすれば立派だが、具体的に(道外の)私たちが納得することが(推進会議や政府から)伝わってこない。むなしい」と述べ、生活や教育の支援策を進めるように求めた。
路上生活者を支援する千葉県在住の女性は、首都圏で生活保護を受けて暮らすアイヌ民族の男性から「俺のような人間が子孫を残してはいけない」と聞いたことを紹介。「このような人の生活実態も調査してほしい」と話した。
生活実態調査の作業部会の報告では、今後の政策について「全国的な見地からの生活・教育面での支援策、特に安定した就労支援、高等教育機関への進学支援、文化伝承への支援の検討が望まれる」と指摘した。この点について、市民外交センター代表で恵泉女学園大教授の上村英明さんは「政策のはっきりとした方向性をなぜ明示しないのか」と述べ、推進会議の議論の進め方を疑問視した。
一方、作業部会長からもアイヌ民族と政府への注文が出された。象徴空間作業部会長で北大アイヌ・先住民研究センター教授の佐々木利和さんは「道外にアイヌ民族の統一された組織をつくってほしい。そうすれば発言力も増す」と指摘した。
生活実態作業部会長で同センター長で教授の常本照樹さんは「アイヌ民族やその文化を知らない国民はまだまだ多い。これを知ってもらうことで、権利に基づく(アイヌ民族の)政策が実行されていくのではないか」と述べ、国が啓発をさらに進めるべきだとの考えを強調した。(神元敦司)
朝日新聞URL http://mytown.asahi.com/hokkaido/news.php?k_id=01000001108010003
アイヌ民族関連ニュースURL http://blog.goo.ne.jp/ivelove/e/2b3f0bfe7f381c3724a22795aa8ab556
国が率先して政策推進をするというのではなく、いまだに多数派に知ってもらわないと政策がすすまないと言っていることは問題だと思います。
また、道外に統一されたアイヌ民族組織を作れば発言力も増す(すなわち政策に反映しやすい)と言っているようでありながら、「統一できていないことが問題」「だから聞けない」と開き直っているようにしかわたしには聞こえないのです。

【日時】8月5日(金)11:00~13:30
【会場】北大構内、アイヌ人骨納骨堂前
地図は、「さまよえる遺骨たち」blogにあります。http://hokudai-monjyo.cocolog-nifty.com/blog/
遺骨が正しくアイヌ民族に返還されることを祈りつつ参列したいと思います。
アイヌ文化振興・研究推進機構主催「アイヌ文化普及啓発セミナー」は都合が重なり、木村多栄子さん(イオル再生事業伝承者育成事業1期生)「私のなかのアイヌ文化」のみ受講となりました。ご自身のライフ・ストーリーと、アイヌとして生き文化伝承を継承して行きたいとの熱い思いを伺うことが出来ました。現在、旭川に住みながらご自分のフチから聞いたこと、白老で学んだこと、旭川アイヌの伝承の違いに興味を持たれて学びを続けておられるそうです。お若い方ですが、差別された体験もお話されました。
少し前になりますが、今年の3月6日に法政大学を会場に公開シンポジウム「今、アイヌであること―共に生きるための政策をめざして」が開催されたようです。案内チラシの「開催趣旨」には以下が記載されていました。
国会で採択された「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」(2008) 以来、アイヌ政策への取組が進められておりますが、この背景には「先住民族の権利に関する国際連合宣言」(2007) があります。現在、アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会による報告(2009) を受けて、アイヌが先住民族であるという認識に基づく政策展開や、民族共生の象徴となる空間の整備が計画されています。これらの政策が実現するためには、多様な文化と民族の共生が尊重されなければなりません。共に生きるための政策とは何か、どのようにすれば実現するのか、このシンポジウムはこれらの問題を考えます。多数のご来場を期待しております。
http://race.zinbun.kyoto-u.ac.jp/event_report/20110306.html
アイヌ政策推進会議のメンバーの多数が来られて話をされたようですが、そのメンバーのひとりでもある篠田謙一(国立科学博物館人類研究部人類史研究グループ長)さんの講演「要旨」には以下が書かれています。
明治期に始まる日本の人類学研究の中で、アイヌ民族の系統と由来は常に重要な研究課題として注目されてきた。その研究の基礎となる人骨の収集も明治から昭和にかけて継続的に行われ、現在では全国の大学研究機関に1500体以上のアイヌ人骨が収集されている。自然人類学は、古代人が残した人体そのものを扱うので、集団の成立や変遷に対して直接的な情報を提供する。アイヌ民族の成立の経緯、あるいは本土日本人を始めとする周辺集団との関係などは、人骨の研究なしには明らかにされることはなかった。本発表では、こうした研究の成果を紹介し、更にDNA分析など最新の自然人類学研究の動向について説明する。
一方、これらの研究に用いられてきた人骨の中にはアイヌの人たちの意向を無視して収集されたものも含まれている。自然人類学の研究者は、人骨を用いてして研究している以上、過去の行為に対する責任を負っており、信頼の回復のために努力をする責務がある。「民族共生の象徴となる空間」の議論が進む中で、人類学研究者としてこの問題をどのように解決すべきなのかということについて、現在の日本人類学会の取り組みを紹介する。
遺骨収集がアイヌ民族の「意向を無視して収集されたものも含まれている」という発言は以前にも目にしたことがありますが、全国の大学研究機関に1500体以上も「収集」されている遺骨がどこでどのようにして「収集」されたかの徹底的な調査、謝罪、返還への努力が全く見られない中で、どんな話をされたのでしょうか。
北大開示文書研究会の6月の「さまよえる遺骨たち」シンポの最中にフロアーからアイヌ民族のIさんが、上記のシンポジウムで、大きなスクリーンにアイヌの人骨の写真を映し出し、このアイヌは病気だった、そのせいで脊椎が固まってしまったんだと解説される場面があったと話されました。その後に電話で再確認をすると、「アイヌ人骨を実験材料のように扱って、脊椎の病気だ、梅毒だと言うものだから、思わず「この泥棒、ちゃんとアイヌのコタンにそれを返せ」と言った」と。
また、「今、アイヌであること」と題して、原田公久枝さんと丸子美記子さんが差別のことなどを話されたと言いますから、どんな流れになったのか、後日に参加者からお話を伺おうと思います。
朝日新聞に過日に案内した「総合的なアイヌ民族政策はどうなるのか」シンポの様子が報道されました。アイヌ政策推進会議の要になるお二人が参加し、関東で活躍しているアイヌ民族の方や市民外交センターの上村さんなどが議論すると聞いて、近ければ是非とも参加したかったですが、どうも総勢50人ほどの小規模なものとなったようで、とても残念です。
以下、記事を引用します。
道外のアイヌ民族政策 都内でシンポ(朝日新聞 2011年08月01日)
■「生活・教育支援進めて」
■「停滞」不満の声
「総合的なアイヌ民族政策はどうなるのか」と題するシンポジウムが31日、東京都内であった。アイヌ民族の政策を具体的に検討する政府の「アイヌ政策推進会議」が6月に作業部会報告をまとめたことを受けて開かれたが、道外に住むアイヌ民族の政策が進んでいないことへの不満を打ち明ける人もいた。
◇
主催したのは、「先住民族の10年市民連絡会」(事務局・東京都)などの市民団体。浦河町出身で、首都圏のアイヌ民族の団体や個人でつくるアイヌウタリ連絡会代表の宇梶静江さんをはじめ、道外のアイヌ民族や先住民族の専門家ら約50人が参加した。
推進会議は「民族共生の象徴空間を整備するための作業部会」と「道外アイヌの実態調査をするための作業部会」で議論し、6月に検討状況が報告された。
これを受けたシンポでは、宇梶さんが道外のアイヌ民族を代表する形で発言。作業部会の名称を挙げ、「『民族共生』と文字にすれば立派だが、具体的に(道外の)私たちが納得することが(推進会議や政府から)伝わってこない。むなしい」と述べ、生活や教育の支援策を進めるように求めた。
路上生活者を支援する千葉県在住の女性は、首都圏で生活保護を受けて暮らすアイヌ民族の男性から「俺のような人間が子孫を残してはいけない」と聞いたことを紹介。「このような人の生活実態も調査してほしい」と話した。
生活実態調査の作業部会の報告では、今後の政策について「全国的な見地からの生活・教育面での支援策、特に安定した就労支援、高等教育機関への進学支援、文化伝承への支援の検討が望まれる」と指摘した。この点について、市民外交センター代表で恵泉女学園大教授の上村英明さんは「政策のはっきりとした方向性をなぜ明示しないのか」と述べ、推進会議の議論の進め方を疑問視した。
一方、作業部会長からもアイヌ民族と政府への注文が出された。象徴空間作業部会長で北大アイヌ・先住民研究センター教授の佐々木利和さんは「道外にアイヌ民族の統一された組織をつくってほしい。そうすれば発言力も増す」と指摘した。
生活実態作業部会長で同センター長で教授の常本照樹さんは「アイヌ民族やその文化を知らない国民はまだまだ多い。これを知ってもらうことで、権利に基づく(アイヌ民族の)政策が実行されていくのではないか」と述べ、国が啓発をさらに進めるべきだとの考えを強調した。(神元敦司)
朝日新聞URL http://mytown.asahi.com/hokkaido/news.php?k_id=01000001108010003
アイヌ民族関連ニュースURL http://blog.goo.ne.jp/ivelove/e/2b3f0bfe7f381c3724a22795aa8ab556
国が率先して政策推進をするというのではなく、いまだに多数派に知ってもらわないと政策がすすまないと言っていることは問題だと思います。
また、道外に統一されたアイヌ民族組織を作れば発言力も増す(すなわち政策に反映しやすい)と言っているようでありながら、「統一できていないことが問題」「だから聞けない」と開き直っているようにしかわたしには聞こえないのです。