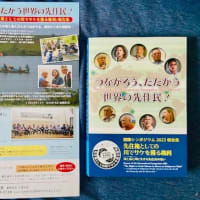質疑で問題となったことをいくつかまとめて挙げます。
アイヌの承諾を得ないで収集した(盗んだ)遺骨について質問が集中。計画中の「民族共生の象徴空間」には“慰霊施設”と“研究施設”の設置が挙げられていますが、そこに皆が疑問を持っているからです。
遺骨収集は、誰が、いつ、どこで、どういった手順を踏んで行ったかという調査がなされないと盗掘か否かわからないので、慰霊のしようも研究材料としての認可もできないと。今回の主催者であり司会の秋辺日出男さんが「研究を承諾するとしても、盗骨と言われているものを差し出す同胞はいないはず」と言われたのが印象的でした。
なお、会場にはアイヌ政策推進作業部会のメンバーである常本照樹さん(北海道大学アイヌ・先住民研究センター長)と
佐々木利和さん(北海道大学アイヌ・先住民研究センター教授)も来られ、質疑に答えられました。
問:遺骨収集の調査をしたのか
答:(篠田)「発掘当事者しか分からない。小金井など発掘者の日記などから倫理的な責任があるものが存在することは明らかだ(音声が聞こえにくかったので当日配布の資料で補足:わたし)。今はどこに何体入っているかは調査したが、それ以降は今後の調査だ。大学にも出せる情報は全部出してくれと言っているが、おそらく分からないだろうというのがかなりの部分あるだろう。それをどうするかが課題。それでも出なかった場合にどうしたらいいかは今後の課題だ。各大学で調査をして情報を出し、遺族に返還できるものを返還し、出来なかったものを集約して慰霊施設におさめることになるだろう。その時に盗骨の調査が深まるかというとそれは疑問だ、全体の流れからするとそれは落ちるのではないか」。
「どこに何体入っているかは調査した」も、よく分からない答弁ですが、その詳細を知りたい。また、「それ以降は今後の調査」だと、今の段階で言っているのが納得いきませんし、盗骨の調査は“落ちる(調べられない)のではないか”との答弁に、わたしばかりではなく、会場に怒りが爆発したと思います。
その後、盗骨されたというご遺族の数人が意見・質問をしました。遺骨の返還と賠償、そして副葬品の返還も北大にする、と。
篠田さんは講演の中で、「アメリカ・オーストラリア型の解決法」として、遺骨研究の禁止と埋め戻していることを紹介し、しかし、それは誤っていると指摘。研究の大切さを強調。そのことを盗堀問題の質問で言ってしまうことでマイナスに働いたように感じます。
だから、まずは返還して、その後に同意を得るという手順を踏んで研究するのがいいのではないかという質問が出ました。それに対して、「その通り。現状で出来る情報開示をきちんとして返還できるものは返還する」とあっさり応答。

問:個別返還時にどの地域からの発掘かは分かっても個人詳細まで分からない時、DNA鑑定で遺族を判明することは可能なのか?
答(篠田):両親、祖父母までなら高い確率で結果が出ると思う。
問:北大は遺骨を発掘した地域の人々と個別に相談をして返還できるものは変換するという手はずをとるべきだと思うがどう考えるか?北大はアイヌ協会としか話さず、個別の対応をしないと聞いている。
答(常本):報告書に書かれていることだが、各大学にお預かりしているものについては可能な限り、大学でお返し出来る方はお返しし、どうしてもお返しできなかったものは象徴空間に集約させて頂いて慰霊させていただく。
問:先日の説明会ではアイヌ協会の各支部を通して返還すると言っていたが、個別返還してくれるということですね。
答(常本):それは、今までの実績として北海道大学では5ヶ所の支部から返還請求があったのに対し、お返ししたことがあったということ。今後、どうするかに関してはこれからの課題。北大以外にも遺骨があるので、返し方もバラバラだと適当ではないので、やはり国を中心にどういう形で窓口を作り、お返しするのかを検討した上で考える。
あれよ? 「アイヌ協会以外とは話しません」と言っていたのに・・・。「返し方もバラバラだと適当でない」も説得力がない。
答(佐々木):皆さんはご存知だと思うけれど、アイヌの墓は誰が埋められているかが分からない。エカシがいれば分かる。今、大学にある人骨は誰のか分からないのがあるだろう。だから、大学で返せないものは、象徴空間に集めた後にじっくりと時間をかけて調べてお返しします (いま出来ません)。
問:今、どういう整理がなされて、どのような情報があるのか?
答(篠田):ケースによる。実は「発掘報告書」というのがあり、それがあればどこの穴からどれを掘ったかがわかる。しかし、昭和30年以降のはあるのもあるが、それ以前はほとんどないので場所の特定が出来ない。
問:北大はどこまで発掘の資料があるのか、どれだけ調べられているのか。
答(常本):北大にある資料に関しては情報公開している。その中に記されているように頭骨については一体一体どの地域のものか記されている。手足については頭骨ほど厳密に分類はされていなく頭骨と別に収められているが基本的にはどの地域かわかるように収められている。各大学で現状調査が文科省の責任で行われている。それとは別に、各大学で責任があるので調査をしている。
問:遺骨返還に関して具体的な方法は?
答(篠田):二つある。ひとつは遺骨から情報を得ること(DNAなど)。他は残された文献を調べること。ただし、文献が残っているものが少ない。遺族が返還を申し出た場合、調べなければならないが大学単位では無理がると私(篠田)は思うので象徴空間に入って調べることはありうると思う。過って返還した場合は返還する側の責任になる。アメリカではDNA鑑定をした後に返還されるため、返還のハードルが高くなる。
これらから分かることは、一大学では調査が出来ないほど困難なものであること(逆にいうと、それほどの問題を起こしたという責任がある)。それらを国の責任として国の徹底的な調査が必要ということ(結局、調査は研究成果となることには目を光らせておく必要あり、そして返還を待つご遺族をまた待たせることに!)。
大学では調査をすすめていると言いつつ、出来ないことを正直に認めて国の責任でやらせてくださいと言えば疑問を持っている側と接点が出来るように感じました。
後の会場からの発言にも「遺族が金で売った」というデマで何十もの苦しみを受けた」というのもあり、問題はそうとう深いことを感じました。
また、アメリカでは研究の成果を先住民族に報告し丁寧な慰霊を行っているのでアイヌ民族の遺骨も村に返された時、本当にこの骨はよいお仕事をして来ましたと受け入れられるような配慮をしてほしい、という意見も出て、うなずきました。
篠田さんは、研究成果をきちんとお伝えして来なかったことが現在、人類学会でも問題にしていると発言。
最後に、北大の関係者(常本さん)の答弁で「遺骨の調査をしている。但し、スピードと詳しさは一緒ではない(ので時間はかかる)。だから、はじめに全体像を調べ、主要なところから順に明らかにするべく国立大学からやっている。調査方法もやりながら改善していっている」と。
そういった趣旨を今まで質問した側にきちんと伝えていないから、問題が深刻化しているのですよ。
また、ほんとうに調査をしているのか第三機関などを作って報告してもらうということも考えてほしいですね。
さて、今日はさっぽろ自由学校“遊”で、佐々木利和さんを招いて話しを聞きます。より詳しく推進会議の内容を聞きに行きます。
市民とともに考える これからのアイヌ政策「アイヌ政策推進会議~作業部会報告書から~」
「民族共生の象徴となる空間」と「北海道外アイヌの生活実態調査」の2つの作業部会に分かれて、議論が進められていたアイヌ政策推進会議。この 作業部会の報告書について説明していただき、意見交換をしたいと思います。
http://www.sapporoyu.org/modules/sy_course/index.php?id_course=280

アイヌの承諾を得ないで収集した(盗んだ)遺骨について質問が集中。計画中の「民族共生の象徴空間」には“慰霊施設”と“研究施設”の設置が挙げられていますが、そこに皆が疑問を持っているからです。
遺骨収集は、誰が、いつ、どこで、どういった手順を踏んで行ったかという調査がなされないと盗掘か否かわからないので、慰霊のしようも研究材料としての認可もできないと。今回の主催者であり司会の秋辺日出男さんが「研究を承諾するとしても、盗骨と言われているものを差し出す同胞はいないはず」と言われたのが印象的でした。
なお、会場にはアイヌ政策推進作業部会のメンバーである常本照樹さん(北海道大学アイヌ・先住民研究センター長)と
佐々木利和さん(北海道大学アイヌ・先住民研究センター教授)も来られ、質疑に答えられました。
問:遺骨収集の調査をしたのか
答:(篠田)「発掘当事者しか分からない。小金井など発掘者の日記などから倫理的な責任があるものが存在することは明らかだ(音声が聞こえにくかったので当日配布の資料で補足:わたし)。今はどこに何体入っているかは調査したが、それ以降は今後の調査だ。大学にも出せる情報は全部出してくれと言っているが、おそらく分からないだろうというのがかなりの部分あるだろう。それをどうするかが課題。それでも出なかった場合にどうしたらいいかは今後の課題だ。各大学で調査をして情報を出し、遺族に返還できるものを返還し、出来なかったものを集約して慰霊施設におさめることになるだろう。その時に盗骨の調査が深まるかというとそれは疑問だ、全体の流れからするとそれは落ちるのではないか」。
「どこに何体入っているかは調査した」も、よく分からない答弁ですが、その詳細を知りたい。また、「それ以降は今後の調査」だと、今の段階で言っているのが納得いきませんし、盗骨の調査は“落ちる(調べられない)のではないか”との答弁に、わたしばかりではなく、会場に怒りが爆発したと思います。
その後、盗骨されたというご遺族の数人が意見・質問をしました。遺骨の返還と賠償、そして副葬品の返還も北大にする、と。
篠田さんは講演の中で、「アメリカ・オーストラリア型の解決法」として、遺骨研究の禁止と埋め戻していることを紹介し、しかし、それは誤っていると指摘。研究の大切さを強調。そのことを盗堀問題の質問で言ってしまうことでマイナスに働いたように感じます。
だから、まずは返還して、その後に同意を得るという手順を踏んで研究するのがいいのではないかという質問が出ました。それに対して、「その通り。現状で出来る情報開示をきちんとして返還できるものは返還する」とあっさり応答。

問:個別返還時にどの地域からの発掘かは分かっても個人詳細まで分からない時、DNA鑑定で遺族を判明することは可能なのか?
答(篠田):両親、祖父母までなら高い確率で結果が出ると思う。
問:北大は遺骨を発掘した地域の人々と個別に相談をして返還できるものは変換するという手はずをとるべきだと思うがどう考えるか?北大はアイヌ協会としか話さず、個別の対応をしないと聞いている。
答(常本):報告書に書かれていることだが、各大学にお預かりしているものについては可能な限り、大学でお返し出来る方はお返しし、どうしてもお返しできなかったものは象徴空間に集約させて頂いて慰霊させていただく。
問:先日の説明会ではアイヌ協会の各支部を通して返還すると言っていたが、個別返還してくれるということですね。
答(常本):それは、今までの実績として北海道大学では5ヶ所の支部から返還請求があったのに対し、お返ししたことがあったということ。今後、どうするかに関してはこれからの課題。北大以外にも遺骨があるので、返し方もバラバラだと適当ではないので、やはり国を中心にどういう形で窓口を作り、お返しするのかを検討した上で考える。
あれよ? 「アイヌ協会以外とは話しません」と言っていたのに・・・。「返し方もバラバラだと適当でない」も説得力がない。
答(佐々木):皆さんはご存知だと思うけれど、アイヌの墓は誰が埋められているかが分からない。エカシがいれば分かる。今、大学にある人骨は誰のか分からないのがあるだろう。だから、大学で返せないものは、象徴空間に集めた後にじっくりと時間をかけて調べてお返しします (いま出来ません)。
問:今、どういう整理がなされて、どのような情報があるのか?
答(篠田):ケースによる。実は「発掘報告書」というのがあり、それがあればどこの穴からどれを掘ったかがわかる。しかし、昭和30年以降のはあるのもあるが、それ以前はほとんどないので場所の特定が出来ない。
問:北大はどこまで発掘の資料があるのか、どれだけ調べられているのか。
答(常本):北大にある資料に関しては情報公開している。その中に記されているように頭骨については一体一体どの地域のものか記されている。手足については頭骨ほど厳密に分類はされていなく頭骨と別に収められているが基本的にはどの地域かわかるように収められている。各大学で現状調査が文科省の責任で行われている。それとは別に、各大学で責任があるので調査をしている。
問:遺骨返還に関して具体的な方法は?
答(篠田):二つある。ひとつは遺骨から情報を得ること(DNAなど)。他は残された文献を調べること。ただし、文献が残っているものが少ない。遺族が返還を申し出た場合、調べなければならないが大学単位では無理がると私(篠田)は思うので象徴空間に入って調べることはありうると思う。過って返還した場合は返還する側の責任になる。アメリカではDNA鑑定をした後に返還されるため、返還のハードルが高くなる。
これらから分かることは、一大学では調査が出来ないほど困難なものであること(逆にいうと、それほどの問題を起こしたという責任がある)。それらを国の責任として国の徹底的な調査が必要ということ(結局、調査は研究成果となることには目を光らせておく必要あり、そして返還を待つご遺族をまた待たせることに!)。
大学では調査をすすめていると言いつつ、出来ないことを正直に認めて国の責任でやらせてくださいと言えば疑問を持っている側と接点が出来るように感じました。
後の会場からの発言にも「遺族が金で売った」というデマで何十もの苦しみを受けた」というのもあり、問題はそうとう深いことを感じました。
また、アメリカでは研究の成果を先住民族に報告し丁寧な慰霊を行っているのでアイヌ民族の遺骨も村に返された時、本当にこの骨はよいお仕事をして来ましたと受け入れられるような配慮をしてほしい、という意見も出て、うなずきました。
篠田さんは、研究成果をきちんとお伝えして来なかったことが現在、人類学会でも問題にしていると発言。
最後に、北大の関係者(常本さん)の答弁で「遺骨の調査をしている。但し、スピードと詳しさは一緒ではない(ので時間はかかる)。だから、はじめに全体像を調べ、主要なところから順に明らかにするべく国立大学からやっている。調査方法もやりながら改善していっている」と。
そういった趣旨を今まで質問した側にきちんと伝えていないから、問題が深刻化しているのですよ。
また、ほんとうに調査をしているのか第三機関などを作って報告してもらうということも考えてほしいですね。
さて、今日はさっぽろ自由学校“遊”で、佐々木利和さんを招いて話しを聞きます。より詳しく推進会議の内容を聞きに行きます。
市民とともに考える これからのアイヌ政策「アイヌ政策推進会議~作業部会報告書から~」
「民族共生の象徴となる空間」と「北海道外アイヌの生活実態調査」の2つの作業部会に分かれて、議論が進められていたアイヌ政策推進会議。この 作業部会の報告書について説明していただき、意見交換をしたいと思います。
http://www.sapporoyu.org/modules/sy_course/index.php?id_course=280