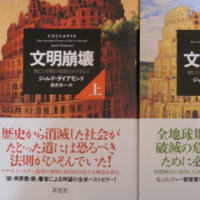今回は、重松清『エイジ』(新潮文庫)です。
しっかし、本当に私って「この作家さんが面白い!」と思ったら、ひたすらその作家さんばかり攻めるなぁ・・・。まさに縦割り行政。お役所仕事的ですな。感想まで事務的にならないように気をつけます・・・(笑)
--------あらすじ--------
ぼくの名はエイジ。東京郊外・桜ヶ丘ニュータウンにある中学の二年生。その夏、町には連続通り魔事件が発生して、犯行は次第にエスカレートし、ついに捕まった犯人は、同級生だった―。その日から、何かがわからなくなった。ぼくもいつか「キレて」しまうんだろうか?…家族や友だち、好きになった女子への思いに揺られながら成長する少年のリアルな日常。山本周五郎賞受賞作。(「BOOK」データベースより)
--------------------
神戸児童連続殺傷事件って覚えていますか?
そう。俗に言う「酒鬼薔薇事件」です。あれが発生したのは、私が高校生の頃でした。しかも私の通う高校のすぐ近所で。
授業中にヘリコプターが飛び(複数のヘリが旋回していて、授業の先生の声も聞き取れないほどでした)、あちこちでマスコミ関係者が取材しており、近所の公園から子どもの姿が消えました。
ウチの高校でもちょとした騒ぎでした。突然降って湧いた騒ぎ。
ごめんなさい。白状すると、ちょっとワクワクした。不謹慎なのはわかっていますが。
「ぼくは、ニュースや新聞記事に通り魔のことが出るたびに、嘘臭いなあと感じてしまう。(中略)じつはこの街はひそかにサスペンスドラマのロケ地に選ばれていて、ぼくたちは知らないうちにエキストラ出演しているんじゃないか、なんて。」(P20)
これは主人公エイジの抱いた感想だけど、私もそうだった。やはり自分には関係ない世界だと思ってた。自分が刺されるなんて実感できないし、誰かを刺すことも、そりゃあ人並みに「こいつ殺したろか」と思ったことだってないとは言わないけど、思うことと、実際行動することには、途方もないほど越えられない大きな壁があるわけで・・・やっぱり所詮他人事だった。だから「嘘臭い」と言うエイジの気持ちは分かる気がする。読みながらこんなことを思い出してました。
じゃあ、犯人が同級生だったら?同じ教室の前の席のヤツだったら?
「エイジ」の登場人物であるエイジ、ツカちゃん、タモツくんの3人は、同級生が犯人の通り魔事件に接し、三者三様の態度をとる。
加害少年に同化して事件を考えたエイジ、
被害者に同化したツカちゃん、
そして、自分には関係ないという立場のタモツくん。
このことは、藤原和博さんの解説に書かれているので、詳しくはそちらを読んでいただきたいのですが、私はタモツくんだったかなぁ・・・。タモツくんほどクールでもないけど。
エイジは、ごく普通の「ホームドラマ」みたいな家庭で育った「普通の」少年。しかし、通り魔として無関係の人間を背後から襲い続けたタカやんだって、特別ガラの悪い子なわけでも、キレやすいわけでもない、「普通の」少年だった。
僕とタカやんはどこが違うのだろう―?
エイジはそれを考える。自分の中にも「その気」はあることを発見する。そして何度も自分の頭の中でシュミレーションしてみる。何度も頭の中で幻のナイフを突き立て、ロールプレイを繰り返すことで、エイジは学ぶ。
「タカやん、オレはもう、ここまでおまえと同じになった。だから、だいじょうぶ、オレはおまえじゃない」(P418)
うーん、この過程が本当にリアルです。
タカやんはホント普通のヤツで、大人しくて、あんま目立たなくて、友達とは違うけどそこそこ話もして・・・、オレだってごく普通のホームドラマみたいな家で、好きなコもいて、友達関係でもちょっと悩みもあって・・・。どこが違う?オレが通り魔にならないって言える?オレとタカやんはホントに違うのか?
このへんのエイジの自問、あるいは、自分の中に「その気」があると発見したときの驚き、恐れは、本当に胸に迫ってきます。
しっかし、重松さんの描く中学生(男子)って、ホント驚くほどリアル。たまに昭和(高度経済成長期)っぽすぎて、「うん?」と思っちゃうこともあるけど、それでもやっぱりリアル。「うまく言えないけど何かイライラする感情」や、「分かってるけどそれをやるのは格好悪い(裏切りになる)という感覚」など。私のほうが重松さんより圧倒的に若いのに、「あぁそういえばそんなことも思ったような気がする」と教えられることもしばしば。
この小説は、中学生エイジの成長物語だ。同級生の通り魔事件、親友との関係、好きな子への思い、家族とのこと・・・。中学生だっていろいろ大変なんだ。
「負けてらんねーよ」
いろいろな経験をして、一歩オトナに近づいたエイジがそう呟くラストは爽やかで、すごく後味の良いものでした。
さて、最後に、重松さんの「キレる」の解釈がなかなか面白い。
「我慢とか辛抱とか感情を抑えるとか、そういうものがプツンとキレるんじゃない。自分と相手とのつながりがわずらわしくなって断ち切ってしまうことが、『キレる』なんじゃないか」(P397,398)
なるほどー。
しっかし、本当に私って「この作家さんが面白い!」と思ったら、ひたすらその作家さんばかり攻めるなぁ・・・。まさに縦割り行政。お役所仕事的ですな。感想まで事務的にならないように気をつけます・・・(笑)
 | エイジ 重松 清 新潮社 2004-06 by G-Tools |
--------あらすじ--------
ぼくの名はエイジ。東京郊外・桜ヶ丘ニュータウンにある中学の二年生。その夏、町には連続通り魔事件が発生して、犯行は次第にエスカレートし、ついに捕まった犯人は、同級生だった―。その日から、何かがわからなくなった。ぼくもいつか「キレて」しまうんだろうか?…家族や友だち、好きになった女子への思いに揺られながら成長する少年のリアルな日常。山本周五郎賞受賞作。(「BOOK」データベースより)
--------------------
神戸児童連続殺傷事件って覚えていますか?
そう。俗に言う「酒鬼薔薇事件」です。あれが発生したのは、私が高校生の頃でした。しかも私の通う高校のすぐ近所で。
授業中にヘリコプターが飛び(複数のヘリが旋回していて、授業の先生の声も聞き取れないほどでした)、あちこちでマスコミ関係者が取材しており、近所の公園から子どもの姿が消えました。
ウチの高校でもちょとした騒ぎでした。突然降って湧いた騒ぎ。
ごめんなさい。白状すると、ちょっとワクワクした。不謹慎なのはわかっていますが。
「ぼくは、ニュースや新聞記事に通り魔のことが出るたびに、嘘臭いなあと感じてしまう。(中略)じつはこの街はひそかにサスペンスドラマのロケ地に選ばれていて、ぼくたちは知らないうちにエキストラ出演しているんじゃないか、なんて。」(P20)
これは主人公エイジの抱いた感想だけど、私もそうだった。やはり自分には関係ない世界だと思ってた。自分が刺されるなんて実感できないし、誰かを刺すことも、そりゃあ人並みに「こいつ殺したろか」と思ったことだってないとは言わないけど、思うことと、実際行動することには、途方もないほど越えられない大きな壁があるわけで・・・やっぱり所詮他人事だった。だから「嘘臭い」と言うエイジの気持ちは分かる気がする。読みながらこんなことを思い出してました。
じゃあ、犯人が同級生だったら?同じ教室の前の席のヤツだったら?
「エイジ」の登場人物であるエイジ、ツカちゃん、タモツくんの3人は、同級生が犯人の通り魔事件に接し、三者三様の態度をとる。
加害少年に同化して事件を考えたエイジ、
被害者に同化したツカちゃん、
そして、自分には関係ないという立場のタモツくん。
このことは、藤原和博さんの解説に書かれているので、詳しくはそちらを読んでいただきたいのですが、私はタモツくんだったかなぁ・・・。タモツくんほどクールでもないけど。
エイジは、ごく普通の「ホームドラマ」みたいな家庭で育った「普通の」少年。しかし、通り魔として無関係の人間を背後から襲い続けたタカやんだって、特別ガラの悪い子なわけでも、キレやすいわけでもない、「普通の」少年だった。
僕とタカやんはどこが違うのだろう―?
エイジはそれを考える。自分の中にも「その気」はあることを発見する。そして何度も自分の頭の中でシュミレーションしてみる。何度も頭の中で幻のナイフを突き立て、ロールプレイを繰り返すことで、エイジは学ぶ。
「タカやん、オレはもう、ここまでおまえと同じになった。だから、だいじょうぶ、オレはおまえじゃない」(P418)
うーん、この過程が本当にリアルです。
タカやんはホント普通のヤツで、大人しくて、あんま目立たなくて、友達とは違うけどそこそこ話もして・・・、オレだってごく普通のホームドラマみたいな家で、好きなコもいて、友達関係でもちょっと悩みもあって・・・。どこが違う?オレが通り魔にならないって言える?オレとタカやんはホントに違うのか?
このへんのエイジの自問、あるいは、自分の中に「その気」があると発見したときの驚き、恐れは、本当に胸に迫ってきます。
しっかし、重松さんの描く中学生(男子)って、ホント驚くほどリアル。たまに昭和(高度経済成長期)っぽすぎて、「うん?」と思っちゃうこともあるけど、それでもやっぱりリアル。「うまく言えないけど何かイライラする感情」や、「分かってるけどそれをやるのは格好悪い(裏切りになる)という感覚」など。私のほうが重松さんより圧倒的に若いのに、「あぁそういえばそんなことも思ったような気がする」と教えられることもしばしば。
この小説は、中学生エイジの成長物語だ。同級生の通り魔事件、親友との関係、好きな子への思い、家族とのこと・・・。中学生だっていろいろ大変なんだ。
「負けてらんねーよ」
いろいろな経験をして、一歩オトナに近づいたエイジがそう呟くラストは爽やかで、すごく後味の良いものでした。
さて、最後に、重松さんの「キレる」の解釈がなかなか面白い。
「我慢とか辛抱とか感情を抑えるとか、そういうものがプツンとキレるんじゃない。自分と相手とのつながりがわずらわしくなって断ち切ってしまうことが、『キレる』なんじゃないか」(P397,398)
なるほどー。