授業中、学生にワークシートにいろいろ書いてもらったりしているのですが、
そのなかですごく気になってしかたないことば遣いがあります。
「講義のなかで先生が話してくれた自由の分類は、
私たちが考えた分類とは違くてびっくりしました。」
「ホッブズとロックでは自由の捉え方が全然違かったのが印象的でした。」
「違くて」 ってなんだあ
「違かった」 なんて言うなあ
これを福大の学生も、看護学校の学生もけっこうみんな使っているんですよ。
うう、気持ち悪い
何年も前からこの言い回しは気になっていたんですが、
福島の方言なんだろうなあと思って、ブログには取り上げずにきたんです。
ワークシートではそう書かれるたびに、
「違くて」 → 「違い」
「違かった」 → 「違っていた」
と添削してあげてはいましたが、それは、
正式な文書では方言ではなく標準語を使うようにしましょうね、
という老婆心による助言にすぎなかったわけです。
ところが調べてみると、これは方言ではなく、全国区の若者ことばのようです。
だとしたら大手を振って 「お前ら間違っとるっ 」 と注意してもいいではないですか。
」 と注意してもいいではないですか。
というわけで、今回晴れてブログネタにさせていただきます。
「違う」 というのは動詞です。
ワ行五段活用の動詞です。
したがって、
違わない、違います、違う、違うとき、違えば、違おう
と活用させなければいけないわけです。
連用形では 「違いて」 が音便になって 「違って」 と変化しますが、
いずれにせよ、これが正しい日本語の文法なのです。
「違くて」 や 「違かった」 は形容詞のような活用になっています。
「正しい」 とか 「深い」 という形容詞なら 「正しくて」 「深かった」 と活用させます。
しかし、繰り返し言いますが、「違う」 というのは動詞です。
形容詞とは違うのです。
上で引用した記事のなかでは、「違う」 は動詞だけど、
その反対語の 「正しい」 は形容詞なので、
それに引きずられて 「違くて」 の誤用が生じたのではないかと推測されています。
しかし、「違う」 の反対語は 「合う」 のはずで、
「合う」 もやはりワ行五段活用の動詞であって、
「合くて (あくて)」 とか 「合かった (あかった)」 なんて絶対に言わないのと同様に、
「ちがくて」 とか 「ちがかった」 も完全に間違いなのです。
上記の記事には、Mr.Children の曲に、
「例えばこれが恋とは違くても」 という歌詞が出てくると書いてあります。
調べてみると、「Everything (It's You)」 という桜井和寿さん作詞の曲で、
なんと1997年にリリースされています。
そんな昔に 「違くて」 なんてことばを聞いたことはなかったと思いますので、
ひょっとすると、この誤用の出発点は桜井さんだったのかもしれません。
もしもそうだとするとおそろしい影響力だっ。
桜井さんは東京都練馬区の出身らしいので、やはり方言とかではないのでしょう。
本人はそれが間違いだということを知っていたのでしょうか?
ぜひとも全CDを回収して、
「例えばこれが恋とは違っても」 と正しくレコーディングし直したCDと
交換してあげてほしいものだと思います。
そのなかですごく気になってしかたないことば遣いがあります。
「講義のなかで先生が話してくれた自由の分類は、
私たちが考えた分類とは違くてびっくりしました。」
「ホッブズとロックでは自由の捉え方が全然違かったのが印象的でした。」
「違くて」 ってなんだあ

「違かった」 なんて言うなあ

これを福大の学生も、看護学校の学生もけっこうみんな使っているんですよ。
うう、気持ち悪い

何年も前からこの言い回しは気になっていたんですが、
福島の方言なんだろうなあと思って、ブログには取り上げずにきたんです。
ワークシートではそう書かれるたびに、
「違くて」 → 「違い」
「違かった」 → 「違っていた」
と添削してあげてはいましたが、それは、
正式な文書では方言ではなく標準語を使うようにしましょうね、
という老婆心による助言にすぎなかったわけです。
ところが調べてみると、これは方言ではなく、全国区の若者ことばのようです。
だとしたら大手を振って 「お前ら間違っとるっ
 」 と注意してもいいではないですか。
」 と注意してもいいではないですか。というわけで、今回晴れてブログネタにさせていただきます。
「違う」 というのは動詞です。
ワ行五段活用の動詞です。
したがって、
違わない、違います、違う、違うとき、違えば、違おう
と活用させなければいけないわけです。
連用形では 「違いて」 が音便になって 「違って」 と変化しますが、
いずれにせよ、これが正しい日本語の文法なのです。
「違くて」 や 「違かった」 は形容詞のような活用になっています。
「正しい」 とか 「深い」 という形容詞なら 「正しくて」 「深かった」 と活用させます。
しかし、繰り返し言いますが、「違う」 というのは動詞です。
形容詞とは違うのです。
上で引用した記事のなかでは、「違う」 は動詞だけど、
その反対語の 「正しい」 は形容詞なので、
それに引きずられて 「違くて」 の誤用が生じたのではないかと推測されています。
しかし、「違う」 の反対語は 「合う」 のはずで、
「合う」 もやはりワ行五段活用の動詞であって、
「合くて (あくて)」 とか 「合かった (あかった)」 なんて絶対に言わないのと同様に、
「ちがくて」 とか 「ちがかった」 も完全に間違いなのです。
上記の記事には、Mr.Children の曲に、
「例えばこれが恋とは違くても」 という歌詞が出てくると書いてあります。
調べてみると、「Everything (It's You)」 という桜井和寿さん作詞の曲で、
なんと1997年にリリースされています。
そんな昔に 「違くて」 なんてことばを聞いたことはなかったと思いますので、
ひょっとすると、この誤用の出発点は桜井さんだったのかもしれません。
もしもそうだとするとおそろしい影響力だっ。
桜井さんは東京都練馬区の出身らしいので、やはり方言とかではないのでしょう。
本人はそれが間違いだということを知っていたのでしょうか?
ぜひとも全CDを回収して、
「例えばこれが恋とは違っても」 と正しくレコーディングし直したCDと
交換してあげてほしいものだと思います。










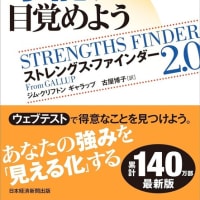














若者言葉と言えば、『ら』抜き言葉が浮かびますが、実際にどれほど広く浸透しているかはわかりません。日本語がこれほど荒れている中で、小学校での英語学習が始まり、日本語の先行きが不安になりました
ら抜きことばも多いですね。
それもワークシートで見かけたら、必ず添削するようにしています。
昔、古田がヒーローインタビューでよく「投げれない」などと言っていて、
ものすごくガッカリした覚えがあります。
http://homepage3.nifty.com/kokubyaku/kotonoha/118-shitoshito.html
変なことをそそのかしたことになるのでしょうか?
「違くて」は私も勘弁して欲しい誤用の一つと考えております。
「ら抜き」は、日本語の歴史からありえることなので、少なくとも口語については態度保留状態です。
私が「違くて」を誤用とするのは、私が知る限りの辞書で活用が違うからです。
「ら抜き」のような語の短縮は「文板」→「札」などの古例もあり、動詞の活用自体も
古語と現代語では異なります。「ら抜き」は、誤用なのか、変化なのか、判断がつきかねております。
「見れる」「起きれる」「寝れる」「食べれる」「来(こ)れる」など、「〜れる」の形で
可能の意味を表す下一段活用の動詞をいう。
「見られる(ミルの未然形ミ+助動詞ラレル)」「起きられる(オキルの未然形オキ+助動詞ラレル)」「寝られる(ネルの未然形ネ+助動詞ラレル)」「食べられる(タベルの未然形タベ+助動詞ラレル)」「来(こ)られる(クルの未然形コ+助動詞ラレル)」などのように、「〜られる」の形が本来の正しい言い方。
「乗る」「釣る」「登る」など五段活用の動詞から生じる下一段活用の可能動詞「乗れる」「釣れる」「登れる」などの影響によるものと考えられている。
東京語では、大正の末から昭和の初めにかけて使われ始め、戦後は特によく使われるように
なった。「見る」「寝る」「来(く)る」など、主として語幹が一音節の動詞から生じたもので
あるが、近年は、「どんな大学でも〈受けれる〉成績」「朝早くはなかなか〈起きれ〉ない」
などのように、語幹が二音節またはそれ以上の音節の動詞にも及んでいる。
られる(助動)
「らる」の口語形。中世以降の語
受け身・可能・自発・尊敬の助動詞。
(1)「れる」と意味・用法は同じであるが、未然形がア段となる動詞には「れる」が付き、
それ以外の場合は「られる」が付くというように、接続のしかたに分担がある。
(2)サ変動詞に接続する場合、「出席される」のように、未然形のうち、「さ」に「れる」
が付くのが普通であるが、書き言葉でのやや改まった言い方では、「出席せられる」の
ように、未然形のうち、「せ」に「られる」が付くこともある
れる(助動)
助動詞「る」の口語形。中世以降の語
受け身・可能・自発・尊敬の助動詞。
(2)可能の意を表す。
「駅までなら一〇分で行か〈れる〉だろう」
----
・「見る」の可能に「見れる」が使われているのに、古風の「見られる」という
受身と誤解される恐れのある表現を使う人がどれだけいるのか?
・「一〇分で行かれるだろう」は可能の「れる」だが、「ら抜き」ではない。
・「ボールを投げられる」は「られる」で可能と分かるが、
「柔道で投げられる」は受身と解釈されないか?
http://homepage3.nifty.com/kokubyaku/kotonoha/120-ranuki.html
ご笑覧下さい。(←学生さんは辞書を引いてね)
(他人の言を借りて自説を主張するという修辞法も使いました。事情を察して許してね)
急ぎ仕事のため粗も多いかと存じます。ご叱正をお願いします。
(←学生さんは辞書を引いてね、誤字指摘も助かるのでよろしく)
人間というのは自己中心的なもので、自分の過ちには甘く、他人の過ちには厳しく接しがちです。
私も、このブログでは相当いい加減なことば遣いをしているのですが、
それは、主として学生向けにこのブログを書いているのだからしかたないのだと言い訳しながら、
でも「違くて」や「ら抜きことば」にはやけに厳しく当たったりするわけです。
まあ言語というのは、そういう自己中心的な価値判断が衝突を繰り返すなかで、
しだいに多数派が形成されて変容を遂げていくのでしょう。
そこまでわかった上で、私は「ならぬものはならぬのだ!」と言い続けてみようかと思います。
「しとしと雪」は単なる夢物語です。眉をひそめる方がいらっしゃることを承知の上で、言い訳を先に書きつつ(←ずるい!)、誤用ってなあに?という問いを書いてみただけです。分かっている方は笑ってくださる筈ですが。
「ら抜き」は、書いている途中で嫌になりました。20行+「辞書を引いてね」という作文のために、どれだけ自己規制を破ったことか。
・論理が飛びまくりで、随筆でなければ、詭弁に近いものです。本当は、もう少し真面目に「覚え書き」に書こうかと思ったテーマです。
・慣用句などの手垢がついた(←こら!)表現の乱発になりました。
・「辞書も見ない者」は私の私的な文には考えられない表現です。普段なら 「辞書も見ぬ者」と文体重視で古語を使うでしょうし、檄文なら「見ぬ奴」と書くほうが私らしいのです。
・そもそも、読みやすく書くか、論文のように意味を限定するために難しい 言葉もいとわずに書くか、という基本方針は無きが如しですね。
でも、意図は伝わったようで、安堵しております。
ただ、何故、小生が先生の説への反論めいた書き込みを繰り返すのか、学生の方には理解できないかも知れませんね。
「学問ってなあに?」と書いておきましょうか。