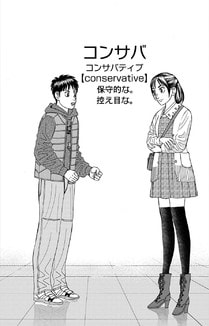TSUTAYAのカードのレンタル登録の有効期限に疑問がある。私は例えば2014年7月2日午後9時頃にTSUTAYAのカードを更新したが、有効期限が2015年7月1日になっていた。店やによると初日から起算して1年間有効なので、この期限になるらしいが、これは法律上不適切な可能性がある。
カードの裏面には会員規約に従うという注意書きがあり、規約を見ると次のように書かれている。
「レンタル利用登録の有効期間は、利用登録日より1年間です。但し、継続してレンタル利用登録を希望される場合には、有効期間満了日の前月1日より再度レンタル利用登録が可能です。なお、レンタル利用登録の手続きには、前項で定める条件の他、TSUTAYA店舗所定のレンタル利用登録料・年会費等が別途必要となります。」(規約第1条3項)。なおT会員規約も同様だが、これに関する有効期限はもうないと回答された。
これ以外期間に関する規約はなく、初日を算入するという規約はない。また原則、民法の規定に従って期間を計算する。
--
民法
第百三十八条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。(解説)
--
民法138条によれば「期間の計算方法は法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めを除き」民法の規定に従う。TSUTAYA側の回答や調査を考えると例外適用の特別法はないし、規約上も「初日を算入する」という趣旨の別段の定めはない。従って民法の規定に従わなければならない。
利用規約によると「利用登録日から1年」が有効期限で、民法140条より、利用登録日の午前0時から期間が開始しない場合は初日不算入だ。大概の顧客は利用登録日の午前0時に登録や期間更新に関する契約をしないので、初日は不算入となる。つまり、上の例でいえば起算日は2014年7月3日、期間満了日が2015年7月2日、応答日が2015年7月3日となる。つまり、カードの有効期限は2015年7月2日が満了するまでというのが法的に正しい有効期限である。2015年7月1日満了までではない。
店によると全国同じらしいが、これはTSUTAYA全店舗が法的に不適切な有効期限で運用している可能性があるということではないのか?TSUTAYAといえば大手だが、このあたりをどう考えているのか尋ねても法的説明は全くなく、そういう説明ができる部署を設けていないので回答できないという。これについては納得いく説明でないことはもちろんのこと、TSUTAYAの対応には非常に疑問がある。
誰か法的に有効な説明ができる方がいればぜひ教えてください。
ただ、ほとんどの人は午前0時でない利用登録日に登録等の契約をし、規約で「利用登録日から1年」となっているなら、法的な期間計算は上で書いたとおりになると思うが、どうなんでしょうね?
解説
[1]参考文献1,2。例えば初日を算入するなら、契約日の午後3時に契約した場合、現実には契約をしていない期間にも関わらずその日の午前0時まで遡及的に法的責任を負うことになります。また契約した時間によって期間の残り時間が変わることになります。それを回避するために24時間以内の時間は切り捨てようという考えが民法140条1項です。
例えば契約日時が2012年1月1日午前10時で「契約日から1年間レンタルする。」という契約なら、1月1日を算入せず2012年1月2日から起算して2013年1月1日満了までレンタルできます。一方、契約日が2011年12月31日で「2012年1月1日から1年間レンタルする。」という契約なら、「2012年1月1日の午前0時から1年間」というのが当事者間の合理的意思解釈ですから「その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。」(民法140条ただし書き)が適用され、2012年1月1日から起算して、2012年12月31日満了までレンタルできます。
TSUTAYAで利用登録を行う場合、ほとんどの人は店舗で登録等の契約をし、その時の時刻は午前0時ちょうどではないです。利用規約にも初日算入の規約はなく単に「利用登録日から1年」有効としか定められてませんから、上の「契約日から1年間レンタルする。」という場合と同じで、民法140条より利用登録日は算入されないのが正当な扱いだと思います。
仮に違うなら、「契約日から1年間レンタル」というケースの期間計算と何が違うのでしょうか?わかる方がいれば教えてください。