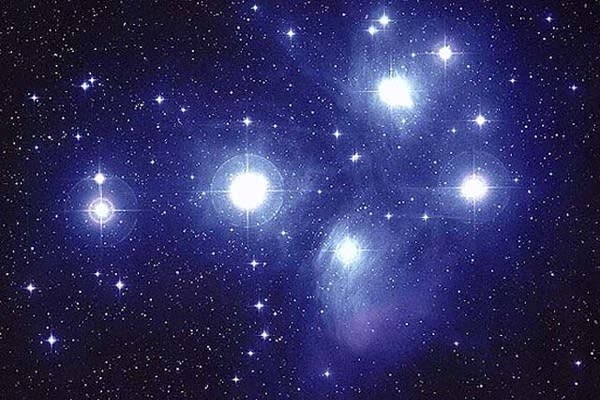アンドロメダ銀河はアンドロメダ座の方に見える銀河。我々の天の川銀河から最も近い銀河であり、距離は約230万光年。
アンドロメダ銀河は約1兆個の恒星からなり、直径22~26万光年[2]。我々の天の川銀河は約1000億個の恒星からなり、直径が約8~10万光年なので、アンドロメダ銀河は天の川銀河より少し大きい。
アンドロメダ銀河は肉眼でも観測することができ、964年には既にアブド・アル・ラフマン・アル・スーフィーによって"小さな雲"と記述されている[2]。かつてこの銀河は我々の銀河の中にあると考えられていたが、宇宙が膨張していることを示した有名なハッブルが1923年にケフェイド型変光星を利用し約90万光年(当時)の距離にあり、銀河系外の天体であることが明らかになった。
約230万光年の彼方にあっても肉眼でみえるのだから、星は密集すると大変明るくなるということだろう。人類がアンドロメダ銀河まで行ける日は来るのだろうか?
(作成日:2011-05-10 03:59:17)
参考
[1]ついてるレオさん"Happy Life" 2006.10.2
[2]Wikipedia アンドロメダ銀河 2011.5.10