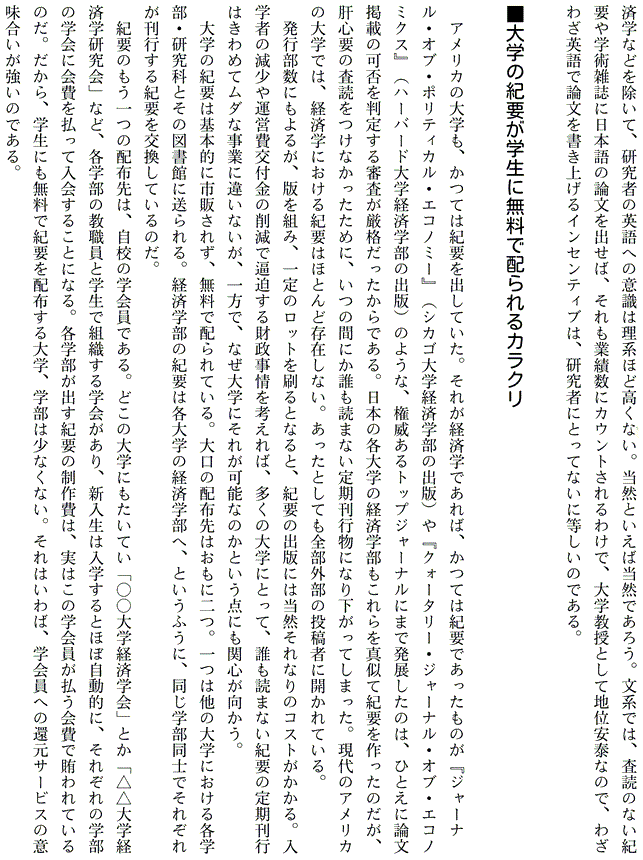専門領域のトップ5%と評価される経済学者が捕食ジャーナルでも相当数の論文を発表していた事が調査でわかった。
その調査を行ったのはFrederick Wallace(Gulf University for Science and Technology、クウェート)とTimothy Perri(アパラチア州立大学、USA)で、「専門分野のトップ5%以内と評価される最も著名な経済学者の27人は彼らの論文のほぼ5%を捕食ジャーナルで発表したという[1][2]」。また、「これらの研究者は2015年だけでも31論文を捕食ジャーナルで発表したという[1][2]」。
捕食ジャーナル(predatory journal)とは掲載料を獲得する目的で投稿論文を掲載する代わりに高額の掲載料をとり、全く査読を行わない又は表面的な査読で質の低い論文でも掲載している学術誌の事。中には平気で虚構論文を載せている雑誌もある。
このような学問を食い物にしている悪質なジャーナルの実態調査については以前に詳しく紹介した。なぜでたらめな査読を行うかも考察した。詳細はリンク先に譲るとして、虚構論文さえ平気で掲載している極めて悪質で恥ずかしい捕食ジャーナルに、なぜ専門分野でトップ5%以内と評価される著名経済学者が論文を掲載しているのか。
リンク先で紹介したように業績の乏しい研究者が業績を稼ぐために、捕食ジャーナルに論文を発表するならまだわかるが、なぜトップの経済学者たちが論文を出版するのか。
捕食ジャーナルで出版するのは、悪質で信用のないジャーナルで論文を出版するのだから、研究者としての信用や評価に悪影響があるかもしれない。そんな雑誌で出さないと業績を稼げないと評価されてしまうかもしれない。だから、捕食ジャーナルで論文を発表するのはやめた方がいいと思うものの、全然気にしないのか。
虚構論文でも掲載している学術誌は査読能力がなく、自分たちの雑誌は信用性がなく社会に害悪を与える論文でも平気で載せていますと公言しているようなものだから、一般には大変な恥で損害のはずだが、そもそも金儲けのために学問を食い物にしているのだから、捕食ジャーナルは全く気にしていないだろう。
[1]によると"What might motivate an experienced economist to publish in a predatory journal ? One possibility is that an inexperienced coauthor handled the submission and the experienced author was ignorant of the journal’s low quality. In most cases it is impossible to reject this hypothesis, but ten of the thirty-one papers published by top 5% authors in predatory journals in 2015 are single authored pieces,and another has two co-authors,both of whom are in the top 5% RePEc,so ignorance cannot be the only explanation.Furthermore, one top 5% economist was a coauthor on three of the papers published in predatory journals in the data set of 2015 publications,and six others in the 5% group had two coauthored papersin predatory journals.Apparently at least some of the top 5% authors are aware of the nature of these journals,but choose to publish in these outlets regardless of quality."
何人かは無知が原因かもしれないが、何人かはわかっていて捕食ジャーナルで出版しているようだ。
でも、今時捕食ジャーナルに関する知識がないというもの少し驚く。リンク先でも紹介したとおり、近年は無料のオープンアクセスジャーナルが急増して、従来の登録制のジャーナルは危機感を持ってきた。ネイチャーだってNature Communicationsというオープンアクセスジャーナルを作ったし、サイエンス誌は一見してわかる虚構論文をブラックリストのオープンアクセスジャーナルに投稿して多数が掲載されたという調査結果を出し、いかにそれらの査読や掲載論文の質が低いかという事をアピールして溜飲を下げた。
論文を発表して飯を食っている人たちで、しかもトップの経済学者なのに、なぜそんな事を知らないのか。経済学者はネイチャーやサイエンスなどの学術のニュースを見ないのか?確かに経済学者はネイチャーやサイエンスではなくてAmerican Economic Review等に掲載させるのだろうが、研究者だったら捕食ジャーナルくらい知っておかないと、上のような理由でいつか不利益を受けるかもしれない。
ネイチャーやサイエンスのニュースは日本の問題や経済学の記事が掲載される事もある。最近は東大医学系の論文捏造がサイエンスで報じられた。私のブログも紹介された。医学系の問題は経済学者にとって対岸の火事だと思っているかもしれないが、近いうちに日本の経済学の分野でも大きな論文捏造事件があるかもしれない。O 30代女性研究者のような悪質な虚構論文を発表した経済学者はいるかもしれない。
虚構論文を発表する者は倫理意識が欠如した極めて悪質なやつで、O 30代女性研究者のように周りの人たちをみんな不幸にする。こういう人物は学界から排除しなければならない。
上で述べたように、虚構論文を発表する研究者や学術誌は信頼性が全くなく社会の害悪になる論文を平気で載せていると思われるので、一般には大きな恥で損害があると思うものの、一部の経済学者はトップの人でさえ故意に捕食ジャーナルで論文を発表するので対策が必要だ。大きな笑いものになっているのに、いまだに論文を撤回していない某女性研究者のような倫理意識や考え方が悪質なものもいる。
虚構論文やそれを発表する研究者、掲載する学術誌を一掃する対策が必要である。
参考
[1]Frederick Wallace, Timothy Perri
"Economists behaving badly: Publications in predatory journals"
MPRA Paper No. 73075, June 1, 2016
[2]Retraction Watch 2016.10.27、直接的にはこの文章の第3段落の翻訳。