何か1つの事が様々な触媒反応を生じて過去の蓄積や
記憶、経験が瞬時に繋がり情景として浮かんでくる事が
多々ある。
またそれにより新たな着想を得たり新たな風景が見えて
くる事がある。
例えば甲子園での全国高校野球大会で宮城県代表校が
東北地方勢として初の優勝をしたとなると、
→初めて深紅の優勝旗が白河の関を越えた
→白河の関の歴史的意義と存在を思う
→白河以北一山百文と蔑まれた明治時代を思う
→戊辰戦争の情景を思う
→戊辰戦争の跡を巡り東北地方を歩いた若き日の記憶が
惹起される
→東北地方の人々や風土の情景が脳裏に浮かぶ
→日本の歴史における東北地方の存在を思う
という感じで思考回路が回る。
従ってもし、甲子園の高校野球大会決勝で宮城県代表校が
優勝していなければこの思考回路になっていないので今私が
若き日の東北地方散策や戊辰戦争を回顧して投稿する事には
なっていないだろう。
物事は何か1つのきっかけで連鎖していくという事を改めて
感じている。
さて、東北地方についてである。
東北地方はかつては日高見国(ひたかみこく)と言われていた。
縄文人による縄文文化が栄えていた日本先住民による生活圏
だった。
更にはコロボックルと言われた身長が60センチ程の小さな
人種も太古の東北地方には存在し、そのコロボックルが文明の
基礎を築いた側面もある。
やがて時代が下り、大和朝廷が12支族により形成されると
支配圏を広げるためにそれまでの先住民族である縄文人政権
に対して侵攻を始めた。
その最たる時代が桓武天皇の時である。
日本史の上では丁度、長岡京が造営されていてなかなか上手く
行かず平安京遷都が検討されていた時期の事である。
日高見国と言われた東北地方は阿弖流為(あてるい)が
統率し攻めてくる朝廷軍に抵抗した。
日本人として今、日本史を俯瞰して見るならば大和朝廷に
よる侵略、縄文人による祖国防衛戦争という事ができるだろう。
今の岩手県胆沢地方の胆沢縄文人が10倍以上の兵力の大和
朝廷軍と互角以上に戦い勝利している。
胆沢縄文人の族長・阿弖流為とモレが縄文人の種族連合を
指揮し東北地方の山河を神出鬼没に展開して大和朝廷軍に対して
大打撃を与えた。
このように東北地方は常に大和朝廷からの侵略に抵抗した
歴史を重ねており、その主な事例が、
・阿弖流為とモレによる日高見大戦争
・安倍一族による厨川の戦い
・奥州藤原氏による中央への抵抗
であろう。
阿弖流為に指揮された縄文人連合による日高見国は強かった
のである。
朝廷軍は多くの幹部が戦死、犠牲者を出しこれに危機感を
抱いた桓武天皇が激高し、
「坂東の安危、この一挙にあり。将軍宜しくこれを勉むべし。」
と激を飛ばしている。
しかし東北地方の地理を知り尽くしている縄文人連合は
阿弖流為の指揮で縦横無尽に展開し朝廷軍を壊乱させている。
朝廷軍は大軍を率いて今の岩手県の衣川に進軍し北上川の
西側に滞留したが、縄文人連合に攪乱され攻めあぐね次第に
犠牲者も出していき兵糧を浪費していった。
これを見かねた桓武天皇が、
「留まったまま30余日を経て何事か。今進軍しなければ時期
を失うではないか。」
と朝廷軍の責任者を叱咤している。
ある時は800人の縄文人軍が2000人の朝廷軍の先発隊
に攻め込んできた。
朝廷軍は突然の攻撃に慌てふためき退却する。
退却する朝廷軍の東から更に縄文人軍が400人攻撃し、
朝廷軍の退路を断った。
朝廷軍は前後を挟まれて進退に窮し、縄文人軍の一方的な
攻撃に晒され多くの部将が次々と戦死していった。
先発隊を壊滅された朝廷軍は瓦解し、衣川の方向へ逃げたり
矢に射たれたり、川に飛び込んで溺死した兵も出ている。
この戦況を朝廷軍の大使である古佐見は大本営発表をして
取り繕ったが現実の被害を知った桓武天皇は激怒して、
「うわべを取り繕って罪を逃れようとしている。不忠である。
国家の大害である。」
と朝廷軍の幹部に敗戦の責任を取らせるために官職から解任
している。
この時の大和朝廷は日高見戦争での敗北、長岡京の遷都失敗
などで疲弊していた。
この時の大和朝廷を支えたのが藤原氏と秦氏である。
つまりこの時、12支族による大和朝廷と日本先住民族の
縄文人による最大決戦が行われたのである。
その後、大和朝廷は坂上田村麻呂を責任者にして東北地方の
縄文人征伐を強化し戦争は激化した。
また別の機会に日高見戦争を改めて検証したいが阿弖流為と
モレは大和朝廷から講和を持ちかけられて騙され捕獲され京都
に連行されていく。
そして今の大阪府枚方市にて斬首された。
哀れである。
東北地方の縄文人連合を指揮した阿弖流為とモレを憐れんだ
後の世の人々が京都の清水寺の境内の一角に阿弖流為、モレの
慰霊碑を建立している。
余談だが縄文人は顔の彫りが深いので美男美女が多い。
東北地方に美女が多いのは必然だと言える。
20代前半当時の若き日の私が奇しくも知り合った東北美人
に惚れてしまったのは男ならば当然であり論を待たない。
その東北美人との着陸に失敗したのも人生の縁であろう。
何故かこの方は今も独身のままでいるそうだが20代前半
当時の若き日の私がこの東北美人を忘れるために10年の歳月
を要したほどである。
日本史を東北地方から検証するアプローチも視野を広げる
ために必要である。















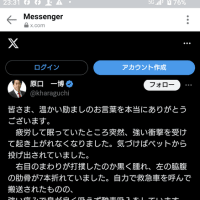
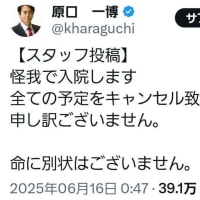















日本の歴史が、不明瞭になるのは、白村江の戦い663年の40年後703年がきっかけなのではと思っています。
それまで、ヤマトは、3箇所有りました。
日の丸は、白い雪に赤い太陽、日髙見国の旗という説が有ります。
長髄彦や安日彦、日髙見国については「東日流外三群誌」や「飛騨の口碑」に書かれています。
飛騨の語り部翁(飛騨の阿礼の子孫)から、神武以前の歴史を伝えられました。
山本健造(著)「明らかにされた神武以前」等福来書店から出ています。