今回の7-9月期GDP2次速報は、実質が前期比+5.3%と0.3の上方修正という結果だった。設備投資が1次の+2.4%から2次の3.4%に高まったのが大きい。もっとも、4-6月期での大きな落ち込みが1次の-4.5%から2次の-5.7%へと深まった反動によるものである。今回の速報では基準改訂がなされ、数値が一新された。改訂で傾向が変わったわけではないが、改めて設備投資の推移を眺めてみよう。
………
経済活動をより大きくするためには、供給力の強化が必要なのだから、設備投資が成長の原動力であることは言うまでもない。では、設備投資は、何によって決まるのか。これを分かっていれば、景気の先行きも知ることができる。日本の場合は、極めて単純で、輸出、住宅、公共の3つの追加的な需要を追うように動く。3つを足し合わせたものは、下図のとおり、不思議なほどピタリと重なる。
とりわけ、輸出の影響力は大きい。輸出を増やすには、それを作るための新たな設備が求められるという単純な理屈である。加えて、住宅を建てれば、そこに備え付ける機材を生産する設備投資も必要になる。金融緩和は、円安による輸出の増加、ローン金利の低下での住宅着工の伸長という、需要の経路を通じて設備投資を促す。経済学の教科書とは違い、直接、設備投資を刺激しているわけではないことに注意しなればならない。
今後の設備投資はどうなるか。コロナ禍で企業収益が低下していて、悲観的な向きが多いけれども、輸出が7-9月期に反転している以上、設備投資も上昇へと変わる。実際、月次で設備投資を推計すると、既に9月には反転していた。10月の鉱工業出荷では、資本財の伸びが目立ったが、その後の出荷内訳表・総供給表の公表で、国内向けであることが確かめられており、生産予測の高さとも相まって、10-12月期の設備投資はかなり高くなろう。
12/9公表の10月の機械受注は、前月比17.1%という、2005年以来の高い伸びになるというポジティブ・サプライズだったが、十分、うなづけるものであった。企業の建設投資に関しても、9月の建設総合統計が既に底入れし、10月の鉱工業出荷の建設財の伸びも踏まえれば、上昇していると見るべきだろう。もちろん、これまでの落ち込みは大きかったが、V字回復に向け着々と歩んでいるように思える。
(図)

………
経済学の教科書では、設備投資は金利で調節されることになっているため、異次元の金融緩和をすれば、景気が回復するという幻想に取り憑かれてしまうが、現実の経営者は、不合理なほど需要リスクに強く支配されていて、輸出や住宅といった「現物」が出て来なければ動かない。アベノミクスでは、緊縮財政を進め、消費税と社会保険料を上げ、円安で輸入物価を高めたから、将来不安を持ち出さずとも、最大需要の消費が増えるはずもない。
経済は、輸出や住宅から設備投資に、そして、所得増を経て消費へ波及し、設備投資に循環する。ただの図表も、見る目があれば、そんなことを教えてくれる。循環を媒介する需要を、あえて途中でせき止めたりしなければ、成長は加速していくのだが、日本は、「あえて」にばかり熱心で、詮無き円安と業界支援策に頼り続けては、失敗を繰り返している。そうして、衰退は運命なのだとあきらめるようになったのである。
(今日までの日経)
国内新規感染3000人超。「勝負の3週間」減らぬ人出。児童手当 高所得層カット。医療費 年収200万円から2割。オンライン診療 かかりつけ医限定。
※感染確認数は、またも増加トレンドになった。マスクを脱着しつつ2時間の会食もOKというのでは、減りがたいのかもしれない。11月景気ウォッチャーの「飲食」の水準は、前月比-4.7ポイントだったが、夏場よりかなり高い。高リスク因子は、外出や移動より会食のはずなのに、行為の特定よりGoToトラベルの是非が議論の的になっている。
………
経済活動をより大きくするためには、供給力の強化が必要なのだから、設備投資が成長の原動力であることは言うまでもない。では、設備投資は、何によって決まるのか。これを分かっていれば、景気の先行きも知ることができる。日本の場合は、極めて単純で、輸出、住宅、公共の3つの追加的な需要を追うように動く。3つを足し合わせたものは、下図のとおり、不思議なほどピタリと重なる。
とりわけ、輸出の影響力は大きい。輸出を増やすには、それを作るための新たな設備が求められるという単純な理屈である。加えて、住宅を建てれば、そこに備え付ける機材を生産する設備投資も必要になる。金融緩和は、円安による輸出の増加、ローン金利の低下での住宅着工の伸長という、需要の経路を通じて設備投資を促す。経済学の教科書とは違い、直接、設備投資を刺激しているわけではないことに注意しなればならない。
今後の設備投資はどうなるか。コロナ禍で企業収益が低下していて、悲観的な向きが多いけれども、輸出が7-9月期に反転している以上、設備投資も上昇へと変わる。実際、月次で設備投資を推計すると、既に9月には反転していた。10月の鉱工業出荷では、資本財の伸びが目立ったが、その後の出荷内訳表・総供給表の公表で、国内向けであることが確かめられており、生産予測の高さとも相まって、10-12月期の設備投資はかなり高くなろう。
12/9公表の10月の機械受注は、前月比17.1%という、2005年以来の高い伸びになるというポジティブ・サプライズだったが、十分、うなづけるものであった。企業の建設投資に関しても、9月の建設総合統計が既に底入れし、10月の鉱工業出荷の建設財の伸びも踏まえれば、上昇していると見るべきだろう。もちろん、これまでの落ち込みは大きかったが、V字回復に向け着々と歩んでいるように思える。
(図)

………
経済学の教科書では、設備投資は金利で調節されることになっているため、異次元の金融緩和をすれば、景気が回復するという幻想に取り憑かれてしまうが、現実の経営者は、不合理なほど需要リスクに強く支配されていて、輸出や住宅といった「現物」が出て来なければ動かない。アベノミクスでは、緊縮財政を進め、消費税と社会保険料を上げ、円安で輸入物価を高めたから、将来不安を持ち出さずとも、最大需要の消費が増えるはずもない。
経済は、輸出や住宅から設備投資に、そして、所得増を経て消費へ波及し、設備投資に循環する。ただの図表も、見る目があれば、そんなことを教えてくれる。循環を媒介する需要を、あえて途中でせき止めたりしなければ、成長は加速していくのだが、日本は、「あえて」にばかり熱心で、詮無き円安と業界支援策に頼り続けては、失敗を繰り返している。そうして、衰退は運命なのだとあきらめるようになったのである。
(今日までの日経)
国内新規感染3000人超。「勝負の3週間」減らぬ人出。児童手当 高所得層カット。医療費 年収200万円から2割。オンライン診療 かかりつけ医限定。
※感染確認数は、またも増加トレンドになった。マスクを脱着しつつ2時間の会食もOKというのでは、減りがたいのかもしれない。11月景気ウォッチャーの「飲食」の水準は、前月比-4.7ポイントだったが、夏場よりかなり高い。高リスク因子は、外出や移動より会食のはずなのに、行為の特定よりGoToトラベルの是非が議論の的になっている。













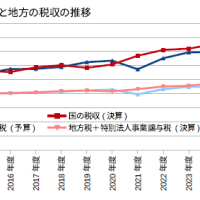

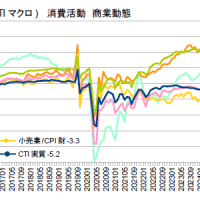
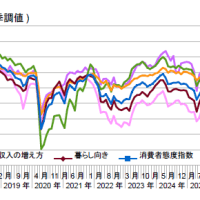
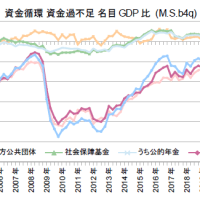

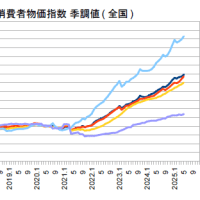




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます