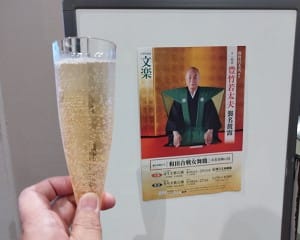〇東京建築祭(2024年5月25日~5月26日)
この週末、東京の多彩な建築を体験し、まちの魅力を再発見する「東京建築祭」が初めて開催された。うれしかったのは、有料のガイドツアーやイベントもあるが、25日・26日の週末には、多くの建築が無料・予約不要で特別公開されていたことである。私は25日(土)は大手町・丸の内・有楽町エリアを、26日(日)は日本橋・京橋エリアを歩いてみた。
・25日:東京ステーションホテル~明治生命館~新東京ビルヂング~国際ビルヂング~堀ビル
「特別公開」と言っても、一部区画のみのアッサリした公開もあるのだが、明治生命館は、資料・展示室もあり、会議室、執務室、応接室など文化的価値の高い主要室をじっくり見学させてくれた。実はふだんから土日に公開されていることを初めて知った。

このエリアは美術館めぐりで歩くことが多い。新東京ビルヂングに美術館はないが、たぶんカフェを求めて入ったことがある。

国際ビルヂングも地下の飲食街には何度もお世話になっているので、建て替え予定と聞いて、ちょっと寂しい。
新橋駅近くの堀ビルは初めて知った。スクラッチタイルの古風な外観はそのままに、シェアオフィスとして活用されていた。
・26日:三井本館~丸石ビルディング~江戸屋~日証館
丸石ビルディングも初めて存在を知って、大ファンになってしまった。「近世ロマネスク様式」というらしく、動物や変な顔の人面があちこちに嵌め込まれている。1階はペルシャじゅうたんのショールームらしかった。


江戸刷毛専門店の江戸屋は小さな店舗で、入場待ちの見学者が大勢いたので、見学はあきらめた。このあたり、我が家からは散歩エリアなので、また普通の日に来ようと思う。
日証館も長い列ができていたが、30分ほど待って、エントランスホールを見学した。ここは渋沢栄一の邸宅だったところ。階段の窓を占領する日本橋川の眺めが、渋沢の構想したウォーターフロント東京のイメージを喚起する。

この日本橋界隈、与謝蕪村の夜半亭跡、べったら市の宝田恵比寿神社、「兜岩」の伝承を持つ兜神社など、建築以外でも意外なスポットに出会えて楽しかった。
それと建築を楽しむ人たちがこんなにたくさんいるとは思っていなかったので、びっくりした。ぜひ来年も開催してほしい。