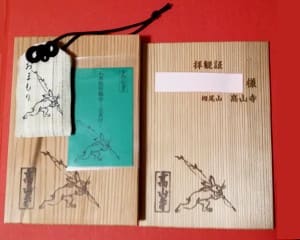〇『大江大河』第1部:全47集(東陽正午陽光影視、2018-2019年)
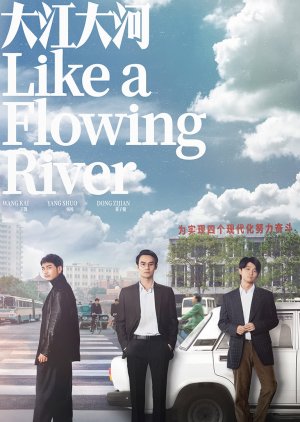 久しぶりに近現代のドラマが見たいと思い、気になっていた本作にした。物語は1978年の夏、緑豊かな農村から始まる。宋運萍(萍萍)と宋運輝(小輝)の姉弟は、同時に大学入学資格を手に入れる。しかし村の役人は、宋家の父親の出自がよくない(労働階級ではない)ことを理由に二人の進学に横槍を入れる。志を曲げない小輝は、共産党が全ての人民に大学進学を許可したという「人民日報」の記事の暗誦を繰り返し、ついに「一人だけ」進学の許可を得る。萍萍は弟に進学の機会を譲り、両親のもとに残る。
久しぶりに近現代のドラマが見たいと思い、気になっていた本作にした。物語は1978年の夏、緑豊かな農村から始まる。宋運萍(萍萍)と宋運輝(小輝)の姉弟は、同時に大学入学資格を手に入れる。しかし村の役人は、宋家の父親の出自がよくない(労働階級ではない)ことを理由に二人の進学に横槍を入れる。志を曲げない小輝は、共産党が全ての人民に大学進学を許可したという「人民日報」の記事の暗誦を繰り返し、ついに「一人だけ」進学の許可を得る。萍萍は弟に進学の機会を譲り、両親のもとに残る。
大学で抜群の成績を挙げた小輝は、巨大な化学プラントを持つ金州化工に就職し、気のいいルームメイトや尊敬できる上司に出会う。現場で先頭になって働き、海外の技術を積極的に取り入れることを進言し、順調に出世していく。工場長の娘の程開顔と家庭を持ち、女の子の父親になった。
一方、村に残った姉の萍萍は、小雷家村の雷東宝に出会う。小雷家は極貧の村だった。雷東宝は生産大隊の副書記(のち書記)として、村を豊かにする方法を必死に探す。承包責任制(生産請負制)について書かれた文書を見つけるが、意味がよく分からない。萍萍の弟が大学生だと聞くと教えを請い、理解すると、果敢にそれを実行に移す。次いで、レンガ焼成窯、電線工場などをつくり、村のために奔走する。萍萍は雷東宝と結婚し、夫を支えながら仲睦まじく暮らしていた。しかし、雷東宝が仕事で村を離れていたとき、身重の萍萍は流産し、本人も身まかってしまう。
呆然自失となる雷東宝。やがて気を取り直し、新たな産業を興し、国営工場と戦い、村民の不満や腐敗を収拾し、豊かになるための奮闘を続けていくが、心の空虚は埋まらない。
前半は、困難に直面してもすぐ解決策が見つかり、根っからの悪人も出てこないので、ずいぶん優しいドラマだと思った。中国人にとって、1970年代末から80年代前半にかけての時代イメージがそうなのかもしれない。しかし前半のほんわか幸せムードに慣れたところでぶち込まれる、萍萍の死の衝撃は強烈で、さすが中国ドラマだと思った。
後半は、小輝を兄と慕っていた少年・楊巡の物語が加わる。10代の若さで商売人を志して東北へ行き、恋人の戴驕鳳を伴って金州に戻って来る。二人は、とにかく金を稼ぐことに必死で、そのことが楊巡の家族との軋轢を生み、楊巡はライバルの罠にはまって、市場も戴驕鳳も失うが、立ち直って、再び商売に没頭する。なぜそんなに金儲けにこだわるのか?と雷東宝に聞かれて「他人に尊重されて生きるため」と答える。
主人公の小輝(王凱)は、とりあえず本編の最後まで大きな失敗はない。雷東宝(楊爍)は、妻の死という大きな喪失感を抱えるが、多くの困難を乗り越え、村に経済的な豊かさをもたらす。この二人は、理想家肌の知的エリートと、学問はないが行動力は抜群の農民という対照的な存在だが、どちらも成功者である。そのまわりには、競争に敗れた者、不幸な偶然に見舞われた者、腐敗に手を染めた者など、多くの「敗残者」が描かれていて、後半は、人生のほろ苦さを感じた。
前半では小輝の陽気なルームメイトだった尋健翔が、新疆の労働改造所に送られ、5年後、すっかり老け込んだ姿で帰ってくる下りは泣けた。また小輝の大学時代の同級生で、同じ金州化工に就職した三叔こと虞山卿も、嫌なヤツだと思っていたが、別れは悲しかった。十分な才能のない人間は、力のある者に取り入って生きていくしかないのだ。
後半で登場する韋春紅は、寡婦の女老板で、雷東宝に惹かれるが、彼の心が今も亡き妻で占められていることを知って、身を引こうとする。韋春紅も戴驕鳳も、時代の荒波の中を必死に生きている点では、男性たちと変わらない。韋春紅役の練練さんは『趙氏孤児案』の宋香を演じた方。しっかりもののおばさんが似合う。前半で退場した萍萍役の童瑶さんはきれいだったなー。すっぴんにお下げ髪の農村少女姿が、70年代の思い出の中に留まる萍萍にぴったりだった。
原作小説は1978年から1992年までの中国を描いているという。1980年代って、まさに現在の中国社会の基礎が形づくられた時代で、現代日本にとっての1950年代みたいなものなんだろう。視聴前は、もっと共産党のプロパガンダ的なドラマなのかと思っていたが、国の政治状況はほとんど描かれなかった。描かないことが政府の方針なのかもしれないが、実際、地方では、せいぜい県政府までが日常接する「政治」なのかもしれない。
最終回の最後の5分は第2部の予告編で、第2部はさらに緊迫の展開が待っていることが分かった。第2部、実は近々放送と聞いていたのだが、新型コロナウィルスの影響で撮影が延期になっているらしい。早くおさまって、ドラマの続きが見られますように。