○NHK大河ドラマ『平清盛』全50回
大晦日に大河ドラマのことを書くのは、2007年の『風林火山』以来である。あのときは大晦日に総集編の放映があったのだが、『平清盛』総集編はまだ見ていない。
私は元来、平家びいきなので、平清盛が大河ドラマの題材になると聞いたときから嬉しかった。主演の松山ケンイチさんはよく知らなかったし、脚本の藤本有紀さんも知らなかった。人物デザインの柘植伊佐夫さんは『龍馬伝』で知っていたけど、あんまり奇抜なことはしないでほしい、と思っていた。
ともかく私は楽しみにしていたのだが、公式ホームページが立ち上がった頃から「王家」という用語に非難が集中し、なんだか面倒くさいことになった。さらに放映当初から「画面が汚い」「暗くて見にくい」という意見が大きく報道された。私は全然そう思わなかったが、実際「汚いわよねえ」と言っているオバサマの会話を耳に挟んだこともある。これは個人の感じ方なのでいたしかたないだろう。
確かに高平太(若き日の清盛)の人物デザインは、私も「ちょっとやり過ぎ」な感じがした。あと、制作者の意図が、新しいものをつくりたいという気持ちと、分かりやすいエンターテインメントにして、それなりに視聴率も稼ごうという気持ちに分裂して、軸が定まらなかったり、和歌の扱いが粗雑だったり(歴史研究の時代考証とは別に、文学・言語担当の考証がほしかった)、序盤はいろいろ頭を抱える局面もあった。
それでも私は、今まで描かれなかった時代を描きたい、新しい大河ドラマをつくりたい、という制作者のもがきみたいなものを感じて、見続けることができたが、最近の視聴者の見切りの早さには、驚かされた。自分が「分からない」「気に入らない」ものはバッサリ拒否なんだな~。あれでは、異なる社会とか異なる文化を描いた古典文学や海外文学なんて、読めないだろう。ネットで検索しただけの知識で、言葉の使い方や演出のここがおかしい、あそこが変、と言い立てられてもなあ…と思った。
同様に「武士の世をつくる!」と大言を吐きながら、何もそれらしい行動を起こさない、いわゆる「厨二病」と揶揄される状態から、なかなか抜け出せない主人公・清盛に対するバッシングも強かった。あの反応を見ていると、一日も早く大人(空気の読める存在)になることを強いられている今の若者って、可哀想だなあと感じた。むかしは、ゆっくり大人になる人間のほうが、大きな器になると言って、許容され、むしろ尊敬されたものなのに。
序盤の迷走を抜けて、ドラマは、保元・平治の乱あたりから俄然、面白くなってきたが、その頃には、離れる視聴者は離れ尽くし、視聴率は10%前後を低迷し、相変わらず面倒くさいアンチが暴れていた。その頃、Wikiによれば第24回放送(6月21日?)からTwitterを用いて、プロデューサーの磯智明氏が番組解説を行うという取り組みが行なわれた。私はドラマに解説を持ち込むという手法が嫌いなので、正直、これには感心しなかった。しかし、ドラマの各回を見終わったあとで、制作スタッフの解説、出演した俳優さんの話、さらに視聴者の感想を読むのが、だんだん面白くなった。制作者の意図以上にドラマの本質をつかんだ感想があったり、笑えるネタもたくさん盛られていた。後半になるほど、いろいろな「仕掛け」(前半とのつながりや、史実や伝承の借用など)に手が込んできて、私が見逃したポイントを教えられたことも一度ならずあった。
公式ホームページでの情報発信も多くなった。最終回放映の後に掲載された、人物デザイン監修・柘植伊佐夫さんの「キャラクターそれぞれの人物デザイン 総集編+」は何度も読み直した。これ、本にしてほしい。私が最も感銘を受けたエピソードは、盛国の餓死による自害シーン、ただ静かに無表情に座すものと、意識が遠のく寸前に涙がひとすじこぼれ落ちるという2バージョンを撮影し、演じる上川隆也さんも柴田監督も「涙をこぼさない方がより感慨が深い」という意見に一致した、というもの。1分にも足らないようなシーンに、これだけの手間ひまと真剣な努力が注がれていることに感激した。
それから、これは「NHKドラマスタッフブログ」のサイトに掲載されている「【詳報】平家は一蓮托生!『平清盛』最終回パブリックビューイング(2012/12/23)」の記事で、松山ケンイチさんが「僕は自分の部屋に清盛の絵を飾っていて、撮影中は毎日手をあわせてから現場に向かっていました」というのにも驚かされた。「どうやったら彼の強さや大きさを表現できるのかいつも考えていたのですが、演技ではなく、人間としてのレベルを上げないと無理なんだと思います」というのも胸を打つ言葉だった。
繰り返すが、私はもとから平家びいきなので、放送終了後のTwitterを読んでいると「平家嫌いだったのに印象が変わった」「負け犬だと思っていた」というつぶやきが多くて、そんなに(一般的日本人にとって)印象悪いのか…と、あらためて苦笑させられた。でも、このドラマによって平家一門のイメージが少しでも変わるとしたら、泉下の清盛入道も喜んでいるだろう。松山ケンイチさんは、清盛の少年時代から老醜までをよく演じた。最後に武士の志を取り戻し、ぶ厚い金色の裘代(きゅうたい)を脱ぎ捨て、軽やかな単衣に変わった姿は、六波羅蜜寺の眼光鋭い清盛像に似ていなくもなかったと思う。
私はあまりテレビを見るほうではないので、このドラマで初めて知った俳優さんが多かった。特に後半に登場した若手の俳優さんは、みんな役にハマっていた。キャスティングもよかったが、それぞれ役作りに熱心だったように思う。直衣の着こなしや、お辞儀などの所作も非常に綺麗だった。これから先、他の時代劇ドラマで、彼らの活躍を見るのがとても楽しみである。
磯Pの年末最後のツイート「振り返ると『平清盛』は、荒波に浮かんだ船のように、いつ沈んでもおかしくない状況でした。このツイッターの場は、私たちにとって雨雲から時折差し込む、光のような希望を与えてくれました。みなさまのおかげで無事、航海を終えることができました」には、感慨深いものがある。今後のテレビ番組って、意外とこんなふうに(制作者と視聴者の直接交流が普通に)なっていくのかもしれない。
【おまけ】9月に東京銀座の「TAU(広島県のブランドショップ)」で行なわれた最初の「盛絵」展に展示されていたオウムのナイミツちゃん
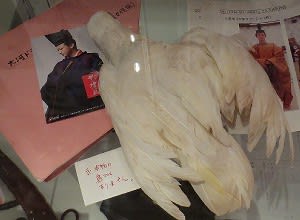
12月23日、NHKスタジオパークの「盛絵」展イベントに登場した磯プロデューサー、柴田ディレクター

ファンが描いた「盛絵」のごく一部。圧巻!

では、そろそろこのへんで、皆様よいお年を。
大晦日に大河ドラマのことを書くのは、2007年の『風林火山』以来である。あのときは大晦日に総集編の放映があったのだが、『平清盛』総集編はまだ見ていない。
私は元来、平家びいきなので、平清盛が大河ドラマの題材になると聞いたときから嬉しかった。主演の松山ケンイチさんはよく知らなかったし、脚本の藤本有紀さんも知らなかった。人物デザインの柘植伊佐夫さんは『龍馬伝』で知っていたけど、あんまり奇抜なことはしないでほしい、と思っていた。
ともかく私は楽しみにしていたのだが、公式ホームページが立ち上がった頃から「王家」という用語に非難が集中し、なんだか面倒くさいことになった。さらに放映当初から「画面が汚い」「暗くて見にくい」という意見が大きく報道された。私は全然そう思わなかったが、実際「汚いわよねえ」と言っているオバサマの会話を耳に挟んだこともある。これは個人の感じ方なのでいたしかたないだろう。
確かに高平太(若き日の清盛)の人物デザインは、私も「ちょっとやり過ぎ」な感じがした。あと、制作者の意図が、新しいものをつくりたいという気持ちと、分かりやすいエンターテインメントにして、それなりに視聴率も稼ごうという気持ちに分裂して、軸が定まらなかったり、和歌の扱いが粗雑だったり(歴史研究の時代考証とは別に、文学・言語担当の考証がほしかった)、序盤はいろいろ頭を抱える局面もあった。
それでも私は、今まで描かれなかった時代を描きたい、新しい大河ドラマをつくりたい、という制作者のもがきみたいなものを感じて、見続けることができたが、最近の視聴者の見切りの早さには、驚かされた。自分が「分からない」「気に入らない」ものはバッサリ拒否なんだな~。あれでは、異なる社会とか異なる文化を描いた古典文学や海外文学なんて、読めないだろう。ネットで検索しただけの知識で、言葉の使い方や演出のここがおかしい、あそこが変、と言い立てられてもなあ…と思った。
同様に「武士の世をつくる!」と大言を吐きながら、何もそれらしい行動を起こさない、いわゆる「厨二病」と揶揄される状態から、なかなか抜け出せない主人公・清盛に対するバッシングも強かった。あの反応を見ていると、一日も早く大人(空気の読める存在)になることを強いられている今の若者って、可哀想だなあと感じた。むかしは、ゆっくり大人になる人間のほうが、大きな器になると言って、許容され、むしろ尊敬されたものなのに。
序盤の迷走を抜けて、ドラマは、保元・平治の乱あたりから俄然、面白くなってきたが、その頃には、離れる視聴者は離れ尽くし、視聴率は10%前後を低迷し、相変わらず面倒くさいアンチが暴れていた。その頃、Wikiによれば第24回放送(6月21日?)からTwitterを用いて、プロデューサーの磯智明氏が番組解説を行うという取り組みが行なわれた。私はドラマに解説を持ち込むという手法が嫌いなので、正直、これには感心しなかった。しかし、ドラマの各回を見終わったあとで、制作スタッフの解説、出演した俳優さんの話、さらに視聴者の感想を読むのが、だんだん面白くなった。制作者の意図以上にドラマの本質をつかんだ感想があったり、笑えるネタもたくさん盛られていた。後半になるほど、いろいろな「仕掛け」(前半とのつながりや、史実や伝承の借用など)に手が込んできて、私が見逃したポイントを教えられたことも一度ならずあった。
公式ホームページでの情報発信も多くなった。最終回放映の後に掲載された、人物デザイン監修・柘植伊佐夫さんの「キャラクターそれぞれの人物デザイン 総集編+」は何度も読み直した。これ、本にしてほしい。私が最も感銘を受けたエピソードは、盛国の餓死による自害シーン、ただ静かに無表情に座すものと、意識が遠のく寸前に涙がひとすじこぼれ落ちるという2バージョンを撮影し、演じる上川隆也さんも柴田監督も「涙をこぼさない方がより感慨が深い」という意見に一致した、というもの。1分にも足らないようなシーンに、これだけの手間ひまと真剣な努力が注がれていることに感激した。
それから、これは「NHKドラマスタッフブログ」のサイトに掲載されている「【詳報】平家は一蓮托生!『平清盛』最終回パブリックビューイング(2012/12/23)」の記事で、松山ケンイチさんが「僕は自分の部屋に清盛の絵を飾っていて、撮影中は毎日手をあわせてから現場に向かっていました」というのにも驚かされた。「どうやったら彼の強さや大きさを表現できるのかいつも考えていたのですが、演技ではなく、人間としてのレベルを上げないと無理なんだと思います」というのも胸を打つ言葉だった。
繰り返すが、私はもとから平家びいきなので、放送終了後のTwitterを読んでいると「平家嫌いだったのに印象が変わった」「負け犬だと思っていた」というつぶやきが多くて、そんなに(一般的日本人にとって)印象悪いのか…と、あらためて苦笑させられた。でも、このドラマによって平家一門のイメージが少しでも変わるとしたら、泉下の清盛入道も喜んでいるだろう。松山ケンイチさんは、清盛の少年時代から老醜までをよく演じた。最後に武士の志を取り戻し、ぶ厚い金色の裘代(きゅうたい)を脱ぎ捨て、軽やかな単衣に変わった姿は、六波羅蜜寺の眼光鋭い清盛像に似ていなくもなかったと思う。
私はあまりテレビを見るほうではないので、このドラマで初めて知った俳優さんが多かった。特に後半に登場した若手の俳優さんは、みんな役にハマっていた。キャスティングもよかったが、それぞれ役作りに熱心だったように思う。直衣の着こなしや、お辞儀などの所作も非常に綺麗だった。これから先、他の時代劇ドラマで、彼らの活躍を見るのがとても楽しみである。
磯Pの年末最後のツイート「振り返ると『平清盛』は、荒波に浮かんだ船のように、いつ沈んでもおかしくない状況でした。このツイッターの場は、私たちにとって雨雲から時折差し込む、光のような希望を与えてくれました。みなさまのおかげで無事、航海を終えることができました」には、感慨深いものがある。今後のテレビ番組って、意外とこんなふうに(制作者と視聴者の直接交流が普通に)なっていくのかもしれない。
【おまけ】9月に東京銀座の「TAU(広島県のブランドショップ)」で行なわれた最初の「盛絵」展に展示されていたオウムのナイミツちゃん
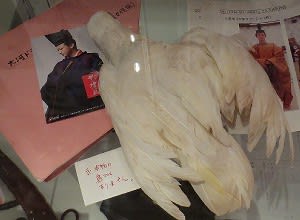
12月23日、NHKスタジオパークの「盛絵」展イベントに登場した磯プロデューサー、柴田ディレクター

ファンが描いた「盛絵」のごく一部。圧巻!

では、そろそろこのへんで、皆様よいお年を。




















