○
日本民藝館 特別展『スリップウェアと西洋工芸』(2012年1月7日~3月25日)
昨年、横浜そごうの『
柳宗悦展』で、とても素敵なスリップウェア(展覧会TOP画像になっている縦縞文様の皿?)を見て、ああ、いいなあと思った。なので、年が明けて、本展が始まるのを楽しみにしていた。
スリップウェア(Slipware)とは、西洋古陶の一種で、日本民藝館のサイトには「18世紀中頃-19世紀末に実用品として作られた英国陶器」と説明されている。西洋一般ではなく「英国」に限る(実際の展示品にはアメリカやオランダの古陶もあった)ということと、意外と時代が新しいことに驚く。ヨーロッパでは、18~19世紀にもまだこんな陶器が使われていたのだとすれば、中国や日本の磁器が熱狂的に迎えられたことにも納得がいく。東洋の白い磁器への憧れから生まれたといわれるオランダ・デルフト焼きのとろりとした白い器も、どんなにか、目にまぶしかったに違いない。
一方で、スリップウェアには独特の魅力がある。ちょっと織部焼に似ていないだろうか。これを古田織部に見せたら何ていうかな~と、脳内で妄想していた。スリップというのは、泥漿(でいしょう、水と粘土を適度な濃度に混ぜたもの)状の化粧土のことで、大胆で軽快な、手描きの幾何学文様が多い。ちょうど鷲田清一さんの仕事論(
だれのための仕事)を読んでいたので、ああ、こういう皿をつくる仕事は、作家として名前の残らない職人の仕事であっても楽しいだろうなあ、と思った。
展示品の皿は、どれも大きくて重たそうだった。どう考えても、個人の「取り皿」ではない。大家族分の肉や野菜をテーブル中央に山盛りにするための皿に見える。たまたま民藝館のコレクションがそうなのか、それともスリップウェアの個人皿って、あまりないのかな。小さめのピューター皿(17世紀、オランダ)が出ていたが、錫(ピューター)は、銀に次ぐ高級品だったみたいだし。当時の庶民の食卓風景がよく分からない。
2階の階段裏の展示ケースには、英国中世(13~16世紀)の壺が並んでいて、私はこれらがスリップウェア以上に気に入った。ちょっと伊賀焼っぽいとも感じた。大展示室で見た大きな壺(フランス、18世紀)も印象的だった。全体を覆う緑釉の剥落具合が水玉模様みたいで、草間彌生を思わせた。
陶磁器の間には、ガラス瓶や布・革製品、木工品(椅子がたくさん置いてあるのに、座れないのがちょっとストレス)などの西洋工芸品も出ていて、珍しかった。中でも目についたのは、西洋古書である。聖歌の楽譜や聖書の断簡が、まるで古筆切のように、額に入れて、ところどころに飾られている。彩色の写本もあれば、版本もある。版本は紙だったが、彩色写本の素材は、紙ではなくて羊皮紙らしかった。こういうとき、民藝館の展示は、こちゃごちゃした解説がないので、自分の目で確かめなければならない。判断は難しいが、緊張感があって、楽しい。断簡だけではなくて、17世紀のグレゴリオ聖歌の楽譜本(金具つきの白総革装)も飾られている。少し汚れてくたびれた感じが、実際に「使われてきた」歴史を感じさせる。なるほど、西洋古書も「民藝」なんだなーと面白かった。
特別展示以外では、「祝い」の工芸をテーマとする室に、三春人形や鴻巣人形を展示。新春らしい。奈良絵の文書の女性がしりあがり寿の絵に似ていた。1階の火消し装束の革羽織(西洋工芸の革製品との関連を意識したかな?)も面白かった。
この日は、入館券購入の際、「今日は西館も御覧いただけます」と言われて、チケットを2枚渡された。おお、そうだったか! 西館、つまり旧柳宗悦邸の定例公開(現在は、展覧会開催中の第2水曜、第2土曜、第3水曜、第3土曜)が始まったのは、いつだったか。私は、かなりたびたび日本民藝館に通っているリピーターだと思うが、今まで一度も公開日に当たらなかったのが不思議である。
西館(旧柳宗悦邸)の間取りは
民藝館のサイトに公開されている。入ってすぐ、思わず声が出てしまったのは、玄関に私の好きな『開通褒斜道刻石(かいつうほうやどうこくせき)』の拓本が飾られていたこと。ホームページの写真(拡大図)の狩猟図(?)の向かい側が拓本だった。
展示順路は2階から。中央の書斎は写真より狭い感じ。ここには(公開の間)職員が常駐している。机まわりに木喰仏とか飾ってあったかな。書棚にばかり気をとられて、並んでいる本のタイトルを舐めるように眺めてしまった。石田幹之助の『長安の春』があるとか、『ドクトル・ジバコ』があるとか。最上段の和装本は何だろ~とか。1階の食堂は洋間と和室がくっついていて、和室には床の間があり、リーチの山水文大皿が飾ってあった。
入館前に、西館入館券を記念撮影。撮っておいてよかった。入館するとすぐ、チケットは取り上げられてしまった。
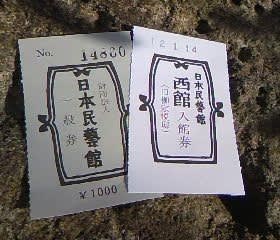






 いま日本で最も有名な経営者、ソフトバンク代表取締役社長の孫正義の評伝。正義個人の生い立ちを超えて、その父母と兄弟たち、さらに祖父母の生涯を、粘り強い取材で、次々に明らかにしていく。1世紀にわたり、命をかけて玄界灘を往還した人びとの物語。その怒涛の展開、よくも悪くも登場人物の「キャラ立ち」ぶりは、安っぽいドラマのシナリオなど、吹き飛んでしまうほど熱くて濃い。いやもう、孫正義なんて、ぜんぜん常識人じゃないか、と思えてくるほどである。失礼ながら、私は孫正義のお父ちゃん・三憲氏の破天荒ぶりが大好きになってしまった(写真、孫さんに似てるな~)。なお「あんぽん」とは、朝鮮から渡ってきた孫一族が日本で名乗った「安本」姓のこと。
いま日本で最も有名な経営者、ソフトバンク代表取締役社長の孫正義の評伝。正義個人の生い立ちを超えて、その父母と兄弟たち、さらに祖父母の生涯を、粘り強い取材で、次々に明らかにしていく。1世紀にわたり、命をかけて玄界灘を往還した人びとの物語。その怒涛の展開、よくも悪くも登場人物の「キャラ立ち」ぶりは、安っぽいドラマのシナリオなど、吹き飛んでしまうほど熱くて濃い。いやもう、孫正義なんて、ぜんぜん常識人じゃないか、と思えてくるほどである。失礼ながら、私は孫正義のお父ちゃん・三憲氏の破天荒ぶりが大好きになってしまった(写真、孫さんに似てるな~)。なお「あんぽん」とは、朝鮮から渡ってきた孫一族が日本で名乗った「安本」姓のこと。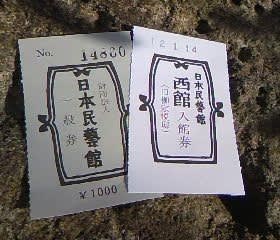
 あるべき労働とは何か。この問いは、ほとんど、あるべき人生とは何か、という問いに重なる。この問いをめぐって、精緻で誠実な分析が続いていくのだが、しばらく読み進んでから、かすかな違和感を感じて、原著の刊行年を確認した。1996年刊。当時すでに社会人だった私からすれば「わずか」15年の間に、日本人の「労働」観は、かなり変わってきているのではないか。
あるべき労働とは何か。この問いは、ほとんど、あるべき人生とは何か、という問いに重なる。この問いをめぐって、精緻で誠実な分析が続いていくのだが、しばらく読み進んでから、かすかな違和感を感じて、原著の刊行年を確認した。1996年刊。当時すでに社会人だった私からすれば「わずか」15年の間に、日本人の「労働」観は、かなり変わってきているのではないか。 最近、日本史の中でいちばん苦手だった中世についての本をいくつか読んでいるうち、この「摂関政治」の時代が気になり始めてきた。一般に摂関政治とは「平安時代に藤原氏(藤原北家)の良房流一族が、代々摂政や関白あるいは内覧となって、天皇の代理者、又は天皇の補佐者として政治の実権を独占し続けた政治形態」(Wiki)と考えられている。したがって、良房:摂政の始まり→基経:関白の始まり→兼家・道長による最盛期、というふうに、藤原北家の歴代を追って記述されることが多いのではないかと思う。
最近、日本史の中でいちばん苦手だった中世についての本をいくつか読んでいるうち、この「摂関政治」の時代が気になり始めてきた。一般に摂関政治とは「平安時代に藤原氏(藤原北家)の良房流一族が、代々摂政や関白あるいは内覧となって、天皇の代理者、又は天皇の補佐者として政治の実権を独占し続けた政治形態」(Wiki)と考えられている。したがって、良房:摂政の始まり→基経:関白の始まり→兼家・道長による最盛期、というふうに、藤原北家の歴代を追って記述されることが多いのではないかと思う。