○神奈川県立歴史博物館 特別展『五姓田のすべて-近代絵画への架け橋-』
http://ch.kanagawa-museum.jp/index.html
幕末から明治初期、西洋絵画の制作と教育普及に功あった五姓田(ごせだ)派の画家たちを取り上げる。8月に前期を見に行ったのだが、展示替えが非常に多いので、できれば後期も見に行きたいと思っていた。最終日になんとか願いを叶えることができた。
会場の入口には、五姓田派の画家たちの紹介パネルが並ぶ。始祖は初代五姓田芳柳(1827-1892)。その次男が五姓田義松。義松の妹が女流画家・渡辺幽香で、夫の渡辺文三郎も洋画家。二代芳柳は初代の養子。なんだ、みんな家族じゃないか、と驚く。会場には、そんな五姓田家の絵画制作の様子を描いた作品がいくつか出ていた。一見したところ、何の変哲もない日本の家族の肖像である。しつらえは、畳に押入れ、火鉢に鉄瓶。絣や縞の地味な着物。けれども、彼らは、当時の最先端技術とも言うべき洋画の習得に励む集団だった。義松の『五姓田一家之図』に描かれた、少女時代の幽香の、きりりとした意志的なまなざしと、くつろいだ自然なポーズは、とりわけ印象的である。
五姓田義松はスケッチによる自画像を多数残している。25歳でパリに留学し、日本人初のサロン入選という偉業を成し遂げた、若き天才らしい驕慢さが表情によくあらわれている。けれども晩年はこれといった活躍もなく、不遇のうちに没したという。西洋画が、家内工業的な「技術」から、個の表現である「芸術」に移行するあたりで、時代の流れから落ちこぼれたのだろうか。
山本芳翠もパリで本格的に洋画を学んだ。5点ほど並んだ女性像は、どれも美しくて見とれた。しかし、最も印象的なのは『浦島図』だろう。亀の背に乗り、女性のような長い黒髪を靡かせる浦島子。ちょっと寸足らずだが、あやしく腰をS字にひねったポーズを取る。亀のまわりに群れつどう、海のニンフたち。たとえば、ルーベンスが描く神話の世界を、無理やり和風テイストに変換したような作品である。浦島子が胸に抱く、工芸の極地のような薔薇色の玉手箱、背景に浮かぶタージマハルか、トプカプ宮殿のような(?)竜宮城など、興味は尽きない。
おまけ。館内の売店で見つけた企画商品。食べられるカラーインクで画像をプリントした1口サイズのチョコレートである。いや、この絵じゃ売れないだろう(笑)と思いながら買ってしまった。
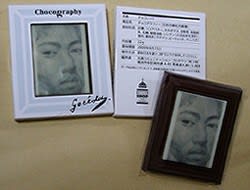
10月から岡山県立美術館に巡回。関西・中国方面の美術ファンの皆さま、おでかけください。
http://ch.kanagawa-museum.jp/index.html
幕末から明治初期、西洋絵画の制作と教育普及に功あった五姓田(ごせだ)派の画家たちを取り上げる。8月に前期を見に行ったのだが、展示替えが非常に多いので、できれば後期も見に行きたいと思っていた。最終日になんとか願いを叶えることができた。
会場の入口には、五姓田派の画家たちの紹介パネルが並ぶ。始祖は初代五姓田芳柳(1827-1892)。その次男が五姓田義松。義松の妹が女流画家・渡辺幽香で、夫の渡辺文三郎も洋画家。二代芳柳は初代の養子。なんだ、みんな家族じゃないか、と驚く。会場には、そんな五姓田家の絵画制作の様子を描いた作品がいくつか出ていた。一見したところ、何の変哲もない日本の家族の肖像である。しつらえは、畳に押入れ、火鉢に鉄瓶。絣や縞の地味な着物。けれども、彼らは、当時の最先端技術とも言うべき洋画の習得に励む集団だった。義松の『五姓田一家之図』に描かれた、少女時代の幽香の、きりりとした意志的なまなざしと、くつろいだ自然なポーズは、とりわけ印象的である。
五姓田義松はスケッチによる自画像を多数残している。25歳でパリに留学し、日本人初のサロン入選という偉業を成し遂げた、若き天才らしい驕慢さが表情によくあらわれている。けれども晩年はこれといった活躍もなく、不遇のうちに没したという。西洋画が、家内工業的な「技術」から、個の表現である「芸術」に移行するあたりで、時代の流れから落ちこぼれたのだろうか。
山本芳翠もパリで本格的に洋画を学んだ。5点ほど並んだ女性像は、どれも美しくて見とれた。しかし、最も印象的なのは『浦島図』だろう。亀の背に乗り、女性のような長い黒髪を靡かせる浦島子。ちょっと寸足らずだが、あやしく腰をS字にひねったポーズを取る。亀のまわりに群れつどう、海のニンフたち。たとえば、ルーベンスが描く神話の世界を、無理やり和風テイストに変換したような作品である。浦島子が胸に抱く、工芸の極地のような薔薇色の玉手箱、背景に浮かぶタージマハルか、トプカプ宮殿のような(?)竜宮城など、興味は尽きない。
おまけ。館内の売店で見つけた企画商品。食べられるカラーインクで画像をプリントした1口サイズのチョコレートである。いや、この絵じゃ売れないだろう(笑)と思いながら買ってしまった。
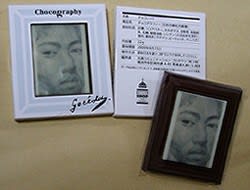
10月から岡山県立美術館に巡回。関西・中国方面の美術ファンの皆さま、おでかけください。















