◆「8月15日」を終戦記念日というか、敗戦記念日というか。いつも悩むところである。終戦記念日というと戦後66年がまったく平和時代だった決め付けてしまわなくてはならないけれど、日本は間接的に米国が行った戦争に加担してきたから、どうも割り切れない。敗戦記念日というと、負けたことへの無念さが感じられ、次の戦争には、必ず勝つぞという何か時代錯誤に陥っている感があり、これも違うような気がしてならない。
しかし、大東亜戦争の犠牲者を冥福を祈る鎮魂の日であるとすれば、ともかく納得できる。それでも、この日を迎えると、マスメディアが、ステレオタイプの報道をして、戦争を回顧するのには、もう飽き飽きしている。特攻隊だの玉砕だの戦艦大和の最期だの玉音盤だの山本五十六だのと、戦後66年にもなるのに変わり映えしない報道をしている。出版の世界でも同様だ。いま必要なのは、これから起こり得る大戦争にどう備えるかであるはずなのに、「悪の戦争経済」を起こそうと策動している動きには、まったく関心を示さないのは、実に由々しきことである。
つまり、戦後生まれの私のように大東亜戦争を知らない世代がすでに70%を超えて、なかには、戦争待望論者さえ増えてきている状況下で、必要なのは、「第3次世界大戦」への備えである。私たちが大戦を食い止めようといかに逆立ちをしても、食い止めることは不可能であるからである。願望と実行とは、計り知れない距離がある。
米国がかかわってきた朝鮮戦争、ベトナム戦争、イラン・イラク戦争、湾岸戦争、アフガニスタン空爆・イラク戦争に対して、日本国民は、ただただ米国を資金援助したり、後方支援するのが、精一杯であった。これからも多分、同じように振舞うしかないだろう。平和憲法下では、他国の戦争には、極力関わらないようにするしかない。いかに反対しても、当事者は聞く耳を持つはずはないのである。また、米国は、引きずり込もうとするだろうが、いろいろ言い訳をして、いかに卑怯だ、ズルイなどと非難されようとも、引っ張り込まれないようにする必要がある。日本のために戦うのは、米軍と韓国軍だけでよい。お任せしましょう。
◆ならば、日本国民は、日本を守るために、どうすればよいのか。軍事力では如何ともし難いので、文化と精神力で勝負するしかない。この66年目の敗戦記念日を迎えるに当り、中曽根康弘元首相が、いいことを言っているのが、大変参考になる。
読売新聞は8月14日付け朝刊1~2面「地球を読む」欄で中曽根康弘元首相の「菅首相退陣へ 国家なき市民主義の限界」と題する論文を掲載し、このなかで、以下のように力説している。
「 安全保障を含めた危機管理について言えば、自民党は長い政権の過去から学んできたが、民主党はあらゆる危機の可能性を研究し、事前の準備を怠りなくする必要がある。「民主主義」を越えた理想と政治理念が必要となる。
国会議員の任務は、国家の運営にあずかることである。国家にはそれぞれ固有の歴史や伝統の個性があり、世界の中でその個性に立って諸国家、諸民族とともに世界の繁栄に貢献となければならない。そして、国家に生きる市民は国家の歴史や伝統から遊離した存在ではない。
国務を担当する政治家の主張が市民生活にのみ焦点を当て、背後にある国家や国民を蔑ろにしては本務に反する。居住地域を大切に生きるとい意味で「市民」という言葉を用いるなら結構なのだが、首相の言葉に歴史や文化の背景が伴わないのでは迫力を欠く。首相は、一国の歴史や文化を背負った存在なのだ。
官政権を通し、民族や国家の歴史の流れを無視した形での、いわゆる歴史的実験ともいうべき「市民主義」の意味が明らかにされ、国家の統治原理としては甚だ不十分である事が示されてきた。
次期政権は、この教訓を生かさなければならない。」
◆南洲翁遺訓「四 萬民の上に位する者、己れを慎み、品行を正しくし、驕奢を戒め、節倹を勉め、職事に勤労して人民の標準となり、下民其の勤労を気の毒に思う様ならでは、政令は行われ難し、然るに草創の始に立ちながら、家屋を飾り、衣服を文(かざ)り、美妾を抱え、蓄財を謀りなば、維新の功業は遂げられ間敷(ましき)也。今となりては、戊辰の義戦も偏へに私を営みたる姿に成り行き、天下に対し、戦死者に対して面目無きぞとて、頻りに涙を催されける」
(現代語訳:全国民の上に立つ政治家や高級官僚など指導者は、自らの生活態度を派手派手しくすることなく、日ごろの言動や振る舞いを正しくして、贅沢三昧の生活ぶりをしないように注意し、勤倹節約に暮らすことに努め、与えられた職務や仕事に専念して、国民全体の模範、手本となり、国民が生活を賭けて働いている苦労を気にかけなくてはならない。そうでなければ、政府がいかに大事な命令や指示を政令として出してても、それが忠実に守られることはできない。だが、まだ明治維新が始まったばかりであるというのに、豪邸を構えて権勢を誇り、服装をきら、びやかに贅沢にして、美しい妾まで囲い、金銀財宝を貯め込むことばかり画策している者が増えているのであれば、明治維新という大きな事業は達成できないだろう。最近は、そういう不心得者の行状ばかり目につく。いまなっては、戊辰の戦いにおいて、世の中を変えようという志を抱いて加わった正義の戦いも、実は私利私欲のためだったととうような姿になってしまい、日本に全体に対しても、戦死者に対しても、本当に申し訳ないことだと、西郷隆盛翁は、しきりに涙を流してられた)
世直しいうにしろ、維新というにしろ、革命というにしろ、その成功の果実は、生き残った者たちが、教享受する。しかし、だからと言って、政権を取った者たちが、権勢を誇り、自分ちちだけの栄耀栄華に酔いしれていては、犠牲になった者たちに顔向けできないと言うことである。
大東亜戦争に敗れた後の第2の開国、いまは、第3開国の時だと菅直人首相は、明言した。その矢先に東日本大地震・大津波・福島第1原発大事故という大事件が起きた。にもかかわらず、菅直人首相は、高価な衣服に身を包み、連日連夜、高級料理店に通い、身内だけで豪華な食事を楽しんでいる。みな、官房機密費で支払っていると言われている。こんな贅沢三昧にうつつを抜かしていて、「市民政治家」とは、ちゃんちゃらおかしいのである。昭和21年10月10日生まれ、戦争を知らない世代の菅直人首相は、第3の開国を唱えるなら、西郷隆盛翁の涙と中曽根康弘元首相の思いを知れ。
本日の「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」
小沢一郎元代表の裁判で、東京地裁が「暗殺防止」のため傍聴席との間に透明なアクリル板設置を決めた背景には、一体何があるのか?
◆〔特別情報①〕
小沢一郎元代表の刑事裁判が10月6日から、東京地裁(大善文男裁判長)で開かれる。資金管理団体「陸山会」の土地取引をめぐり、政治資金規正法違反罪で強制的に起訴された事件である。公判前整理手続きで、2012年1月の通常国会開会前に証拠調べを終わらせる方向で調整、早ければ来春ごろに判決が言い渡される見通しといい、東京地裁は、小沢一郎元代表の安全に配慮し、傍聴席との間に透明なアクリル板を設置するなど警備態勢を強化する。自民党の幹事長や民主党の代表を務めたからという。小沢一郎元代表の命を狙う者とは?。
つづきはこちら→「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」*有料サイト(申し込み日から月額1000円)
メルマガ(有料)での配信もしております。
お申し込みはこちら↓

板垣英憲の過去著書より連載しております↓
『自・社連合が小沢一郎への逆襲をはじめた』1994年7月30日刊
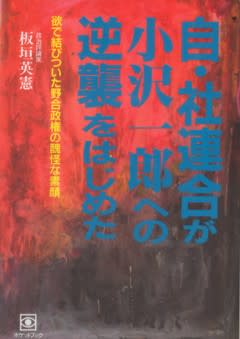
もくじ
3章 社会党が"野合連合"をした裏にあった台所事情
―官房機密費の蜜の味を求めた社会党―
羽田連合政権との決別の断を下した村山富市
「政治家の力量では自民党が勝るが、個人の人格では社会党に及ばない」
中央政界では、むかしからこういう言い方がされてきた。村山富市は、そうした社会党の人材の典型のような人物である。
長い眉毛で好々爺然とした村山富市は、大正十三年三月三日生まれ。十一人兄弟の七番目である。大分高等小学校、東京市立商業学校、明治大学専門部政治経済学科に入り、学徒出陣で陸軍に入隊した。昭和二十一年に明治大学を卒業した。昭和二十八年、二十九歳のときヨシエ夫人と結婚した。
つづきはこちら→「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」*有料サイト(申し込み日から月額1000円)
四王天延孝陸軍中将の名著「猶太(ユダヤ)思想及運動」 No.128
第三章 ロシヤ革命と猶太
前回からの続き
諾代表の試みた報告演説に依つて、螢働者の反政府的運動の最も広く進展して居る所は濁逸であることが判つた。決議文の作成に当たり極端説を唱へたのはレーニン、ラデツク(ユダヤ)、ローザ・ルユクセンブルグ(ユダヤ女)及彼等一味の党友連で、彼等は總同盟罷工とか、怠業叉は武装的叛乱と云つた断然たる手段により、戦争中止のために戦ふべきことを提議した。
つづきはこちら→「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」*有料サイト(申し込み日から月額1000円)
メルマガ(有料)での配信もしております。
お申し込みはこちら↓

板垣英憲マスコミ事務所

ブログランキング
新刊本が増刷(4刷)となりました。全国一般書店にて好評発売中!

「孫の二乗の法則 孫正義の成功哲学」(PHP文庫)
板垣英憲著(←amazonへジャンプします)
ソフトバンクを3兆円企業に育て上げた稀代の起業家・孫正義。その成功の原動力となったのが、自らの人生・経営哲学を「25文字」の漢字に集約した「孫の二乗の法則」である。これを片時も忘れないことで、孫は幾多の苦難を乗り越えてきた。では、私たちが自分の仕事や人生に活用するにはどうすればいいか。その秘訣を本書では伝授する。「孫の二乗の法則」を本格的に解説した唯一の書、待望の文庫化!(本書カバーより)
しかし、大東亜戦争の犠牲者を冥福を祈る鎮魂の日であるとすれば、ともかく納得できる。それでも、この日を迎えると、マスメディアが、ステレオタイプの報道をして、戦争を回顧するのには、もう飽き飽きしている。特攻隊だの玉砕だの戦艦大和の最期だの玉音盤だの山本五十六だのと、戦後66年にもなるのに変わり映えしない報道をしている。出版の世界でも同様だ。いま必要なのは、これから起こり得る大戦争にどう備えるかであるはずなのに、「悪の戦争経済」を起こそうと策動している動きには、まったく関心を示さないのは、実に由々しきことである。
つまり、戦後生まれの私のように大東亜戦争を知らない世代がすでに70%を超えて、なかには、戦争待望論者さえ増えてきている状況下で、必要なのは、「第3次世界大戦」への備えである。私たちが大戦を食い止めようといかに逆立ちをしても、食い止めることは不可能であるからである。願望と実行とは、計り知れない距離がある。
米国がかかわってきた朝鮮戦争、ベトナム戦争、イラン・イラク戦争、湾岸戦争、アフガニスタン空爆・イラク戦争に対して、日本国民は、ただただ米国を資金援助したり、後方支援するのが、精一杯であった。これからも多分、同じように振舞うしかないだろう。平和憲法下では、他国の戦争には、極力関わらないようにするしかない。いかに反対しても、当事者は聞く耳を持つはずはないのである。また、米国は、引きずり込もうとするだろうが、いろいろ言い訳をして、いかに卑怯だ、ズルイなどと非難されようとも、引っ張り込まれないようにする必要がある。日本のために戦うのは、米軍と韓国軍だけでよい。お任せしましょう。
◆ならば、日本国民は、日本を守るために、どうすればよいのか。軍事力では如何ともし難いので、文化と精神力で勝負するしかない。この66年目の敗戦記念日を迎えるに当り、中曽根康弘元首相が、いいことを言っているのが、大変参考になる。
読売新聞は8月14日付け朝刊1~2面「地球を読む」欄で中曽根康弘元首相の「菅首相退陣へ 国家なき市民主義の限界」と題する論文を掲載し、このなかで、以下のように力説している。
「 安全保障を含めた危機管理について言えば、自民党は長い政権の過去から学んできたが、民主党はあらゆる危機の可能性を研究し、事前の準備を怠りなくする必要がある。「民主主義」を越えた理想と政治理念が必要となる。
国会議員の任務は、国家の運営にあずかることである。国家にはそれぞれ固有の歴史や伝統の個性があり、世界の中でその個性に立って諸国家、諸民族とともに世界の繁栄に貢献となければならない。そして、国家に生きる市民は国家の歴史や伝統から遊離した存在ではない。
国務を担当する政治家の主張が市民生活にのみ焦点を当て、背後にある国家や国民を蔑ろにしては本務に反する。居住地域を大切に生きるとい意味で「市民」という言葉を用いるなら結構なのだが、首相の言葉に歴史や文化の背景が伴わないのでは迫力を欠く。首相は、一国の歴史や文化を背負った存在なのだ。
官政権を通し、民族や国家の歴史の流れを無視した形での、いわゆる歴史的実験ともいうべき「市民主義」の意味が明らかにされ、国家の統治原理としては甚だ不十分である事が示されてきた。
次期政権は、この教訓を生かさなければならない。」
◆南洲翁遺訓「四 萬民の上に位する者、己れを慎み、品行を正しくし、驕奢を戒め、節倹を勉め、職事に勤労して人民の標準となり、下民其の勤労を気の毒に思う様ならでは、政令は行われ難し、然るに草創の始に立ちながら、家屋を飾り、衣服を文(かざ)り、美妾を抱え、蓄財を謀りなば、維新の功業は遂げられ間敷(ましき)也。今となりては、戊辰の義戦も偏へに私を営みたる姿に成り行き、天下に対し、戦死者に対して面目無きぞとて、頻りに涙を催されける」
(現代語訳:全国民の上に立つ政治家や高級官僚など指導者は、自らの生活態度を派手派手しくすることなく、日ごろの言動や振る舞いを正しくして、贅沢三昧の生活ぶりをしないように注意し、勤倹節約に暮らすことに努め、与えられた職務や仕事に専念して、国民全体の模範、手本となり、国民が生活を賭けて働いている苦労を気にかけなくてはならない。そうでなければ、政府がいかに大事な命令や指示を政令として出してても、それが忠実に守られることはできない。だが、まだ明治維新が始まったばかりであるというのに、豪邸を構えて権勢を誇り、服装をきら、びやかに贅沢にして、美しい妾まで囲い、金銀財宝を貯め込むことばかり画策している者が増えているのであれば、明治維新という大きな事業は達成できないだろう。最近は、そういう不心得者の行状ばかり目につく。いまなっては、戊辰の戦いにおいて、世の中を変えようという志を抱いて加わった正義の戦いも、実は私利私欲のためだったととうような姿になってしまい、日本に全体に対しても、戦死者に対しても、本当に申し訳ないことだと、西郷隆盛翁は、しきりに涙を流してられた)
世直しいうにしろ、維新というにしろ、革命というにしろ、その成功の果実は、生き残った者たちが、教享受する。しかし、だからと言って、政権を取った者たちが、権勢を誇り、自分ちちだけの栄耀栄華に酔いしれていては、犠牲になった者たちに顔向けできないと言うことである。
大東亜戦争に敗れた後の第2の開国、いまは、第3開国の時だと菅直人首相は、明言した。その矢先に東日本大地震・大津波・福島第1原発大事故という大事件が起きた。にもかかわらず、菅直人首相は、高価な衣服に身を包み、連日連夜、高級料理店に通い、身内だけで豪華な食事を楽しんでいる。みな、官房機密費で支払っていると言われている。こんな贅沢三昧にうつつを抜かしていて、「市民政治家」とは、ちゃんちゃらおかしいのである。昭和21年10月10日生まれ、戦争を知らない世代の菅直人首相は、第3の開国を唱えるなら、西郷隆盛翁の涙と中曽根康弘元首相の思いを知れ。
本日の「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」
小沢一郎元代表の裁判で、東京地裁が「暗殺防止」のため傍聴席との間に透明なアクリル板設置を決めた背景には、一体何があるのか?
◆〔特別情報①〕
小沢一郎元代表の刑事裁判が10月6日から、東京地裁(大善文男裁判長)で開かれる。資金管理団体「陸山会」の土地取引をめぐり、政治資金規正法違反罪で強制的に起訴された事件である。公判前整理手続きで、2012年1月の通常国会開会前に証拠調べを終わらせる方向で調整、早ければ来春ごろに判決が言い渡される見通しといい、東京地裁は、小沢一郎元代表の安全に配慮し、傍聴席との間に透明なアクリル板を設置するなど警備態勢を強化する。自民党の幹事長や民主党の代表を務めたからという。小沢一郎元代表の命を狙う者とは?。
つづきはこちら→「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」*有料サイト(申し込み日から月額1000円)
メルマガ(有料)での配信もしております。
お申し込みはこちら↓

板垣英憲の過去著書より連載しております↓
『自・社連合が小沢一郎への逆襲をはじめた』1994年7月30日刊
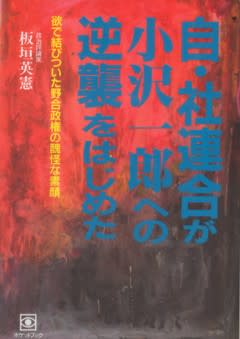
もくじ
3章 社会党が"野合連合"をした裏にあった台所事情
―官房機密費の蜜の味を求めた社会党―
羽田連合政権との決別の断を下した村山富市
「政治家の力量では自民党が勝るが、個人の人格では社会党に及ばない」
中央政界では、むかしからこういう言い方がされてきた。村山富市は、そうした社会党の人材の典型のような人物である。
長い眉毛で好々爺然とした村山富市は、大正十三年三月三日生まれ。十一人兄弟の七番目である。大分高等小学校、東京市立商業学校、明治大学専門部政治経済学科に入り、学徒出陣で陸軍に入隊した。昭和二十一年に明治大学を卒業した。昭和二十八年、二十九歳のときヨシエ夫人と結婚した。
つづきはこちら→「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」*有料サイト(申し込み日から月額1000円)
四王天延孝陸軍中将の名著「猶太(ユダヤ)思想及運動」 No.128
第三章 ロシヤ革命と猶太
前回からの続き
諾代表の試みた報告演説に依つて、螢働者の反政府的運動の最も広く進展して居る所は濁逸であることが判つた。決議文の作成に当たり極端説を唱へたのはレーニン、ラデツク(ユダヤ)、ローザ・ルユクセンブルグ(ユダヤ女)及彼等一味の党友連で、彼等は總同盟罷工とか、怠業叉は武装的叛乱と云つた断然たる手段により、戦争中止のために戦ふべきことを提議した。
つづきはこちら→「板垣英憲(いたがきえいけん)情報局」*有料サイト(申し込み日から月額1000円)
メルマガ(有料)での配信もしております。
お申し込みはこちら↓

板垣英憲マスコミ事務所
ブログランキング
新刊本が増刷(4刷)となりました。全国一般書店にて好評発売中!

「孫の二乗の法則 孫正義の成功哲学」(PHP文庫)
板垣英憲著(←amazonへジャンプします)
ソフトバンクを3兆円企業に育て上げた稀代の起業家・孫正義。その成功の原動力となったのが、自らの人生・経営哲学を「25文字」の漢字に集約した「孫の二乗の法則」である。これを片時も忘れないことで、孫は幾多の苦難を乗り越えてきた。では、私たちが自分の仕事や人生に活用するにはどうすればいいか。その秘訣を本書では伝授する。「孫の二乗の法則」を本格的に解説した唯一の書、待望の文庫化!(本書カバーより)

















