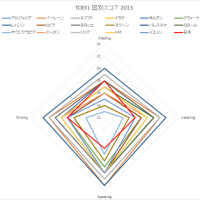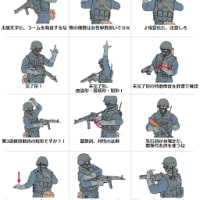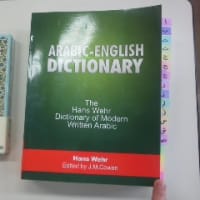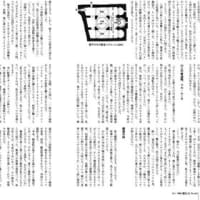Tasbih の話のコメント欄で、お数珠の話が出たので、高校時代、国語の時間に聞いた話を思い出しました。
近松門左衛門が、自分の書いた脚本に、一生懸命に句点を打っているのを見て、ある人が、どうして句点なんかにそう一生懸命になるのかと、せせら笑ったそうです。その人は、お数珠屋さんでした。
そのお数珠屋さんに、門左衛門は、ある日、注文を出したそうです。
「ふたえにして
くびにかけるじゅず」
二重にして首に掛ける数珠!相当に長いお数珠になりますね。お数珠屋さんは、注文通りの長い品を作って、近松邸に届けたそうです。ところが、門左衛門は、私はこんなに長いお数珠を頼んだ覚えはない、と言って、点をひとつ:
ふたえにし、て
くびにかけるじゅず
正解は、「二重にし手首に掛ける数珠」だったのです。
…という話が、どうアラビア語と関係あるのかと申しますと、先月末の会議で、アラビア語の音韻関連の発表があり、こうした区切り場所による解釈の違いの出る実例が、いくつか上げられたからです。
例えば、単語レベルだと、
سل ما تريد sal maa turiidu (彼女が何を欲するのか、尋ねろ)
→salmaa turiidu (サルマーが欲する)
のような例がありますし、或いは、単語の区切れ目ではなく、句の区切れ目ということで言えば、
قال الملك هو صالح
は、1単語目の次で区切って読めば、「彼は言った、その王が正しい」ですが、2単語目の次で区切れば、「その王は言った、彼が正しい」となります。
近松門左衛門が、自分の書いた脚本に、一生懸命に句点を打っているのを見て、ある人が、どうして句点なんかにそう一生懸命になるのかと、せせら笑ったそうです。その人は、お数珠屋さんでした。
そのお数珠屋さんに、門左衛門は、ある日、注文を出したそうです。
「ふたえにして
くびにかけるじゅず」
二重にして首に掛ける数珠!相当に長いお数珠になりますね。お数珠屋さんは、注文通りの長い品を作って、近松邸に届けたそうです。ところが、門左衛門は、私はこんなに長いお数珠を頼んだ覚えはない、と言って、点をひとつ:
ふたえにし、て
くびにかけるじゅず
正解は、「二重にし手首に掛ける数珠」だったのです。
…という話が、どうアラビア語と関係あるのかと申しますと、先月末の会議で、アラビア語の音韻関連の発表があり、こうした区切り場所による解釈の違いの出る実例が、いくつか上げられたからです。
例えば、単語レベルだと、
سل ما تريد sal maa turiidu (彼女が何を欲するのか、尋ねろ)
→salmaa turiidu (サルマーが欲する)
のような例がありますし、或いは、単語の区切れ目ではなく、句の区切れ目ということで言えば、
قال الملك هو صالح
は、1単語目の次で区切って読めば、「彼は言った、その王が正しい」ですが、2単語目の次で区切れば、「その王は言った、彼が正しい」となります。