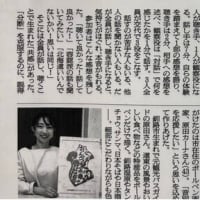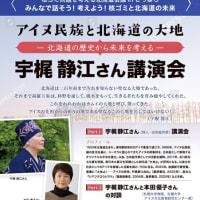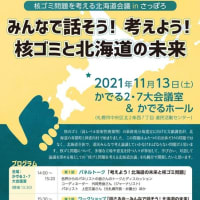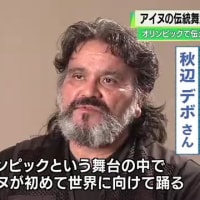チコロナイの植林に参加して
小田博志(札幌市)
きっかけはNHKの番組「あるダムの履歴書~北海道・沙流川流域の記録~」
(ETV特集、2010年2月7日放送)でした。
二風谷ダム裁判の過程を描いたこの力作ドキュメンタリーの最後で、
チコロナイが紹介されたのです。
それを見て僕は、建設的で説得力のある実践だと思い、
いつか参加したいと思うようになりました。
僕が参加している日本平和学会で、全国キャラバンという企画があり、
去年(2012年)の8月30日に北海道大学を会場にして
「脱植民地化のための平和学とは―北海道/アイヌモシリで考える」
というシンポジウムを開催しました。
これは室蘭工大の松名隆さん、清末愛砂さんらと準備を進めたもので、
『アイヌ民族の復権―先住民族と築く新たな社会』(法律文化社、2011年)
という本がヒントになっていました。
室蘭工大での打ち合わせのときに松名さんは貝澤耕一さんにその場で電話して、
すぐに出演の承諾を取り付けてくださいました。
アイヌ民族の復権の現場に立ってこられた貝澤さんが基調講演をしてくださったことで、
このシンポジウムの意義は高まりました。
次の日の二風谷スタディー・ツアーでは、
貝澤さんのご案内でチコロナイの森を見学することができ、
植林を実際にしてみたいという思いが強くなりました。
そして今回、植林を体験してみて、いろいろな出身と立場の老若男女が、
森林の再生への思いを一つにして、二風谷に集う時間はすばらしいと思いました。
何かを育てるということは人を活き活きとさせるものですね。
この運動を立ち上げられた貝澤耕一さんと大阪の「緑の地球ネットワーク」の関係者の皆さん、
運営を担ってこられた理事と事務局の方々に感謝いたします。
大勢の分の食事を用意してくださった貝澤美和子さんをはじめ女性の皆さん、ありがとうございます。
もっとあったらいいかなと思ったのは、アイヌ文化との結びつきでした。
山に入る前にカムイノミをしたら、アイヌと山との関係についてもっと学べるのでは。
オヒョウを植える前か後にアットゥシについて説明があるといいですね。
今後はすでに植えた木々の育成が大事だというお話でしたが、
そこにアイヌの自然との付き合い方を実地で学ぶエコツアーを組み合わせると面白いと思います。
持続可能な未来は、このチコロナイの森から始まる。
それを実感しました。ここは大事なシンボルだと思います。
本当の治水は森林の再生からという貝澤正さんの先駆的な想いが北海道の他の地域にも伝わって、
第2、第3のチコロナイが誕生すること、
そして、それが自然と人間とのつながりを回復する大きい流れに合流していくことを願います。