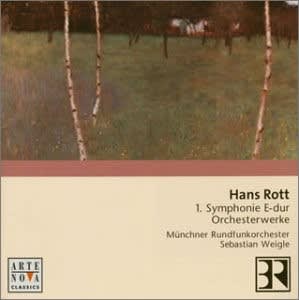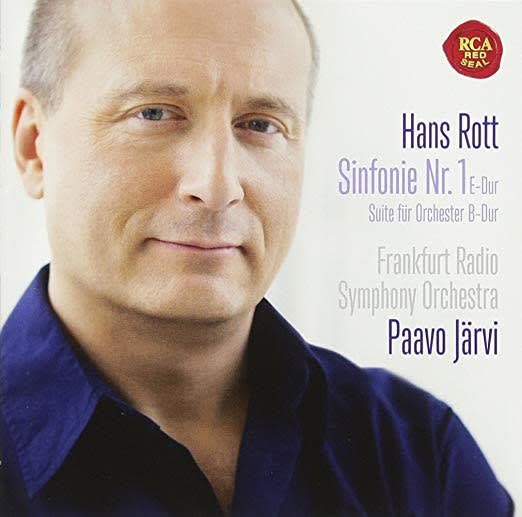きょうは明日のNHK交響楽団とパーヴォのコンサートに備えて、予習もかね、上野の東京文化会館の音楽資料室に行ってまいりました!
実際予習できたのは、ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番だけでしたが、楽譜や、過去の名演奏の研究もでき、大変有意義なものとなりました。
ミニ知識は、またどこかで披歴するとして、きょうは備忘録的に、私がわからなかった音楽用語などを列記して、クラシック初心者の方のための、手引きの一助となれば幸いです。
〇音楽用語一覧
1) moderato (モデラート): 中くらいの速さで
2) con passione (コン・パッシオーネ):情熱的に
3) Un poco piū mosso (ウン・ポコ・ピゥ・モッソ): 少し躍動して
4) Pesante (ペザンテ):重く
5) Allegro(アレグロ):速く
6) Maestoso(マエストーゾ) :荘厳に
7) Meno mosso(メノ モッソ):今までより遅く
8) Adagio sostenuto(アダージオ・ソステヌート): ゆるやかに、音の長さを十分保って
9) Acceler (accelerando アッチェレランド):だんだん速く
10) Presto (プレスト、) 速く急に
11) Pi ū vivo :いままでより大きく、活発に
12) Risoluto (リゾルート):きっぱりと (>ラフマニノフの曲を語る上では欠かせないキーワードだそうです)
〇そのほかの音楽用語
1) 国民楽派;19世紀中ごろから20世紀にかけて、民族主義的な音楽を作った作曲家の総称。主にロマン派時代の作曲家をさす。
例) ロシア楽派:グリンカ、「五人組」(バラキレフ、キュイ、ムソルグスキー、ボロディン、リムスキ=コルサコフ) 1850年~70年代にかけて、ロシア民族の伝統と、民衆生活に根差す、音楽をめざした作曲家
そのほかの国々:ピアソラ、ガーシュイン、コープランド、ハチャトリアン、ヤナーチェク、バルトーク、
コダーイ、シベリウス、ファリャ、グリーグ、ニールセン、スメタナ、ドヴォルザークなど
2) 属音(ぞくおん dominant): 音階中、主音に次いで、重要な音のこと。本来は、「支配的な音」という意味。ヨーロッパの長短調における、主音の5度上の音であった。それに対して、5度下の音は、下属音と呼ばれる。
3) テュッティ(tutti):イタリア語表記による音楽用語で、「全部」の意味。演奏しているすべての奏者が、同時に演奏すること。ソロ(solo)の対義語。オルガンでは、フル・オルガンによる演奏のこと。
4) 調号(ちょうごう、 英:key signature, 独:Tonart-vorzeichning)
五線記譜法で用いる変化記号の一種で、楽曲の調を示す。調子記号と言われる。
例)#、♭、本位記号
5) 移調(いちょう、英:transposition 独:Transponierung)
一つの楽曲を、曲の形式を変えることなく、原調とは、違う調に、音域を移し替える操作のこと。
例)ハ長調⇒ 原曲長3度上方へ移調すれば、ホ長調に。
6) カデンツ(終止形):
楽曲の終止への過程を形成する、音進行の定型。
機能和声における、和音による終止法には、以下の五類型がある。
① 完全終止 さらに、これを正格(全)終止、変格終止に分類できる。
② 不完全終止
③ 半終止
④ 偽終止
⑤ フリギア終止
7) 三部形式:楽曲構成の、基礎的な形式のひとつ。
A(提示部)-B(対照部)-A(再現部) という形式で、各部分のそれぞれ8小節からなるもの。古典派の作曲家たちによって確立。
8) ソナタ形式(sonata form) :もともと、ソナタの第1楽章として発展してきた形式だが、ほかの楽章にも用いられる。
全体は3部分
① 提示部(呈示部)
ある楽曲によって、主題あるいは、それに相当する重要な素材を提示する部分。ソナタ形式で現れる。原則としては、調性や、また性格上も対照的な第1、第2主題の提示がある。
② 展開部 提示部で示された、二つの主題が動機、分割されて、展開される。また、この部分では自由に転調がなされる。楽曲の初めに提示された主題や、重要な楽想のもつ可能性を、種々の角度から引き出し、発展させる部分。ソナタ形式では、提示部の次に位置する。多くの転調がなされる。主題が動機やそれ以下の小さな単位に分割される。または結合されることが多い。フーガでは、主題と応答が各声部に行き渡り、主題が完全に提示される提示部または展開部という。
③ 再現部 recapitulation
ソナタ形式において、提示部、展開部に続く第3の主要部分。提示部の主題と素材が、ほぼ忠実に主調で再現される。三部形式、ロンド形式では同じ用語が用いられることもある。
番外編 コーダ:楽曲または楽章に終結感をもたらすために置かれた結尾部分。規模は大小様々である。
9)ストレッタ(stretto):「押し合った」「緊迫した」の意味。
① フーガでは、ある声部の主題が完結する前に、他の声部が応答して入り、畳みかけるように重なっていく部分及びその手法。
② 加速のテンポで、奏でるオペラのフィナーレの一種。
③ ベートーベンの交響曲第5番以降の器楽の楽章のコーダが、この用法が用いられる。
このほか、きょうの資料として、参考にしたのは、以下の通りです。
1) 映像:ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮、アレクシス・ワイセンベルク(ピアノ)、
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団(演奏)によるレーザーディスク
「ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 作品18」
(ドイツ・グラモフォン社より)

2) 楽譜:
「ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番」音楽之友社 OGT2145 2010年12月10日初刷
(解説:野中一郎)

以上です。
2)の、この楽譜をなんとか読みながら、1)のレーザーディスクを見たのですが、実はこの時の録画・録音が、その後の同曲のお手本となっているという印象を強く受けました。
非常に規格正しく、楽譜に忠実で、格調高いのです。しいていうなら、ロマンの香りというより、第3楽章の最後を飾る、Piū vivo(今までより活発に)、そして、ラフマニノフの曲を語る上で欠かせない用語、risoluto(リゾルート、きっぱりと)という、威風堂々たる楽想を基軸にもってきているので、非常に壮大なファンタジーになっています。
ピアノ協奏曲の域を超えた、ある種交響曲的な風格を備えた名演となっています。
正直、この録画・録音を超える演奏は、なかなかお目にかかったことがないように思いますが、きっとパーヴォのことなので、成算があると思います。
わざわざロシアの俊英ピアニスト・ガブリリュクさんを連れてきたことからもわかるように、きっとすごい仕掛けが待っているのではないかと、楽譜を読みながら、大変ワクワクしました!
そのくらい、超絶技巧を駆使しますし、演奏者すべてにタフネスさが求められている、傑作中の傑作ですね。
明日、明後日の演奏もしっかり拝聴して、パーヴォの起こす「音楽革命」を体感したいと思います!16日は完売ということですので、明日15日(金)、ぜひ、NHKホールにおこしくださいませ!