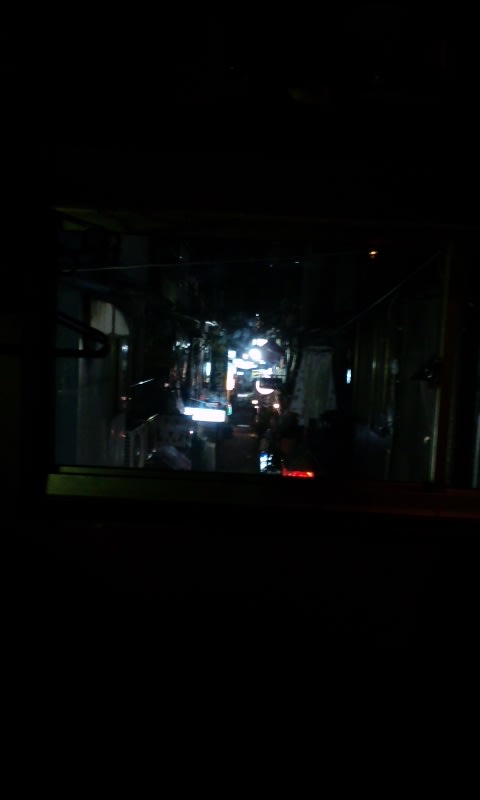敗戦記
小沢一郎流「どぶいた選挙」を闘って(8)
有田芳生
東京や横浜に同潤会アパートが出来たのは、関東大震災後のこと。近代日本ではじめてコンクリート造りのアパートメントが建設された。茗荷谷に建築された大塚女子アパートに、共同浴場、エレベーター、売店、音楽室などが設置されたことは画期的であった。しかし総合的な都市計画のなかったことが、日本全国にいびつな街を作り上げたのである。この国は関東大震災、敗戦という都市整備のための2回のチャンスを逃したまま、いまに至っている。これからでも「人間の顔をした都市計画」を実現することは可能なのだ。
いまの日本には「成熟社会」に対応したモデル住宅が求められている。増加する高齢者への負担があまりにも大きいからだ。デイサービスに向うお年寄りたちは、時間をかけて施設で時間を過ごす。足腰が弱っている人にとっては、迎えの車に乗せられて移動するのは肉体的、精神的に大変なことだ。たとえば居住地(の近く)に24時間対応の浴場施設があればどうだろう。そこにはクリニックや文化施設もあり、大学の公開講座や退職者による各種催しや講座もある。高齢者だけでなく、若い人たち、あるいは現役世代も楽しめるような文化会館も併設される。「成熟社会」に対応した居住モデルとは、何も高齢者のためにだけつくられるのではない。
それを実現するには時代観の大転換が必要だろう。もはや「右肩上がり」の経済成長を求めるのではなく、生活の質を充実させる「成熟社会」の実現こそ目指さなければならない。そのための居住モデルである。阪神・淡路大震災規模の地震や風速80メートルにも耐えうる共同住宅を作るには、まず建築基準法を改正しなければならない。容積率と耐震強度は関係がない。特定地域の容積率を緩和し、緑地を増やして高層住宅を整備する。これは日本国内向けの課題に終わらない。(詳しいことは省略。いずれまとまった形で報告する予定でいる)
専門家によれば、日本の建築は、規格が単一でないために、一棟づつのオーダメイドであり、いわば英国屋でスーツを作っているようなものだという。部品を標準化し、工場生産を取り入れることによって建築費を3分の1にできるという試算もあるという。もちろん建物の色やデザインなどは住民の総意で決めていく。湾岸地域を職住接近の街に開発することで郊外を自然豊かな街に育てていくことも可能だという専門家もいる。
2050年には世界人口は100億人を超える。中国、インド、中東をはじめとして世界中で建築需要がある。日本の技術を総動員して新産業を創設するのだ。マグニチュード8の震災にも耐えるシステムを世界に輸出する。ある専門家は「日本のアポロ計画」だと表現した。中央防災会議が検討した首都直下地震についてのシュミレーションでは、被害総額が約112兆円だとされている。起きてからの被害を想定するのではなく、地震が来ても被害を最小限に抑える施策がいまから求められている。
政権交代したとはいえ、いまの日本に欠けているのは国家目標である。明治維新以来の日本を振り返れば、国家目標のあるときにこそ社会は活性化した。言葉を代えて言うならば、国家目標なき社会は衰退していくのみだ。産業構造を時代に合ったものに作り替えていき、そこに人間らしい街造りを組み込んでいく。「成熟社会」とは「衰退社会」ではないのだ。
板橋での政治活動の1年は、わたしに大きな課題を与えてくれた。過ぎ去った時間をもはやあれこれと振り返ることはしない。2009年夏の選挙で敗北したとはいえ、成熟社会の居住モデルを創造する仕事は、日本から世界へと広がっていく壮大なテーマである。その実現のための新しい挑戦をしなければならない。選挙を終えてそんな思いを抱えながらも眼の前には重い扉がそびえていた。新党日本副代表としての立場に逡巡が芽生えたからである。(続く)