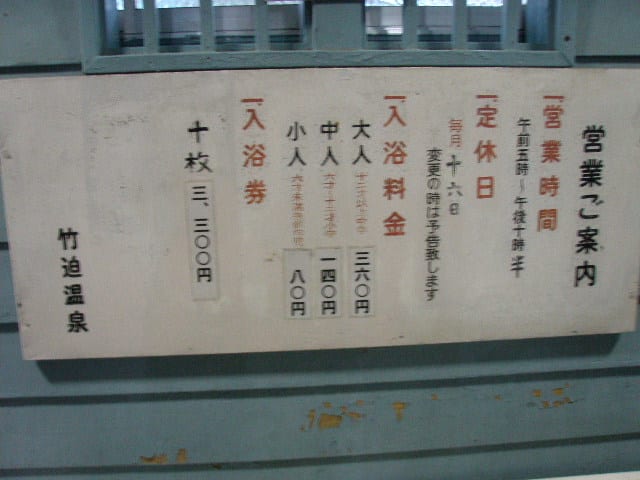4月29日(日)都心に向う連休中の電車は昼間でも人が多い。池袋でパソコンを買う二女に付き合う。本屋にでも寄ろうかと思ったけれど、人ごみを避けてすぐに帰宅。反対方向への電車はガラガラ。早稲田と法政の野球を観ていたら居眠り。単行本『X』の取材計画をたてる。木村久夫さんの上官だった方とようやく連絡が取れた。奈良市と箕面市に健在だった。資料を確認。厚生労働省が12回にわたって検討した「子どもの心の診療医」についての報告書を読む。診療を希望しても1か月から5か月、医療機関によっては何年もの待機を求められる。いまや子供たちの「心の問題」の解決が社会的課題になっているにもかかわらず、専門的に従事している医師は何と70人弱だ。法律が変わらなくとも医師の要請は「やる気」になればできること。南アフリカのワインを飲みながら久々にテレビを見た。NHKの「日本国憲法誕生」と教育テレビの寺山修司特集。「待っていても何も変わらない」というのが47歳で亡くなった寺山のメッセージだ。長田弘さんの『本を愛しなさい』(みすず書房)を読む。最初に取り上げているのは詩人のW?H?オーデン。「子どもは大人の親なんだ」とは詩人ワーズワスの言葉。これを引いたオーデンはこう書く。
わたしたちは成長して、べつの人間になったりしない。おなじ人間が幼児から大人になっていくだけだ。大人とこどものちがいは一つしかない。子どもはじぶんが誰かを知らない。大人はじぶんが誰だか知ってしまった人間だ。じぶんの悩みごとをひとに打ちあけても、それが軽くなるわけでないと悟ったとき、人ははじめて子どもであることをやめるのだ。
ふと子供のころを思い出すことがある。遠くまで来てしまったものだなというよりも、性格は変わらないなという思いがある。たいして意味のない追想。脈絡なく「追憶」の映画と音楽が蘇る。石原慎太郎都知事に会ったときのことを書いたが、大事なことを忘れていた。特攻攻撃の是非について聞いたとき、わたしは戦術としても無謀で、効果もなかったことを統計で示した。アメリカ側の概略統計によれば、特攻機の命中率はフィリピン戦他27パーセント、沖縄戦13?4パーセントで、トータルすると16?5パーセントである。撃墜されたり不時着した機体が多いのだ。石原さんの認識は、あそこまで追いつめられたから「仕方なかったんじゃないですか」という。そうではなく軍部指導者は残忍な特攻攻撃などを採用すべきではなかった。映画では特攻を命じた大西瀧治郎中将が最後に責任を取って切腹したことをリアルに描いている。石原「美学」はそこにあるようだ。そこには強い違和感があるものの、なぜ特攻隊などというファナティックな戦術が生れ、若き貴重な生命が失われていったかを考えさせられるきっかけにはなる。石原映画についてはこのブログのコメント欄に寄せられてるさまざまな意見をぜひ見ていただきたい。