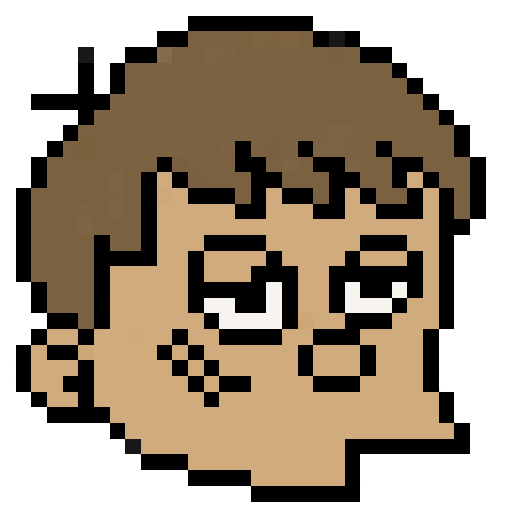例によってとっくに帰ってきているのですが、ひとまず報告まで。
北朝鮮から帰ってまいりました。
今回の訪朝は約5日間。目的は「よど号メンバーへの取材」でした。
もちろん北朝鮮に行くのは初めてでしたが、平壌での滞在は、驚きの連続でした。
今改めてしみじみと振り返るに「あ~ いい街だったなぁ。また行きたい」というノンキな感想なのですが・・・
まぁでもほんとに楽しかった。
楽しかったんだからしょうがない!!!
というわけでわたくし、洗脳されて戻ってまいりました。
取材が目的とはいえ、観光に半分は費やしておりまして。
そこらへんのコントロールはこちらでは効かなかったのでしょうがないのです。
だいたい「平壌観光」といわれるコースで行く場所は殆ど訪れたと思います。
それではざっと、向こうで何をしてきたかを箇条書き。
・平壌観光
・よど号グループとの連合赤軍総括(今回、元・連合赤軍兵士 植垣康博さんが初訪朝)
・絶叫マシーン乗った
・サーカス観覧
・犬食った
・中学校参観
・よど号グループの帰国問題。欧州拉致疑惑とどう闘うか
・よど号グループインタビュー
おいおい、詳細はブログにて書いていきます。
先日交番の前を通りましたら、つい先週まで一緒にいた「よど号グループ」の方々の手配写真ポスターが貼ってありました。
なんだか不思議な気分だなーと思いつつ眺めておりましたが、なるほどこうして見ると反社会的な人達と映るかもしれない。
でも向うで会った彼らは、まったく「普通のオッサン」で、いい人で・・・。
今でも複雑な思いはあれ、訪朝時「拉致をした人達に会いに行く」と警戒して行ったものの、帰国時には「いや、彼らはやってないんじゃないか・・・」と率直に思いました。
そこにはもちろん、約一週間共に過ごしたという「情」もありますが、それだけではない「理由」をインタビューで語って下さいました。
それについてはいつか完成する映画の方で。
北朝鮮から帰ってまいりました。
今回の訪朝は約5日間。目的は「よど号メンバーへの取材」でした。
もちろん北朝鮮に行くのは初めてでしたが、平壌での滞在は、驚きの連続でした。
今改めてしみじみと振り返るに「あ~ いい街だったなぁ。また行きたい」というノンキな感想なのですが・・・
まぁでもほんとに楽しかった。
楽しかったんだからしょうがない!!!
というわけでわたくし、洗脳されて戻ってまいりました。
取材が目的とはいえ、観光に半分は費やしておりまして。
そこらへんのコントロールはこちらでは効かなかったのでしょうがないのです。
だいたい「平壌観光」といわれるコースで行く場所は殆ど訪れたと思います。
それではざっと、向こうで何をしてきたかを箇条書き。
・平壌観光
・よど号グループとの連合赤軍総括(今回、元・連合赤軍兵士 植垣康博さんが初訪朝)
・絶叫マシーン乗った
・サーカス観覧
・犬食った
・中学校参観
・よど号グループの帰国問題。欧州拉致疑惑とどう闘うか
・よど号グループインタビュー
おいおい、詳細はブログにて書いていきます。
先日交番の前を通りましたら、つい先週まで一緒にいた「よど号グループ」の方々の手配写真ポスターが貼ってありました。
なんだか不思議な気分だなーと思いつつ眺めておりましたが、なるほどこうして見ると反社会的な人達と映るかもしれない。
でも向うで会った彼らは、まったく「普通のオッサン」で、いい人で・・・。
今でも複雑な思いはあれ、訪朝時「拉致をした人達に会いに行く」と警戒して行ったものの、帰国時には「いや、彼らはやってないんじゃないか・・・」と率直に思いました。
そこにはもちろん、約一週間共に過ごしたという「情」もありますが、それだけではない「理由」をインタビューで語って下さいました。
それについてはいつか完成する映画の方で。