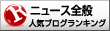13)就職戦線
大学4年の新学期が始まって一週間ほど経ったある日、高村宗男が声をかけてきた。「おい、就職説明会があさって開かれるというが、一緒に聞きに行かないか?」と言う。 新学年がスタートしたばかりだというのに、もう就職の話しが出てくるのかと行雄は“せっつかれる”思いがした。
彼が志望していた出版関係の就職試験は、秋口にならないと始まらないので“のんびり”していたが、高村の目指す新聞社などはもっと早く試験を行なうというのだ。 高村が誘ってきたのと、何か就職の参考になれば良いかと考え、行雄は彼と一緒に説明会に出てみることにした。
当日の午後、就職説明会は本校舎の大教室で開かれたが、出席してみると驚いたことに、超満員の学生で会場は溢れ返っていた。両脇の通路にも学生がぎっしりと詰めかけて身動きが取れないほどだ。何か熱気のようなものが伝わってくる。遅れて行った行雄と高村は、教室の壁に押し付けられるようにして聞くしかなかった。
やがて、講師であるN経済新聞社の某部長が現われ説明会が始まる。眼鏡をかけた小柄で神経質そうな彼は、「日本経済の現状と就職戦線の見通し」と題して話しを始めた。経済成長率がどうのとか有効求人倍率がどうのとか、行雄のような文学部の学生にはまったく縁のない話しが出てくる。
会場に早く来て着席している学生は多分、政経学部や商学部、法学部といった所の者がほとんどなのだろう。講師の話しに熱心に耳を傾けているようで、メモをとったりしているのが多くいた。 行雄には彼の話しは良く理解できなかったが、東京オリンピックを翌年に控え日本経済はまずまずの上昇基調にあるが、就職戦線は未だ厳しいものがあるということらしい。
一時間余りにわたる講演が終って、学生達はぞろぞろと大教室を出ていく。行雄はようやく“人いきれ”から解放される思いがしたが、説明会の熱気に圧倒された余韻が消えない。「すごい人数だったな」と高村に声をかけると、「早稲田は人が多いんだよ」と彼は答える。
「君は新聞社(の試験)を受けると言っていたから、だいぶ参考になっただろう」と聞くと、高村は「さあね、俺は記者になりたいだけさ」と答えた。 二人は外に出ると大隈講堂の方へ歩いていった。「君は出版社を目指しているようだが、今年は採用が少ないようでけっこう大変みたいだな」「そうか・・・」行雄は相づちを打ったが、一抹の不安が胸をよぎる。
「宮部や山西達も出版社を受けると言っていたが、なにせ試験が遅いだろう。もし落ちたら、もう1年大学に残ってしまうのじゃないかと心配していた。もっとも、俺が行きたい新聞社も沢山受けに来るから大変だけどね」 高村の話しに、行雄は就職戦線の厳しさを改めて思い知らされた。
この頃から彼は、就職試験に備えて過去数年間の試験問題集を調べることになった。また、マスコミ関係を受験するのには、どうしても時事問題を知っておく必要があるので、新聞を出来るだけ丹念に読んだりテレビニュースをよく見たりするようになった。
歌舞伎研究会の会合にはたまに出席していたが、百合子とはまったく没交渉で口もきかない。授業で彼女と一緒にいる時も挨拶も何もしないのだから、二人の関係は完全に冷えきっていた。 ある日、行雄が教室でぼんやりしていると、口の悪い宮部進が「君はまるで“老人”みたいだな」と冷やかしてきた。
行雄は一瞬ムッとしたが、いつも生気のない様子で黙々としている自分を顧みると、そう言われるのも無理はないと思い、宮部に返す言葉もなかった。 この時期、彼は意気を阻喪して溌溂とした精神をまったく失い、いつも“悲哀”のうちに過ごしている風であった。だから、老人みたいだと言われるのだろう。これも全て、百合子との関係が上手くいっていなかったからである。
憂愁の日々を送っているうちに、悲哀を忘れさせる催しが開かれた。5月に入ると、文学部で軟式野球のクラス別対抗試合が行なわれたのだ。 もともと行雄は野球が好きだったので、彼はこの対抗試合に飛びついた。日頃の憂さを晴らすには持って来いの行事だ。
クラス委員である彼は、俄然張り切ってメンバーを揃えることになったが、仏文科の学生などというものは個人主義の傾向が強く、団体競技に最も相応しくない連中である。 しかも、ふだん授業に出てこない者が多いため、9人以上の選手を集めるのは一苦労だった。
幸い、ピッチャーは「稲尾はこうやって投げるんだ」と得意気に語っていた徳田誠一郎に決め、キャッチャーには、これも高校時代に少し野球をやっていたという古屋実を当てることにして、なんとかバッテリーを確保することができた。
あとの野手は、誰がどこを守ろうともその日次第ということになり、行雄はライトやセンターの外野の他にも、サードやショートの内野も守ることにした。彼はすっかりやる気になって、父の国義が会社の野球大会で使っていたというユニフォームを借りて出場することにした。
打順やポジションは監督役のクラス委員が決めることだが、行雄は絶えず一番バッターで打つことにして打撃ボックスに入った。 ユニフォームを着ているのは敵味方を通じてほとんどいなかったから、どうも目立つらしい。口うるさい宮部が「村上は全学連のデモの時よりも張り切っているぞ」と“ちゃかす”のだった。
柔弱な学生の多い文学部の中では、早めに準備や態勢を整えた仏文科Bクラスのチームはわりに強かったようだ。 一回戦の独文科Aチームを難なく打ち破り、二回戦はエースの徳田がアルバイトで急に休んだので慌てたが、高村、橋本、宮部らの継投で国史科Bチームをなんとか下した。
キャッチャーで四番バッターの古屋は、さすが高校時代に野球をやっていただけに、大柄でがっちりした体格を活かしてホームランを含む長打を連発した。リードオフマンの行雄もシュアなバッティングでヒットを2本放ち、また選球眼を活かしてフォアボールを選んでは出塁した。
三回戦の相手は、強敵と目される国文科Cチームだった。しかし、この時は徳田がマウンドに復帰し安定した投球をしたので、緊迫した投手戦のゲームになったが2対1の僅少差で勝つことができた。 もっとも、前回アルバイトで欠場した徳田に対しては、行雄らメンバーが「勝手に休むなよ」と釘を刺したのである。
この頃になると、勝ち進んできたためにクラス内の意気が揚がってきた。特に“主砲”の古屋は、苦戦した三回戦でも決勝のタイムリーヒットを打っただけに「このままいけば優勝だ!」と気勢をあげる。それを聞いていた堀込恵子が「頑張ってね、私達も応援に行くわ」と、ニコニコ笑いながら声をかけてきた。 しかし、彼女の後ろに座っている中野百合子は、何の関心もないかのように押し黙って俯いていた。行雄は内心、面白くない女だなと思った。
準々決勝の相手は社会学科Aチームだったが、これも古屋、橋本、高村らが良く打ったので快勝した。行雄も盗塁したりスクイズバントを決めるなど小技を発揮して勝利に貢献したが、この日は打撃の方はそれほど良くなく、また盗塁した時に足を少し挫いた。しかし、プレーをしている時は楽しいもので、全ての憂いは消し飛んだ感があった。
数日後、大学近くの某私立高校のグラウンドを借りて、準決勝の試合が行なわれた。相手は優勝候補と目される英文科Bチームである。このチームはそれまで圧倒的な強さを発揮して勝ち進んできており、高校時代に野球をやったり、草野球に興じるメンバーが何人もいるようだった。
しかし、こちらも古屋や徳田のような経験者を擁している、絶対に負けるものかという意気込みで試合に臨んだ。 プレーボールになると、駆けつけた堀込や渡辺悦子、山西美佐らのクラスメートも盛んに声援を送ってくれる。こんなことは滅多にない。仏文科Bチームは燃えるような気持になった。
一回の裏、こちらの攻撃となり行雄が左のバッターボックスに入ると、彼女らの応援の他に私立高校の女生徒までが校舎の屋上から“黄色い”喚声を送ってきた。彼は少し照れ臭くなったが、相手のピッチャーと向かい合った。素晴らしいストレートやカーブが来る。アウトコーナーを衝くボールに手を出し、第一打席は三塁ゴロに倒れた。
見事な制球力を持つ相手ピッチャーに、仏文科Bチームはなかなかヒットが出ない。徳田も良く投げていたが、味方のエラーもあって三回に2点、四回に1点を取られる。 こちらは三回裏に初めてヒットが出て、次の打者もフォアボールを選んで出塁、行雄の当たり損ねのショートゴロの間にようやく1点が入った。
この後、英文科Bチームは六回に2点を追加、こちらは五回のチャンスに1点止まりで、向うが優勢のまま最終回の七回裏を迎えた。クラスメートの女の子達は、相変らず熱心に応援してくれる。 最終回、相手のピッチャーに少し疲れが見えたところでこちらが1点を追加、二死だがなおランナーが二、三塁のところで行雄に打順が回ってきた。
彼は球速がやや衰えたストレートに的を絞り、3球目を強振した。ボールはピッチャーの頭上を越えてセンター前のヒットになり、三塁ランナーが生還、二塁ランナーも三塁を回って一気に本塁に突っ込んだが、センターの好返球によってタッチアウト、ゲームセットとなった。試合は英文科Bチームが5対4で勝ったのである。
準決勝で敗退したのは残念だったが、行雄は野球を思う存分やれて楽しかったし満足していた。主砲の古屋は、この日はあまり活躍できなかったので悔しがっていたが、メンバーは皆、クラスメートの女性が最後まで応援してくれたのが嬉しかったようだ。
翌日、野球で高揚した気分が抜けない行雄は、応援に来なかった百合子に宛てて“これ見よがし”に手紙を出した。極めて子供っぽい振舞いではあったが、彼は自分の活躍ぶりを自慢げに披露した上で、彼女の親友である渡辺悦子が応援に来ていたというのに「なぜ中野さんは来なかったのか、残念である」と、皮肉を込めて書いたのであった。
野球大会が終るとやっと落ち着いた気分になり、行雄は学年末の卒業論文をどうするか、そろそろ題目を固めておかないといけないと考えた。高村はバルザックに決まっていたが、徳田に聞いてみると、彼も中山教授との関係ですでにポール・エリュアールに固めていると言う。
行雄は高校時代、ロマン・ロランから強い影響を受けたこともあって仏文科に進学してきたので、当初はこの文豪をテーマに卒論をまとめようと考えていたが、百合子との関係で自分の“堕落ぶり”を嫌と言うほど体験したため、自分はロマン・ロランのような高貴な人を扱うにはまったく相応しくないと、考えを改めていた。
このため、もっとポピュラーで親しみやすい作家が良いのではと思い、アルベール・カミュやアンドレ・ジッド、アンドレ・マルローらを視野に入れて考えていたが、橋本がマルローをやると聞き、カミュについては宮部の他に何人もの学生が取り組むというので、次第にアンドレ・ジッドでもやろうかという気持になった。彼は卒論の題材で、他のクラスメートと同じになりたくないと考えたのだ。
そんなことを考えているうちに、6月中旬のある日、行雄は文学部の掲示板にO製薬会社の新入社員募集の案内を目に留めた。そこには採用試験の日程などが記されていた。 彼は就職試験シーズンが到来したことを肌で感じ、試しに受験してみるのも良いかなと思ったが、マスコミ関係ではないので見送ることにした。
それから数日して掲示板を見た時、行雄はハッとして立ち止まった。そこには、東京のFテレビ局の就職案内が出ていたのだ。よく読むと、7月上旬に法政大学の会場を借りて就職試験を実施すると書いてある。 マスコミ関係では初めての求人案内だ。彼は出版社を目指していたが、同じマスコミなら受験してみるのも良いかと考えた。
念のためクラスメートと話してみると、宮部らの他に、新聞社志望の高村までがFテレビ局を受けてみると言う。これで行雄も決心がついた。 そうと決まると、彼は卒業論文のことなどはすっかり忘れて、マスコミ受験に必要不可欠な「時事問題集」などを読み始めた。受験するからには、合格してやるぞという気持になっていたのだ。
やがて、Fテレビ局の採用試験の日が来た。行雄は高村や宮部と共に、試験会場となる法政大学に赴いた。受けに来た学生は千人ほどいるのだろうか、試験は幾つかの教室に分散して行なわれた。行雄は高村と同じ試験会場だったが、宮部は他の会場へ行った。
出てきた時事問題の中には事前に勉強したものも相当あり、行雄は「しめた!」と思ったが、分からないものや難しい出題も少なくなかったので、結果に自信は持てなかった。 しかし、外国語の受験では英語、フランス語、ドイツ語の中で、フランス語を選択して受けたところ、それほど難しいとは思わなかった。
その他の課目の出題も受けて試験が終ると、行雄は高村、宮部と一緒に帰路についた。宮部と行雄はまずまずの出来だという感触でいたが、高村は「いやあ、けっこう難しかったな。でも、新聞社の試験の予行演習だと思えば参考になったよ」と、さばさばした表情で語った。
Fテレビ局の試験を終えて、行雄はアンドレ・ジッドのフランス語の文献を集め始めた。翻訳本ではジッド選集を持っていたが、原文もある程度読んでおかないと格好がつかない。丸善書店や紀伊国屋書店に出かけて、「地の糧」や「背徳者」「狭き門」などポピュラーなものから集めていった。
ジッドの文章は平易で分かりやすく、フランス語の“見本”みたいなものだから行雄は好きだった。これなら自分でもそれ程苦労しなくても読めると思ったが、いずれにしろ就職がどうなろうとも、卒論を仕上げないと卒業できないのだから、まずは引用しやすいポイントの文章を洗っていくことにした。
法政大学での試験から一週間ほど経って、Fテレビ局の社屋で一次試験の合格発表が行なわれることになった。新宿区河田町にある社屋を訪れると、建物の外に掲示板が設置されていて、合格者の受験ナンバーの一覧表が貼り出されている。
千人ほども受験したのだから、不合格になっても気を落とすまいと自分に言い聞かせながら、行雄は掲示板に近づいた。何人かの学生も見に来ている。少し緊張していたが、ダメでもいいと思いながら一覧表に目を通していくと、自分の受験ナンバーが載っていたので行雄は「やった~!」と感じた。合格者は全部で60人ほどいる。
一覧表の脇に、合格者が二次試験の「面接」を受けるための手続きなどが記されていた。彼はすぐに「そうか、まだ面接が残っているぞ」と自分に言い聞かせた。これで合格ではない、最終的な合否はまだ先のことなのだ、就職試験とは面倒臭いものだと思わざるを得なかった。
一次試験の結果は、宮部も高村も不合格であった。宮部は手応えを感じていただけに残念がっていたが、高村は「いい勉強になった」と言って気にも留めていなかった。 行雄は母にFテレビ局の一次試験に合格したことを告げると、久乃は「それなら、すぐに石山さんの所へ行きましょう」と言う。
彼にはそんな気持はまったくなかったが、石山というのはFテレビ報道部の副部長で、行雄の兄・国雄の早稲田大学時代の先輩だから、二次試験の面接で便宜を図ってもらうために伺おうというのだ。行雄は「そんなことをしなくてもいいじゃないか」と反論したが、久乃はどうしても一緒に行こうと言う。
母が熱心に促すので、“世間知らず”の行雄もとうとう折れて石山の家へ伺うことになった。 行雄は石山太郎と面識があった。それは彼の小学、中学時代に、石山が国雄の案内で何度か村上家に来たことがあるからである。国雄が大学の雄弁会で石山の世話になっているというので、父の国義が彼と談笑しているのを見たことがある。
また中学時代だったか、当時ラジオのN放送局報道部員だった石山が重いデンスケ(録音機)を担いでやって来て、何のテーマだか知らないが街の声を取材したいからと言って、国雄にインタビューしていたことがあった。 行雄はそんなことを思い出しながら日曜日の午後、久乃に連れられて東京・中野区内の石山の家を訪れた。
彼は背が高くて痩身だったが、昔と同じように目がギョロリと輝き精悍な顔付きをしていた。年の頃は36~7歳といったところだろうか。「Fテレビを受けるのなら、早く言ってくれれば良かったではないですか」 快活な声を上げて彼は久乃に語りかける。「いえ、この子はなにぶん何も話しませんので」と久乃が答えた。
彼女はこの後、息子が二次試験の面接を受けるので、型通りに「宜しくお願い致します」と挨拶してから石山と雑談を交わした。 国雄の生活ぶりや彼の家族の話題が中心だったが、やがて石山は、国雄と一緒に父の国義から酒をご馳走になったことなど昔話しを持ち出して、久乃と談笑していた。
そのうちに話題はテレビのことに移った。「ところで、行雄君はテレビ局に入って何がしたいの?」 石山の問いにすぐには答えられなかったが、何か言わなければならない。「僕は文学部なので、ドラマとか・・・ドキュメンタリーみたいなものをやりたいのですが」行雄が辛うじて答える。別に明確な目標があってテレビ局の試験を受けたわけではない。
「ふむ、ドラマね・・・」石山の顔に一瞬、怪訝(けげん)な表情が浮かんだ。彼は報道の副部長だから、ドラマなどには関心がないのだろうか。行雄はそう考えたが、他に答えようがない。 仕方がないので「まだはっきりした目標はありません。テレビ局に決まったわけではないので」と続けると、石山が笑い出した。
「そりゃあ、そうでしょう。いろいろな職場の研修を受けていくうちに、大体の方向が決まっていくものですよ、お母さん」彼は久乃の方を向いて語った。彼女はまた「なにぶん宜しくお願い致します」と返事をするのみだった。
石山の奥さんがテーブルに二度目のお茶を運んできて、今度は4人で四方山(よもやま)話しとなったが、一時間ほどして久乃親子は席を立つことになった。 帰宅の途中で行雄が「石山さんにあんなお願いをして、迷惑だったんじゃないの」と文句を付けると、久乃は「親しくさせてもらっている人に何も知らせないのは、かえって相手に失礼なことなのよ。それが“世間”なの」と答えた。
それから数日して、Fテレビ局で第二次試験の面接が行なわれた。会社の中堅幹部と見られる5人ほどの面接担当者が、あれこれと質問してくる。 行雄はできるだけ背筋を真直ぐに伸ばして、口頭試問に答えていった。テレビ局で何をやりたいかという質問に対しては、「ドラマ作りをしたい」とはっきり答えた。
事前に身上調書を提出させられていたので、それに基づく質問も幾つかあった。少し戸惑ったのは、眼鏡をかけた“理屈っぽい”感じの担当者が「君の思想信条の欄には『汎神論』と書いてあるが、『汎神論』とは何なのか、分かりやすく説明してほしい」と質問してきたことだ。
そんなことまでは聞かれないだろうと思っていたから、行雄はやや緊張して答え始めたが、説明しているうちに時間がどんどん過ぎていくような気がして、もっと簡潔に答えられないものかと焦ってきた。それでも腹を固めて丁寧に説明を終えると、その担当者はニヤリと笑った。少し嫌な感じがしたが、詮ないことである。
他の質問にはだいたい要領よく端的に答えたつもりだが、「汎神論」の時の答弁が長すぎたようで、面接試験の後それだけが気がかりだった。 しかし、第二次試験の結果発表は早かった。2日後には合格者の自宅に電話で通知があり、行雄もFテレビ採用の内定を受けたのである。
彼にはまだ出版社への未練が残っていたが、テレビ局への就職が内定したことで気持は大きく変った。早めに就職先を決めてしまえば、後が楽である。 また出版社の入社試験は秋以降と遅いから、それにこだわってもし落ちたら、就職浪人か留年の恐れが出てくる。
テレビ局も悪くはないと思った。どんな仕事に就かせられるか分からないが、テレビはこれから発展するマスコミ産業だ。その当時、テレビ受像器は一般家庭に急速に普及してきており、前年の昭和37年には、全国のテレビ保有台数は一千万台に到達していた。さらに翌年の東京オリンピックに向けて、保有台数が飛躍的に伸びると共に“カラー化”も実現することが予測されていた。
テレビの将来は大きく開かれていると行雄は思った。 それに、Fテレビの初任給が約3万円というのも魅力があった。この当時の大学卒の初任給は、せいぜい2万円程度というのが相場だったからだ。 とにかく就職が第一である。社会主義流の言葉を借りれば「働かざるもの、食うべからず」だ。行雄はFテレビに入社することを決め家族に伝えると、父母も兄も大いに喜んでいた。