小石川植物園の入り口前で、ジーパンのポケットからジャック・ダニエルの小瓶を取り出しまずは一口。そこに入るのかどうかを逡巡し始めちゃったのだから、またの機会でいいだろう。「じゃあ、播磨坂にでも行くか」と進路を急遽変更。江戸時代、その坂の近くに松平播磨守の上屋敷があったことから播磨坂と呼ばれるようになったと、どこかの掲示板に出ていた。しかし、松平播磨守ってだれやねん?そして、ということは、播磨の国とは直接の関係はないのだろう。播州赤穂浪士と関係があるのかなあと、瞬間、勝手に想像したのだけれども、そういうことではなさそうだ。
K印刷の脇から播磨坂の坂下に出ると、車道は車両通行止めにされている。そして坂上の春日通まで桜並木が続き、花見客で大賑わいだ。しかし、花見の前にトイレに行きたい。坂上に向かって右側のなにかの会館では、子ども向けの体験学習会が臨時に開かれているようだ。どうせそこにはトイレもあるだろうから、ちょいと拝借することにする。「ちょっとトイレ行ってくる」と妻に告げると、「あっ、私も」と夫婦で連れション。その2階に昇って、ジョボジョボジョボジョボ。
男子用トイレに向かって小用をしつつ、勢いよく黄色の液体を噴出している貧弱なわが息子を眺めていると、ジュデス・バトラーが『ジェンダー・トラブル』(青土社)で生物学的な男女の性差なんてものはない、というようなことを述べていたことを思い出した。『ジェンダー・トラブル』自体が大変に難解な書で、いま述べた小生の理解はただの誤解かもしれないし、もしくは彼女の策略に陥っているのかもしれない。しかし、小生に限らず多くの読者が、「こいつはなんちゅうバカなんだ?」と解釈したのも事実だろう。
そこでふと、わが息子は外に飛び出ているけれど、それが内側に入り込めばわが娘となるんだなあと考え出した。つまり、玉々は卵巣であり、陰茎は子宮ということになる。となると、同じ形状のものが外に出ていればオス、内側に出ていればメスという性差が生じるということになる。したがって、結局は同じものなのだから、性差というのは存在するのだろうかと疑問に思ったわけである。
これと同じ話をバトラーが述べていたということわけでは、ない。DNAがどうのこうのと付け焼刃の生物学を展開したような、たいして面白くもない話だったように記憶している。そうではなく、性差がある/ない、という論理はどのように構築されるのだろうかという単純な疑問が、貧弱な息子を眺めつつ湧き起こってきたという意なのだ。男女ともに同じようなものを抱えているから同質だろという主張と、それが外にあるか内にあるかで大きなちがいだろ、という主張があり(ほかにもあるのかもしれない)、そのどちらがより説得性の高い内容を唱えているのだろうか。最近、またバトラーが注目を浴びているせいなのか、妙なことが気になった。
トイレから出ると、体験学習をしている教室の壁に日刊スポーツの号外が張られているのが目に留まる(アレ?スポニチだっけ?)。要するに、スポーツ新聞のいつもの一面トップの体裁で、内容だけ文京区桜祭りの宣伝に置き換えているものだ。それをしげしげ読んでいると、小石川が石川啄木終焉の地であり、その縁で盛岡のナンチャラ祭り(固有名詞を忘れた)が小石川でも行われるらしい。ヘー、知らなかった。しかし、松山で坊ちゃん電車を見かけたときに感じた違和感に似たものを覚えてしまう。
江戸っ子漱石は松山に飛ばされたけれど、松山にはまったくなじめず、その挫折を昇華すべく『坊ちゃん』を著したわけである。そのため、松山きらいという苦々しさこそがあの短編の大意だろう。それを街の観光PRに使うのだから、松山ってバカじゃないかと思ってしまうのはしょうがない。一方啄木の場合、故郷盛岡からは石もて追われた口じゃなかったのか?啄木なんて人間としてはただのダメダメちゃんなのだから、それに石を投げた人を批判したいわけでは、ない。しかし、そういう地元の恥を地元PRに使っていることにはなじめないものを感じるということである。
ところが、そのトイレを借りた会館を出ると、その右手に三陸名物ホタテの姿焼き500円なんていうテントの屋台が出ているではないか。しかもすでに10人ばかりが並んでいる。さっき昼飯食ったばかりというのに、香ばしい匂いが食欲をかきたてる。妻もよだれがたれそうな顔をしていやがる。「あれ食べる?」とたずねると、「美味しそうだねえ」「でも、ふたつはいらないだろう」「そうだね。1個買って二人で分けようか。私が列に並ぶから、あんた、座って食べられる場所どっか確保して」との厳命がくだる。アイアイサー以外の返事はありえない。
車道の脇に場所を確保したつもりで腰をおろしてウイスキーをチビチビなめつつ屋台の様子を眺めていると、小学生の女の子が顔を真っ赤にしながらトングを使って一生懸命にホタテを焼いている。それで味の悪かろうはずはないものの、あえて小学生を使うオトナたちの底意地の悪さも透けて見えてくる。啄木のきらった故郷なるものは、そのオトナたちへの嫌悪だったのかなあと勝手に想像しつつ(つまりは、そんなに啄木を読んでいない)、妻の番になることを待つことになった。
K印刷の脇から播磨坂の坂下に出ると、車道は車両通行止めにされている。そして坂上の春日通まで桜並木が続き、花見客で大賑わいだ。しかし、花見の前にトイレに行きたい。坂上に向かって右側のなにかの会館では、子ども向けの体験学習会が臨時に開かれているようだ。どうせそこにはトイレもあるだろうから、ちょいと拝借することにする。「ちょっとトイレ行ってくる」と妻に告げると、「あっ、私も」と夫婦で連れション。その2階に昇って、ジョボジョボジョボジョボ。
男子用トイレに向かって小用をしつつ、勢いよく黄色の液体を噴出している貧弱なわが息子を眺めていると、ジュデス・バトラーが『ジェンダー・トラブル』(青土社)で生物学的な男女の性差なんてものはない、というようなことを述べていたことを思い出した。『ジェンダー・トラブル』自体が大変に難解な書で、いま述べた小生の理解はただの誤解かもしれないし、もしくは彼女の策略に陥っているのかもしれない。しかし、小生に限らず多くの読者が、「こいつはなんちゅうバカなんだ?」と解釈したのも事実だろう。
そこでふと、わが息子は外に飛び出ているけれど、それが内側に入り込めばわが娘となるんだなあと考え出した。つまり、玉々は卵巣であり、陰茎は子宮ということになる。となると、同じ形状のものが外に出ていればオス、内側に出ていればメスという性差が生じるということになる。したがって、結局は同じものなのだから、性差というのは存在するのだろうかと疑問に思ったわけである。
これと同じ話をバトラーが述べていたということわけでは、ない。DNAがどうのこうのと付け焼刃の生物学を展開したような、たいして面白くもない話だったように記憶している。そうではなく、性差がある/ない、という論理はどのように構築されるのだろうかという単純な疑問が、貧弱な息子を眺めつつ湧き起こってきたという意なのだ。男女ともに同じようなものを抱えているから同質だろという主張と、それが外にあるか内にあるかで大きなちがいだろ、という主張があり(ほかにもあるのかもしれない)、そのどちらがより説得性の高い内容を唱えているのだろうか。最近、またバトラーが注目を浴びているせいなのか、妙なことが気になった。
トイレから出ると、体験学習をしている教室の壁に日刊スポーツの号外が張られているのが目に留まる(アレ?スポニチだっけ?)。要するに、スポーツ新聞のいつもの一面トップの体裁で、内容だけ文京区桜祭りの宣伝に置き換えているものだ。それをしげしげ読んでいると、小石川が石川啄木終焉の地であり、その縁で盛岡のナンチャラ祭り(固有名詞を忘れた)が小石川でも行われるらしい。ヘー、知らなかった。しかし、松山で坊ちゃん電車を見かけたときに感じた違和感に似たものを覚えてしまう。
江戸っ子漱石は松山に飛ばされたけれど、松山にはまったくなじめず、その挫折を昇華すべく『坊ちゃん』を著したわけである。そのため、松山きらいという苦々しさこそがあの短編の大意だろう。それを街の観光PRに使うのだから、松山ってバカじゃないかと思ってしまうのはしょうがない。一方啄木の場合、故郷盛岡からは石もて追われた口じゃなかったのか?啄木なんて人間としてはただのダメダメちゃんなのだから、それに石を投げた人を批判したいわけでは、ない。しかし、そういう地元の恥を地元PRに使っていることにはなじめないものを感じるということである。
ところが、そのトイレを借りた会館を出ると、その右手に三陸名物ホタテの姿焼き500円なんていうテントの屋台が出ているではないか。しかもすでに10人ばかりが並んでいる。さっき昼飯食ったばかりというのに、香ばしい匂いが食欲をかきたてる。妻もよだれがたれそうな顔をしていやがる。「あれ食べる?」とたずねると、「美味しそうだねえ」「でも、ふたつはいらないだろう」「そうだね。1個買って二人で分けようか。私が列に並ぶから、あんた、座って食べられる場所どっか確保して」との厳命がくだる。アイアイサー以外の返事はありえない。
車道の脇に場所を確保したつもりで腰をおろしてウイスキーをチビチビなめつつ屋台の様子を眺めていると、小学生の女の子が顔を真っ赤にしながらトングを使って一生懸命にホタテを焼いている。それで味の悪かろうはずはないものの、あえて小学生を使うオトナたちの底意地の悪さも透けて見えてくる。啄木のきらった故郷なるものは、そのオトナたちへの嫌悪だったのかなあと勝手に想像しつつ(つまりは、そんなに啄木を読んでいない)、妻の番になることを待つことになった。















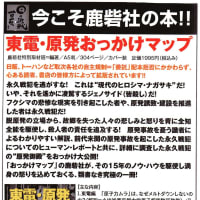




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます