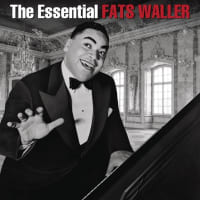ザ・ビートルズの新譜『ライヴ・アット・ザ・ハリウッド・ボウル』を聴いた。
それから、連動企画のように製作されたドキュメンタリー映画『ザ・ビートルズ~EIGHT DAYS A WEEK ‐ The Touring Years』を見た。
どっちも、率直に言って、まあまあだった。
冒頭からいきなりこじれますが、読んで(そうか、まあまあなのか)と思わないでほしい。早飲み込みするひとが、昔から苦手だ。ところが世の中の頭のいい人、センスのいい人、感性の高い人の8割近くはすばやい理解こそを誇りとしているので、常にやりずらい。
まあまあのケタが、ザ・ローリング・ストーンズやザ・フー、ジミ・ヘンドリクスからセックス・ピストルズ、ニルヴァーナまで、ありとあらゆる大物とはもとから違う。この手の音楽ジャンルで、まあまあの意味が他と隔絶しているのは、ビートルズとエルヴィス・プレスリーとボブ・ディランのみ。
これは、個人の好みや、どっちが良い悪いかさえ別の話なのだ。レコードの数だけだったら、僕はビートルズよりストーンズやエルヴィス・コステロのほうが多く持っているかもしれない。繰り返し聴いた回数なら、『アビイロード』より中島みゆき『寒水魚』のほうが断然多い。
カップラーメンをこよなく愛し、中華は脂っこくてマズいと言う人はゼンゼンいていいけど、だからといって四川の歴史をないがしろにする権利までは持たないのと同じ。この大前提は理解したうえで、今回は読んで頂きたい。
1990年代半ばの『アンソロジー』プロジェクト以来、手を変え品を変え、レストアやリミックスなどによる“ビートルズの新作”を提供してきたアップルに対して、それなりに長い時間をかけ、逡巡も重ねた上で言葉にする、まあまあ、である。
もうね、いいですよ。アップル商法は、いったん段落をつけても……という気持ち。
〈21世紀にもザ・ビートルズは偉大であることを伝え、それをセールス面でも証明しなくてはいけない〉
この重たいミッションを、代を引き継ぎながら、アップルはよくまあ、これまで世界のマーケットに向けて遂行してきたと思う。振り返っても、感謝の念ばかりだ。たのしい思いを、ずいぶんさせて頂きました。
でも、とうとう、遂に。まあまあ、のところまで素材の底は見えたと思う。
〈ザ・ビートルズは今の若者が聴いてもカッコいいロックバンドなのだ!!〉というテーゼも、もう限界はあると認めてよいのではないか。
音楽性どうこう以前の問題。すでに遥か昔に解散した、現役じゃないバンドにワクワクしてくれと求めたところで、生理的にムリなのだ。明らかに年齢層がかなり高い角川シネマ有楽町の客席を見まわして、今度こそ本当に、それを実感した。
悲観や皮肉で、さようならアップル商法、と言っているのではない。
〈いまだにビートルズは凄くて、アデルやワンダイにもセールス的に引けを取らないぞ〉
と頑張るプロモーションのコンセプトならば、もう卒業しても、ビートルズは大丈夫、ということだ。
僕はハタチ過ぎる頃まで、ビートルズの公式発表曲は全部持っているのがレコードを聴く人間の基本中の基本中の基本、と心の底から思っていた。そして、よく考えたら該当する人間がまわりにほとんどいないのに気付き、けっこう深刻なクライシスに襲われた。
それでもみんなビートルズをよく知っているし、曲は好き。
むしろもう、読書家における『新約聖書』みたいなもので、〈よく聴くバンド・好きなバンド〉のカテゴリーに入れるほうが、そぐわない。今やビートルズの存在は文化というより、文化的背景の域だから。これ以上の普遍化は無いだろう。
冒頭では撥ねつける書き方をしたものの、歴史的基礎はわきまえてほしい、というだけで。ビートルズなんか、もう、無理に聴く必要は無いのだ。
たまにいらっしゃる「ストゥージズやジョイ・ディヴィジョン、ルー・リードはいいけどビートルズはダサい」などとムキになって突っかかってくる人にも、「あー、さすが。あなた、最高にロック聴くセンスいいからな。あなたならそうでしょうとも」と、あしらう術をいつの間にか身に付けた。
ビートルズとエルヴィスとディランは、ひとつひとつが各論ではなく総論。〈聴かずに死ねるか!〉と言ったら最後、言ったほうがヤボになるトップ3、という括り方もできる。
まあ、ここまで書いたので、中身の話もしようか。パソコンの中の別ファイルに書いたメモを、ひとつにまとめる。
まず、『ライヴ・アット・ザ・ハリウッド・ボウル』のモトになった『ザ・ビートルズ・スーパー・ライヴ![アット・ハリウッド・ボウル]』について。
1977年にリリースされた、ビートルズ初の公式ライヴ・アルバム。ずっとCD化されてこなかった。
以下は、数年前にフェイスブックにあげたのを多少いじった文章。ドキュメンタリーについて考えている時にこのレコードを初めて手に入れた、という道筋で書いている。
―ふだん物書きで個人商いをしているので、映画も本も仕事とつながってくるなか、たまの中古レコード探しは純粋なたのしみです。人と比べたことはないけど、古いロックやポップスに関しては比較的くわしいほうかもしれません。この半年の間に聴いた中古レコードのなかで、いちばんドキュメンタリーを感じたのが、ザ・ビートルズのこれでした。
ビートルズに関しては中学生の頃から耳にし続けています。『ルパン三世』の再放送と『未来少年コナン』以来の宮崎アニメ同様、常にあんまり近すぎてファンかどうかすら、自分ではよく分かりません。
1964年、1965年のアメリカ公演のテープを座付プロデューサーだったジョージ・マーティンがリミックスし(ただしノーダビングとのこと)、解散から7年後の1977年に発売されたザ・ビートルズ(当時)唯一の公式ライヴ・アルバム。
昔は、同級生のお姉ちゃんに聞かせてもらっても「ガチャガチャしてるからいいや」とテープに録音を頼まなかったアルバムでした。今では〈CD化されない有名アルバム〉の代名詞的存在です。ちょくちょく行く店の棚で見つけて飛びつきましたね。しかも中古LPは現在、かなり廉価になっているから助かる。
「ガチャガチャしてる」とは、つまりスタジオのオリジナル録音とはテイクが違うし歓声も入っているから、ということでした。生ものっぽさを未完成と感じて、イヤでしたね。“ドキュメンタリー的表現”に目覚める前の十代の感覚を、むしろ面白く感じます。
ライヴ・アルバムは全部“ドキュメンタリー的表現”として語れるか。そこはまた話は別になると思いますが、本盤にはそう捉えたいところがあります。
まず、そのグループが解散後に発表される〈蔵出し音源もの〉のハシリである点。
録音当時は(あの有名なファンの絶叫で演奏がかき消され)使い物にならなかったものが、新技術によって商品化が可能になった、アーカイブと技術の密接な関係という点でも先駆である点。
そして、後追い世代のビートルズ評価に影響を与える作品となった点です。
解散から発売までの7年の距離に、批評的なおもしろみが幾つも生まれています。
「ビートルズからすべてがはじまった」式の団塊世代ロマンにはけっこう僕も辟易してきましたが、たくさんの音楽関係者が寄稿したLPのライナーノートを読むと、日本におけるビートルズのロマンティックな〈神格化〉はジョン・レノンの夭折以前、70年代からすでに進んでいたことが分かります。
ひいきの引き倒し、うっとりメロメロなコメントが多いなか、あくまでビートルズは1950年代のアメリカでのファースト・インパクトをイギリスに持ち込んだセカンド・インパクト、「第二のロックンロールの時代をもたらした存在」とクールかつ端的に把握しているのは中村とうよう。さすがです。
ビートルズがビッグバンの中心でなきゃ気が済まない。これは〈神格化〉世代のよくないクセで。ビートルズの凄さは逆に、そうじゃないところにあります。
ファンから作り手にまわり、いろいろなジャンルを統括した上で独創を編んだ最初の世代。
演奏に(オレたちはロックンロールが好きだからロックンロールをやっている)というある種の対象化、「自意識」という批評性を持ち込み、ポップ・ミュージックのインフラを刷新した。
結果、いい悪い抜きで、その前のポピュラー音楽はどう聴いても、ビートルズ以前としか聴こえなくなった。
「色が付いちまうから」、アマチュア時代から戦略的にエルヴィスをカヴァーしなかった逸話も含め、精神的なリーダーだったジョンの考えは、映画でいうとシネマ・ヴェリテとヌーヴェルヴァーグに近かったのだと思います。
聴くと、4人が叩き上げのステージ・バンドだったことがよく分かります。
ビートルズといえば音響設備の悪い環境と多忙に嫌気がさして後期は一切ライヴをしなかったことで有名ですが、ソロになりPAが整備された後のポールらのライヴ大好き振りは、本盤を聞けばずいぶん納得できます。
1964年のライヴは『ビートルズ・フォー・セール』録音のあいだのツアーで(そのため時間が無くてあのアルバムはオリジナルが揃えられなかった)、1965年のほうは初夏に『ヘルプ』の録音を終え、秋に『ラバー・ソウル』を始める間。本盤をオリジナル・アルバムの間に置くと、忙しさと変化がずいぶん立体的に見えて面白い。
ロックンロールの遺産を吸収し尽くし、いよいよオリジナル以外のなにものでもない曲想、アイデアが浮かんで止まらない時。1年前のヒット曲なんかもう過去に感じて、早くショーを終わらせてスタジオに入りたい。そんな心境もギラギラと伝わります。
「ボーイズ」のドラムとベースのラウドな立ち上がりは、ダスト・ブラザーズなんかが好きな人もオッとなりそう。「ハード・デイズ・ナイト」はスタジオテイクよりもちょっとスローで重たく、途端にみるみる滲み出るブルースの黒み成分。
それにつけてもの、ポール。虚心で聴いてほしいです。こんだけ異常な、オルタナティヴな“リード・ベース”をうねらせながら、「♪ぼくのサリーはのっぽでかわいい子」と笑顔でシャウトするヒッチャカメッチャカなひとに対して、「ポールはロックじゃない」は、ないでしょう。
ロックな人は“ロック”なだけに頑固だから、説くとかえって依怙地になってしまうのでもう言いませんけど。
以上。そして、未発表の4曲を加え、リミックス/リマスターを施してタイトルが若干変わった、今年の『ライヴ・アット・ザ・ハリウッド・ボウル』についてのメモ。
―『スーパー・ライヴ!』と聴き比べしなくても、大歓声とのミックスの分離の、ヌケの良さは明らか。
映画では、ハリウッド・ボウルはあくまで一部なので、疑似サントラのようなプロモーションはまぎらわしい。でも、公式ライヴのお色直しは、映画と同じタイミングじゃなければ、やりづらかったのだろう。CDと映画の同時リリースで、“アメリカで成功するビートルズ”らしいキー・ビジュアル―西海岸のまぶしい青空の下の4人―を統一しているのは、そういうことなのだろう。
よくよく考えたら、中身はもう(ボーナストラックを除いて)持っているわけで、大カンゲキとはいかなかった。それでも、音がよくなったぶん、面白い。
ポールのベースはもはやフリー・フォーム。リンゴの、パンクの長男みたいな力任せで正確なビートと、別の意味でバンドを引っ張る。いや、ジョンのリズム・ギターも相当。それぞれ個性が強いリードが、三方に向かって強いまま、よくもこんなに調和しているな。
決して、コクのあるライヴ演奏というわけではない。そういう味わいをステージで披露することはかなわないまま解散したバンドだった、と逆説的に語ってしまう皮肉も、この盤の中にはある。
『アンソロジー1』で、すでに初期のライヴがかっこいいことは証明済みなので、僕等より上の世代の風聞「ライヴはへた」は、気にする必要はない。初出となった「ベイビーズ・イン・ブラック」のスローのどろっとした感じは、まっすぐ後期、『アビイロード』につながる。ヘビー・ワルツで、ブルースで。1964年と、いろんな手、アレンジが即座に試せる1965年の間の、進化のスピードこそが味わいどころかも。
このメモで書いてあるように、映画『ザ・ビートルズ~EIGHT DAYS A WEEK ‐ The Touring Years』は、まるでハリウッド・ボウルのライヴ映像が中心になっているかのようなイメージがあるのだが、実際は違い、他にもいろいろなステージが登場する。
ビートルズの歩みをライヴ活動というアングルで絞って編み直してみた、『アンソロジー』外伝、と捉えたほうが正しい。
実は僕が見ていて、いちばん前のめりになった映像は、ハリウッド・ボウルより1年前、マンチェスターでのライヴ。アニマルズやハーマンズ・ハーミッツなどのステージと組み合わせた1964年の音楽映画『ポップ・ギア』からのものだ。『ポップ・ギア』は翌年日本でも公開されているが、ソフト化されていないので、大いに得した気分。国内のショービジネスのエースになった(あとはアメリカ乗り込むのみ)麒麟児たちの勢い、ギラギラと伝わる。
しかし、この公演が映画の隠れ目玉ってところに、ハリウッド・ボウルのCDと連動で売る際の、説明のしにくさが付きまとうわけで。アップルさん、もうムリしなくても……と言いたくなるのは、こういうところからなのだ。
監督は、ロン・ハワード。
なにしろ『アメリカン・グラフィティ』のスティーヴ役で、ロジャー・コーマン門下で。ひいきにしたい人ではあったが、『ビューティフル・マインド』を見て、ああ、この人は違うんだ、ハリウッドの正統派として確実にやりたい人なんだと気付いて以来、(僕にとっては)そんなに無理して新作を見なくてもよい人になっていた。
ロン・ハワードが監督すると今年の春にニュースを読み、大体、手堅い感じになるんだろうなあ……と淡々と感じた通りの、大体、手堅い感じの音楽ドキュメンタリーになっていた。
ビートルズがスタジオに籠ってからの話は、ズバッと切ってもいいはずなのだが(正直、えッ、サージェント軍曹以前で終らせない考え方がよく分からない……と思ったが)、多少くどくなっても親切な、正史と照らしてズレのない内容になるほうを選ぶあたりが、当代の〈ミスター・アメリカ映画〉ならでは。
連載「ワカキコースケのDIG!聴くメンタリー」の第15回目で、『ビートルズ物語』を取り上げた。
http://webneo.org/archives/37607
ビートルズのアメリカ進出が大成功したのは、イギリスのローカル出身音楽グループにとっても、ケネディ大統領暗殺直後のアメリカにとっても、奇跡的なタイミングだったのでは、ということを書いた。
ガキの頃にブリティッシュ・インヴェイジョンを経験したロン・ハワードが、まさにそこに(アメリカの監督である自分がビートルズの映画を引き受ける根拠として)力点を置いていたのは、こっそり、我が意を得たりだった。いずれ気付いてくれる人もいるでしょう。
ロバート・ゼメキスが監督していたら……と合計3度ほど思ったものの、それは失礼というものだな。
さて、映画は、やはりレストアされた1965年のシェイ・スタジアムのライヴ映像が付いている。
この説明が公式の記事を読んでも、『レコードコレクターズ』10月号の特集記事を読んでも、今ひとつ分かりずらい。
結局は僕もかなりシネフィルなところがあるので、本編の中に入ったボーナス映像なのか、併映と考えてよいのか、ハッキリしないと落ち着かない。日本のどこかにきっと数人はいる、モヤモヤしている方のため、長くなったついでに、ざっくりと整理しておきます。
○今秋公開の映画は、本編109分、シェイ・スタジアムのライヴ映像31分の、合計140分。
○おそらく、この140分は「劇場公開版」ということになり、ソフト化された場合は、本編109分が分離されるか、あるいは追加映像などで違う内容・尺になるのだろう。
○シェイ・スタジアムは、これまで発表されてきた映像と、基本は同じ。アメリカでテレビ放送用に撮影され(撮影クレジットは、後にテレビドラマ『将軍 SHOGUN』やウォルター・ヒル監督作品などで活躍するアンドリュー・ラズロだ)、後に日本でも、『THE BEATLES/シェアスタジアム』の邦題で、劇場初登場となる『マジカル・ミステリー・ツアー』とともに、1977年に公開された。
○といっても、昔のママではなく、ステージ部分に絞った再編集が施されている。さらに近年発見されたという、観客席からファンがカメラで撮っていた映像も織り込まれた、新ヴァージョンになっている。
この31分だけ、単体のソフトになってくれても嬉しい。
ジョンのひじ弾きオルガンなど、今までよく見て、聴いてきた以外では、リンゴがヴォーカルの「アクト・ナチュラリー」が印象的。
冷静に考えたら当時、バック・オーウェンスのカントリー・ソングを、世界のアイドルがこんな激しいノリでカヴァーするなんて、凄いことである。ほどなくして勃興するカントリー・ロックのヒントとなり、後押しになったはずだと、どうしたって思う。ジャニーズがニューシングルで演歌を歌うようなもの、と想像してもらうといい。
「これからくるのはこの音だぜ、田舎のおっさんだけのものにしとくのは勿体ないんだよ!」と、せっかくフォーク・ロックで世に出たザ・バーズのメンバーにカントリーを教えてかき乱し、ストーンズのキースにもこっぴどいコンプレックスを植え付けてから世を去った風雲児グラム・パーソンズが、〈ビートルズはなんとカントリーすら好きだった〉ってところを、どう感じていたのか。証言があったら、ぜひ知りたい。
アップルさんの今までのご労苦に感謝しつつ、もうそんなに無理なさらなくても……という主旨で書いてきたが。
もちろん、今、スパッとやめられても困る。
未だソフト化されない飢餓度においては、音楽ジャンルどころか、世界中の映画全て含めてもトップクラスの『ビートルズ/レット・イット・ビー』があるので。
1984年のTBS深夜のノーカット放送はVHSで録画しており、僕はさんざんっぱら見ているんだけども。公益的には、僕が録画もってる自慢したって仕方ない。
ドカーンと4Kレストア、しかも劇場公開のオリジナル版で他のフッテージは別ディスクに収録、という最後の大花火を打ち上げてくれる日を、いつまでもお待ち申し上げております。