◎ホワイトクローバーを播いたのですが、これは野菜ではありません。
欧米の民間療法では干した花を使用すると書いてありますが、目的は緑肥とマルチングと目に優しい畑にすることです。
土が丸見えよりも楽しいかな?と思いました。

こんな感じになってくれたらな、と思っています。
播いたタネの数は、なんと約5万粒!
笑っちゃいますね。
子供たちが面白がって播き過ぎました(笑)
それでも規定量らしいです。
◎緑肥ってなんでしょうか。
お馴染みのウィキペディアを見てみましょう。
=========================
【緑肥】
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%91%E8%82%A5
ウィキペディア:フリー百科事典
(引用)
緑肥(りょくひ)とは、栽培している植物を、収穫せずそのまま田畑にすきこみ、つまり、植物と土を一緒にして耕し、後から栽培する作物の肥料にすること、またはそのための植物のことである。
~中略~
戦後、硫安(硫酸アンモニウム)、尿素など、安価な化学肥料が大量生産されるまでは、窒素肥料になる物は貴重品で、人間の糞尿、捕れすぎた魚や、食用にならない海藻(ホンダワラなど)とともに、肥料としてよく利用されていた。根瘤バクテリアとの共生により、空中の窒素を同化するマメ科のクローバー、ルピナス、ウマゴヤシ、レンゲソウなどが多く用いられていた。
=========================
田畑に鋤き込むことはしません。
そのまま田畑に鋤き込んでも効果はありません。むしろ悪影響を与えます。(こちらの記事内のリンク先を参照してください。)
自然に枯れていき自然に土に還っていけばいいと思います。
◎重視したのは根瘤バクテリアの部分です。
=========================
【根瘤菌】
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B9%E7%B2%92%E8%8F%8C
ウィキペディア:フリー百科事典
=========================
根瘤バクテリアには光合成で得た有機物を提供し、植物には根瘤バクテリアが窒素固定をした無機物が提供される、なんとも素敵な共生関係が成り立っています。
◎緑肥としてはイネ科も有用です。
ですので、イネ科であるキビも購入しました。
キビは鳥が食べるので、他の作物の鳥被害を抑える効果も期待しています。
鳥が来てくれたら糞も落としてくれるでしょうし、ここでも共生関係を重視しています。
また、イネ科に付いたアブラムシを捕食する昆虫類を、早くから呼びこむことで、アブラムシ被害も抑えられると良いなと思っています。
自然農の醍醐味は、こうした共生関係をまんべんなく成り立たせることだろうと思います。
◎他にも、マルチング(ウィキペディア:フリー百科事典)効果によって雑草の発生を制限したり、微妙な日陰を作ってくれることで、夏場の土温度の上昇を抑制したり、光がないと発芽しないくせに乾燥すると発芽しにくいニンジンのような作物の発芽を手伝ってくれたり、いろいろな効果があるのではないかな?と思いました。
モノは試しです。
食べたいものだけを食べるのではなく、出来たものを出来ただけ食べる生き方って、なんとなく生活に余裕ある雰囲気ありません?(笑)
次回の農園訪問は3月5日の予定です。
発芽してくれるか楽しみです。
でも、発芽してくれなくてもいいんです。
発芽しないということは、発芽に適していないということです。
いろんなタネを播いてみれば、何かしらは発芽して育ってくれるでしょう。
何かが発芽すると、自然な形で他の植物も発芽するものです。
土は人間が作るのではなく、植物たちが自分たちで考え、自分たちの住処を作っていくのだと思います。
そのダイナミックな多様性を見ることが、今いちばんの楽しみです。
欧米の民間療法では干した花を使用すると書いてありますが、目的は緑肥とマルチングと目に優しい畑にすることです。
土が丸見えよりも楽しいかな?と思いました。

こんな感じになってくれたらな、と思っています。
播いたタネの数は、なんと約5万粒!
笑っちゃいますね。
子供たちが面白がって播き過ぎました(笑)
それでも規定量らしいです。
◎緑肥ってなんでしょうか。
お馴染みのウィキペディアを見てみましょう。
=========================
【緑肥】
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%91%E8%82%A5
ウィキペディア:フリー百科事典
(引用)
緑肥(りょくひ)とは、栽培している植物を、収穫せずそのまま田畑にすきこみ、つまり、植物と土を一緒にして耕し、後から栽培する作物の肥料にすること、またはそのための植物のことである。
~中略~
戦後、硫安(硫酸アンモニウム)、尿素など、安価な化学肥料が大量生産されるまでは、窒素肥料になる物は貴重品で、人間の糞尿、捕れすぎた魚や、食用にならない海藻(ホンダワラなど)とともに、肥料としてよく利用されていた。根瘤バクテリアとの共生により、空中の窒素を同化するマメ科のクローバー、ルピナス、ウマゴヤシ、レンゲソウなどが多く用いられていた。
=========================
田畑に鋤き込むことはしません。
そのまま田畑に鋤き込んでも効果はありません。むしろ悪影響を与えます。(こちらの記事内のリンク先を参照してください。)
自然に枯れていき自然に土に還っていけばいいと思います。
◎重視したのは根瘤バクテリアの部分です。
=========================
【根瘤菌】
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B9%E7%B2%92%E8%8F%8C
ウィキペディア:フリー百科事典
=========================
根瘤バクテリアには光合成で得た有機物を提供し、植物には根瘤バクテリアが窒素固定をした無機物が提供される、なんとも素敵な共生関係が成り立っています。
◎緑肥としてはイネ科も有用です。
ですので、イネ科であるキビも購入しました。
キビは鳥が食べるので、他の作物の鳥被害を抑える効果も期待しています。
鳥が来てくれたら糞も落としてくれるでしょうし、ここでも共生関係を重視しています。
また、イネ科に付いたアブラムシを捕食する昆虫類を、早くから呼びこむことで、アブラムシ被害も抑えられると良いなと思っています。
自然農の醍醐味は、こうした共生関係をまんべんなく成り立たせることだろうと思います。
◎他にも、マルチング(ウィキペディア:フリー百科事典)効果によって雑草の発生を制限したり、微妙な日陰を作ってくれることで、夏場の土温度の上昇を抑制したり、光がないと発芽しないくせに乾燥すると発芽しにくいニンジンのような作物の発芽を手伝ってくれたり、いろいろな効果があるのではないかな?と思いました。
モノは試しです。
食べたいものだけを食べるのではなく、出来たものを出来ただけ食べる生き方って、なんとなく生活に余裕ある雰囲気ありません?(笑)
次回の農園訪問は3月5日の予定です。
発芽してくれるか楽しみです。
でも、発芽してくれなくてもいいんです。
発芽しないということは、発芽に適していないということです。
いろんなタネを播いてみれば、何かしらは発芽して育ってくれるでしょう。
何かが発芽すると、自然な形で他の植物も発芽するものです。
土は人間が作るのではなく、植物たちが自分たちで考え、自分たちの住処を作っていくのだと思います。
そのダイナミックな多様性を見ることが、今いちばんの楽しみです。










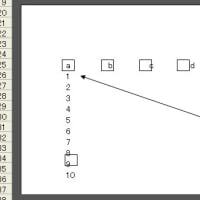
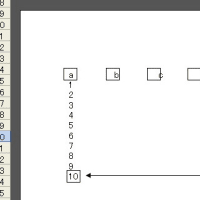
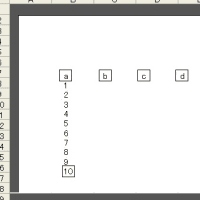





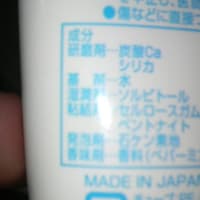
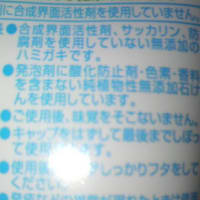
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます