やがて仏教は、ブッダの最重要課題である輪廻超脱の問題を前面から取り下げがちになっていく。ブッダが霊魂といった主題を「無記」や「反実体論」によって封じてしまったため、論理的に整合性がなくなってしまったのかもしれない。あるいは、輪廻超脱は特に珍しい思想ではなく、ウパニシャッドでもジャイナ教でも説かれていたことだったから、もっと違う道を歩む必要があったのかもしれない(新しい宗教は新しい考え方を求めるのが自然だから)。
もっと本質的に考えると、輪廻超脱は「こうすれば確実である」と保証することが不能なものだからなのかもしれない。さとりを開いて八正道を実践したとしても、「もう生まれ変わることはない」と確証されるわけではないから、不確かな将来の輪廻超脱よりも、この現状において「生の苦を超える」ことが重要だと考えられたのかもしれない。
仏教の中心主題は、「苦の克服=妄執の消尽」ということに移り、さらにその哲学的理論化であり、仏教独自の哲学でもある「縁起・空」の問題へと集中していく。大乗仏教が「空」を主題とした中観思想と、「妄執の消尽」を主題とした唯識思想という二大潮流を形成したのは、ここからの自然な帰結だったと言えるだろう。
こういった発展は、仏教を奇妙な宗教へと変貌させていく。反実体論の哲学と、無意識の心理学が、ほとんど仏教の中心となり、仏教は思弁的な学問と心理的修練になっていってしまう。
とりわけ現代の仏教学者は、仏教をこうした哲学・心理学的なものとして捉える傾向がある。
《釈迦の教義は人の心の悩みを解決することをめざした。心の悩みの解決は祭式のような外形的行為によっては達成されない。各人が自己の内面から行う変革によらねばならない。そのための基本的な出発点となるのが四諦・八正道や十二因縁の教義である。これは、一言でいえば、苦悩のよってきたる淵源を追求し、その淵源(おそらく〈我あり〉との妄執)を取り除くことを教えている。これは当時にあっては驚くほど科学的・合理的な態度である。しかも、自己存在の問題について、現代の深層心理学を先取りするような先見性を示している。これは仏教発展の背後に都市と商人階級という進んだ社会があった事実を反映しているかもしれない。》(CD版平凡社世界大百科事典・定方 晟)
《仏教の歴史を通じて、出家であれ在家であれ仏教者たちは、禅定もしくは三昧に入るように修行し、禅定や三昧において仏教的真理を知る知恵を得、悟りを悟っていたと考えられる。禅定や三昧によって表層意識を消滅させつつ深層意識を自覚化していき、最深層意識をも消滅させると同時に、彼自身の実存においてあらゆる衆生にゆきわたる根本真理を知る知恵を得、悟りを悟ったのである。したがって悟りとは、そのようなしかたで自我的な人格から解脱して自由になり、衆生に対して無礙(むげ)自在にはたらく新しい仏菩薩的人格へと生まれ変わることであるといってよい。》(同、荒牧 典俊)
事典の記述ということなので、あまり突っ込みを入れるのはフェアではないだろうけれども、「苦悩の淵源を取り除く」とか「最深層意識をも消滅させる」「自我的な人格から自由になる」といったことは、実際のところ可能なのかどうか、筆者にはよくわからない。
まあそれはともかく、ここには輪廻の問題や「死後の問題」はまったく出てこない。端的に言えば、「悩み苦しみを脱して、静穏な境地に到る、あるいは素晴らしい人格になる」という、人生論的、と言って悪ければ、心理学的内容が主となっている。
ここに仏教の特殊さがある。それは、「準無神論的宗教」というものである。人格の陶冶や心の平安の獲得のための哲学および心理学。あるいは人生訓・自己探究術。ないしは精神修養術。
だが、それは宗教なのだろうか。ショーペンハウアーは、「仏教は生理学であり精神衛生学だ」と言ったが、それが正しいのだろうか。
「死後の問題」は「無記」、つまり論じてもしょうがないから論じない、ということになってしまったのか。
いささか意地悪に言えば、哲学や心理学なら、今のわれわれには、もう少し現代的で身近なものがあるのだから、わざわざ難解な仏典を読まなくてもいいのではないか? 仏教の哲学や心理学は、現代の哲学や心理学にはない、何か素晴らしく、しかも実りある知見をもたらしてくれるのだろうか?
仏教をおとしめているのではない。むしろ、「生の苦は欲望・妄執から生じるから、我欲を抑えなさい」という教えは、きわめてまっとうだし、それによってよい人格が形成されたり、社会が平和になったり、さらには輪廻超脱が促進されたりもすることもあるだろうから、まことに素晴らしい教えだろう。少なからぬ人が、ディテールはともかく、漠然と仏教に対してシンパシーを感じるのは、この教えが人類の普遍的な精神的(霊的)真理であるからだろう。
現世のどろどろとした欲まみれの世界を離れ、清く安らかな心で生きるということは、ほとんどの宗教が説いていることであるし、それは現世内の「功利的な」問題としても非常に価値があると、多くの人は捉えている。坐禅が人気があるのも、そうした心の平安を実現するものと思われているからだろう。
そして、仏教のこの教えが二千数百年を通して生き続け、日本を始めとするアジアの精神文明に大きな影響を与えたことは、否定すべくもない。特に日本文化では、「我欲を離れる」ということを無意識的に賞揚する傾向があるが、それは仏教の教えを長時間かけて骨肉化したものと言えるかもしれない。
* * *
こうした仏教の神髄を体現していた一人に、クリシュナムルティがいる。彼は何も信じないし、何も欲しない。我欲をはるかに離れた地点から、生をみつめ、他者と会い、美しい言葉を残した。
《あるがままの真理を見ることの中にのみ自由があり、そして知恵は、その真理の知覚である。あるがままは決して静止的ではなく、それを受動的に注視するためには、あらゆる蓄積からの自由がなければならない。》
《精神が動機を持っていないとき、それが自由であって、いかなる切望によっても駆り立てられていないとき、それが完全に静謐であるとき、そのとき真理は、それ自体としてある。》(『生と覚醒のコメンタリー』から)
こういった立場は現世を超越して、ある意味では非常に魅力的である。
ただし、こうした立場からは、庶民が知りたいことへの答えは出てこない。
「死んだらどうなりますか」「死んだ親は今どうなっていますか」「何のために我欲を抑えなければいけないんですか」「なんでお坊さんにお金を払わなければいけないんですか」、さらには「なんで人を殺してはいけないんですか」「なんで自殺してはいけないんですか」……
そういった問いはこうした地点からは却下される。クリシュナムルティはたとえば死後の問題に対してこう答える。
《ただひとりある者だけが、原因を持たないもの、不可測のものと交わりうる。ただひとりある者にとって、死はない。ただひとりある者には、終りはありえない。》
こういう答えもあるのだろうし、こういう答えに心底納得する人もいるのだろう。少なからぬ人にとって、あるいは筆者のような凡人にとっては、どうも普通の会話ではないなと思うけれども、それは致し方ないのかもしれない。
ひとつ、付け加えておく。こうした「超越性の排除」「形而上学の回避」は、近代の唯物論的知性と、実は適合的である。死後とか霊魂とか超越的存在者といった概念は捨て去られる。「私はない」というのは、「私は脳内の電気信号である」とか「私は様々な構造の出会う結節点に過ぎない」という捉え方に似ていなくもない。また仏教は「実在」そのものを不問に付すわけだから、唯物論と真正面から敵対する必要もない。
近代の仏教学者や仏教徒が、仏教のこうした哲学・心理学的側面をことさらに強調するのは、それによって唯物論との衝突が回避できるからである。彼らは言う。「浄土はそれを信じる人の心の中にあるのです」「死者供養は生きている人のためにあるのです」「六道輪廻も仏菩薩も浄土往生も、実体ではなく、心の問題として捉えるべきなのです」……
しかし、それでいいのだろうか。「ヤハウェの顔を避けて」立ち回るのが宗教なのだろうか。
ある禅僧は、「生まれる前に私はなく、死の後に私はない、それをさとるのが禅である」と得々と説いたと言うが、それはまったく唯物論そのものである。
まあ、仏教は八万四千の法門があるのだから、それもまた仏教、と言えるのかもしれない。ただ、そういう立場を取る人たちが、葬儀をしてお金をもらうのはいささか詐欺的ではないかという疑いは生じるところである。
もっとはっきり言えば、「死後存続問題を切り捨てるのは自由だが、そうしておきながら葬儀・法事でお金をもらうとしたら、それはほとんど詐欺ではないか」ということになるのではないか。
もっと本質的に考えると、輪廻超脱は「こうすれば確実である」と保証することが不能なものだからなのかもしれない。さとりを開いて八正道を実践したとしても、「もう生まれ変わることはない」と確証されるわけではないから、不確かな将来の輪廻超脱よりも、この現状において「生の苦を超える」ことが重要だと考えられたのかもしれない。
仏教の中心主題は、「苦の克服=妄執の消尽」ということに移り、さらにその哲学的理論化であり、仏教独自の哲学でもある「縁起・空」の問題へと集中していく。大乗仏教が「空」を主題とした中観思想と、「妄執の消尽」を主題とした唯識思想という二大潮流を形成したのは、ここからの自然な帰結だったと言えるだろう。
こういった発展は、仏教を奇妙な宗教へと変貌させていく。反実体論の哲学と、無意識の心理学が、ほとんど仏教の中心となり、仏教は思弁的な学問と心理的修練になっていってしまう。
とりわけ現代の仏教学者は、仏教をこうした哲学・心理学的なものとして捉える傾向がある。
《釈迦の教義は人の心の悩みを解決することをめざした。心の悩みの解決は祭式のような外形的行為によっては達成されない。各人が自己の内面から行う変革によらねばならない。そのための基本的な出発点となるのが四諦・八正道や十二因縁の教義である。これは、一言でいえば、苦悩のよってきたる淵源を追求し、その淵源(おそらく〈我あり〉との妄執)を取り除くことを教えている。これは当時にあっては驚くほど科学的・合理的な態度である。しかも、自己存在の問題について、現代の深層心理学を先取りするような先見性を示している。これは仏教発展の背後に都市と商人階級という進んだ社会があった事実を反映しているかもしれない。》(CD版平凡社世界大百科事典・定方 晟)
《仏教の歴史を通じて、出家であれ在家であれ仏教者たちは、禅定もしくは三昧に入るように修行し、禅定や三昧において仏教的真理を知る知恵を得、悟りを悟っていたと考えられる。禅定や三昧によって表層意識を消滅させつつ深層意識を自覚化していき、最深層意識をも消滅させると同時に、彼自身の実存においてあらゆる衆生にゆきわたる根本真理を知る知恵を得、悟りを悟ったのである。したがって悟りとは、そのようなしかたで自我的な人格から解脱して自由になり、衆生に対して無礙(むげ)自在にはたらく新しい仏菩薩的人格へと生まれ変わることであるといってよい。》(同、荒牧 典俊)
事典の記述ということなので、あまり突っ込みを入れるのはフェアではないだろうけれども、「苦悩の淵源を取り除く」とか「最深層意識をも消滅させる」「自我的な人格から自由になる」といったことは、実際のところ可能なのかどうか、筆者にはよくわからない。
まあそれはともかく、ここには輪廻の問題や「死後の問題」はまったく出てこない。端的に言えば、「悩み苦しみを脱して、静穏な境地に到る、あるいは素晴らしい人格になる」という、人生論的、と言って悪ければ、心理学的内容が主となっている。
ここに仏教の特殊さがある。それは、「準無神論的宗教」というものである。人格の陶冶や心の平安の獲得のための哲学および心理学。あるいは人生訓・自己探究術。ないしは精神修養術。
だが、それは宗教なのだろうか。ショーペンハウアーは、「仏教は生理学であり精神衛生学だ」と言ったが、それが正しいのだろうか。
「死後の問題」は「無記」、つまり論じてもしょうがないから論じない、ということになってしまったのか。
いささか意地悪に言えば、哲学や心理学なら、今のわれわれには、もう少し現代的で身近なものがあるのだから、わざわざ難解な仏典を読まなくてもいいのではないか? 仏教の哲学や心理学は、現代の哲学や心理学にはない、何か素晴らしく、しかも実りある知見をもたらしてくれるのだろうか?
仏教をおとしめているのではない。むしろ、「生の苦は欲望・妄執から生じるから、我欲を抑えなさい」という教えは、きわめてまっとうだし、それによってよい人格が形成されたり、社会が平和になったり、さらには輪廻超脱が促進されたりもすることもあるだろうから、まことに素晴らしい教えだろう。少なからぬ人が、ディテールはともかく、漠然と仏教に対してシンパシーを感じるのは、この教えが人類の普遍的な精神的(霊的)真理であるからだろう。
現世のどろどろとした欲まみれの世界を離れ、清く安らかな心で生きるということは、ほとんどの宗教が説いていることであるし、それは現世内の「功利的な」問題としても非常に価値があると、多くの人は捉えている。坐禅が人気があるのも、そうした心の平安を実現するものと思われているからだろう。
そして、仏教のこの教えが二千数百年を通して生き続け、日本を始めとするアジアの精神文明に大きな影響を与えたことは、否定すべくもない。特に日本文化では、「我欲を離れる」ということを無意識的に賞揚する傾向があるが、それは仏教の教えを長時間かけて骨肉化したものと言えるかもしれない。
* * *
こうした仏教の神髄を体現していた一人に、クリシュナムルティがいる。彼は何も信じないし、何も欲しない。我欲をはるかに離れた地点から、生をみつめ、他者と会い、美しい言葉を残した。
《あるがままの真理を見ることの中にのみ自由があり、そして知恵は、その真理の知覚である。あるがままは決して静止的ではなく、それを受動的に注視するためには、あらゆる蓄積からの自由がなければならない。》
《精神が動機を持っていないとき、それが自由であって、いかなる切望によっても駆り立てられていないとき、それが完全に静謐であるとき、そのとき真理は、それ自体としてある。》(『生と覚醒のコメンタリー』から)
こういった立場は現世を超越して、ある意味では非常に魅力的である。
ただし、こうした立場からは、庶民が知りたいことへの答えは出てこない。
「死んだらどうなりますか」「死んだ親は今どうなっていますか」「何のために我欲を抑えなければいけないんですか」「なんでお坊さんにお金を払わなければいけないんですか」、さらには「なんで人を殺してはいけないんですか」「なんで自殺してはいけないんですか」……
そういった問いはこうした地点からは却下される。クリシュナムルティはたとえば死後の問題に対してこう答える。
《ただひとりある者だけが、原因を持たないもの、不可測のものと交わりうる。ただひとりある者にとって、死はない。ただひとりある者には、終りはありえない。》
こういう答えもあるのだろうし、こういう答えに心底納得する人もいるのだろう。少なからぬ人にとって、あるいは筆者のような凡人にとっては、どうも普通の会話ではないなと思うけれども、それは致し方ないのかもしれない。
ひとつ、付け加えておく。こうした「超越性の排除」「形而上学の回避」は、近代の唯物論的知性と、実は適合的である。死後とか霊魂とか超越的存在者といった概念は捨て去られる。「私はない」というのは、「私は脳内の電気信号である」とか「私は様々な構造の出会う結節点に過ぎない」という捉え方に似ていなくもない。また仏教は「実在」そのものを不問に付すわけだから、唯物論と真正面から敵対する必要もない。
近代の仏教学者や仏教徒が、仏教のこうした哲学・心理学的側面をことさらに強調するのは、それによって唯物論との衝突が回避できるからである。彼らは言う。「浄土はそれを信じる人の心の中にあるのです」「死者供養は生きている人のためにあるのです」「六道輪廻も仏菩薩も浄土往生も、実体ではなく、心の問題として捉えるべきなのです」……
しかし、それでいいのだろうか。「ヤハウェの顔を避けて」立ち回るのが宗教なのだろうか。
ある禅僧は、「生まれる前に私はなく、死の後に私はない、それをさとるのが禅である」と得々と説いたと言うが、それはまったく唯物論そのものである。
まあ、仏教は八万四千の法門があるのだから、それもまた仏教、と言えるのかもしれない。ただ、そういう立場を取る人たちが、葬儀をしてお金をもらうのはいささか詐欺的ではないかという疑いは生じるところである。
もっとはっきり言えば、「死後存続問題を切り捨てるのは自由だが、そうしておきながら葬儀・法事でお金をもらうとしたら、それはほとんど詐欺ではないか」ということになるのではないか。


















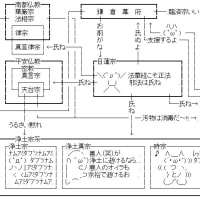

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます