13日(金)。昨日はトリトン・アーツ・ネットワークの「クァルテット・ウィークエンド」のチケット発売日だったので、チケットデスクに電話をして4回分のコンサートを予約しました
まず古典四重奏団の「ムズカシイはおもしろい!~モーツアルト全曲2014の1~3」で、①9月27日(土)午後2時から、②10月10日(金)午後7時から、③10月26日(日)午後2時からの3公演(モーツアルトの弦楽四重奏曲のレクチャー・コンサート)です もう1枚は来年3月15日(日)午後2時からのクァルテット・エクセルシオ「Quartet+(プラス)」(シューベルト”ます”他)です
もう1枚は来年3月15日(日)午後2時からのクァルテット・エクセルシオ「Quartet+(プラス)」(シューベルト”ます”他)です 会場はすべて晴海のトリトン・スクゥエアの第一生命ホールです。室内楽はいいですね
会場はすべて晴海のトリトン・スクゥエアの第一生命ホールです。室内楽はいいですね



 閑話休題
閑話休題 

立川談四楼著「声に出して笑える日本語」(光文社文庫)を読み終わりました 著者の立川談四楼は1951年生まれ。70年に立川談志に入門し、83年に立川流落語会第1期真打になっています
著者の立川談四楼は1951年生まれ。70年に立川談志に入門し、83年に立川流落語会第1期真打になっています 数年前まで、NHK=BSで放映していた「週刊ブックレビュー」のゲスト出演した時の冴えたコメントが思い出に残っています。いい人でした。惜しい人を・・・・・って、まだ生きています
数年前まで、NHK=BSで放映していた「週刊ブックレビュー」のゲスト出演した時の冴えたコメントが思い出に残っています。いい人でした。惜しい人を・・・・・って、まだ生きています

私は、本を読んでいて気に入った箇所があるとミミを折る癖がありますが、この本は折ったミミだらけ まるでウサギです。とくに気にいった話をいくつかご紹介すると・・・・・
まるでウサギです。とくに気にいった話をいくつかご紹介すると・・・・・
①助詞の「の」と「は」を間違えると大変の巻
整形をしようとする彼女に、本当は「おまえね、人間は顔じゃないよ」と言って慰めようとしたのに、
「おまえはね、人間の顔じゃないよ」と言ってしまった
・・・・・・1分後、彼氏の頭には包丁が・・・・・おお、こわっ
②中国がらみ
「良いことをした人は天国へ、
悪いことをした人は地獄へ、
普通に生きた人は中国へ行く 」
」
・・・・・・最近では中国行きも激減してるかも
③成長魚の話
TBS「さんまのスーパーからくりTV」の「ご長寿早押しクイズ」を見ていたら、『出世魚のハマチは大きくなったら何になる?』という問いが出て、某老人が『刺身』と大きな声で答えた。正解にしてやればいいのに
・・・・・・私も同感です
④御守の矛盾
某神社の絵馬に「合格祈願 仏教大学」というのがあったという
暴走族はオートバイを飾り立てるのが好きだが、必ずといっていいぐらい「交通安全の御守」を付けている。
・・・・・・最近の暴走族は信号を守るそうですよ
⑤インドの諺
インドに「明日できることは今日するな」との諺があるというのです。気に入りました この諺の前に、鉄は熱いうちに打てなどという言葉の何と無力なことでしょう
この諺の前に、鉄は熱いうちに打てなどという言葉の何と無力なことでしょう で今や、「明日できることは今日するな」は私の座右の銘なのです
で今や、「明日できることは今日するな」は私の座右の銘なのです
・・・・・・「今日できないことは明日もできない」というのはどうでしょうか
以上、ここでご紹介したのは、ホンの一部です。プロの落語家は普段から世間で交わされる会話に耳を傾けていることが良く分かりますよね
はっきり言って、この本は電車の中で読んではいけません。「季節の変わり目には、よく出没するよね、こういう人」と指差されること必至です よい子はおうちで読んでね
よい子はおうちで読んでね

















 プログラムは①ルーセル「フルート、弦楽三重奏、ハープのためのセレナード」、②ワーグナー「ジークフリート牧歌」、③モーツアルト「弦楽四重奏曲第14番ト長調K.387」です
プログラムは①ルーセル「フルート、弦楽三重奏、ハープのためのセレナード」、②ワーグナー「ジークフリート牧歌」、③モーツアルト「弦楽四重奏曲第14番ト長調K.387」です 結局それは杞憂に終わりましたが、それでも1年前と比べれば聴衆は減っていると思います
結局それは杞憂に終わりましたが、それでも1年前と比べれば聴衆は減っていると思います ハープは35キロから45キロ位とのこと。相当の重さですね
ハープは35キロから45キロ位とのこと。相当の重さですね 村松さんの演奏楽器であるコントラバスは15キロ程度、チューバもやはり15キロくらいあるとのことです。大変な重労働なのですね
村松さんの演奏楽器であるコントラバスは15キロ程度、チューバもやはり15キロくらいあるとのことです。大変な重労働なのですね
 これも村松スタイルとして定着するようです
これも村松スタイルとして定着するようです

 4つの楽章から成りますが、第1楽章は伸びやかで晴れ晴れとした曲想、第2楽章は半音階で交互にピアノとフォルテが連続して出てきます
4つの楽章から成りますが、第1楽章は伸びやかで晴れ晴れとした曲想、第2楽章は半音階で交互にピアノとフォルテが連続して出てきます すべての楽章が生き生きと息づいていて、すごく流れがスムーズです。こういうモーツアルトを演奏してほしいものです
すべての楽章が生き生きと息づいていて、すごく流れがスムーズです。こういうモーツアルトを演奏してほしいものです




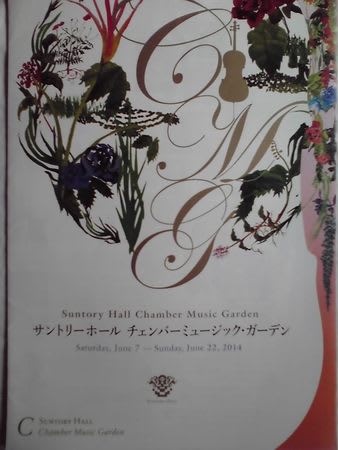
 大ホールであればチケット・ゲートの手前にショップがあるので存在に気が付くのですが、小ホールの場合は、わざわざ奥まで行かないと分からないところにあるので、存在に気が付かない、あるいは知っていても営業しているとは思わない人が多いのではないか、と思いました
大ホールであればチケット・ゲートの手前にショップがあるので存在に気が付くのですが、小ホールの場合は、わざわざ奥まで行かないと分からないところにあるので、存在に気が付かない、あるいは知っていても営業しているとは思わない人が多いのではないか、と思いました
 フンメルはサリエリに作曲を、ハイドンにオルガンを習い、ハイドンの推薦で26歳の時にエステルハージ家の楽士長になりました
フンメルはサリエリに作曲を、ハイドンにオルガンを習い、ハイドンの推薦で26歳の時にエステルハージ家の楽士長になりました


 ですよ。
ですよ。 朝日は全国紙ですから、北は北海道から南は沖縄まで、基本的にこの音楽時評が載っているわけですが、札幌での演奏評が果たしてどれだけの人の目に触れるでしょうか
朝日は全国紙ですから、北は北海道から南は沖縄まで、基本的にこの音楽時評が載っているわけですが、札幌での演奏評が果たしてどれだけの人の目に触れるでしょうか
 最後まで読んで振り返ってみると、解説のしようがないことが分かります。少しでも解説をしたら則”ネタバレ”になってしまうからです
最後まで読んで振り返ってみると、解説のしようがないことが分かります。少しでも解説をしたら則”ネタバレ”になってしまうからです

 メンデルスゾーンの弦楽四重奏曲第5番を聴きたかったのですが、さんざん迷った挙句、諦めることにしました。わざわざサントリーホールまで行っても、チケットが売り切れじゃ元も子もありませんから
メンデルスゾーンの弦楽四重奏曲第5番を聴きたかったのですが、さんざん迷った挙句、諦めることにしました。わざわざサントリーホールまで行っても、チケットが売り切れじゃ元も子もありませんから 「鑑定士と顔のない依頼人」と「メイジ―の瞳」の2本立てですが、時間的に「鑑定士と顔のない依頼人」が11時25分からとちょうどいいので、1本だけ観ることにしました
「鑑定士と顔のない依頼人」と「メイジ―の瞳」の2本立てですが、時間的に「鑑定士と顔のない依頼人」が11時25分からとちょうどいいので、1本だけ観ることにしました

 ついに彼女を壁の外に連れ出すことに成功、自分の秘密部屋に隠した数多くの女性肖像画を披露し、結婚を誓う
ついに彼女を壁の外に連れ出すことに成功、自分の秘密部屋に隠した数多くの女性肖像画を披露し、結婚を誓う

 このブログでも何回か取り上げました。「10年ひと昔」と言いますが、ネット社会の現在は「3か月ひと昔」になってしまったような気がします
このブログでも何回か取り上げました。「10年ひと昔」と言いますが、ネット社会の現在は「3か月ひと昔」になってしまったような気がします

 この日、コンサートの予定はないので、ホール入口の「当日券売り場」に行って尋ねました
この日、コンサートの予定はないので、ホール入口の「当日券売り場」に行って尋ねました
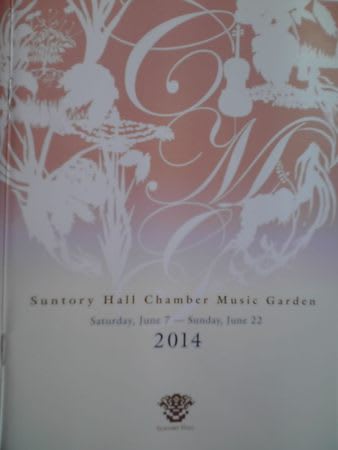



 そんなこととはツユ知らず・・・・・・誉田哲也著「ドルチェ」(新潮文庫)を読み終わりました
そんなこととはツユ知らず・・・・・・誉田哲也著「ドルチェ」(新潮文庫)を読み終わりました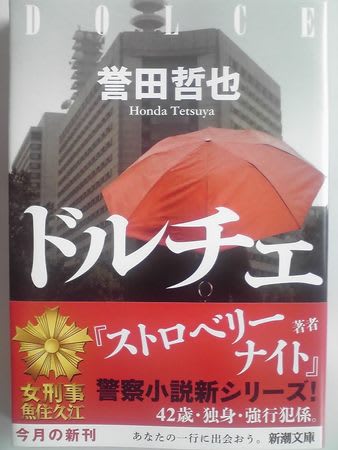


 」
」

 モーツアルト好きはそんなこと全然考えない。終わったらあとは、楽しくホイリゲでビールやワインを飲んで騒ぐ
モーツアルト好きはそんなこと全然考えない。終わったらあとは、楽しくホイリゲでビールやワインを飲んで騒ぐ オペラにしてもそうだろうけど、たとえば演出家でも、ブーレーズが振ったものを聴くと、ここをどうやったかというのを調べたくなるわけですよ。『ブーレーズはここでディミヌエンドした』とか『このテンポはどうだ』とか。だけど、たとえばデュトワが振ったものは、別に調べたりしないで、ただ聴いて、そこに埋まって酔えればいいという感じがするんです
オペラにしてもそうだろうけど、たとえば演出家でも、ブーレーズが振ったものを聴くと、ここをどうやったかというのを調べたくなるわけですよ。『ブーレーズはここでディミヌエンドした』とか『このテンポはどうだ』とか。だけど、たとえばデュトワが振ったものは、別に調べたりしないで、ただ聴いて、そこに埋まって酔えればいいという感じがするんです 」
」



