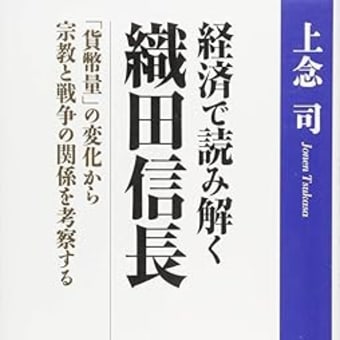上皇という存在は、天皇が生前退位した場合にのみ発生するため、日本史の中では限られた条件下でしか存在しない。海外事例では、王位を退いた元王様が引き続き権力を発揮し続けることは稀有であるが、日本史上には多くの上皇政治(院政)を行った事例がある。逆に日本で「院政」と言えば引退したのに権力を手放さない権力者の代名詞のようになっている。平成天皇が生前退位する際にも、議論になったと思われるこの点について、古代から振り返ってみる、というのが本書。特に筆者が得意とするのは中世、詳述されるのは、白河、鳥羽、後白河時代の専制、承久の乱がもたらした朝廷と武家の新しい関係、中級貴族たちが担った上皇の徳政、両統迭立と後醍醐、後嵯峨上皇の院政、婆娑羅大名にも脅かされた天皇と上皇などである。
白河院の父、後三条天皇は母方の縁者に藤原氏一族をもたなかった。そのため自分の意志による親政を実施、荘園整理令により荘園の公地公民化を実現、藤原氏が保有する荘園の3分の1を削減して摂関家の経済力を弱体化させ、結果的に藤原氏による摂関政治に終止符を打った。この時の藤原氏の当主は頼通、摂関政治の権力の大元は天皇の外戚となること、母方の尊属が摂政・関白で天皇を代理するという一点だったため、親政を行う天皇出現により体制崩壊までに至ってしまう。ちょうど母系社会、招婿婚の時代から、父系社会の婚姻形態に移行する時期でもあった。白河天皇には、異母弟が二人もいて皇太弟となっており、自分の息子である堀河が確実に即位できるよう、自分が上皇となり朝廷のトップで居続けることにより、思惑の実現を図る。白河上皇は長命だったため、堀河、鳥羽、崇徳の代まで実権を握り続けた。院政の始まりである。
荘園を支える「職の体系」は藤原氏や上皇を支える経済的基盤だった。律令制の基本は土地の公領制だが、開発した農地を寺社に寄進することで租税を免れる仕組みが荘園。開発した土地の地主が、国司からの徴税を免れるため自らが荘園管理者となり、国司への牽制力を持つ寺社が領家として存在、その上に本家としてスポンサーになるのが皇族、摂関家、大寺社となる。上皇としては、寄進された荘園を自らが建てた寺の所有としトンネル会社のごとく使う。こうして形成されたのが鳥羽上皇の八条院領であり長講堂領である。武家が力を持ち始め、南北朝から室町時代になると天皇の力は官位を与えるだけの象徴的存在に成り下がり、それも幕府に伺いを立てなければできなくなるのに、存在を全否定されることなく継続した理由は、こうした土地所有の職の体系が背景にあった。逆に言えば、こうした職の体系を越える土地支配の論理を室町武家政権が作り出せなかった、それを実現したのが信長・秀吉であった。
在家地主は下司と呼ばれ、やがて武装し武士団として大きな力を持つ存在となっていく。土地所有の仕組みは時代とともに変化、その変化が鎌倉・室町・戦国時代への体制変化をもたらす。つまり本来は天皇家の力の源泉となるべき農地を、上皇、摂関家、寺社などが奪い合うという構図が、公領地の律令制、摂関政治下の荘園、関東武士団の台頭と頭領による所領安堵、領地の奪い合いが起きる戦国時代、そして中央政権による土地の統合管理である太閤検地へとつながる。
白河上皇のあと鳥羽上皇の後継者争いとして保元の乱・平治の乱がおきて、後白河上皇に味方した平氏がいっとき力を得るが、頼朝率いる関東武士団に制圧される。ドラマとしては源平合戦として描かれる戦いは、土地の支配という切り口で見れば、実は後白河院と武士勢力の戦いだった。頼朝の勝利が確定すると、後白河院は頼朝征伐の院宣を発出するが、逆に頼朝による全国への受領設置、守護設置を認める結果となる。これが1185年、実質的な土地支配者の移行であり鎌倉幕府開始と見られる。まだこの時点では、頼朝の勢力圏は関東圏、鎌倉中心であり、西国は朝廷勢力圏だったが、承久の乱で後鳥羽上皇所有の土地を関東武士たちに与えて赴任させることで、鎌倉政権の全国支配が進むことになる。
後鳥羽勢力の再興を恐れていた幕府としては、後鳥羽系の嫡系に皇統を渡らせないため、仲恭天皇を廃し後鳥羽の兄、後高倉院の系統の後堀河天皇を即位させた。後高倉院は天皇に即位することなく院政を敷くが、すぐに死去。実権を握ったのが九条道家。後堀河天皇の后に娘を嫁がせ、その子が四条天皇として即位することである意味での摂関政治を復活させた。道家の息子は幕府の四代将軍の頼経であった為、道家は特異なポジションを獲得したことになる。道家の政治は20年ほども継続、鎌倉政権は道家への警戒感から、親子ともその地位から引きずり降ろされる。そして即位させられたのが後嵯峨上皇、目指したのが「徳政」で、庶民からの訴訟を積極的に取り上げた。「雑訴の興行」と称される徳政に必要な人材は、実務を担う中級貴族だった。中級貴族とは、殿上人の中でも名家階級で蔵人・弁官から蔵人頭、参議、中納言まで出世できる家柄で、大臣にまで出世できる羽林家や大臣家、はたまた最上級の摂関家などの上級貴族とは一線を画されていた。中国史を学ぶ紀伝道、儒学を学ぶ明経道、律令を学ぶ明法道、算術を学ぶ算道を身につける才覚が実務を担う貴族・官人の評価基準とされた。
この頃になると院政とはいっても幕府による皇位継承への介入が起きている。上皇による徳政が一定の成果を上げて安定したシステムとなり、寺社や社会からも評価されることを警戒した鎌倉政権は、後嵯峨上皇が狙っていた亀山天皇、後宇多天皇へと続いた皇統に、その皇太子として後深草天皇の皇子をねじ込み、亀山上皇の政治権力を阻害しようと企む。この2つの系統が大覚寺統と持明院統となり両統迭立が始まる。土地支配の視点から見れば、従来からの寺社勢力と新興武士勢力の覇権争いとなり、建武政権やその後の足利政権でも、この両者の覇権争いが、後醍醐天皇の反乱や観応の擾乱、嘉吉の変、応仁の乱など様々な勢力争いの要因となる。表面上は朝廷と幕府、鎌倉と京、南北朝、将軍家・兄弟間の跡目相続争いなどとして見えてくる様々な競合は、実はその後ろで指示している寺社勢力、地方豪族、荘園管理者などの勢力争いでもあった。
室町幕府の時代になると朝廷の権威は更に低下、婆娑羅大名と言われた土岐頼遠による上皇との出会い頭の襲撃事件が起こり、さすがにこのときは足利直義により斬首される。そんな時代でも天皇の権威が維持されたのは、先に述べた土地支配の「職の体系」を越える論理が存在しなかったためである。南北朝に分かれた時代に、北朝に皇統を戻したかった室町政権に知恵を貸したのが、婆娑羅大名の佐々木道誉。南朝に持ち去られた三種の神器の代わりになる象徴を考え出し、後光厳天皇即位に貢献したと言われる。そこまでしても天皇の権威維持を図る必要があったということ。朝廷と幕府はギブ・アンド・テイクの関係、室町王権論と呼ばれるが、筆者は、幕府が権威を利用したのであり、力関係は明らかに幕府が強かったと主張、義満時代以降は貴族たちもこぞって幕府詣でをするようになり、上皇が持っていた権威まで義満が奪った。これ以降、織田、豊臣、徳川と続く武家政権が皇位継承や土地支配の実質的な覇権を握ることになる。
江戸時代にこの構図に抗ったのが後水尾天皇。家康の遺言で輿入れする東福門院和子の入内に先立ち、後水尾天皇は「およつ御寮人事件」を引き起こす。すでに二人の子供を産ませていたことが発覚したのである。第一子を後継者とするのが儒学思想であり、秀忠はおよつ御寮人と関係する6人の公卿たちを流罪とし、和子を嫁がせた。その後起きたのが紫衣事件。武家の宗旨だった禅宗の高僧任免にまで介入した後水尾天皇の任命した勅許を幕府が取り消した。その後、無位無官の家光の乳母春日局が天皇拝謁を強行したことに反発した後水尾天皇は幕府に断らず退位。東福門院の娘を即位させ明正天皇とした。後水尾天皇は上皇となり85歳まで生きて幕府を糾弾した。
明治以降は、天皇の生前退位はなかったが、平成天皇が退位の気持ちを表明することで、宮内庁はこれを特例的に認める法制整備を行った。背景には、宮内庁としては皇室典範は変えられない前例を死守したかったことがある。上皇と天皇の勢力争いなどの政治的争いを引き起こしたくなかった明治維新政府の意向を意識したのではないか、という。国体護持にこだわって戦争を引き伸ばした反省、皇位継承にまつわる議論の行方、象徴天皇と万世一系へのこだわり、などさまざまな思惑が交錯するこの議論は、学会でもタッチしにくい分野である。本書内容は以上。
上皇と現役天皇の関係、武家勢力と朝廷、土地支配の背景について、よく分かる解説の一冊だと思う。なにより戦後の日本史研究は、現在でもなお、戦中までの皇国史観に支配された戦前の学説を引きずっている、という筆者の主張には、反対派・賛成派、様々な言い分があり賛否が渦巻いていることと推測できる。それでもあえての主張は潔さも感じる。素人である読者を強く意識し、あくまで分かりやすい記述に努める姿勢に素人読者の一人として感謝したい。