(以下、日本経済新聞から転載)
=================================
「医療通訳」外国人も安心 派遣制度やIT活用 専門性高め、対話しやすく
2012/9/6付
日本語を理解できない外国人の患者に医師らの言葉を伝える「医療通訳」の取り組みが広がっている。通訳を独自に養成する病院があるほか、自治体などが地域の医療機関に通訳を派遣する制度も始まっている。日本で暮らす外国人が200万人を超えるなか、医師との意思疎通を助け、安心して医療を受けられる環境を整えるのが狙いだ。
ブラジル人患者の診察に同席し、内容を通訳する南谷かおり医師(左から2人目)=大阪府泉佐野市のりんくう総合医療センター
「娘さんの下痢はウイルス性の腸炎によるものですね。1~2週間で治りますよ」。8月下旬、りんくう総合医療センター(大阪府泉佐野市)。生後7カ月の次女、アンナちゃんを抱くブラジル人のマリザ・キユナさん(27)に男性小児科医が語りかけると、傍らに座る同センターの南谷かおり医師(47)がポルトガル語で通訳した。
支払いまでお供
「原因がやっと分かった」。キユナさんはほっとした様子。仕事の都合で約2年前に来日し、簡単な日本語しか分からない。数日前、下痢をしたアンナちゃんを同府岸和田市の自宅近くの病院に連れていったが、医師が話すのは日本語と英語のみ。「雰囲気で深刻ではないと分かった」が、原因が分からず下痢も続いたため、不安になって同センターを訪れた。
同センターは英語(月~木曜日)、中国語(火曜日)、スペイン語(火・木曜日)、ポルトガル語(同)を無料で通訳。事前予約をするか当日に申し出れば、待機している通訳が受け付けから支払いまで付き添う。
通訳を始めたのは2006年。近くの関西国際空港から外国人が搬送される例が増えたのを機に、ブラジルで医師免許をとった南谷医師を中心に、10人未満の体制でスタート。現在は先輩とペアで働く研修生を含め、約60人の通訳が登録している。主婦や会社員、看護師らが空いた時間に活動し、11年度の通訳件数は約730件と、06年度の約8倍に増えた。
南谷医師は「医師の言葉は専門的で曖昧なことが多く、現場での研修が大切」と語る。以前、「肝機能を示す数値が上がった(症状が悪化している)」というのを、「症状が改善している」と研修生が誤って訳し、その場で注意したこともあるという。
互いの技術向上を目指し、昨夏には同センターの通訳などが一般社団法人「りんくう国際医療通訳翻訳協会(IMEDIATA=イメディアータ)」を設立。まずは今年10月から来年3月まで医療通訳のワークショップを開催する予定で、参加者を募っている。
自治体が主導
自治体主導の取り組みも広がっている。外国人労働者が東京都に次いで多い愛知県は4月、医療通訳の派遣を開始。電話による24時間対応の通訳や紹介状などの翻訳も受け付けている。7月末までに計227件の利用があったという。
派遣は現在、県内59の病院・診療所で利用できる。対応言語は英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語で、県が認定した約80人が活動する。電話ではこの4カ国語に加え、ハングルとタガログ語が使える。料金は派遣が2時間3千円からで、医療機関と患者が折半する仕組みだ。
厚生労働省によると、自動車関連産業が集積する愛知県の外国人労働者数は約8万4千人(11年10月末時点)。県の担当者は「ポルトガル語を中心に潜在的なニーズは高い。今後、認定通訳、医療機関ともに増やしたい」と話す。
10年前から医療通訳を派遣している神奈川県では、ほぼ右肩上がりで利用件数が伸びている。
県と連携して派遣に取り組む特定非営利活動法人(NPO法人)の「多言語社会リソースかながわ(MICかながわ)」(横浜市神奈川区)によると、11年度の派遣は3676件で、03年度の3.4倍に上る。派遣先の医療機関は当初の6から35まで拡大。対応言語も5から10に増やした。
同法人事務局の高山喜良さん(67)は「患者と医師の間で円滑な意思疎通を図るため、通訳の医療知識の習得を重視している」と話し、年3回の講習会参加を義務化。感染症や在宅医療など、毎回異なるテーマで医師らに講義を依頼し、専門性を高めている。
IT(情報技術)機器を使い、遠隔での通訳を導入する動きも出てきた。NPO法人「多文化共生センターきょうと」(京都市下京区)は和歌山大と組み、多機能携帯端末「iPad(アイパッド)」などを使ってテレビ電話のように通訳するシステム「You tran(ユートラン)」を開発した。
病院と通訳がそれぞれ1台ずつ端末を置き、無線LANで接続。端末内蔵のカメラで互いの映像を見ながら会話をする。
本格的に使ったのは今年6月。難病の治療で来日した患者はスペイン語しか分からない。治療にあたる病院に高度な通訳がおらず、同法人からも距離があったため、ユートランを使った。「身ぶり手ぶりが見えて、電話よりも正確な通訳ができる」と同法人の重野亜久里さん(39)。遠隔通訳は熟練の技術が必要だが、研修で順次人材を養成する計画だ。
◇ ◇
客観診断、研究広がる 脳や血液を検査
日本で暮らす外国人は長期的には増加傾向にあり、2011年末の登録者数は約208万人と、00年から約40万人増えた。日本の医療機関で健康診断や最先端医療を受けるために来日する「医療ツーリズム」も広がっており、医療通訳の必要性は今後、高まることが予想される。
一方で医療通訳は人命や個人情報に深く関わる面もあり「プロを育成する態勢づくりが急務」との声も上がる。現在、医療通訳の資格はなく、地域団体などが独自に育成して認定。仕事や家事の合間を利用して活動する人が多い。
全国の関係者が09年に立ち上げた「医療通訳士協議会」(大阪府吹田市)は「プロを育成するには認定制度などで身分を保証し、適切な報酬を与えることが必要」と訴え、今年中にも制度のあり方について本格的な議論に入る。
経済産業省も医療ツーリズムなどを背景に、9月中にも専門家を集めて議論を始める見通し。ただ「資格の枠が硬直し、現場と乖離(かいり)してしまっては本末転倒」(MICかながわ事務局の高山喜良さん)との指摘もあり、これまでの各地の取り組みを生かした柔軟な制度づくりが求められている。
(佐野敦子、黒滝啓介)
=================================
「医療通訳」外国人も安心 派遣制度やIT活用 専門性高め、対話しやすく
2012/9/6付
日本語を理解できない外国人の患者に医師らの言葉を伝える「医療通訳」の取り組みが広がっている。通訳を独自に養成する病院があるほか、自治体などが地域の医療機関に通訳を派遣する制度も始まっている。日本で暮らす外国人が200万人を超えるなか、医師との意思疎通を助け、安心して医療を受けられる環境を整えるのが狙いだ。
ブラジル人患者の診察に同席し、内容を通訳する南谷かおり医師(左から2人目)=大阪府泉佐野市のりんくう総合医療センター
「娘さんの下痢はウイルス性の腸炎によるものですね。1~2週間で治りますよ」。8月下旬、りんくう総合医療センター(大阪府泉佐野市)。生後7カ月の次女、アンナちゃんを抱くブラジル人のマリザ・キユナさん(27)に男性小児科医が語りかけると、傍らに座る同センターの南谷かおり医師(47)がポルトガル語で通訳した。
支払いまでお供
「原因がやっと分かった」。キユナさんはほっとした様子。仕事の都合で約2年前に来日し、簡単な日本語しか分からない。数日前、下痢をしたアンナちゃんを同府岸和田市の自宅近くの病院に連れていったが、医師が話すのは日本語と英語のみ。「雰囲気で深刻ではないと分かった」が、原因が分からず下痢も続いたため、不安になって同センターを訪れた。
同センターは英語(月~木曜日)、中国語(火曜日)、スペイン語(火・木曜日)、ポルトガル語(同)を無料で通訳。事前予約をするか当日に申し出れば、待機している通訳が受け付けから支払いまで付き添う。
通訳を始めたのは2006年。近くの関西国際空港から外国人が搬送される例が増えたのを機に、ブラジルで医師免許をとった南谷医師を中心に、10人未満の体制でスタート。現在は先輩とペアで働く研修生を含め、約60人の通訳が登録している。主婦や会社員、看護師らが空いた時間に活動し、11年度の通訳件数は約730件と、06年度の約8倍に増えた。
南谷医師は「医師の言葉は専門的で曖昧なことが多く、現場での研修が大切」と語る。以前、「肝機能を示す数値が上がった(症状が悪化している)」というのを、「症状が改善している」と研修生が誤って訳し、その場で注意したこともあるという。
互いの技術向上を目指し、昨夏には同センターの通訳などが一般社団法人「りんくう国際医療通訳翻訳協会(IMEDIATA=イメディアータ)」を設立。まずは今年10月から来年3月まで医療通訳のワークショップを開催する予定で、参加者を募っている。
自治体が主導
自治体主導の取り組みも広がっている。外国人労働者が東京都に次いで多い愛知県は4月、医療通訳の派遣を開始。電話による24時間対応の通訳や紹介状などの翻訳も受け付けている。7月末までに計227件の利用があったという。
派遣は現在、県内59の病院・診療所で利用できる。対応言語は英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語で、県が認定した約80人が活動する。電話ではこの4カ国語に加え、ハングルとタガログ語が使える。料金は派遣が2時間3千円からで、医療機関と患者が折半する仕組みだ。
厚生労働省によると、自動車関連産業が集積する愛知県の外国人労働者数は約8万4千人(11年10月末時点)。県の担当者は「ポルトガル語を中心に潜在的なニーズは高い。今後、認定通訳、医療機関ともに増やしたい」と話す。
10年前から医療通訳を派遣している神奈川県では、ほぼ右肩上がりで利用件数が伸びている。
県と連携して派遣に取り組む特定非営利活動法人(NPO法人)の「多言語社会リソースかながわ(MICかながわ)」(横浜市神奈川区)によると、11年度の派遣は3676件で、03年度の3.4倍に上る。派遣先の医療機関は当初の6から35まで拡大。対応言語も5から10に増やした。
同法人事務局の高山喜良さん(67)は「患者と医師の間で円滑な意思疎通を図るため、通訳の医療知識の習得を重視している」と話し、年3回の講習会参加を義務化。感染症や在宅医療など、毎回異なるテーマで医師らに講義を依頼し、専門性を高めている。
IT(情報技術)機器を使い、遠隔での通訳を導入する動きも出てきた。NPO法人「多文化共生センターきょうと」(京都市下京区)は和歌山大と組み、多機能携帯端末「iPad(アイパッド)」などを使ってテレビ電話のように通訳するシステム「You tran(ユートラン)」を開発した。
病院と通訳がそれぞれ1台ずつ端末を置き、無線LANで接続。端末内蔵のカメラで互いの映像を見ながら会話をする。
本格的に使ったのは今年6月。難病の治療で来日した患者はスペイン語しか分からない。治療にあたる病院に高度な通訳がおらず、同法人からも距離があったため、ユートランを使った。「身ぶり手ぶりが見えて、電話よりも正確な通訳ができる」と同法人の重野亜久里さん(39)。遠隔通訳は熟練の技術が必要だが、研修で順次人材を養成する計画だ。
◇ ◇
客観診断、研究広がる 脳や血液を検査
日本で暮らす外国人は長期的には増加傾向にあり、2011年末の登録者数は約208万人と、00年から約40万人増えた。日本の医療機関で健康診断や最先端医療を受けるために来日する「医療ツーリズム」も広がっており、医療通訳の必要性は今後、高まることが予想される。
一方で医療通訳は人命や個人情報に深く関わる面もあり「プロを育成する態勢づくりが急務」との声も上がる。現在、医療通訳の資格はなく、地域団体などが独自に育成して認定。仕事や家事の合間を利用して活動する人が多い。
全国の関係者が09年に立ち上げた「医療通訳士協議会」(大阪府吹田市)は「プロを育成するには認定制度などで身分を保証し、適切な報酬を与えることが必要」と訴え、今年中にも制度のあり方について本格的な議論に入る。
経済産業省も医療ツーリズムなどを背景に、9月中にも専門家を集めて議論を始める見通し。ただ「資格の枠が硬直し、現場と乖離(かいり)してしまっては本末転倒」(MICかながわ事務局の高山喜良さん)との指摘もあり、これまでの各地の取り組みを生かした柔軟な制度づくりが求められている。
(佐野敦子、黒滝啓介)















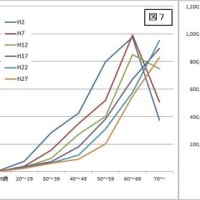
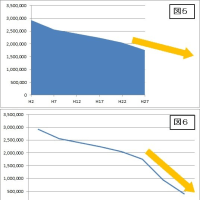
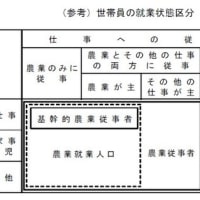
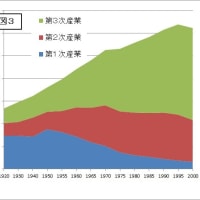
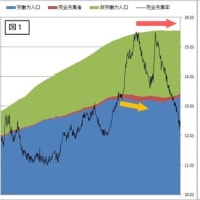
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます