幼少時における親からの愛情不足により、愛に飢えるようになった女性の、壮絶な人生を描き出す。それはほとんど病的なまでに、人の愛を求めて求めて、求めるために与えた。その結果、彼女はつぎつぎと不幸を背負っていく。
普通にいって、これはアダルトチルドレンや境界型人格障害の自伝である。幼少時の愛情が不足していたために(『愛を乞う人』では凄惨な虐待シーンがあったが、そこまではいかないようだ)、「ひとりぼっちよりはいい」と共依存的な恋人からの暴力沙汰に耐える姿は痛々しい。
それにもかかわらず、この映画はおもしろい。なおかつ泣ける。この映画を見たあとでは、ホームレスのいる風景だって、いとおしくなる。世界の底を体験させることで、観客はある種の癒しを得る。
これだけ悲惨な物語を、いかにして感動作へと変貌させるか。ここでアイデンティティの操作を行う。つまり監督は内面から彼女の感受性を感じたりはしない立場で映画を作っていくのである。
ミュージカル・シーンを挿入し、アニメーションの花や鳥を画面に飛ばす。台詞も適度に笑える場面を作る。本当のアダルトチルドレンや境界型人格障害とは違うなにものかになっていく。その過程で、その人格は一般化され、理解可能なものへと変更されていく。
そうやって、適度に無毒化された人物造形が行われているのが、この『嫌われ松子の一生』である。
中谷美紀によると、撮影現場は壮絶だったという。中島監督は中谷を罵倒し続けたそうだ。中谷は引退まで考えたという。そこまで女優を追い詰めて、松子に近づける。ベルナルド・ベルトルッチが『ラストエンペラー』のジョン・ローンに孤独感を出させるために、ミーティングに呼び出しては、全員でシカトしたとかいう演出法は、映画作りの逸話としてはいくらでも転がっている。この映画では、悲惨すぎて笑えるくらいにならなければならないわけで、一旦追い詰めて、その向こう側でのハッピーを演出することになる。なるほどこれはただごとではないが、普通に考えて、役者が作品世界に浸りこむとそこまでいかず悲惨さを悲惨に演じることになるだろう。そこを突き放した位置にある監督が容赦なく一押しするわけである。ある種の巨匠的な方法論である。
そうした方法論が自己撞着的な甘い表現から抜け出た明るさにつながり、さらにその明るさから逆に悲惨さが照らし出されるわけだ。
さらに、ゲイ的なキャンプな表現手法がそこに彩を加える。女囚や女郎宿といったゲイ好みのシチュエーションや、お花や小鳥のアニメーションがヒラヒラ飛んでいるというあまりにもキャンプな映像が出現する。新宿CODEのゲイ・ミックス・クラブイベント「Hits」のフライヤーが、ミュージシャンになるといって家を飛び出して東京にきた笙の部屋に張られていたことから、予測できようものだが、ほとんどウォルト・ディズニーの『ファンタジア』や『メリー・ポピンズ』のような感覚で、そこまでやってくれると度肝を抜かれ、あっぱれといいたい。
一人の作家が作業をするだけでは、そこまで特殊な一人一人の人物像を一般化できないだろう。原作のほうは未読であるが、相当ヘビーな作品になっているようだ。そちらは当事者あるいは当事者と相当近しい人間が作った作品に違いない。
アイデンティティから作家が遠ざかった距離にあるほうが、有利にはたらく映画つくり。見るものが共感する余地を与える技術。そこには大人の怜悧な技が散りばめられている。
アイデンティティと作品についてはこちらも見てね。
普通にいって、これはアダルトチルドレンや境界型人格障害の自伝である。幼少時の愛情が不足していたために(『愛を乞う人』では凄惨な虐待シーンがあったが、そこまではいかないようだ)、「ひとりぼっちよりはいい」と共依存的な恋人からの暴力沙汰に耐える姿は痛々しい。
それにもかかわらず、この映画はおもしろい。なおかつ泣ける。この映画を見たあとでは、ホームレスのいる風景だって、いとおしくなる。世界の底を体験させることで、観客はある種の癒しを得る。
これだけ悲惨な物語を、いかにして感動作へと変貌させるか。ここでアイデンティティの操作を行う。つまり監督は内面から彼女の感受性を感じたりはしない立場で映画を作っていくのである。
ミュージカル・シーンを挿入し、アニメーションの花や鳥を画面に飛ばす。台詞も適度に笑える場面を作る。本当のアダルトチルドレンや境界型人格障害とは違うなにものかになっていく。その過程で、その人格は一般化され、理解可能なものへと変更されていく。
そうやって、適度に無毒化された人物造形が行われているのが、この『嫌われ松子の一生』である。
中谷美紀によると、撮影現場は壮絶だったという。中島監督は中谷を罵倒し続けたそうだ。中谷は引退まで考えたという。そこまで女優を追い詰めて、松子に近づける。ベルナルド・ベルトルッチが『ラストエンペラー』のジョン・ローンに孤独感を出させるために、ミーティングに呼び出しては、全員でシカトしたとかいう演出法は、映画作りの逸話としてはいくらでも転がっている。この映画では、悲惨すぎて笑えるくらいにならなければならないわけで、一旦追い詰めて、その向こう側でのハッピーを演出することになる。なるほどこれはただごとではないが、普通に考えて、役者が作品世界に浸りこむとそこまでいかず悲惨さを悲惨に演じることになるだろう。そこを突き放した位置にある監督が容赦なく一押しするわけである。ある種の巨匠的な方法論である。
そうした方法論が自己撞着的な甘い表現から抜け出た明るさにつながり、さらにその明るさから逆に悲惨さが照らし出されるわけだ。
さらに、ゲイ的なキャンプな表現手法がそこに彩を加える。女囚や女郎宿といったゲイ好みのシチュエーションや、お花や小鳥のアニメーションがヒラヒラ飛んでいるというあまりにもキャンプな映像が出現する。新宿CODEのゲイ・ミックス・クラブイベント「Hits」のフライヤーが、ミュージシャンになるといって家を飛び出して東京にきた笙の部屋に張られていたことから、予測できようものだが、ほとんどウォルト・ディズニーの『ファンタジア』や『メリー・ポピンズ』のような感覚で、そこまでやってくれると度肝を抜かれ、あっぱれといいたい。
一人の作家が作業をするだけでは、そこまで特殊な一人一人の人物像を一般化できないだろう。原作のほうは未読であるが、相当ヘビーな作品になっているようだ。そちらは当事者あるいは当事者と相当近しい人間が作った作品に違いない。
アイデンティティから作家が遠ざかった距離にあるほうが、有利にはたらく映画つくり。見るものが共感する余地を与える技術。そこには大人の怜悧な技が散りばめられている。
アイデンティティと作品についてはこちらも見てね。












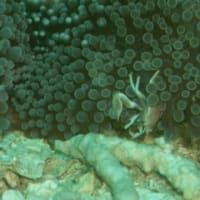







tamano文士の評論を読むと、大きく頷けるところも多々あります。
私のようなものに、トラックバックしていただき、申し訳ありません。ありがとうございました。 冨田弘嗣
僕自身は、たいへん面白かったんですけどね。むしろ『下妻物語』のほうが消化不良だったというか。
うちの相方さんなんかは、帰りの車のなかで「松子ちゃ~~ん」とかいいながら、うるうるなってましたよ。
で、どうしてこんなに、「はまれる」のか。作家のアイデンティティと作品の中心人物への距離感って、結構問題だよなあと。
大木裕之という映画作家と話をしていたときに、彼が「ブロークバック・マウンテンでアン・リーは本気で映画を作っていない」といったわけです。
彼は、自分のアイデンティティに最も深く関与しながら映画を作ってきた。彼の映画の方法論とは、ぜんぜん違うものが、アイデンティティの表現に出現してきていることへの、いらだちのようなものがあるんじゃないかなと思ったわけです。
とはいえ、そんなことを考える人はほぼ皆無であることも、各ブログをみていて実感。みんな、「松子ちゃ~~~ん」なのね。