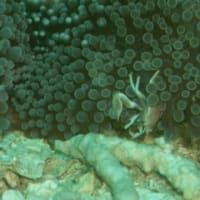ギドン・クレーメルの無伴奏の旧盤といえば、極めて刺激的といえば聞こえはいいが、相当な緊張感を強いられるもので、もっというとどこかぎすぎすして、「俺はとがっているぞ! 最先端の音楽表現を作ってるぞ!」という気負いのようなものすら感じさせるほどだった。
この秋に出てから、食事のときも、パソコンに向かうときも、ヘビーローテーションなこの新盤は、なるほどたしかに尖った演奏にも聞こえるが、クレーメルの「バイオリンを呪縛してきたのは歌わなければならないということだ」という言葉とは裏腹に、崇高な歌を内包する絶妙なバランスの上に立つ。そして、そのバランスは決して、天才的といわれるような若者の演奏によくあるようなぎりぎりのところで成立する危ういバランスではなく、きっちりと練りこまれ、長年弾き込まれてきたものだけが到達しうる安定した演奏である。
バッハの音楽のなかでも、「この一曲だけを残したとしても大作曲家といわれたであろう」というようなことをしばしば口に上らせる、音楽の小宇宙「シャコンヌ」が、かくも軽やかに重く、荘重にして軽快に、荘厳かつ軽妙に鳴り響いたことはいまだかつて一度もない。
たとえばドイツ的な解釈のお手本たるヘンリック・シェリングの盤はこの曲をバイオリンによる教会音楽ととらえた。彼の持ち味の野太いながら端正な音は、教会の音響ではまさにオルガンのような響きをもたらした。その味は、後続のどんな盤がでようとも失われることはない。
ロシアからナタン・ミルシテインは、あまりに華麗なテクニックで、線が細いなかにも凛とした風情を漂わせることに成功した。
また、ロシアから登場した世紀の下手うまバイオリニスト、ヨーゼフ・シゲティは、自らのバイオリンテクニックの不足を気合で補うかのような壮絶な演奏を残している。かすれる音、定まらない音程など、テクニックのゆらぎすら音楽を表現するためにあるかのような高いレベルでの奇跡的な演奏である。
クレーメルは、シゲティの後釜を狙うかのように、歌のない音のかすれもものともしない気合の演奏を以前は聞かせていたのである。シゲティにはないテクニックを得たクレーメルは、シゲティの精神をもっとテクニック豊かに表現しようとした。しかし、シゲティの老獪なシャコンヌには、いま一歩およばなかった感がある。
クレーメルは慌てることなく、この曲を20年間弾き続けて来た。
10年1日というが、一流の音楽家としてコンサートでバイオリン一本で舞台に立ち、だれの助力もなく、この曲を演奏するのは並大抵のことではないはずだ。彼はそれを繰り返すうちに、一音一音を発見し、全体像を見直していく作業を続けてきたのであろう。そうした音楽に対する誠実な姿勢が、歌となってこぼれ落ちる。
なるほどそれはいわゆる「歌っている」表現ではないだろう。しかし、ちょっとしたボーイング、ちょっとしたアクセント、ちょっとした音の引き際、高音を奏でるときのまるでハーモニクスのような音、そうしたちょっとした表現がすべてこなれていて、聞き苦しいところがまったくないのだ。
なるほど20年経っても、同じ曲を同じ音符のまま弾くことしか音楽家にはゆるされていない。しかし、その中で確実に歩を進めることができる。そして天才的な演奏家がその名声におごることなく、それを成し遂げたがゆえに、バッハ演奏の歴史に新たな1ページを加えることになった。
この秋に出てから、食事のときも、パソコンに向かうときも、ヘビーローテーションなこの新盤は、なるほどたしかに尖った演奏にも聞こえるが、クレーメルの「バイオリンを呪縛してきたのは歌わなければならないということだ」という言葉とは裏腹に、崇高な歌を内包する絶妙なバランスの上に立つ。そして、そのバランスは決して、天才的といわれるような若者の演奏によくあるようなぎりぎりのところで成立する危ういバランスではなく、きっちりと練りこまれ、長年弾き込まれてきたものだけが到達しうる安定した演奏である。
バッハの音楽のなかでも、「この一曲だけを残したとしても大作曲家といわれたであろう」というようなことをしばしば口に上らせる、音楽の小宇宙「シャコンヌ」が、かくも軽やかに重く、荘重にして軽快に、荘厳かつ軽妙に鳴り響いたことはいまだかつて一度もない。
たとえばドイツ的な解釈のお手本たるヘンリック・シェリングの盤はこの曲をバイオリンによる教会音楽ととらえた。彼の持ち味の野太いながら端正な音は、教会の音響ではまさにオルガンのような響きをもたらした。その味は、後続のどんな盤がでようとも失われることはない。
ロシアからナタン・ミルシテインは、あまりに華麗なテクニックで、線が細いなかにも凛とした風情を漂わせることに成功した。
また、ロシアから登場した世紀の下手うまバイオリニスト、ヨーゼフ・シゲティは、自らのバイオリンテクニックの不足を気合で補うかのような壮絶な演奏を残している。かすれる音、定まらない音程など、テクニックのゆらぎすら音楽を表現するためにあるかのような高いレベルでの奇跡的な演奏である。
クレーメルは、シゲティの後釜を狙うかのように、歌のない音のかすれもものともしない気合の演奏を以前は聞かせていたのである。シゲティにはないテクニックを得たクレーメルは、シゲティの精神をもっとテクニック豊かに表現しようとした。しかし、シゲティの老獪なシャコンヌには、いま一歩およばなかった感がある。
クレーメルは慌てることなく、この曲を20年間弾き続けて来た。
10年1日というが、一流の音楽家としてコンサートでバイオリン一本で舞台に立ち、だれの助力もなく、この曲を演奏するのは並大抵のことではないはずだ。彼はそれを繰り返すうちに、一音一音を発見し、全体像を見直していく作業を続けてきたのであろう。そうした音楽に対する誠実な姿勢が、歌となってこぼれ落ちる。
なるほどそれはいわゆる「歌っている」表現ではないだろう。しかし、ちょっとしたボーイング、ちょっとしたアクセント、ちょっとした音の引き際、高音を奏でるときのまるでハーモニクスのような音、そうしたちょっとした表現がすべてこなれていて、聞き苦しいところがまったくないのだ。
なるほど20年経っても、同じ曲を同じ音符のまま弾くことしか音楽家にはゆるされていない。しかし、その中で確実に歩を進めることができる。そして天才的な演奏家がその名声におごることなく、それを成し遂げたがゆえに、バッハ演奏の歴史に新たな1ページを加えることになった。