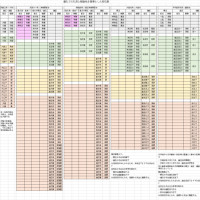万葉雑記 色眼鏡 卅七 万葉仮名歌の進化を楽しむ
今回は表記方法において平仮名の和歌に分類される歌を中心に鑑賞して行きます。ただし、平仮名和歌ですから、普段に目にする漢字ひらかな交じりの和歌ではありません。つまり、平仮名和歌とは、つぎのようなものです。
万葉集巻二十 大伴家持の歌より、
集歌4305 許乃久礼能 之氣伎乎乃倍乎 保等登藝須 奈伎弖故由奈理 伊麻之久良之母
訓読 木(こ)の暗(くれ)の茂き峯(を)の上(へ)を霍公鳥(ほととぎす)鳴きて越ゆなり今し来らしも
私訳 木の枝下を暗くするように木々が立派に茂る峰の頂をホトトギスが鳴きながら飛び越えていく。今、ホトトギスが鳴く、その季節が来たようだ。
例題として万葉集に載る歌を紹介しましたが、標準的に歌の表記方法について説明する時、平仮名の和歌として有名なのは古今和歌集の歌々です。私たちが目にする一般市販の歌集解説書では、「万葉仮名という漢字だけで書かれた万葉集に対して、純和風の平仮名だけで書かれた古今和歌集」とその歌の表記の特徴を対比して説明されていると思います。今回は、そのような原資料の点検を省略し、使う資料は不確かな伝聞の、さらなる又聞きであるような解説や説明は、一度、棚上げにして、本来の原文表記を材料として鑑賞していきます。
平仮名には、万葉仮名、変体仮名、現代のひらかな(明治三十三年小学令施行規則に載る仮名)が同じ仲間に入ると思います。それぞれは平仮名の進化過程での分類で、文字表現においてその文字の画数は大きく違っていても、それぞれの文字は一字で一音、和語の音のみを表し、表記される文字自体は万葉仮名や変体仮名であっても表意文字としての力を持ちません。それで同じ仲間に入ると考えています。なお、ここでは学問的な定義は行いませんし紹介もしません。ここでの決まりこととして同じ仲間と云うことでご了承ください。
さて、万葉集に載る歌で平仮名だけ、つまり、一字一音の万葉仮名で本格的に和歌が詠われたのを確認ができるのは巻五に載る梅花の歌三二首の宴のものからです。考古学的には木簡に残る「難波津の歌」などから、ずっと、以前から一字一音での万葉仮名で歌は記録されていたと思われますが、作歌を行う時に意図して一字一音の万葉仮名で歌を創り、詠ったのは梅花の歌三二首の宴からと考えられます。それ以前のものが遺物や伝来物として存在するのは口唱で知られる歌を文字として書き取ったと云う結果としてのものと考えます。作歌態度からのものではありません。
色々と能書きを垂れ流しましたが、次に有名な歌人が作歌した平仮名歌を紹介します。万葉集から二人、古今和歌集から一人です。
大伴旅人 万葉集巻五 集歌822
和何則能尓宇米能波奈知流比佐可多能阿米欲里由吉能那何列久流加母 (原文表記)
わかそのにうめのはなちるひさかたのあめよりゆきのなかれくるかも (ひらかな読み)
吾が苑に梅の花散るひさかたの天より雪の流れ来るかも (訓読万葉集)
大伴家持 万葉集巻二十 集歌4297
乎美奈弊之安伎波疑之努藝左乎之可能都由和氣奈加牟多加麻刀能野曽 (原文表記)
をみなへしあきはきしぬきさをしかのつゆわけなかむたかまとののそ (ひらかな読み)
をみなへし秋萩しのぎさを鹿の露別け鳴かむ高円の野ぞ (訓読万葉集)
紀貫之 古今和歌集 歌番2
曽天悲知弖武春比之美川乃己保礼留遠波留可太遣不乃可世也止久良武 (原文表記)
そてひちてむすひしみつのこほれるをはるかたけふのかせやとくらむ (ひらかな読み)
袖ひぢてむすびし水のこほれるを春立つけふの風やとくらむ (藤原定家自筆伊達家本より)
今回のテーマはこの三人の歌を紹介して、本来の趣旨は終わりです。平仮名歌ですから、それを紹介したところで、終わりです。また、表記方法において、三人の作品には相違はありません。それで、原文とその現代語訳を紹介すれば、終わりと云うことになります。
ただし、紹介するものに違和感を持たれる御方がいらっしゃると思います。その違和感の背景を紹介しますと、現代の古典文学の研究は鎌倉時代初期に藤原定家が翻訳したものをテキストとして使用するのが基準で、万葉集だけが鎌倉時代中期に仙覚が残した西本願寺本万葉集を底本とした校本万葉集をテキストとして使用します。また、江戸から明治時代では万葉集もまた訓読みされた訓読万葉集(有名なところでは鹿持雅澄の万葉集古義)をテキストとして使用するため、訓読万葉集と古今和歌集との相違を理解するのは困難でしょう。元々、それらのテキストは漢字ひらかな交じりの表記スタイルに統一することを目的に原文から翻訳したものですから、表記スタイルにおいては相違があってはいけないのです。
一方、今日の原本の姿を復元しようとする研究は、ここで示したような原文表記の姿を示します。この原文表記の姿を見て、深刻な問題と思われるか、それとも、それがどうしたと思われるかは立場です。ただ、単純に表記方法からの古今和歌集を特徴的に「平仮名の和風の和歌」と説明するものは詐欺的な真っ赤なウソであることは明白です。万葉集の平仮名和歌と古今和歌集の歌とには表記方法において相違は存在しません。およそ、和歌の表記方法について平仮名と云う音字表記に絞れば万葉集から古今和歌集への進化はありません。一方、表記方法を楷書や崩し草仮名連綿と云う書体(書風)に絞れば進化や変化はあります。ただ、それが貫之時代にはどうであったかは日本語や書道の歴史では資料が不足するために不明という扱いとなっています。
<以下、おまけです>
書筆における書体について考えますと、万葉集は楷書だったと思われますが、古今和歌集については不明です。古今和歌集より少し前に作成された新撰万葉集の和歌が楷書で書筆されてあることから楷書のスタイルを否定できません。一方、古今和歌集の奉呈と同時代か、やや下るとされる秋萩帖の書体は変体仮名での崩しの連綿体ですので、古今和歌集が崩しの連綿体で書筆された可能性もあります。ただし、十世紀初頭に変体仮名での崩しの連綿体が、奉呈される歌集を書筆することにおいて公に認められた書体であったかは確証がありません。歴史的資料として崩し連綿体に先行する書体である草仮名の文章として有名な「有年申文」は貞観九年(867)のものですから、古今和歌集奉呈の延喜五年(905)までに平仮名表記法がどれほど進化を遂げたのでしょうか。自己流の崩しでは文字は読めません。文字が文字としてあるためには崩しにも共通の認識とルールが必要です。ここらあたりの研究は残される資料が不足しているため非常に困難なようです。
なお、石川九楊氏が「万葉仮名でよむ『万葉集』」(岩波書店)で論を展開される時、古今和歌集の古写本である秋萩帖、寸松庵色紙、高野切の書筆の文字に、崩しの文字ですが、変体仮名の文字を確実に捕えられています。書筆スタイルが楷書と崩しの連綿との相違があっても歌を認識する時、そこには万葉仮名(または変体仮名)と云う漢字の文字があります。つまり、歌を表記すると云う作業では、本質においては同じではないでしょうか。
しかしながら、紀貫之は古今和歌集の仮名序の文を閉じるにあたって「歌の様をも知り ことの心を得たらむ人は 大空の月を見るがごとくにいにしへを仰ぎて 今をこひざらめかも」と述べ、古今和歌集と万葉集とを比べれば、きっと、古今の方が好いと云うであろうと述べています。
では、何が違うのでしょうか。大伴旅人と紀貫之の両者は、この一字一音の万葉仮名(変体仮名)だけで歌を詠うことについて歌論を書いていますから、それを鑑賞してみたいと思います。
最初に大伴旅人の和歌に対する歌論です。
天平二年正月十三日、萃于帥老之宅、申宴會也。于時、初春令月、氣淑風和、梅披鏡前之粉、蘭薫珮後之香。加以、曙嶺移雲、松掛羅而傾盖、夕岫結霧、鳥封穀而迷林。庭舞新蝶、空歸故鴈。於是盖天坐地、促膝飛觴。忘言一室之裏、開衿煙霞之外。淡然自放、快然自足。若非翰苑、何以濾情。詩紀落梅之篇。古今夫何異矣。宜賦園梅聊成短詠。
序訓 天平二年正月十三日に、帥の老の宅に萃(あつ)まりて、宴會を申く。時、初春の令月(れいげつ)にして、氣淑(よ)く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後(はいご)の香を薫(かをら)す。加以(しかのみにあらず)、曙の嶺に雲移り、松は羅(うすもの)を掛けて盖(きぬがさ)を傾け、夕の岫(くき)に霧結び、鳥は穀(うすもの)に封(こ)められて林に迷ふ。庭には新蝶(しんてふ)舞ひ、空には故鴈歸る。於是、天を盖(きにがさ)とし地を坐とし、膝を促け觴(さかずき)を飛ばす。言を一室の裏(うち)に忘れ、衿を煙霞の外に開く。淡然と自ら放(ほしきさま)にし、快然と自ら足る。若し翰苑(かんゑん)に非ずは、何を以ちて情を壚(の)べむ。詩に落梅の篇を紀(しる)す。古(いにしへ)と今とそれ何そ異ならむ。宜しく園の梅を賦(ふ)して聊(いささ)かに短詠を成すべし。
私訳 天平二年正月十三日に、大宰の帥の旅人の宅に集まって、宴会を開いた。時期は、初春のよき月夜で、空気は澄んで風は和ぎ、梅は美女が鏡の前で白粉で装うように花を開き、梅の香りは身を飾った衣に香を薫ませたような匂いを漂わせている。それだけでなく、曙に染まる嶺に雲が移り行き、松はその枝に羅を掛け、またその枝葉を笠のように傾け、夕べの谷あいには霧が立ち込め、鳥は薄霧に遮られて林の中で迷い鳴く。庭には新蝶が舞ひ、空には故鴈が北に帰る。ここに、天を立派な覆いとし大地を座敷とし、お互いの膝を近づけ酒を酌み交わす。心を通わせて、他人行儀の声を掛け合う言葉を部屋の片隅に忘れ、正しく整えた衿を大自然に向かってくつろげて広げる。淡々と心の趣くままに振る舞い、快くおのおのが満ち足りている。これを書に表すことが出来ないのなら、どのようにこの感情を表すことが出来るだろう。漢詩に落梅の詩篇がある。感情を表すのに漢詩が作られた昔と和歌の今とで何が違うだろう。よろしく庭の梅を詠んで、いささかの大和歌を作ろうではないか。
旅人は「淡然自放、快然自足。若非翰苑、何以濾情」と述べています。およそ、心の写生です。その時、心の想いを表現するにあたり文字化での技術的な障害を取り払ったものが、一字一音の万葉仮名による表記法です。人麻呂調とでも云うような漢語と万葉仮名とを使用した表意文字の力を最大限に利用して表現するものではありません。
一方、紀貫之は古今和歌集の仮名序で和歌について次のように歌論を展開しています。(標準的な仮名序の文では含まれる、後年に定家が書き入れと思われる解説文はその仮名序の文から抜いてあります)
やまと歌は人の心を種としてよろづの言の葉とぞなれりける 世の中にある人 事 業しげきものなれば心に思ふことを見るもの聞くものにつけて言ひいだせるなり
花に鳴くうぐひす 水に住むかはづの声を聞けば生きとし生けるもの いづれか歌をよまざりける
力をも入れずして天地を動かし目に見えぬ鬼神をもあはれと思はせ男女のなかをもやはらげ猛きもののふの心をもなぐさむるは歌なり
この歌 天地の開け始まりける時よりいできにけり
しかあれども 世に伝はることは久方の天にしては下照姫に始まり
あらがねの地にしてはすさのをの命よりぞおこりける ちはやぶる神世には歌の文字も定まらず すなほにして 言の心わきがたかりけらし 人の世となりて すさのをの命よりぞ 三十文字あまり一文字はよみける
かくてぞ花をめで 鳥をうらやみ 霞をあはれび 露をかなしぶ 心 言葉多く 様々になりにける
遠き所もいでたつ足もとより始まりて 年月をわたり高き山も麓の塵ひぢよりなりて 天雲たなびくまで生ひのぼれるごとくに この歌もかくのごとくなるべし
難波津の歌は帝の御初めなり
安積山の言葉は采女のたはぶれよりよみて
この二歌は歌の父母のやうにてぞ手習ふ人のはじめにもしける
そもそも歌の様六つなり 唐の歌にもかくぞあるべき
その六種の一つにはそへ歌 おほさざきの帝をそへたてまつれる歌
難波津に咲くやこの花冬ごもり今は春べと咲くやこの花
と言へるなるべし
二つにはかぞへ歌
咲く花に思ひつくみのあぢきなさ身にいたづきのいるも知らずて
と言へるなるべし
三つにはなずらへ歌
君に今朝あしたの霜のおきていなば恋しきごとに消えやわたらむ
と言へるなるべし
四つにはたとへ歌
わが恋はよむともつきじ荒磯海の浜の真砂はよみ尽くすとも
と言へるなるべし
五つにはただこと歌
いつはりのなき世なりせばいかばかり人の言の葉うれしからまし
と言へるなるべし
六つにはいはひ歌
この殿はむべも富みけりさき草の三つ葉四つ葉に殿造りせり
と言へるなるべし
今の世の中 色につき人の心花になりにけるより あだなる歌 はかなき言のみいでくれば 色好みの家に 埋れ木の人知れぬこととなりて まめなるところには 花すすき穂にいだすべきことにもあらずなりにたり
その初めを思へば かかるべくなむあらぬ いにしへの世々の帝 春の花のあした 秋の月の夜ごとにさぶらふ人々をめして 事につけつつ歌をたてまつらしめたまふ
あるは花をそふとてたよりなき所にまどひ あるは月を思ふとてしるべなき闇にたどれる心々を見たまひて さかしおろかなりと知ろしめしけむ しかあるのみにあらず さざれ石にたとへ 筑波山にかけて君を願ひ 喜び身に過ぎ 楽しび心に余り 富士の煙によそへて人をこひ 松虫のねに友をしのび 高砂 住の江の松もあひ生ひのやうにおぼえ 男山の昔を思ひいでて 女郎花の一時をくねるにも歌をいひてぞなぐさめける
また春のあしたに花の散るを見 秋の夕ぐれに木の葉の落つるを聞き あるは年ごとに鏡の影に見ゆる雪と浪とを嘆き 草の露水の泡を見てわが身をおどろき あるは昨日は栄えおごりて時を失ひ世にわび 親しかりしもうとくなり あるは松山の浪をかけ 野なかの水をくみ 秋萩の下葉を眺め 暁のしぎの羽がきを数へ あるはくれ竹のうき節を人に言ひ 吉野川をひきて世の中をうらみきつるに 今は富士の山も煙たたずなり 長柄の橋も造るなりと聞く人は歌にのみぞ心をなぐさめける
とあります。 (万葉集のブログであると云う趣旨から意訳は省略します)
また、同時に貫之は仮名序で次のようにも述べています。
この人々をおきて またすぐれたる人も くれ竹の世々に聞こえ 片糸のよりよりに絶えずぞありける これよりさきの歌を集めてなむ 万葉集と名づけられたりける
ここにいにしへのことをも歌の心をもしれる人わづかに一人二人なりき しかあれど これかれ得たるところ得ぬところたがひになむある かの御時よりこの方 年は百年あまり 世は十継になむなりにける いにしへのことをも歌をも知れる人よむ人多からず
つまり、紀貫之もまた歌の本質論において「いにしへのことをも歌の心をもしれる人わづかに」の文章から推察して、旅人の「淡然自放、快然自足。若非翰苑、何以濾情」を越えることは出来なかったようです。ただ、紀貫之は技法を六種に分け、詳しく述べています。ここが違うのでしょう。そして、紹介しませんでしたが平安時代初期を代表する歌人たちの名を挙げ、その作風を評論することで紀貫之は平安時代の作品の方向性を示しています。また、貫之たちは一字一音の万葉仮名(変体仮名)だけで表記された歌だけが持つ特性である「音」だけの表現から、日本語が持つ同音異義の言葉において「遊ぶ」ことに気が付き、それを最大限に活用しました。それも「調べの雅さ」を基調とし、和歌において言葉で「遊ぶ」ことを最低限の作歌ルールとしたようです。それゆえに濁音もまた清音表記とするルールで解釈に幅を持たせました。古今和歌集の特徴として掛け詞、縁語などが多用されていると評論しますが、もし、それがなければ先に見たように旅人たちの梅花の歌三二首の宴でのものと、一体、どこが違うのかと云うことになります。
例として、先の貫之の歌番2について見てみますと、一字一音の万葉仮名(変体仮名)表記の歌の中に二つの景色を見ることが出来ます。その姿は万葉調ではありませんし、大衆がたやすく詠えるようなレベルの歌でもありません。そこが古今調なのでしょう。
曽天悲知弖武春比之美川乃己保礼留遠波留可太遣不乃可世也止久良武 (原文表記)
そてひちてむすひしみつのこほれるをはるかたけふのかせやとくらむ (ひらかな読み)
袖ひぢてむすびし水のこほれるを春立つけふの風やとくらむ (藤原定家自筆伊達家本より)
ケースA;秋に汲んだせせらぎの清水の水が冬に凍り、さらに春の訪れに寒さが緩んだと中国漢詩の句「春風解凍」から解釈する立場
袖浸(ひぢ)て掬(むすび)し水の凍(こほ)れるを春立つ今日の風や解くらむ
ケースB;歌番一の応答に位置し、春がやって来て、寒さの緩むせせらぎの清水を思わず両手で掬ったが、ちょうど、今日吹く春一番の風に身を煽られ手から水がこぼれたと解釈する立場
袖浸(ひぢ)て結(むすび)し水の零(こぼ)れるを春立つ今日の風や疾くらむ
当然、定家もこの解釈を了解していたのでしょう、それでキーワードとなる「むすびし」、「こほれる」、「とくらむ」については語感で解釈を拘束する可能性のある漢字表記を用いていません。しかしながらこの解釈が成り立つとしますと、万葉集に「人麻呂のくびき」が存在したように、古今和歌集に新たな「貫之のくびき」が誕生したことになります。一体、だれが、このような高度な言葉遊びの歌を詠えるのでしょうか。ただ、現代においては、それも関係はないようです、今、古今和歌集の特徴をこのように捕えるような人はいませんし、漢字ひらかな和歌に翻訳したものでしか鑑賞しませんから。
今回、万葉仮名(変体仮名)歌を紹介することから旅人と貫之の和歌への態度をも触れました。これはあくまでも素人のする戯言です。一般的に、このような解釈や理解は行いません。また、古今和歌集の歌と万葉集の万葉仮名歌との間に表記において区分などは存在しないなどとは主張しません。ご来場の方々は大人と思いますので、そこは大人の対応で「あっ、そう」として下さい。そうでなきゃ、大学への受験生と国文の学生さんたちが可哀そうです。
今回は表記方法において平仮名の和歌に分類される歌を中心に鑑賞して行きます。ただし、平仮名和歌ですから、普段に目にする漢字ひらかな交じりの和歌ではありません。つまり、平仮名和歌とは、つぎのようなものです。
万葉集巻二十 大伴家持の歌より、
集歌4305 許乃久礼能 之氣伎乎乃倍乎 保等登藝須 奈伎弖故由奈理 伊麻之久良之母
訓読 木(こ)の暗(くれ)の茂き峯(を)の上(へ)を霍公鳥(ほととぎす)鳴きて越ゆなり今し来らしも
私訳 木の枝下を暗くするように木々が立派に茂る峰の頂をホトトギスが鳴きながら飛び越えていく。今、ホトトギスが鳴く、その季節が来たようだ。
例題として万葉集に載る歌を紹介しましたが、標準的に歌の表記方法について説明する時、平仮名の和歌として有名なのは古今和歌集の歌々です。私たちが目にする一般市販の歌集解説書では、「万葉仮名という漢字だけで書かれた万葉集に対して、純和風の平仮名だけで書かれた古今和歌集」とその歌の表記の特徴を対比して説明されていると思います。今回は、そのような原資料の点検を省略し、使う資料は不確かな伝聞の、さらなる又聞きであるような解説や説明は、一度、棚上げにして、本来の原文表記を材料として鑑賞していきます。
平仮名には、万葉仮名、変体仮名、現代のひらかな(明治三十三年小学令施行規則に載る仮名)が同じ仲間に入ると思います。それぞれは平仮名の進化過程での分類で、文字表現においてその文字の画数は大きく違っていても、それぞれの文字は一字で一音、和語の音のみを表し、表記される文字自体は万葉仮名や変体仮名であっても表意文字としての力を持ちません。それで同じ仲間に入ると考えています。なお、ここでは学問的な定義は行いませんし紹介もしません。ここでの決まりこととして同じ仲間と云うことでご了承ください。
さて、万葉集に載る歌で平仮名だけ、つまり、一字一音の万葉仮名で本格的に和歌が詠われたのを確認ができるのは巻五に載る梅花の歌三二首の宴のものからです。考古学的には木簡に残る「難波津の歌」などから、ずっと、以前から一字一音での万葉仮名で歌は記録されていたと思われますが、作歌を行う時に意図して一字一音の万葉仮名で歌を創り、詠ったのは梅花の歌三二首の宴からと考えられます。それ以前のものが遺物や伝来物として存在するのは口唱で知られる歌を文字として書き取ったと云う結果としてのものと考えます。作歌態度からのものではありません。
色々と能書きを垂れ流しましたが、次に有名な歌人が作歌した平仮名歌を紹介します。万葉集から二人、古今和歌集から一人です。
大伴旅人 万葉集巻五 集歌822
和何則能尓宇米能波奈知流比佐可多能阿米欲里由吉能那何列久流加母 (原文表記)
わかそのにうめのはなちるひさかたのあめよりゆきのなかれくるかも (ひらかな読み)
吾が苑に梅の花散るひさかたの天より雪の流れ来るかも (訓読万葉集)
大伴家持 万葉集巻二十 集歌4297
乎美奈弊之安伎波疑之努藝左乎之可能都由和氣奈加牟多加麻刀能野曽 (原文表記)
をみなへしあきはきしぬきさをしかのつゆわけなかむたかまとののそ (ひらかな読み)
をみなへし秋萩しのぎさを鹿の露別け鳴かむ高円の野ぞ (訓読万葉集)
紀貫之 古今和歌集 歌番2
曽天悲知弖武春比之美川乃己保礼留遠波留可太遣不乃可世也止久良武 (原文表記)
そてひちてむすひしみつのこほれるをはるかたけふのかせやとくらむ (ひらかな読み)
袖ひぢてむすびし水のこほれるを春立つけふの風やとくらむ (藤原定家自筆伊達家本より)
今回のテーマはこの三人の歌を紹介して、本来の趣旨は終わりです。平仮名歌ですから、それを紹介したところで、終わりです。また、表記方法において、三人の作品には相違はありません。それで、原文とその現代語訳を紹介すれば、終わりと云うことになります。
ただし、紹介するものに違和感を持たれる御方がいらっしゃると思います。その違和感の背景を紹介しますと、現代の古典文学の研究は鎌倉時代初期に藤原定家が翻訳したものをテキストとして使用するのが基準で、万葉集だけが鎌倉時代中期に仙覚が残した西本願寺本万葉集を底本とした校本万葉集をテキストとして使用します。また、江戸から明治時代では万葉集もまた訓読みされた訓読万葉集(有名なところでは鹿持雅澄の万葉集古義)をテキストとして使用するため、訓読万葉集と古今和歌集との相違を理解するのは困難でしょう。元々、それらのテキストは漢字ひらかな交じりの表記スタイルに統一することを目的に原文から翻訳したものですから、表記スタイルにおいては相違があってはいけないのです。
一方、今日の原本の姿を復元しようとする研究は、ここで示したような原文表記の姿を示します。この原文表記の姿を見て、深刻な問題と思われるか、それとも、それがどうしたと思われるかは立場です。ただ、単純に表記方法からの古今和歌集を特徴的に「平仮名の和風の和歌」と説明するものは詐欺的な真っ赤なウソであることは明白です。万葉集の平仮名和歌と古今和歌集の歌とには表記方法において相違は存在しません。およそ、和歌の表記方法について平仮名と云う音字表記に絞れば万葉集から古今和歌集への進化はありません。一方、表記方法を楷書や崩し草仮名連綿と云う書体(書風)に絞れば進化や変化はあります。ただ、それが貫之時代にはどうであったかは日本語や書道の歴史では資料が不足するために不明という扱いとなっています。
<以下、おまけです>
書筆における書体について考えますと、万葉集は楷書だったと思われますが、古今和歌集については不明です。古今和歌集より少し前に作成された新撰万葉集の和歌が楷書で書筆されてあることから楷書のスタイルを否定できません。一方、古今和歌集の奉呈と同時代か、やや下るとされる秋萩帖の書体は変体仮名での崩しの連綿体ですので、古今和歌集が崩しの連綿体で書筆された可能性もあります。ただし、十世紀初頭に変体仮名での崩しの連綿体が、奉呈される歌集を書筆することにおいて公に認められた書体であったかは確証がありません。歴史的資料として崩し連綿体に先行する書体である草仮名の文章として有名な「有年申文」は貞観九年(867)のものですから、古今和歌集奉呈の延喜五年(905)までに平仮名表記法がどれほど進化を遂げたのでしょうか。自己流の崩しでは文字は読めません。文字が文字としてあるためには崩しにも共通の認識とルールが必要です。ここらあたりの研究は残される資料が不足しているため非常に困難なようです。
なお、石川九楊氏が「万葉仮名でよむ『万葉集』」(岩波書店)で論を展開される時、古今和歌集の古写本である秋萩帖、寸松庵色紙、高野切の書筆の文字に、崩しの文字ですが、変体仮名の文字を確実に捕えられています。書筆スタイルが楷書と崩しの連綿との相違があっても歌を認識する時、そこには万葉仮名(または変体仮名)と云う漢字の文字があります。つまり、歌を表記すると云う作業では、本質においては同じではないでしょうか。
しかしながら、紀貫之は古今和歌集の仮名序の文を閉じるにあたって「歌の様をも知り ことの心を得たらむ人は 大空の月を見るがごとくにいにしへを仰ぎて 今をこひざらめかも」と述べ、古今和歌集と万葉集とを比べれば、きっと、古今の方が好いと云うであろうと述べています。
では、何が違うのでしょうか。大伴旅人と紀貫之の両者は、この一字一音の万葉仮名(変体仮名)だけで歌を詠うことについて歌論を書いていますから、それを鑑賞してみたいと思います。
最初に大伴旅人の和歌に対する歌論です。
天平二年正月十三日、萃于帥老之宅、申宴會也。于時、初春令月、氣淑風和、梅披鏡前之粉、蘭薫珮後之香。加以、曙嶺移雲、松掛羅而傾盖、夕岫結霧、鳥封穀而迷林。庭舞新蝶、空歸故鴈。於是盖天坐地、促膝飛觴。忘言一室之裏、開衿煙霞之外。淡然自放、快然自足。若非翰苑、何以濾情。詩紀落梅之篇。古今夫何異矣。宜賦園梅聊成短詠。
序訓 天平二年正月十三日に、帥の老の宅に萃(あつ)まりて、宴會を申く。時、初春の令月(れいげつ)にして、氣淑(よ)く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後(はいご)の香を薫(かをら)す。加以(しかのみにあらず)、曙の嶺に雲移り、松は羅(うすもの)を掛けて盖(きぬがさ)を傾け、夕の岫(くき)に霧結び、鳥は穀(うすもの)に封(こ)められて林に迷ふ。庭には新蝶(しんてふ)舞ひ、空には故鴈歸る。於是、天を盖(きにがさ)とし地を坐とし、膝を促け觴(さかずき)を飛ばす。言を一室の裏(うち)に忘れ、衿を煙霞の外に開く。淡然と自ら放(ほしきさま)にし、快然と自ら足る。若し翰苑(かんゑん)に非ずは、何を以ちて情を壚(の)べむ。詩に落梅の篇を紀(しる)す。古(いにしへ)と今とそれ何そ異ならむ。宜しく園の梅を賦(ふ)して聊(いささ)かに短詠を成すべし。
私訳 天平二年正月十三日に、大宰の帥の旅人の宅に集まって、宴会を開いた。時期は、初春のよき月夜で、空気は澄んで風は和ぎ、梅は美女が鏡の前で白粉で装うように花を開き、梅の香りは身を飾った衣に香を薫ませたような匂いを漂わせている。それだけでなく、曙に染まる嶺に雲が移り行き、松はその枝に羅を掛け、またその枝葉を笠のように傾け、夕べの谷あいには霧が立ち込め、鳥は薄霧に遮られて林の中で迷い鳴く。庭には新蝶が舞ひ、空には故鴈が北に帰る。ここに、天を立派な覆いとし大地を座敷とし、お互いの膝を近づけ酒を酌み交わす。心を通わせて、他人行儀の声を掛け合う言葉を部屋の片隅に忘れ、正しく整えた衿を大自然に向かってくつろげて広げる。淡々と心の趣くままに振る舞い、快くおのおのが満ち足りている。これを書に表すことが出来ないのなら、どのようにこの感情を表すことが出来るだろう。漢詩に落梅の詩篇がある。感情を表すのに漢詩が作られた昔と和歌の今とで何が違うだろう。よろしく庭の梅を詠んで、いささかの大和歌を作ろうではないか。
旅人は「淡然自放、快然自足。若非翰苑、何以濾情」と述べています。およそ、心の写生です。その時、心の想いを表現するにあたり文字化での技術的な障害を取り払ったものが、一字一音の万葉仮名による表記法です。人麻呂調とでも云うような漢語と万葉仮名とを使用した表意文字の力を最大限に利用して表現するものではありません。
一方、紀貫之は古今和歌集の仮名序で和歌について次のように歌論を展開しています。(標準的な仮名序の文では含まれる、後年に定家が書き入れと思われる解説文はその仮名序の文から抜いてあります)
やまと歌は人の心を種としてよろづの言の葉とぞなれりける 世の中にある人 事 業しげきものなれば心に思ふことを見るもの聞くものにつけて言ひいだせるなり
花に鳴くうぐひす 水に住むかはづの声を聞けば生きとし生けるもの いづれか歌をよまざりける
力をも入れずして天地を動かし目に見えぬ鬼神をもあはれと思はせ男女のなかをもやはらげ猛きもののふの心をもなぐさむるは歌なり
この歌 天地の開け始まりける時よりいできにけり
しかあれども 世に伝はることは久方の天にしては下照姫に始まり
あらがねの地にしてはすさのをの命よりぞおこりける ちはやぶる神世には歌の文字も定まらず すなほにして 言の心わきがたかりけらし 人の世となりて すさのをの命よりぞ 三十文字あまり一文字はよみける
かくてぞ花をめで 鳥をうらやみ 霞をあはれび 露をかなしぶ 心 言葉多く 様々になりにける
遠き所もいでたつ足もとより始まりて 年月をわたり高き山も麓の塵ひぢよりなりて 天雲たなびくまで生ひのぼれるごとくに この歌もかくのごとくなるべし
難波津の歌は帝の御初めなり
安積山の言葉は采女のたはぶれよりよみて
この二歌は歌の父母のやうにてぞ手習ふ人のはじめにもしける
そもそも歌の様六つなり 唐の歌にもかくぞあるべき
その六種の一つにはそへ歌 おほさざきの帝をそへたてまつれる歌
難波津に咲くやこの花冬ごもり今は春べと咲くやこの花
と言へるなるべし
二つにはかぞへ歌
咲く花に思ひつくみのあぢきなさ身にいたづきのいるも知らずて
と言へるなるべし
三つにはなずらへ歌
君に今朝あしたの霜のおきていなば恋しきごとに消えやわたらむ
と言へるなるべし
四つにはたとへ歌
わが恋はよむともつきじ荒磯海の浜の真砂はよみ尽くすとも
と言へるなるべし
五つにはただこと歌
いつはりのなき世なりせばいかばかり人の言の葉うれしからまし
と言へるなるべし
六つにはいはひ歌
この殿はむべも富みけりさき草の三つ葉四つ葉に殿造りせり
と言へるなるべし
今の世の中 色につき人の心花になりにけるより あだなる歌 はかなき言のみいでくれば 色好みの家に 埋れ木の人知れぬこととなりて まめなるところには 花すすき穂にいだすべきことにもあらずなりにたり
その初めを思へば かかるべくなむあらぬ いにしへの世々の帝 春の花のあした 秋の月の夜ごとにさぶらふ人々をめして 事につけつつ歌をたてまつらしめたまふ
あるは花をそふとてたよりなき所にまどひ あるは月を思ふとてしるべなき闇にたどれる心々を見たまひて さかしおろかなりと知ろしめしけむ しかあるのみにあらず さざれ石にたとへ 筑波山にかけて君を願ひ 喜び身に過ぎ 楽しび心に余り 富士の煙によそへて人をこひ 松虫のねに友をしのび 高砂 住の江の松もあひ生ひのやうにおぼえ 男山の昔を思ひいでて 女郎花の一時をくねるにも歌をいひてぞなぐさめける
また春のあしたに花の散るを見 秋の夕ぐれに木の葉の落つるを聞き あるは年ごとに鏡の影に見ゆる雪と浪とを嘆き 草の露水の泡を見てわが身をおどろき あるは昨日は栄えおごりて時を失ひ世にわび 親しかりしもうとくなり あるは松山の浪をかけ 野なかの水をくみ 秋萩の下葉を眺め 暁のしぎの羽がきを数へ あるはくれ竹のうき節を人に言ひ 吉野川をひきて世の中をうらみきつるに 今は富士の山も煙たたずなり 長柄の橋も造るなりと聞く人は歌にのみぞ心をなぐさめける
とあります。 (万葉集のブログであると云う趣旨から意訳は省略します)
また、同時に貫之は仮名序で次のようにも述べています。
この人々をおきて またすぐれたる人も くれ竹の世々に聞こえ 片糸のよりよりに絶えずぞありける これよりさきの歌を集めてなむ 万葉集と名づけられたりける
ここにいにしへのことをも歌の心をもしれる人わづかに一人二人なりき しかあれど これかれ得たるところ得ぬところたがひになむある かの御時よりこの方 年は百年あまり 世は十継になむなりにける いにしへのことをも歌をも知れる人よむ人多からず
つまり、紀貫之もまた歌の本質論において「いにしへのことをも歌の心をもしれる人わづかに」の文章から推察して、旅人の「淡然自放、快然自足。若非翰苑、何以濾情」を越えることは出来なかったようです。ただ、紀貫之は技法を六種に分け、詳しく述べています。ここが違うのでしょう。そして、紹介しませんでしたが平安時代初期を代表する歌人たちの名を挙げ、その作風を評論することで紀貫之は平安時代の作品の方向性を示しています。また、貫之たちは一字一音の万葉仮名(変体仮名)だけで表記された歌だけが持つ特性である「音」だけの表現から、日本語が持つ同音異義の言葉において「遊ぶ」ことに気が付き、それを最大限に活用しました。それも「調べの雅さ」を基調とし、和歌において言葉で「遊ぶ」ことを最低限の作歌ルールとしたようです。それゆえに濁音もまた清音表記とするルールで解釈に幅を持たせました。古今和歌集の特徴として掛け詞、縁語などが多用されていると評論しますが、もし、それがなければ先に見たように旅人たちの梅花の歌三二首の宴でのものと、一体、どこが違うのかと云うことになります。
例として、先の貫之の歌番2について見てみますと、一字一音の万葉仮名(変体仮名)表記の歌の中に二つの景色を見ることが出来ます。その姿は万葉調ではありませんし、大衆がたやすく詠えるようなレベルの歌でもありません。そこが古今調なのでしょう。
曽天悲知弖武春比之美川乃己保礼留遠波留可太遣不乃可世也止久良武 (原文表記)
そてひちてむすひしみつのこほれるをはるかたけふのかせやとくらむ (ひらかな読み)
袖ひぢてむすびし水のこほれるを春立つけふの風やとくらむ (藤原定家自筆伊達家本より)
ケースA;秋に汲んだせせらぎの清水の水が冬に凍り、さらに春の訪れに寒さが緩んだと中国漢詩の句「春風解凍」から解釈する立場
袖浸(ひぢ)て掬(むすび)し水の凍(こほ)れるを春立つ今日の風や解くらむ
ケースB;歌番一の応答に位置し、春がやって来て、寒さの緩むせせらぎの清水を思わず両手で掬ったが、ちょうど、今日吹く春一番の風に身を煽られ手から水がこぼれたと解釈する立場
袖浸(ひぢ)て結(むすび)し水の零(こぼ)れるを春立つ今日の風や疾くらむ
当然、定家もこの解釈を了解していたのでしょう、それでキーワードとなる「むすびし」、「こほれる」、「とくらむ」については語感で解釈を拘束する可能性のある漢字表記を用いていません。しかしながらこの解釈が成り立つとしますと、万葉集に「人麻呂のくびき」が存在したように、古今和歌集に新たな「貫之のくびき」が誕生したことになります。一体、だれが、このような高度な言葉遊びの歌を詠えるのでしょうか。ただ、現代においては、それも関係はないようです、今、古今和歌集の特徴をこのように捕えるような人はいませんし、漢字ひらかな和歌に翻訳したものでしか鑑賞しませんから。
今回、万葉仮名(変体仮名)歌を紹介することから旅人と貫之の和歌への態度をも触れました。これはあくまでも素人のする戯言です。一般的に、このような解釈や理解は行いません。また、古今和歌集の歌と万葉集の万葉仮名歌との間に表記において区分などは存在しないなどとは主張しません。ご来場の方々は大人と思いますので、そこは大人の対応で「あっ、そう」として下さい。そうでなきゃ、大学への受験生と国文の学生さんたちが可哀そうです。