《創られた賢治から愛すべき真実の賢治に》
そして相馬は、 これまでともすれば美化されがちだった賢治文学の根源に関わる問題をもう一度洗い直してみる時期に来ているような気がするのである。本稿では、花巻農学校に就職した前後の状況についていくつかのささやかな問題を提起してみようと思う。
<『宮沢賢治 第6号』(洋々社、昭和61年)187pより>と論をスタートさせ、「生徒諸君に寄せる」に関することとか、日蓮宗志向の動機に関わることとかについて論じ、最後の方では
これとて賢治の本音ではあるまい。本音はむしろ、「学校をやめて一月から東京へ出る筈だつた」のであり、それが諸般の事情から延期せざるを得なくなったので、宣言どおり取りあえず〈本統の百姓〉の真似ごとをすることになったのである。「春」と題する詩篇は、そういう自分の覚悟を述べたものであろう。
陽が照って鳥が啼き
あちこちの楢の林も
けむるとき
ぎちぎちと鳴る汚い掌を
おれはこれからもつことになる
しかし、賢治は作品においてはもちろんのこと、書簡においても、かなり思い切った自己脚色を試みている。友人や教え子に宛てた書簡に作品の一節を挿入するようなことは決して珍しいことではない。こんなことは創作にたずさわる者の間ではよく見受けられることであるが、賢治の場合はその脚色(もしくは潤色)されたイメージで彼の実人生が語られ、そこから逆に作品を意味づけていることがあまりに多い。
<『宮沢賢治 第6号』(洋々社、昭和61年)195pより>陽が照って鳥が啼き
あちこちの楢の林も
けむるとき
ぎちぎちと鳴る汚い掌を
おれはこれからもつことになる
しかし、賢治は作品においてはもちろんのこと、書簡においても、かなり思い切った自己脚色を試みている。友人や教え子に宛てた書簡に作品の一節を挿入するようなことは決して珍しいことではない。こんなことは創作にたずさわる者の間ではよく見受けられることであるが、賢治の場合はその脚色(もしくは潤色)されたイメージで彼の実人生が語られ、そこから逆に作品を意味づけていることがあまりに多い。
と展開していた。
まさにそのとおりだと私も肯った。一般に作品に「脚色(もしくは潤色)」はつき物であり、読者は皆そのことを弁えていてそこに書かれていることは安直に「実人生」に還元できないということは知っているのだが、たしかに、どいうわけか賢治の場合に限っては「賢治の場合はその脚色(もしくは潤色)されたイメージで彼の実人生が語られ、そこから逆に作品を意味づけていることがあまりに多い」と、私もそう思わざるを得なかったことがしばしばあったからである。
そして、相馬は次のようなことを述べて締めくくっていた。
質量共にこれほどの労作・佳作を書き残した賢治であればこそ実人生においては〈邪道〉を生きる生活無能者であり、自然科学の学究ではあるが気質的にはシャマニズム的〈狂気〉を内蔵していた無頼はであっても一向に不思議ではないのだが、どういうわけか賢治研究者の中には、裸の〈宮沢賢治〉を素直に裸だと認めたがらず、各人各様にきらびやかな衣裳を着せて得意になっている人が少なくない。作品の評価と合わせて、裸身の賢治を自分の肉眼で捉えてほしいものである。
<『宮沢賢治 第6号』(洋々社、昭和61年)195pより>私は一瞬言葉を失った。ここまで強烈な言葉〝〈邪道〉〟を用いて、しかも賢治のことを
〈邪道〉を生きる生活無能者であり
と言い切っていることにである。
そしてあることを思い出した。それは、吉田司が『宮澤賢治殺人事件』において、賢治のことを出羽三山の〝即身物(ミイラ)信仰〟を持ちだして、
坊さんが地に掘った穴の中で飲まず食わず、ミイラになりながら、農民救済のために「五穀豊穣」を祈り続けて死んでゆく。ミイラ化した僧の遺体は、湯舟できれいに洗って、金銀の法衣を着せ、お寺の中央の祭壇に飾る。
<『宮澤賢治殺人事件』(吉田司著、太田出版)252pより>と述べて、賢治をこの〝即身物〟になぞらえていたことを。ただし私は、このなぞらえ方は否定仕切れないもののどうも抵抗感があった。
ところが、この度先のような相馬の賢治評価を知ったならば、一概に吉田の賢治の見方を切り捨てるわけにもゆかなくなった。相馬の見方はある意味吉田のそれよりも強烈だからだ。
そしてこの時思い出した。この「相馬正一」という名がどこにあったかを。
 続きへ。
続きへ。前へ
 。
。 ”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。
”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。【『宮澤賢治と高瀬露』出版のご案内】

 その概要を知りたい方ははここをクリックして下さい。
その概要を知りたい方ははここをクリックして下さい。













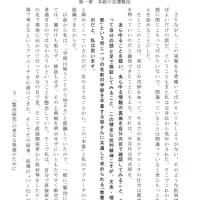
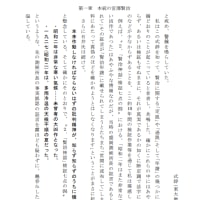
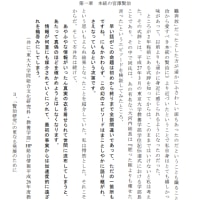
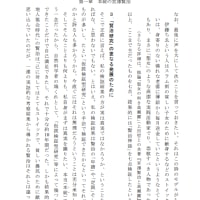

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます