『共苦する力』をはじめとして,亀山郁夫には数多くのドストエフスキーに関する文芸評論があります。ドストエフスキー以外にもあるのかもしれませんが,僕はそうしたものは読んでいません。したがって僕が知っているのは,ドストエフスキーを評論する亀山郁夫だけです。そして亀山のドストエフスキー評論には,際立った特徴があると僕は感じています。簡単にいえば,亀山の評論には,亀山自身の人間性というものが,著しく露出しているように思えるのです。
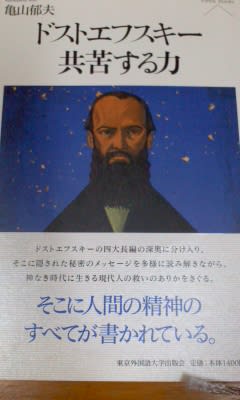
これは亀山のドストエフスキー評論に限ったことではなく,文芸評論家による文芸評論というのは,その評論家自身の自己表現です。というか,それは職業として文芸評論をする人間に限ったことでもなく,だれであるにせよ,評論というのは評論する人間の自己表現であるといえるでしょう。ですから,多かれ少なかれ,そこに評論家自身の個性が表出してくること自体は,当然といえば当然のことです。ただ,亀山の場合,それが極度であるように僕には感じられます。少なくとも,僕はこんなに自己表出していると感じられるような文芸評論を書く人を,亀山以外には知りません。
表出するその個性を一言で表すなら,亀山はロマンティストであると僕はいいます。その亀山のロマンティシズムが激しく文章に表れるとき,正直なところ僕は辟易としてしまうこともあります。ただ,これは諸個人の感受性の差異に還元される筈。僕が辟易とする場面を,むしろ好ましく感じる読者がいたとしても,まったく驚くには値しません。
このような理由から,亀山のドストエフスキー論に接するとき,ドストエフスキーの小説を知っているというだけでは不十分なのではないかと,僕はあるときから思うようになりました。亀山の評論を理解するために必要なのは,むしろ亀山がどんな人なのかを知ることなのかもしれません。
現実的に存在する個物res singularisであるXが原因causaとなって,同じ属性attributumの別の個物であるYの存在existentiaが消滅する。このとき,XがYを限定し,YはXによって限定されているということ,もっと具体的にいえばそこで存在の限定が行われているということについては,異論は出ないと想定し,先に進めます。このとき,僕はこのことを,XがYの存在を否定し,YはXによって存在を否定されていると理解します。いい換えれば,少なくともこの場合においては,存在の限定determinatioと存在の否定negatioとを,同一の意味として解するということです。
このことは,おそらく力potentiaという観点から考えれば,その妥当性をよりよく理解できるものと思います。Yの現実的存在が消滅するというのは,Yの現実的本性actualis essentiaが消滅するというのと同じことです。スピノザの哲学において実在性realitasというのは,力という観点から把握される限りでの本性です。したがって本性があるならば実在性もあります。逆に本性が消滅するならば実在性も消失すると考えなければなりません。もっともこの例でいえば,Yの存在が消滅するという前提なのですから,存在が消滅したものに実在性が備わっていると主張すること自体が不条理です。
よって,一般的にいって,ある事物が実在する,あるいは実在し得るということは,その事物の力を示します。これに反して,ある個物に関してそれが現実的に存在しないとか,存在し得ないという場合には,それはその個物の無力impotentia,これは必ずしも全面的な無力とはいえず,部分的な無力というべきかもしれませんが,少なくとも一定の意味における無力を示すのは間違いありません。このこと自体は,第一部定理一一第三の証明でスピノザが前提している事柄を,現実的に存在する場合の個物に該当させたといえますから,スピノザの哲学のうちで妥当性を有すると僕は考えます。
無力というのが力の否定であることはとくに説明するまでもなく明らかです。よって力あるものを無力なものにするということは,そのものを否定するnegareという意味になると僕は考えるのです。
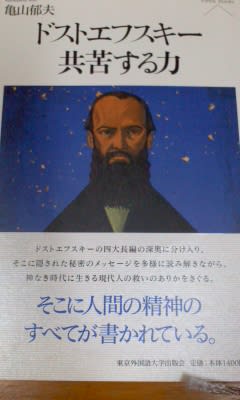
これは亀山のドストエフスキー評論に限ったことではなく,文芸評論家による文芸評論というのは,その評論家自身の自己表現です。というか,それは職業として文芸評論をする人間に限ったことでもなく,だれであるにせよ,評論というのは評論する人間の自己表現であるといえるでしょう。ですから,多かれ少なかれ,そこに評論家自身の個性が表出してくること自体は,当然といえば当然のことです。ただ,亀山の場合,それが極度であるように僕には感じられます。少なくとも,僕はこんなに自己表出していると感じられるような文芸評論を書く人を,亀山以外には知りません。
表出するその個性を一言で表すなら,亀山はロマンティストであると僕はいいます。その亀山のロマンティシズムが激しく文章に表れるとき,正直なところ僕は辟易としてしまうこともあります。ただ,これは諸個人の感受性の差異に還元される筈。僕が辟易とする場面を,むしろ好ましく感じる読者がいたとしても,まったく驚くには値しません。
このような理由から,亀山のドストエフスキー論に接するとき,ドストエフスキーの小説を知っているというだけでは不十分なのではないかと,僕はあるときから思うようになりました。亀山の評論を理解するために必要なのは,むしろ亀山がどんな人なのかを知ることなのかもしれません。
現実的に存在する個物res singularisであるXが原因causaとなって,同じ属性attributumの別の個物であるYの存在existentiaが消滅する。このとき,XがYを限定し,YはXによって限定されているということ,もっと具体的にいえばそこで存在の限定が行われているということについては,異論は出ないと想定し,先に進めます。このとき,僕はこのことを,XがYの存在を否定し,YはXによって存在を否定されていると理解します。いい換えれば,少なくともこの場合においては,存在の限定determinatioと存在の否定negatioとを,同一の意味として解するということです。
このことは,おそらく力potentiaという観点から考えれば,その妥当性をよりよく理解できるものと思います。Yの現実的存在が消滅するというのは,Yの現実的本性actualis essentiaが消滅するというのと同じことです。スピノザの哲学において実在性realitasというのは,力という観点から把握される限りでの本性です。したがって本性があるならば実在性もあります。逆に本性が消滅するならば実在性も消失すると考えなければなりません。もっともこの例でいえば,Yの存在が消滅するという前提なのですから,存在が消滅したものに実在性が備わっていると主張すること自体が不条理です。
よって,一般的にいって,ある事物が実在する,あるいは実在し得るということは,その事物の力を示します。これに反して,ある個物に関してそれが現実的に存在しないとか,存在し得ないという場合には,それはその個物の無力impotentia,これは必ずしも全面的な無力とはいえず,部分的な無力というべきかもしれませんが,少なくとも一定の意味における無力を示すのは間違いありません。このこと自体は,第一部定理一一第三の証明でスピノザが前提している事柄を,現実的に存在する場合の個物に該当させたといえますから,スピノザの哲学のうちで妥当性を有すると僕は考えます。
無力というのが力の否定であることはとくに説明するまでもなく明らかです。よって力あるものを無力なものにするということは,そのものを否定するnegareという意味になると僕は考えるのです。













