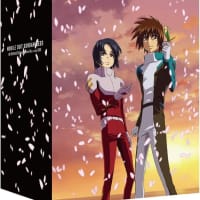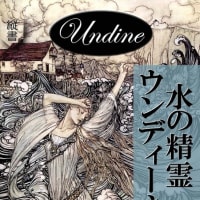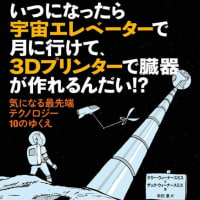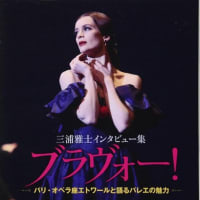今回、エミリー・ディキンスンの詩がひとつ出てくるんですけど……実をいうと小説のはじまる一番最初にも、本当はエミリー・ディキンスンの詩を書いておく予定でした(^^;)
でもなんでそれがないかっていうと、単に書き忘れたのです

なので、代わりにここに書き記しておきたいと思うんですけど……なんていうか、ある程度お話が進んだあとか、小説を最後ま読んだあと、この詩を読むとなんとなく意味がわかるという、そんな感じかな、なんて思いますm(_ _)m
>>悲しみのようにひそやかに
夏は過ぎ去った――
遂に、あまりにもひそやかで
裏切りともおもえないほどに――
もうとうに始まった黄昏のように
蒸留された静けさ、
またはみずから引きこもって
午後を過ごしている「自然」――
夕暮れの訪れは早くなり――
朝の輝きはいつもと違う――
ねんごろで、しかも胸の痛むような優美さ、
立ち去ろうとする客人のように――
このようにして、翼もなく
船に乗ることもなく
わたしたちの夏は軽やかに逃れ去った、
美しきものの中に。
(『ディキンスン詩集』新倉俊一さん訳編/思潮社より)
ではでは、↓にある、「わたしが死のために止まることが出来なかったので……」という詩については、また次回前文のほうに載せたいと思っています♪(^^)
それではまた~!!

ぼくの大好きなソフィおばさん。-【5】-
「きのうわたし、先生にどこまでお話したのだったのかしら?」
翌日も午後の二時にソフィ・デイヴィスのことをロイが訪ねてみると、彼女はベッドの上に体を起こして本を読んでいるところだった。ロイが本のタイトルに目を落としてみると、<エミリー・ディッキンソン詩集>と、そこには書いてあった。
「エミリー・ディキンスンがお好きなんですか?」
「ええ。だって、彼女の詩の中には死を歌ったものが多いでしょう?そのせいかどうか、読んでいるととても慰められますの。彼女の代表的な詩のひとつである、「わたしが死のために止まることが出来なかったので……」なんて、本当に素晴らしいですわ。エミリーは内陸育ちだったかもしれませんけど、わたしは浜育ちでしたからね、彼女の詩のひとつの――」
そう言ってソフィは、本のページを繰ると、目当ての詩を見つけて、ロイに向かって指差していた。
<歓喜とは
陸に生まれた心が海へと向かうこと
街並みを通りすぎ 岬をこえて
永遠へと深々と入ってゆくこと――
水夫たちには理解できるだろうか
山に囲まれて育った私たちが
岸から一海里と離れぬうちに覚える
この神聖な恍惚を――>
「むしろ逆に、海辺で育ってしまうと、こうした発想は起きないかもしれませんわね。先生、わたし最近思うんですよ。エミリーは死者の国へ行くことを<海を渡る>といったように表現したことがあったと思いますけど、死ぬっていうのは、もしかしてそういうことなんじゃないかって」
「そうですね。人間の意識というか霊魂といったものが、遠く見知らぬ海を渡って、ある種の魂の冒険ののちに天国のような場所へ向かうのかもしれません」
「まあ、先生ったら異教徒のようなことをおっしゃって!」
六月だというのに、薄手のカーディガンを着ているソフィは、老婦人としてとても魅力的であった。コーエン院長に聞いた話によると、ソフィは朝の回診時にはすでに身仕舞いをこざっぱりと整え、いつも清潔な様子で感じよく話をするという。
そしてコーエン院長が「その気になればとても社交的になれるが、実際はそうしたことを好まない女性であるように見える」……と指摘したのは、実に的を得た表現であるように、ロイには思えた。
「確かに僕は、キリスト教の理念を大切にしたホスピスで働いてますし、ソフィさんもご存知のとおり、ホスピスに付属したチャペルに日曜ごと、患者と出席してもいますよ。けれど結局<死>とか<天国>といったものは――実際に自分が死んでみなけりゃわからないことですからね。たとえば、一般に自殺者の魂は天国へ行けないと言われますが、聖書にはそんなこと、明確に書いてなんていないわけですから。ただ、十戒のうちの第六戒、「汝殺すなかれ」という言葉の内には、己のことも殺してはならぬということも含むと解釈されているだけですよ。そして僕が死んで天国へ行った時に、イエス・キリストを信じていたけれども人生の暗闇に飲み込まれ、自殺した死者の魂がそこにいたとしますね?そしたら果たして僕は言うでしょうか……「なんでこいつが天国にいるんだ!おかしいじゃないか」なんていうことを?」
「わたし、今の言葉で先生のことがますます好きになりましたわ」
ソフィは老眼鏡を外すと、エミリー・ディキンスンの詩集を閉じて、ベッドの斜め向かいに座る精神科医と向き合った。
「先生、わたし以外にも先生にお話を聞いて欲しい患者さんが他にもたくさんいらっしゃることですし、きのうの続きから早速お願いします」
「そうですね。じゃあ、ええと確か……三十歳の時にご結婚されたバートランドさんに、九歳の男の子がいらっしゃって――会った瞬間に彼に対して気の毒に思ったというところまで、きのうはお話されていたと思いますが……」
ロイは今目の前にいる患者の顔色や服装についてなど、速記で軽く書き記すと、クリップボードに止めた紙に彼女が話したことを、この日もさらさらと書き留めることにした。
* * * * * * *
バートランド=フィッシャーがノースルイスに持つ別邸は、門から邸宅までの距離が軽く五十メートルはあった。青銅の柵がリモコンによって自動で開くと、白のストレッチ型リムジンは玄関口まで進んでいき、恭しく運転手がドアを開くのと同時、ソフィはその壮麗な屋敷の天辺までを一息で見上げた。
壁は赤銅色で、ファザードには随分凝った彫刻が施してあった。庭にはお約束とばかり噴水が吹き上げており、玄関から屋敷の中へ入ってみると、今度は大理石の美しい床がソフィの足を迎えた。二階へ続く中央階段は広々としており、親柱に掘られた女神像がまず真っ先にソフィの心を捉える。
「まあ、本当に、なんて素敵なお屋敷……」
ソフィが惚れ惚れとして感嘆の声を上げていると、
「気に入ったかね?」
バートランドはしっかりした響きの低音の声で、そう新妻の耳元に囁いた。
「ええ、とっても。それで、お坊ちゃんのお部屋はどちらのほうになるのかしら?」
結婚前にちょっとした淑女教育を受けていたソフィは、丁寧な口調でそう言い、手袋を外しながら広い玄関ホールをきょろきょろと見回した。
「サラ、アンドリューはどうした?」
玄関口では、何人もの召使いが屋敷の主人を出迎えていたが、サラと呼ばれた女中頭の中年女は、バートランドに睨まれ一瞬怯えたような顔の表情になる。
「大体、四時ごろお父さま方がお着きになると、前もってお知らせしてあったのですが……」
サラは見るからにおどおどした口調で言った。彼女は今年五十になる女で、フィッシャー家には二十歳の時からすでにもう三十年も勤めていた。癖のある赤毛をどうにかまとめてひっつめた、顔にそばかすの浮かぶやせぎすの女である。
「まさかとは思うが、臍を曲げているわけではあるまいな。もっとも、そんなのも新しいお母さんの姿を見れば、すっかり元に戻るに違いないが……」
「いいのよ、バート。子供のすることですもの。それに、お夕食の時にはどのみち顔を合わせることになるでしょうし……」
サラも、女中のひとりのアンナも、バートランドが二十も若いおつむの足りなそうな娘にキスするのを見て、すっかり呆れていた。主人の女遊びの激しさはつとに有名で、若いメイドの中には手出しされた者もあったが、そんなことをこの新妻が果たして知っているのかどうか――サラはそんな会話をアンナと目と目で終えていた。
ソフィが自分の部屋で着替えを済ませ、夕食の席に着こうとすると、義理の息子となったアンドリューがすでに食堂のテーブルにいるのがわかった。バートランドは表情筋のあまり動かない、いかめしい顔つきのまま家長席に座っており、ソフィはその右に、アンドリューは左に席を占めている。
長方形の長いテーブルの上には、ダマスク織りのテーブルクロスが敷かれ、六月の夏の花々が花器に美しく装われていた。新しく家族となった三人は、婚約時に一度顔を合わせていたとはいえ、これが二度目の顔合わせである。バートと息子アンドリューの間には共通の会話など何もなかったし、ソフィはバートが何も話さないのを見て、仕方なしにアンドリューに学校のことを聞いてみることにした。
「学校へは行ってないんです、僕」
何かの科白を読み上げる時のような、妙に平板な声でアンドリューは答えた。
「えっと、でも不登校ってわけじゃないんでしょう?」
(もしそうだったらどうしようかしら)と思ったソフィの考えは、「優秀な家庭教師をつけてある」というバートの声で遮られる形となった。
「それでも、去年までは学校へ行っておったんだがな。サラが言うには原因不明の腹痛が起きるとかで、以来、屋敷の図書室に閉じこもって本ばかり読んでおるとか。まあ、べつに構わん。私立中学の試験にさえ無事パスしてくれればな。前にも言ったとおり、あの学校にはおまえが仲良くしておいて将来的に損のない家柄の子たちが大勢いるんだ。そういう子たちと若いうちからコネクションを作って一緒に遊んでおけば、おまえがいつかわしの事業を継いだ時、互いの会社を助けあえるというものだろう」
「そうですね、お父さん」
バートは息子のほうを見ていなかったが、アンドリューの顔というか目の表情に、ちらと軽蔑と嘲笑の色が走るのを、ソフィは見逃さなかった。
「スポーツは、好きじゃないの?」
どうしても間が持たなくて、仕方なくソフィがそう聞いた時、
「ハハハ」と、バートはここで初めて、さも愉快そうに笑った。「こいつは誰に似たのか、スポーツのほうがからきし駄目ときてる。とてもわしの息子とも思えん。野球でもサッカーでもバスケでも、何かひとつでいいからたしなむ程度のものを持っていてもらいたいんだがな」
「僕が好きなのは、乗馬とテニスですよ、お父さん」
父親に侮辱されて、アンドリューの顔が初めて年相応に赤くなった。ソフィはどうにかフォローしたかったが、そもそも自分がした質問がよくなかったのだと、後悔するばかりだった。
「乗馬とテニスか!だからおまえは駄目だというんだ、アンドリュー。乗馬もテニスも結局、個人競技じゃないか。わしが言ってるのはな、団体競技のことだ。何人もの仲間と連携をとってプレーしなきゃならんスポーツのことだよ。おまえは結局臆病者なんだ。それで人にどう思われるかが不安で、学校でもまともに話せんのだろう。違うか、ええ?」
ガチャン、という音をさせてフォークとナイフを皿の上に置くと、アンドリューはその場から逃げるように立ち去っていた。女中の何人かが「お坊ちゃま!」と叫んで呼びとめようとするが、当然アンドリューは振り返りもしなかった。
「あんな言い方……あんまりじゃありませんか」
結婚する前に特訓した甲斐あって、ソフィは巧みに鹿の肉を切り分けながら上品な口調でそう言った。といっても、ソフィは自分が食べているのが鹿の肉とは知らず、おそらく前もってそう知っていたとすれば、口に入れたりはしなかったろう。
「いや、男の子というのはな、ソフィ。こっちから発破をかけてやって怒りを爆発させるくらいじゃなきゃいかん。このわしに食ってかかって来て、いつか父さんを越えてやるんだと、そのくらいのハングリー精神でもないことには、将来わしの事業なぞとても継いではいけないだろうよ」
ソフィはそのあとはただ黙って粛々と食事を続けた。食後に場所を移してワインを飲むと、バートは彼が結婚の目的としていたものを欲しがったので、ソフィはある種の義務感から契約を履行するように、彼に体を分け与えたのだった。
バートに抱かれる前にソフィはアンドリューのことを考え、一度中断されはしたものの、精力の強い夫が疲れて寝てしまうと、やはり再びアンドリューのことを考えはじめた。まだ九つほどの小さな子を、あんな精神状態で放っておくのは良くないことだと思ったし、彼の落ち込む原因となる発言をしたのは自分なのである……だが、ソフィは突如出来たこの義理の息子との間に多くのことを期待していたわけではない。
【シンデレラ・ストーリーか、それとも金で買われた娼婦か!?】という言葉が、とある写真週刊誌に載っていたが、まったくそのとおりだというようにソフィは自分でも思っていた。そのような継母に、果たしてあんな繊細そうに見える子が心を開いてくれるものだろうか?
ソフィはこの時、(それでも何かしなくては……)と思い、スリップの上にガウンを身にまとうと、緋毛氈の敷かれた廊下を歩いて、なんとなく庭先に出た。
庭ではリーリーという虫の音が聴こえ、それだけでなくガァガァいう蛙たちの求婚の合唱が幾重にも重なってここまで届いていた。庭のどこかに池があるのかもしれないとソフィは思った。生ぬるい夜気が頬を心地よくなぶっていき、ガウンの隙間から入りこんでくる風が気持ちいい。
(あら、向こうの別棟らしき建物は何かしら?明かりがついているけど、召使いたちの宿舎ってわけじゃないわよね)
屋敷内の見取り図がどうなっているのかまるでわからないソフィは、意を決すると思いきって裸足まま、その建物のほうへ駆けていった。月明かりだけを頼りに薄闇の中を走っていくと、蛙の合唱がますます大きくなり――池にかかる橋の横を通りすぎた頃には、その音色はひどく切なげな訴えをもってソフィの耳朶を打った。
「まあ、なんて素敵な建物かしら」
ソフィはそう思いながら、小さなチャペルのように見える白塗りの建物の窓から、まずはそっと中を覗きこむことにした。あたたかな優しい、淡いオレンジ色の光の向こうには、蔵書が何百冊となく詰まった重厚な本棚が並んでいるのが見える。
そしてその本棚の並ぶ手前側にあるスペースには、アンティーク調の机がいくつか並んでおり、ここが屋敷の<図書室>なのだろうということが、ソフィにもわかる。
ソフィは今の自分の格好が義理の息子に好感を持ってもらえるものでないとわかっていたが、それでもどうにか髪と服装のほうを整えて、そっと図書室の中へ入っていくことにした。
「あなた、誰?」
アンドリューは本から顔を上げると、どこか呆れたような顔をしてソフィのことを見た。
「あら、さっき会ったばかりの、あなたの新しいお義母さんじゃないの。もう顔を忘れたってわけじゃないでしょう?」
「ああ、あのおばさんか」
<おばさん>という言葉にソフィは少しグサッと来たが、「せめてお姉さんと呼びなさい!」とは言えなかった。自分だって九つくらいの時には――三十歳という年齢の大人を見る時、「おばさん」とか「おじさん」としか思ってなかったのだから……。
「そうよ、そのおばさんよ。別にお母さんって呼びたくなかったらそれでいいのよ。坊や、一体なんの御本を読んでいたの?」
アンドリューが少し恥ずかしそうに本を隠したので、なんとはなし、ソフィはその本のタイトルを知りたくなった。
「ふうん。『ナルニア国物語』ね。おばさんも好きよ。昔勤めてた喫茶店の本棚に置いてあったの。マスターの趣味でね」
「こんなの、子供が読む本だよ」
そう言ってアンドリューは、机に積んであった他の難しそうな哲学の本を手に取ろうとする。
「あんただって子供じゃないの!」
ソフィはおかしくなって笑いだした。そしてアンドリューの座る椅子の横に陣取ると、今度は机に積んであった他の本をぱらぱらと読みはじめる。『ツァラトゥストラはかく語りき』、『神曲』、『バガヴァッド・ギーター』……ソフィが九歳の時には読んでみようなどとはまるで思ったことのない本ばかりだった。
「ねえ、坊や。本当にこの本に書いてあることを一言一句間違いなく読んで、きちんと内容を理解してるってわけじゃないんでしょう?」
「おばさんみたいな馬鹿な人にはわからないよ、たぶん」
アンドリューはまるでそっぽを向くようにして『神曲』の続きを読みはじめている。
「まあ、まだ二度ばかりしか会ってないのに、どうしておばさんが馬鹿だってわかるのかしら?この賢い坊やには」
「だって、メイドのサラやアンナが言ってたもん。旦那さまが今度結婚する若い娘は、自分たちと同じくらいしか教養がなくて、高校すら出ていないって」
ソフィはここで絶句した。食事時にはあんなに恭しい態度だったメイドたちが、そんな陰口を子供に聴こえるところで話していただなんて!
「あんた、お父さんのことはどう思ってるの?わたしは血の繋がりのない継母だからまあいいとしても……お父さんのことは好き?それとも……」
「嫌いだよ、父さんなんて」と、今にも唾を吐きそうな顔つきでアンドリューは言った。「死ねばいいんだ、あんな奴」
何故なのだろう、この時ソフィの胸を快い衝撃が走っていった。もしこの時偽善的な態度で「父さんのことは尊敬しています」などと言われたら――ソフィは相当がっかりしたに違いない。
「でも、おばさんは父さんのことを愛してるんでしょ?」
(愛してなかったら結婚しないよね?)といったような、子供らしい純粋な目つきで見つめられ、ソフィは今度、胸が詰まりそうになった。このような汚れのない眼差しで見つめられては、嘘をつくということがどうしても出来ない気がしたのである。
「坊や、坊やはおばさんのことをどのくらい知ってるのかしら?高校も出てないお馬鹿さんだってことの他に」
「なんか、メイドたちが写真週刊誌の記事を見たりしてたから、そういうのは読んだよ。でもああいうものは浅はかで馬鹿な人たちが読んで、まったくそのとおりだとかって鵜呑みにするものなんだっておばあさまが言ってた。だから僕も信じないよ、おばさんが父さんに金で買われた奴隷だなんていうことはね」
ここでソフィは、あんまりおかしくなって声に出して笑った。実をいうとアンドリューが最初に出会った時、彼女に一番惹かれた点がこの<声>だったかもしれない。二階からこっそり姿を隠して新しい母親の姿を見ようとしたのだが、すぐに聞いたこともないような魅惑的な声の主が気になり――彼は身を隠していたトルソ像から、うっかり姿を見せてしまったのである。
「そうねえ。今はもう奴隷貿易なんてどこの国もやってないでしょうしねえ」
なおも愉快そうに声を立てて笑いながら、ソフィは言った。
「でもね、坊や。おばさんはたぶん、坊やのお母さんがお父さんのことを愛していたようには、たぶんお父さんのことを愛してないと思うわ。お父さんはね、坊やのお母さんのフローレンスさんを本当に愛してたから、二度と結婚するつもりはなかったんですって。でもおばさんと結婚したのはね、おばさんがなかなかお父さんに靡かなかったせいなのよ。それで意地になってとうとう最後にはプロポーズまでしてしまったのね。おばさんも……前に失くした恋人のことを今も一番に愛してるの。だからおばさんにとってお父さんは二番手だし、お父さんにとってもわたしは二番手なのよ。でもだからこそうまくいくってこともあるって、坊やにはわかってもらえるかしら?」
「いいんだよ、おばさん。僕に気を遣わなくて」
アンドリューは内気な少年がよくそうするように、隣のソフィのことをちゃんとは見ないのだが、時々ちらと盗み見るようにしながら言った。
「第一、僕はあんな奴のことには興味がないんだ。だから、おばさんがどこの馬の骨とも知れないあばずれでも、一向構わないんだよ。父さんに毒でも盛ってさ、遺産をがっぽりせしめるつもりだとかいうのでも全然いいんだ。というか、むしろ楽しみにしてる。おばさんがブランド物の服だのアクセサリーだの、ジャッキー・ケネディばりに浪費しまくって、父さんなんか破産すればいいんだよ」
「まあ、坊や」
ソフィはそれ以上何も言わなかった。ただアンドリューのことをふくよかな胸に抱くと、その額におやすみのキスをしただけだった。ジミー・チュウの香水の香りが数秒間彼のことを包み込む。
「じゃあそのうち、ふたりでお父さんを殺すための計画でも練りましょうね。それに、九つくらいの坊やがこんなに夜更かしするのは良くないとおばさんは思うけど――坊やはいつも何時ぐらいに眠ってるの?」
「十二時くらいかな。その頃になってもここの電気がついてるとね、サラが明かりを手に持って流石に「寝ろ!」って言いにくるんだよ。だから僕、十二時少し前には自分のベッドの中に入ることにしてるんだ」
「そうなの。じゃあまた明日、ここでおばさんとお話しましょうね……坊やが嫌じゃなかったらだけど」
「べつに、嫌じゃないよ」
ソフィが立ち去っていく後ろ姿を見て、初めて彼女が裸足であることにアンドリューは気づいた。そして、闇の中に新しい継母のことを見送ると、本に目を落としたまま、アンドリューはソフィのことを考えた。
(あのおばさんは、すごく変だ)とアンドリューは思った。(お父さんを殺すための計画を一緒に練ろうだって!もしかして本当にお金目的で父さんと結婚したのかな……いや、僕が何にもまして変だと思うのは、あの人は本当は父さんみたいな人と結婚するような人じゃないってことだ。あんな歳の離れた年寄りと結婚するより、もっと他にいい人がいそうなもんだけれど……)
アンドリューはそこまで考えてから、不意に胸ポケットの懐中時計を手に取り、どこか恭しい様子でその文字盤を眺めた。この金鎖の懐中時計はアンドリューのことを七歳まで育ててくれた祖母がくれたもので、祖母は夫から遺産として受け継ぎ、またアンドリューの祖父がそのまた祖父から受け継いだという、由緒ある品物だった。
「十一時半か。僕もそろそろ寝ることにしようっと」
アンドリューはこの日の夜、二階にある自分の寝室でベッドに入ると、新しい継母のソフィおばさんのことを考えた。彼女が自分の癖のある褐色の髪に指を入れて撫でてくれた時のことや、妖精のような声で笑った時のこと、また「いつも何時に寝るのか」と心配してくれたことなど……。
女中のサラは、あくまで自分の職務の一貫としてアンドリューの就寝時間を気にするのだったが、ソフィおばさんが自分のことを「気にかけて」そう言ってくれたことが、アンドリューにはわかっていた。たぶんそのうち、自分くらいの歳の子供はもっと早く眠るべきだとかなんとか、うるさく言ってくるかもしれない。
(チェッ、新しい継母さんだってさ。煩わしいこって。それに僕のこと、「坊や」だって!僕はもう九つにもなるっていうのに!)
アンドリューはそんなふうにブツブツ思おうとしたが、それでもやはりソフィおばさんのことを父親とは違い、「嫌い」というようには思えなかった。けれど、彼はあまりに「愛情」といったものから遠ざかっていたので、誰かが芯から自分を愛してくれるとは思いもしなかったし、まるで期待することすらしなかったのである。
* * * * * * *
本当なら、前日に受け取るはずだった新婚旅行のお土産の数々を受け取ったのち、アンドリューは自分専用の学習室に閉じこもりきりになった。
午前中に三時間、また午後から二時間、アンドリューはトマス・マクレガーという若い男の教師について、ドイツ語やフランス語といった外国語や、算数や化学、また哲学や神学などの授業を受けた。
マクレガー先生は熱意のある良い先生ではあったが、時々お説教くさいのが玉に瑕で、彼が大人の男ぶって「僕も君くらいの歳の頃には……」なんて話しはじめると、アンドリューは不愉快な顔の表情を隠しもしなかった。
マクレガー先生のお話で他に多いのは、海やボート、それにセーリングのことだったろうか。彼はトライアスロンが好きで競技大会に出るため、日々体を鍛えることを惜しまないといったタイプの男でもあった。
「アンディ、君の今の生きる目的はなんだい?僕はね、次の競技大会に出るために、朝はここへやって来るまでの間に五キロは走ってくるよ。君はきっと僕のことを馬鹿みたいだとかって今思ってるだろう?けれどね、アンディ。人生にはそうした目標が必要なんだよ。じゃないと、ただ同じところをぐるぐる回る犬のようになってしまうからね。そして一度目標が決まったとなれば、そこへ向けて精一杯努力するんだ。毎朝五キロも走るのは、そりゃとても苦しいことさ。けど、目標の崇高さがその苦しさを忘れさせてくれる……今は僕の言ってることがわからなくても、いつか君が大人になった時にでも僕の言葉を思い出してくれたらって思うよ」
(うぇっ)とアンドリューは思い、この博識でハンサムな教師に対して、心の中で舌を出した。だが、マクレガー先生のことをクビにするということはアンディには出来ない。何故といって優秀な教師である彼のことを追い出したとすれば――父親が激怒して「だったら学校へ戻れ!」と叱りつけるに違いないからだ。
授業の終わった最後に、マクレガー先生はアンドリューの人格や情緒の形成のために、必ずこうした有難いお話をひとつかふたつ、していってくださる……だがアンディはその度にマクレガー先生に対し、疎ましい思いを新たにするきりなのだった。
「君がおととし大切なおばあさまを亡くして、その後不登校になった気持ちはわかるよ。けどね、アンディ……」
「先生、もう三時を過ぎました」
『契約の時間はもう終了です』という目つきでもってアンドリューが無表情に睨むと、マクレガー先生は「もうそんな時間か」と言って、机の上の教科書類を片付けはじめる。
「アンドリュー、君は今年の夏、どう過ごすつもりなんだい?」
「べつに。バカンスの予定は特にこれといってありませんが」
ここでマクレガー先生は、ちょっと肩を竦めていた。彼のこの動作を見るたびにアンディは、どうしてこう先生はいちいち芝居がかった身振りをしたがるのだろうと不思議で仕方がない。
「もし良かったらだけど、アンディ……僕は友達とヨーロッパに避暑へ行く予定なんだ。みんなに君のことを話したらさ、一緒にどうかってことになったんだけど、君はどう思う?」
「さあ。先生はご婚約者の方や僕とは話の合わなそうな筋肉マッチョな方々と旅行へ行くのでしょう?僕がご一緒しても、楽しいとは一かけらも思えない気がするのですが」
アンドリューはここまで言ってやってスッとした。マクレガー先生は鈍いので、折に触れて、「偽善的な態度で手を差し伸べられても嬉しくない」ということを知らしめてやる必要があるのだ。
「アンディ、君はどうしてそう、アメフトをやってる人や、僕みたいに体を鍛えるのが好きな男のことをすぐ軽蔑するんだい?みんな気のいい連中ばかりだし、中にはもう結婚して子供もいるのがいるから――ちょうどいい遊び相手になれるんじゃないかなって思ったんだけどね」
「先生、僕は前にも申し上げた気がするのですが、そうした気遣いは一切無用です。先生はただ、僕が父の望む私立中学に合格するよう指導するのが仕事であって、そのために結構なお給料をいただいてるはずなんですから。今年の夏の旅行のことなど、それぞれ好きなところに行くか、あるいはどこにも行かないかして、帰ってきてからどうこう互いにしゃべればいいんです。それでは、失礼します」
アンドリューは自分専用の学習室から出ていくと、一目散に外へ出て、池のほうへ駆けていった。そこからは適度に潅木に周囲を囲まれた赤銅色の屋敷が眺められ、またアンドリューが絶対マクレガー先生を入れたくないと思う小さな図書室の建物が見える。
アンドリューはマクレガー先生が「君の図書室へ行ってみたいな」などと遠まわしに言うたび、これまでどうにかうまく煙に巻いてきたのだった。
「でももしいつかあいつが――土足でずかずか僕の聖域に入りこんで来やがったらこう言ってやる。『この筋肉マッチョの豚野郎め!すっこんでろ!!』……それとも、『この偽善者の豚野郎!』と、どっちがあいつにはより効果的なんだろう?」
毎日の習慣として、この時もアンドリューは池のまわりを散策してから四万冊もの蔵書の収められた図書室へ向かうことにした。池には日本風の朱塗りの太鼓橋がかかっていて、その上から手を叩くと錦鯉がうようよとアンドリューの元にまでやって来る。
アンドリューは昼ごはんの時に出たパンを、サラの目を盗んで毎日ポケットにこっそり押しこんでいた。そして今、ポケットの中から気前良くパン屑を放ってやると、魚たちは一生懸命パクパクとやりはじめる。
マクレガー先生がこの屋敷へやって来たばかりの頃、アンドリューは(この先生はどの程度なんだろう?)と思い、この太鼓橋の一番膨らんだところで、朱塗りの欄干に手をかけてこう聞いたことがある。
「先生、この知能の低い馬鹿な鯉どもは、どうやって僕の手を叩く音を認識してるんでしょうか?見る限りおよそ、人間の耳に当たる器官がまったくないような気がするのですが」
この時マクレガー先生は、「ええと、それはだな、アンドリュー……」と言いかけて、最後にはまったく別のことに話をすりかえてしまった。それでもアンドリューは、先生があとから調べて自分に教えてくれるかもと思い、期待してずっと待っていた。けれど先生の口からはいつも全然別のこと――「きのう十キロサイクリングして爽快だった」だのいう、アンドリューにとってはどうでもいい話しか聞かれなかったのである。こうしてマクレガー先生はアンドリューから<用なし>の見えない印を、額のあたりに押されたというわけだった。
アンドリューは飢えた鯉どもに餌をやり終えると、今度は池の縁にある茂みのあたりで、池を泳ぐカイツブリのことを待つことにした。白鳥などの水鳥に比べると、べつに美しくもない、べつにどうでもいいような鳥ではある。だが、アンドリューがおばあさまを亡くしたあと、池のほとりで泣いていた時、そのカイツブリが随分向こうの遠くから、びっくりするような勢いで一直線にやってきたのである。
その時アンドリューは鯉にパン屑を全部やってしまったので、餌に出来るようなものが何もなかった。けれどカイツブリはただ黙って水際のアンドリューを恐れるでもなく慰めてくれた。彼はただじっとそこにいるというだけではあったが、アンドリューはやがて涙が引き、カイツブリが餌目的ではなくそばにいたらしきことが嬉しくなった……その日以降、アンドリューが午後に池のほとりへやって来ると、そのカイツブリは必ずアンドリューをそれと認めて一直線に向かってくるのだった。
「おお、よしよし。おまえのために一等とっときの美味しいパン屑を残しておいたよ。またそのうち別のご馳走も持ってくるから、楽しみにしていておくれ」
餌を食べ終わっても暫くはカイツブリがそこにいるので、そういう時アンドリューはいつも、彼に対して色々な話をした。その話は声に出して囁かれるものもあれば、また心の中でだけ交わされる場合もあった。
「僕に新しい継母さんが出来たんだけどさ、すごく綺麗な人なんだ。まあ、僕の死んだ母さんほどじゃないけど、僕のこと、坊やなんて呼ぶんだよ。おかしいだろ?でもなんとしてもわかんないのはさ、あんなそこそこまともそうな人が、なんで父さんみたいな冷血漢と結婚したかってことなんだけど……もしかしたら今日、またあの人は僕の図書室にやって来るかもしれない。そしたら、僕……高校も出てないっていうあの人に、マクレガー先生の物真似でもして、少しかものを教えてやろうかなって思う。もし仲良くなれたら、あのおばさんをここに連れてきて、おまえにも会わせてあげるね」
そこまで聞くとこの賢いカイツブリは、まるで了解したとでもいうように、池の水際からすいーっと離れていった。その後、アンドリューがとても不思議だったのは、アンドリューとソフィの関係がしっくりいくようになった頃――カイツブリに独り言を聞かせる必要がなくなった頃――池のほとりにアンドリューが下りていっても、まるで向こうが見向きもしなくなったことだった。
それはまるで自然が、小さな悲しい子供の必要を知っていて、人間的な言葉でない慰めをある一定期間与えてくれた出来事のような気がして……アンドリューの中に大人になってからも、優しい記憶を残すということになった。
>>続く。