『現代詩手帖』のふたつのアンソロジー特集を読んだ。8月号が「現代詩アンソロジー2000-2009」、同じく9月号は「現代詩アンソロジー2010-2019」であった。所収作品は、アンソロジーの常として偏りがあるのかもしれないし、不足もあるのかもしれないが、おおむね楽しく読むことができた。のではあるが、同時に掲載されている、選者4名――瀬尾育生・野村喜和夫・小池昌代・蜂飼耳――によるふたつの「討議」、すなわち「二〇〇〇年代、詩に何が起こったのか」(8月号)、「10年代から現在へ――いま、詩は」(9月号)を読むあいだ、幾度となく、あの馴れ親しんだ「嫌な気分」に襲われることにもなった。ひとことでいうなら「何度これが繰り返されるのか」という脱力感・徒労感、すべてのひとびとが記憶喪失に陥っているのではないかという感覚、である――こういった体験には俳壇であれ歌壇であれTwitterのタイムラインであれ、いたるところで出くわすものであり、私がたんに「日本の現代詩の世界」における時の流れの速度に不慣れであるというだけなのかもしれないが。そのすべてのポイントに詳細に触れることはできない。締め切りもある。そこで、榎本櫻湖によって提起された困惑を、導きの糸としてみよう。榎本はこう書いている。《この、不可解な現象をまえに、いったいどう反応すればいいのかがわからない》(榎本[2020])。
同アンソロジーには、瀬尾育生選により榎本櫻湖「わたしは肥溜め姫」(『増殖する眼球にまたがって』より)が収録されている。榎本の主要な困惑は、彼女が《これまでに公刊してきた書物のなかで、わたしは自身のセクシュアリティに言及したことは一度もないし、創作するうえではそれを主題にすることを周到に避けてきた》にもかかわらず、《書き手の属性を重視して作品と書き手をともにあるカテゴリーにふりわける》(同前)という、明白な暴力に、不意打ちのように曝されたことに起因する。むろんいわゆる「アウティング」が起きたのではない。榎本はSNSで自らがMtFのトランスジェンダーであることを公言している。文脈が分かるように、9月号の討議から引用しておこう(瀬尾他[2020b: 23-24])。
野村 それから、榎本櫻湖さんは、ぼくが挙げるべきだったんでしょうが、瀬尾さんが挙げられたので、そちらにお願いすることにしました。榎本さんの書き方は、一〇年代の他の詩人たちと一味も二味も違っている。散文的でないという意味では突出して散文的でない。逆に榎本櫻湖が一〇年代に登場した意味を他の詩人たちと関係づけて言えるか、ぼくにはわからないんです。あえて言えば、瀬尾さんがおっしゃっていた、セクシュアリティの問題と絡めると、榎本さんも一〇年代に登場した詩人にふさわしいかな、という気がしました。
瀬尾 榎本櫻湖さんや森本孝徳さん。こういう詩をぼくがわかって選んでいるのかといえば、もちろんそんなことはなくて、こんな難しい詩が、わかるはずがないです。でもそれが現在の詩の世界で意味をもつかどうかは、わかるわからないとは別の問題で、わからないけど、これが問題だろう、これについてどう考えるかがこれから詩を考えるうえで問われることになるだろう、という直感があるわけです。
ゼロ年代の詩人たちは、まだ男女の性愛的なもののかたちを維持していますが、一〇年代の詩人たちになるとそれは本格的に崩れていく。性自体が多形的に複数化していく。ジェンダー論という領域に、ぼくはほとんど無知なんですが、九〇年代くらいまで「女性詩」という言葉をメルクマールにして動いてきた詩の流れがあったと思う。その流れを担ってきた人たちが、榎本さんをはじめとして、ゼロ年代、一〇年代の詩を、どんなふうに語ることになるのかはとても興味深い。ぜひ聞いてみたいことです。
このたった3段落だけでも、話は複雑に錯綜しているように見える。あえて整理するとこうなるだろうか。(1)野村が「書き手の属性」に触れてしまう。(2)それを受けた瀬尾が《わかるはずがない》と、榎本にいわせれば《なんとも抑圧的で排他的な言動》(榎本、同前)をしてしまう。(3)続けて瀬尾はゼロ年代までは維持されていた《男女の性愛的なもののかたち》が10年代には崩れたと「時代診断」し、その《多形的に複数化》した性を描く書き手のひとりとして榎本を位置づけてしまう。(3.1)さらに瀬尾は、そうした《流れ》を90年代までの《女性詩》と同等の(私の言葉でいえば「機能的に等価な」)カテゴリーとして見てしまう。この錯綜に、筋、ロジックを見出すことは難しい。まるで精神分析の自由連想法のように、キーワードからキーワードへと飛び移り、文脈をずらしつつ、話が先へ(下流へ)と流れてゆく。起伏のある斜面を、より窪んだ位置へと水が流れてゆくように。アカデミックな「討議」ではこうしたことは生じにくいかもしれない。これは「討議」と題されてはいるが、かの奇妙な日本文化である「座談会」のように見える。
筋が通るように理解できなくもない点をあげれば、野村による(1)の発言は、前号(8月号)での瀬尾の発言を前提としているのではないか、という点だ。瀬尾は8月号の討議で《ゼロ年代・一〇年代ということを厳密に考えたほうがいいと思うのは、パースペクティブは大事だと思うんですよ》(瀬尾他[2020a: 13])と述べている。野村の発言は、10年代を捉えるひとつのパースペクティブの内に榎本を位置づけ、配置することが難しい、という吐露のように見える。野村は《わかるはずがない》とは述べておらず、《他の詩人たちと関係づけて》言うことに困難を感じる、とだけいっているのだから(野村は先の発言に先立って、《二〇〇〇年代から二〇一〇年代、詩の散文化という傾向が顕著になっていく》(瀬尾他[2020b: 15])と述べており、こうした「傾向」=「散文化」に反する書き手として榎本を捉えている)。こうした「困難さ」を前にして、手がかりが求められるように、利用可能な(available)意味的リソースとして、「作者の属性」が偶発的にあるいは慣性的に飛びつかれた、というのが、ここで起きたことだろうと思う。社会学(ないし社会心理学)でいう縮減(Reduktion)の機能を果たすように、意味的資源は用いられる。
この点から先はやはり錯綜している。書き手たちの《関係づけ》の難しさと、作品が《わかるはずがない》ということとは何の関係もないし、ましてや性の多形的複数化とは何の関係もない。ここで参照されている「性の多形的複数化」という文脈は、同じく9月号の「討議」に現れている。引用しておこう(瀬尾他[2020b: 16-17])。
瀬尾 日本の近代詩のなかでは、詩が上手くなるっていうのは、詩が性愛的になるということを指していると思うんですよ。男女の性愛が細やかに書けることを指して、詩が上手くなると言う。そういう意味では、若い詩人たちは決して「上手く」はならない。(略)
男女の性愛を外していくと、そこにふたつの流れができる。ひとつはn個の性。性が多形的になって、さまざまな性愛のかたちへ拡散してゆくという場合。もうひとつは、「性愛」ではなく「友愛」だ、というはっきりとした線が走っている場合。たとえば中尾太一さんの主題ですね。最果タヒさんでも性愛的なものの排除というモチーフがとても大きい。すくなくとも男女が固定されるような性愛は、はっきり消されている。
野村 たしかに、現象的にはここ十年ぐらい、ヘテロの性愛をテーマにした作品は減っていますね。トランスジェンダー的な、いや瀬尾さんのようにn個の性と言ったほうがいいな、そういうところからの表現が増えている気がします。
ここでやや教科書的なことを述べておく。榎本櫻湖がトランスジェンダーである(というより、現時点では彼女がそう見做される・自らをそう見做すことが可能な社会構造に、われわれは生きている)ということは、《セクシュアリティの問題》とは関係がない。ここ二十年、セクシュアル・マイノリティを「LGBT」と呼ぶ(ことにする)言説がヘゲモニーを握っているため、MtFのTGと見做される榎本は、現時点ではセクシュアル・マイノリティである(とされる)(だからこそ、榎本はこの点を批判していない)。が、術語としてのセクシュアリティは、「セックス/ジェンダー/セクシュアリティの三位一体神学」(上野[1997])を記述・相対化(さらには批判)するものであって、つまりほとんど「性的指向」(sexual orientation)と同義に用いられている。榎本はMからFへとトランスした女性である、というだけであり、性的指向とは関係がない。ジェンダーのみが関与的になる(ここですぐさま注釈が必要になる。いま述べたことは、TG当事者がセクシュアリティの問題に巻き込まれない、ということを意味しない。TGというカテゴリー、意味的リソースを入手するまで、「自分は同性愛者だと思っていた」と述べるTG当事者は少なくない)。またここにあるのはFとMという旧来型の2個の性別であり、n個の性とも関係がない。それでも《セクシュアリティの問題》であると主張するならば、「ジェンダー・アイデンティティはセクシュアリティによって強く規定される」という、より一層「強い主張」をなさなければならなくなるし、そのためにはそれなりに分厚い論証が必要になるだろう。
n個の性とはドゥルーズ&ガタリ(以下D&G)が『アンチ・オイディプス』で提起した概念のうちのひとつだが、瀬尾のいうような「性愛」か「友愛」かという区別のあとに、あるいは《男女の性愛を外して》という条件のあとに分類されるような概念ではない。むしろそうした諸区別・諸分類の前提であり、先行する可能性の条件である。《愛をかわすことは、一体となることでもなければ、二人になることでさえもなく、何十万にもなることなのだ》(D&G[1972=2006: 下巻152])。《性が多形的になって、さまざまな性愛のかたちへ拡散してゆく》のではない。つねにあらかじめ、さまざまなかたちへ拡散しているのだ。「さまざまな友愛のかたち」はあり得ないとでもいうのであろうか。n個の性を有意義な概念として用いるには、D&Gのいう「分裂分析」の文脈、接続したり切断したりする機械、生産する欲望機械の概念とともに用いなければならない(そうでなければいったい何を意味するというのだろうか)。もんだいは、《男女の性愛》というときの男女が、ひとりの(ふたりの)人物、人間として――カントの術語でいえば統一(Einheit)として――把握されてしまっている点にあるのではないか。分裂分析は、この統一を多数多様化する。《分裂分析は、ひとりの主体の中におけるn……個の性の多様な分析であり、人間的形態の表象を超えていくのだ》(D&G、同前)。
このもんだいはまた、「作者」という過剰に単純化(縮減)された観念を召喚することにも結びつくかもしれない(「人」へのバックラッシュといってもよいだろう)。D&Gの次の著書『千のプラトー』の書き出しはこうだ。《われわれは『アンチ・オイディプス』を二人で書いた。二人それぞれが数人だったのだから、それだけでもう多数になっていた》(D&G[1980=2010: 上巻15])。愛する誰かやそうでない誰かをひとり(Einheit)の人物として見て(表象して)しまうことは、症候(symptoms)であろう。詩も詩人も症候であろう。D&Gの分裂分析の術語系でいえば、脱領土化のあとにくる再領土化であろう。必要なことは、どうしようもなく症候を(再領土化を)生きてしまっているわれわれが、脱領土化された景色も同時に観る、ということだ。あなたがどうしようもなくシス・ジェンダーであり、どうしようもなくヘテロであるとき、自己を社会のなかでの症候として観ること。また当該社会を症候として観ること。偶発的に顕在化した現象の、偶発的な固着として観ること。とあるベッドの上で、膣に男根が収納されている、と仮定してみよう。この男根がより奥へと押されるとき、どの性がどの性を欲望しているのだろうか。引き続いて手前に引かれるとき、どの性がどの性を欲望しているのか(ここまでですでに4つの性が想定された)。その運動を駆動する欲望機械のどれとどれが接続し、いかなる切断が生じているのか。あるいは一本の煙草を指に挟むとき、どの性がどの性を欲望しているのか。口に煙草を咥えるとき、煙を吸うとき、口から煙草を離すとき、煙を吐くとき、それぞれどの性がどの性を欲望しているのか。いかなる機械たちの離接が生じているのか。
D&Gが述べていることから逸脱して、「読む」ことも同様である、と考えてみよう。エクリチュールがとある単一のテクストであるように見えるとき(これもまたわれわれの呈するどうしようもない症候のひとつだ)、それはいかなる諸機械の諸離接であるのか。改行においていかなる切断が(あるいは接続が)設けられているのか。一行のなかにいくつの機械の離接が生じているのか。ひとつの文字はいくつの機械に所属しているのか(機械の数と、単語や文字や音の数は一致しないだろう。この現実をあからさまにカリカチュアライズしたものが加藤郁乎の句集『牧歌メロン』だともいえる)。エクリチュールは多形倒錯的に(こういってよければクイアに)、多数のテクストを遂行(perform)するだろう。ひとつ(ひとり)の観察者(当該社会はこれを「読者」と見做す)が「読む」のはせいぜい数個のテクストかもしれない(このようにも読める、あのようにも読める、というわけだ)。社会においては、たったひとつとはいわないまでも、少数のテクストがヘゲモニーを(一時的にかもしれないが)握ることになるだろう。その意味で、テクスト論のあとに現われた「読者主義」はあり得ないアイディアであり、テクスト論の誤読の産物である。テクストが作者のものでないからといって、読者のものになるわけではない。テクスト論が差し向けるのは、どの観察者によってテクストと見做されたものが、いかなる社会的布置連関・権力関係において、いかにしてヘゲモニーを握ったのか、ということの分析、ということになるだろう。
性愛について、また性愛の否定としての友愛については能弁であった9月号討議には、奇妙なことに「恋愛」が欠落している。意図的なあるいは無意識的な否認なのかもしれないし、恋愛は性愛のサブカテゴリーである、という認識なのかもしれない。しかしそのとき、《性愛的なものの排除というモチーフがとても大きい。すくなくとも男女が固定されるような性愛は、はっきり消されている》(瀬尾)と見做される最果タヒが、別の文脈、『現代詩手帖』同号掲載の、豊崎由美・広瀬大志「『恋愛詩』が消えた!?」においては《なぜ最果さんの詩が広く読まれているか、それは彼女の詩のモチーフが恋愛だから》(広瀬)と断定されることと、奇妙なコントラストをなしてしまう。観察者の違いによるヘゲモニー争いが起きているのだろうか。最果作品では、性愛を消したところにおいて恋愛が抽出・結晶化されている、と解釈できなくもないが、ならばやはり友愛と呼びうるところに、なぜか「恋愛」という意味的資源が滑り込んでいる、ということになる。これは、ふたつの症候として考えることができる。すなわち、瀬尾たちの議論においては性器的欲望・性器的行為を「性愛」と名指し、これを行為者の内面に帰属する(セクシュアリティ化する)作法が優位であり、他方で、広瀬たちの議論においては性器的行為も含めて、初恋から失恋、不倫、SMまで幅広く、およそ恋愛に関係しそうな事柄はすべて「恋愛」と名指し、これを普遍化・自然化する作法が優位である。いずれの作法もわれわれにとって馴れ親しまれたものであり、現実に両立しているといえる。恋愛という症候について述べておくと、たとえば広瀬は同対談で《原初的な詩の持ち味は恋愛観から派生するものだと思っています(略)恋愛は実際にはほとんど誰でもが経験する》(豊崎・広瀬[2020: 92])と――アセクシュアルやアロマンティックなど様々な「A-」たちへの――差別的とも受け取られかねない発言をしており、セクシュアリティについて生じた――三位一体神学!――のと同様の、排他的暴力が起きていることが分かる。マジョリティのふるまいを、自然で、歴史的に普遍的なことであると遠近法的に錯視する傾向は、恋愛という症候にかんしても生じる。だから再領土化は危険なことなのだ。ネイションについてベネディクト・アンダーソンたちが、同性愛者についてミシェル・フーコーたちが、言説以前のもの「として」想定される自然なセックス(生物学的性)についてジュディス・バトラーたちが、家族について多数の社会学者たちが、脱領土化された景色を見せてくれたように、恋愛についてもそうすることが必要だろう。それは政治的に正しい詩を書くためでもないし、道徳的であるためでもない。われわれの症候、錯視をこそ、権力は梃子にするのだし、そのため、われわれの言表や感情は容易に政治的に利用されてしまうからだ(それにしても、「政治的正しさ」とは、他者を歓待するという倫理が、たんに政治的に「のみ」正しい、といわんばかりであり、不快な響きをもつ言葉だ)。
社会学者ニクラス・ルーマン(Luhmann[1982=2005])は、愛(Liebe)を、17世紀に分出したコミュニケーション・メディアのうちのひとつであることを発見している(彼は「象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディア」とよぶ。なお、ここでルーマンが「愛」とよぶものは、われわれの文脈でいう「恋愛」のことである)。コミュニケーションの成功――すなわち他者の行為または体験に、自己の行為または体験を接続すること――は「ありそうもないこと」(Unwahrscheinlichkeit)である。なぜどこの馬の骨とも分からぬ者の書いた文章を読み・理解し・「恋愛を脱領土化せよ」なる提案にのらなければならないのか。このありそうもなさを前提とすることで、社会学が取り組むべき問題が浮かび上がる。成功する見込みがないはずなのに、実際には成功しているケースが少なくとも存在する、いい換えれば社会がいま現にあるということは、成功させるためのメカニズムがある(ないし、あった)はずであり、それはいかなる淘汰の過程を生き延びてきたのか、という問題である。たとえば貨幣は、売り手や買い手が互いに誰であるかに無関心でありながら、売買を成功させる、そうしたコミュニケーション・メディアである。愛も同様に社会進化上の獲得物である。愛というメディアが可能にするのは、他者の体験(愛される)に自己の行為(愛する)を接続する、という特殊なコミュニケーションである。他者の体験を、自己の行為の前提として受け入れる、というきわめてありそうもない事態が生じることになる。他者が自らの体験を語るとき、その特殊性ゆえに、聞き入れることはありそうもない。だが私は彼女の一風変わったものの見方を注意深く聴き、彼女のものの見方を前提として私の行為を企てるのだ。その理由は「彼女が彼女だから」である。その意味で、貨幣がインパーソナルな関係を拡大する(近代社会のコインの表といえる)ものであったのとは対照的に、愛はパーソナルな関係を「深める」(近代社会のコインの裏)。愛が社会進化上の獲得物であるならば、まさに進化の途上にある社会において、その意味内容・使用方法は変化する。現にわれわれが「愛のコミュニケーション」や「愛についてのコミュニケーション」を行うことを可能にし、行うことで再生産される意味的濃縮物の蓄積を社会構造とよぶとき、これに対応して、当該社会がその社会の自己記述を行う。これをゼマンティク(Semantik)とよぶ。ゼマンティクは主要にはテクストとして保持される。愛については、初期には恋愛小説が、近年では映画、テレビドラマ、漫画、ポップ・ミュージックなどがその役割を果たしている。詩もその役割を果たしてきたといえる(この歴史社会学的分析については、やはり豊崎・広瀬[2020]が役に立つ)。現にコミュニケーションを可能にし、条件付けている社会構造に対して、記述・描写の役割を担うゼマンティクはそれゆえ、遅れる。「時代遅れだ」と感じられることもあるだろう。しかし、社会構造がゼマンティクを一方的に規定するわけではない。ゼマンティクが新しい社会への変動を促し、方向づけ、刺激することもある(古いものでは宗教革命に出版物が果たした役割を、卑近な例では「ソーシャル・ディスタンス」なるキャッチフレーズを考えればよい)。
さて、現代詩から「恋愛が消えた」という事態は、何を表現しているのか(何のゼマンティクなのか)。豊崎・広瀬[2020]によれば、ポップス、サブカル、詩から分離した「ポエム」、短歌などが恋愛詩を継承した、とされているが、妥当だろうか。社会構造を事後的に記述する、というゼマンティクの役割のみを見るならば妥当であろう。しかしそれらにおいて表現されている「恋愛」は明らかに「時代遅れだ」と感じさせるものであるし、むしろそのレトロな雰囲気を楽しむものになってはいないか(ポップ・ミュージックの文脈で流行の「レトロ・フューチャー」でさえない)。むろん、たとえば短歌においては川野芽生『Lilith』(2020年)のように恋愛(という制度)を《奇習》とまでよび、《狂恋を逃れむがため》と歌い上げる「新しい」ポエジー(というか、現在的なポエジー)が生じてはいるが。現代詩について、言語との格闘を抜きにして考えることは難しい。8月号討議(瀬尾他[2020a])から9月号討議(瀬尾他[2020b])にいたるまで、頻出語ともなっている「読めなさ」は、そのまま現在の恋愛について、ひいてはコミュニケーションについて、生々しく、なにごとかを伝えようとしていると読めないだろうか(私は、8月号討議で、小笠原鳥類の作品が「線というより面」「読むというより見る」と評されているのを目にして、衝撃を受けた。私自身は新しい時代の落語の台本ででもあるかのように、昂揚感をもって「読む」を楽しんでいたからだ。この断絶は越えがたい。ことほどさように、コミュニケーションはありそうにないのだ)。私の仮説だが、現代詩から、恋愛も性愛も消えてなどいない。いや、そうよぶ必要のない、別の可能性が探られている。いまげんざい「恋愛」や「性愛」と習慣的によばれている社会的事実と、われわれの個別の経験が、どうしようもなく乖離している。スクリーンに映し出される映像と、観客席に座るものの尻の痛みほどに、離れている。新しい、別の社会構造が必要だ。それがいまげんざい「読めない」とされている現代詩において指し示されている。(社会)進化のつねとして、どれが淘汰され、どれが選択されるのかは、偶発的ではあるが。豊崎・広瀬[2020]において《エロス的恋愛詩》のひとつとして言及されている野村喜和夫「オルガスムス屋、かく語りき」(『デジャヴュ街道』より)は、たしかに目に見える文字で「読める」部分を頼りにするなら、ヘテロ男女の性愛を描いたものではあるのだが、これほどクイアな感触を与えるエクリチュールもそうそうないだろう。もちろん、「ヘテロもクイア」という短絡は、差し控えられるべきだ。マイノリティのもんだいが棚上げされてしまう危険をともなうからだ。せいぜい「ヘテロでもクイア」とよびうる領域が、切り開かれる可能性がある、というに留めておかなければならない。「クイア文学」なるカテゴリーはあり得ない。あるのは「クイアな読み」だけだ。必要なのは、新しい「読み」である。
【文献表】
Deleuze, Gill; Guattari, Félix, 1972, L'Anti-Œdipe, Paris: Les Éditions de Minuit. = 2006、宇野邦一訳『アンチ・オイディプス――資本主義と分裂症』河出文庫。
――――, 1980, Mille Plateaux, Paris: Les Éditions de Minuit. = 2010、宇野邦一他訳『千のプラトー――資本主義と分裂症』河出文庫。
榎本櫻湖、2020、「わたしはまたしてもなにも書かなかったことにされるんですか? 『現代詩アンソロジー2010-2019』に抵抗する」『現代詩手帖』vol.63, no.10: 148-150。
Luhmann, Niklas, 1982, Liebe als Passion: Zur Codierung von Intimität, Frankfurt: Suhrkamp. = 2005、村中知子・佐藤勉訳『情熱としての愛――親密さのコード化』木鐸社。
瀬尾育夫・野村喜和夫・小池昌代・蜂飼耳、2020a、「二〇〇〇年代、詩に何が起こったのか」『現代詩手帖』vol.63, no.8: 10-26。
――――、2020b、「10年代から現在へ――いま、詩は」『現代詩手帖』vol.63, no.9: 10-27。
豊崎由美・広瀬大志、2020、「『恋愛詩』が消えた!?」『現代詩手帖』vol.63, no.9: 92-108。
上野千鶴子、1997、「セックス/ジェンダー/セクシュアリティの三位一体神学の解体のあとで」『現代思想』vol.25, no.6: 88-93。
同アンソロジーには、瀬尾育生選により榎本櫻湖「わたしは肥溜め姫」(『増殖する眼球にまたがって』より)が収録されている。榎本の主要な困惑は、彼女が《これまでに公刊してきた書物のなかで、わたしは自身のセクシュアリティに言及したことは一度もないし、創作するうえではそれを主題にすることを周到に避けてきた》にもかかわらず、《書き手の属性を重視して作品と書き手をともにあるカテゴリーにふりわける》(同前)という、明白な暴力に、不意打ちのように曝されたことに起因する。むろんいわゆる「アウティング」が起きたのではない。榎本はSNSで自らがMtFのトランスジェンダーであることを公言している。文脈が分かるように、9月号の討議から引用しておこう(瀬尾他[2020b: 23-24])。
野村 それから、榎本櫻湖さんは、ぼくが挙げるべきだったんでしょうが、瀬尾さんが挙げられたので、そちらにお願いすることにしました。榎本さんの書き方は、一〇年代の他の詩人たちと一味も二味も違っている。散文的でないという意味では突出して散文的でない。逆に榎本櫻湖が一〇年代に登場した意味を他の詩人たちと関係づけて言えるか、ぼくにはわからないんです。あえて言えば、瀬尾さんがおっしゃっていた、セクシュアリティの問題と絡めると、榎本さんも一〇年代に登場した詩人にふさわしいかな、という気がしました。
瀬尾 榎本櫻湖さんや森本孝徳さん。こういう詩をぼくがわかって選んでいるのかといえば、もちろんそんなことはなくて、こんな難しい詩が、わかるはずがないです。でもそれが現在の詩の世界で意味をもつかどうかは、わかるわからないとは別の問題で、わからないけど、これが問題だろう、これについてどう考えるかがこれから詩を考えるうえで問われることになるだろう、という直感があるわけです。
ゼロ年代の詩人たちは、まだ男女の性愛的なもののかたちを維持していますが、一〇年代の詩人たちになるとそれは本格的に崩れていく。性自体が多形的に複数化していく。ジェンダー論という領域に、ぼくはほとんど無知なんですが、九〇年代くらいまで「女性詩」という言葉をメルクマールにして動いてきた詩の流れがあったと思う。その流れを担ってきた人たちが、榎本さんをはじめとして、ゼロ年代、一〇年代の詩を、どんなふうに語ることになるのかはとても興味深い。ぜひ聞いてみたいことです。
このたった3段落だけでも、話は複雑に錯綜しているように見える。あえて整理するとこうなるだろうか。(1)野村が「書き手の属性」に触れてしまう。(2)それを受けた瀬尾が《わかるはずがない》と、榎本にいわせれば《なんとも抑圧的で排他的な言動》(榎本、同前)をしてしまう。(3)続けて瀬尾はゼロ年代までは維持されていた《男女の性愛的なもののかたち》が10年代には崩れたと「時代診断」し、その《多形的に複数化》した性を描く書き手のひとりとして榎本を位置づけてしまう。(3.1)さらに瀬尾は、そうした《流れ》を90年代までの《女性詩》と同等の(私の言葉でいえば「機能的に等価な」)カテゴリーとして見てしまう。この錯綜に、筋、ロジックを見出すことは難しい。まるで精神分析の自由連想法のように、キーワードからキーワードへと飛び移り、文脈をずらしつつ、話が先へ(下流へ)と流れてゆく。起伏のある斜面を、より窪んだ位置へと水が流れてゆくように。アカデミックな「討議」ではこうしたことは生じにくいかもしれない。これは「討議」と題されてはいるが、かの奇妙な日本文化である「座談会」のように見える。
筋が通るように理解できなくもない点をあげれば、野村による(1)の発言は、前号(8月号)での瀬尾の発言を前提としているのではないか、という点だ。瀬尾は8月号の討議で《ゼロ年代・一〇年代ということを厳密に考えたほうがいいと思うのは、パースペクティブは大事だと思うんですよ》(瀬尾他[2020a: 13])と述べている。野村の発言は、10年代を捉えるひとつのパースペクティブの内に榎本を位置づけ、配置することが難しい、という吐露のように見える。野村は《わかるはずがない》とは述べておらず、《他の詩人たちと関係づけて》言うことに困難を感じる、とだけいっているのだから(野村は先の発言に先立って、《二〇〇〇年代から二〇一〇年代、詩の散文化という傾向が顕著になっていく》(瀬尾他[2020b: 15])と述べており、こうした「傾向」=「散文化」に反する書き手として榎本を捉えている)。こうした「困難さ」を前にして、手がかりが求められるように、利用可能な(available)意味的リソースとして、「作者の属性」が偶発的にあるいは慣性的に飛びつかれた、というのが、ここで起きたことだろうと思う。社会学(ないし社会心理学)でいう縮減(Reduktion)の機能を果たすように、意味的資源は用いられる。
この点から先はやはり錯綜している。書き手たちの《関係づけ》の難しさと、作品が《わかるはずがない》ということとは何の関係もないし、ましてや性の多形的複数化とは何の関係もない。ここで参照されている「性の多形的複数化」という文脈は、同じく9月号の「討議」に現れている。引用しておこう(瀬尾他[2020b: 16-17])。
瀬尾 日本の近代詩のなかでは、詩が上手くなるっていうのは、詩が性愛的になるということを指していると思うんですよ。男女の性愛が細やかに書けることを指して、詩が上手くなると言う。そういう意味では、若い詩人たちは決して「上手く」はならない。(略)
男女の性愛を外していくと、そこにふたつの流れができる。ひとつはn個の性。性が多形的になって、さまざまな性愛のかたちへ拡散してゆくという場合。もうひとつは、「性愛」ではなく「友愛」だ、というはっきりとした線が走っている場合。たとえば中尾太一さんの主題ですね。最果タヒさんでも性愛的なものの排除というモチーフがとても大きい。すくなくとも男女が固定されるような性愛は、はっきり消されている。
野村 たしかに、現象的にはここ十年ぐらい、ヘテロの性愛をテーマにした作品は減っていますね。トランスジェンダー的な、いや瀬尾さんのようにn個の性と言ったほうがいいな、そういうところからの表現が増えている気がします。
ここでやや教科書的なことを述べておく。榎本櫻湖がトランスジェンダーである(というより、現時点では彼女がそう見做される・自らをそう見做すことが可能な社会構造に、われわれは生きている)ということは、《セクシュアリティの問題》とは関係がない。ここ二十年、セクシュアル・マイノリティを「LGBT」と呼ぶ(ことにする)言説がヘゲモニーを握っているため、MtFのTGと見做される榎本は、現時点ではセクシュアル・マイノリティである(とされる)(だからこそ、榎本はこの点を批判していない)。が、術語としてのセクシュアリティは、「セックス/ジェンダー/セクシュアリティの三位一体神学」(上野[1997])を記述・相対化(さらには批判)するものであって、つまりほとんど「性的指向」(sexual orientation)と同義に用いられている。榎本はMからFへとトランスした女性である、というだけであり、性的指向とは関係がない。ジェンダーのみが関与的になる(ここですぐさま注釈が必要になる。いま述べたことは、TG当事者がセクシュアリティの問題に巻き込まれない、ということを意味しない。TGというカテゴリー、意味的リソースを入手するまで、「自分は同性愛者だと思っていた」と述べるTG当事者は少なくない)。またここにあるのはFとMという旧来型の2個の性別であり、n個の性とも関係がない。それでも《セクシュアリティの問題》であると主張するならば、「ジェンダー・アイデンティティはセクシュアリティによって強く規定される」という、より一層「強い主張」をなさなければならなくなるし、そのためにはそれなりに分厚い論証が必要になるだろう。
n個の性とはドゥルーズ&ガタリ(以下D&G)が『アンチ・オイディプス』で提起した概念のうちのひとつだが、瀬尾のいうような「性愛」か「友愛」かという区別のあとに、あるいは《男女の性愛を外して》という条件のあとに分類されるような概念ではない。むしろそうした諸区別・諸分類の前提であり、先行する可能性の条件である。《愛をかわすことは、一体となることでもなければ、二人になることでさえもなく、何十万にもなることなのだ》(D&G[1972=2006: 下巻152])。《性が多形的になって、さまざまな性愛のかたちへ拡散してゆく》のではない。つねにあらかじめ、さまざまなかたちへ拡散しているのだ。「さまざまな友愛のかたち」はあり得ないとでもいうのであろうか。n個の性を有意義な概念として用いるには、D&Gのいう「分裂分析」の文脈、接続したり切断したりする機械、生産する欲望機械の概念とともに用いなければならない(そうでなければいったい何を意味するというのだろうか)。もんだいは、《男女の性愛》というときの男女が、ひとりの(ふたりの)人物、人間として――カントの術語でいえば統一(Einheit)として――把握されてしまっている点にあるのではないか。分裂分析は、この統一を多数多様化する。《分裂分析は、ひとりの主体の中におけるn……個の性の多様な分析であり、人間的形態の表象を超えていくのだ》(D&G、同前)。
このもんだいはまた、「作者」という過剰に単純化(縮減)された観念を召喚することにも結びつくかもしれない(「人」へのバックラッシュといってもよいだろう)。D&Gの次の著書『千のプラトー』の書き出しはこうだ。《われわれは『アンチ・オイディプス』を二人で書いた。二人それぞれが数人だったのだから、それだけでもう多数になっていた》(D&G[1980=2010: 上巻15])。愛する誰かやそうでない誰かをひとり(Einheit)の人物として見て(表象して)しまうことは、症候(symptoms)であろう。詩も詩人も症候であろう。D&Gの分裂分析の術語系でいえば、脱領土化のあとにくる再領土化であろう。必要なことは、どうしようもなく症候を(再領土化を)生きてしまっているわれわれが、脱領土化された景色も同時に観る、ということだ。あなたがどうしようもなくシス・ジェンダーであり、どうしようもなくヘテロであるとき、自己を社会のなかでの症候として観ること。また当該社会を症候として観ること。偶発的に顕在化した現象の、偶発的な固着として観ること。とあるベッドの上で、膣に男根が収納されている、と仮定してみよう。この男根がより奥へと押されるとき、どの性がどの性を欲望しているのだろうか。引き続いて手前に引かれるとき、どの性がどの性を欲望しているのか(ここまでですでに4つの性が想定された)。その運動を駆動する欲望機械のどれとどれが接続し、いかなる切断が生じているのか。あるいは一本の煙草を指に挟むとき、どの性がどの性を欲望しているのか。口に煙草を咥えるとき、煙を吸うとき、口から煙草を離すとき、煙を吐くとき、それぞれどの性がどの性を欲望しているのか。いかなる機械たちの離接が生じているのか。
D&Gが述べていることから逸脱して、「読む」ことも同様である、と考えてみよう。エクリチュールがとある単一のテクストであるように見えるとき(これもまたわれわれの呈するどうしようもない症候のひとつだ)、それはいかなる諸機械の諸離接であるのか。改行においていかなる切断が(あるいは接続が)設けられているのか。一行のなかにいくつの機械の離接が生じているのか。ひとつの文字はいくつの機械に所属しているのか(機械の数と、単語や文字や音の数は一致しないだろう。この現実をあからさまにカリカチュアライズしたものが加藤郁乎の句集『牧歌メロン』だともいえる)。エクリチュールは多形倒錯的に(こういってよければクイアに)、多数のテクストを遂行(perform)するだろう。ひとつ(ひとり)の観察者(当該社会はこれを「読者」と見做す)が「読む」のはせいぜい数個のテクストかもしれない(このようにも読める、あのようにも読める、というわけだ)。社会においては、たったひとつとはいわないまでも、少数のテクストがヘゲモニーを(一時的にかもしれないが)握ることになるだろう。その意味で、テクスト論のあとに現われた「読者主義」はあり得ないアイディアであり、テクスト論の誤読の産物である。テクストが作者のものでないからといって、読者のものになるわけではない。テクスト論が差し向けるのは、どの観察者によってテクストと見做されたものが、いかなる社会的布置連関・権力関係において、いかにしてヘゲモニーを握ったのか、ということの分析、ということになるだろう。
性愛について、また性愛の否定としての友愛については能弁であった9月号討議には、奇妙なことに「恋愛」が欠落している。意図的なあるいは無意識的な否認なのかもしれないし、恋愛は性愛のサブカテゴリーである、という認識なのかもしれない。しかしそのとき、《性愛的なものの排除というモチーフがとても大きい。すくなくとも男女が固定されるような性愛は、はっきり消されている》(瀬尾)と見做される最果タヒが、別の文脈、『現代詩手帖』同号掲載の、豊崎由美・広瀬大志「『恋愛詩』が消えた!?」においては《なぜ最果さんの詩が広く読まれているか、それは彼女の詩のモチーフが恋愛だから》(広瀬)と断定されることと、奇妙なコントラストをなしてしまう。観察者の違いによるヘゲモニー争いが起きているのだろうか。最果作品では、性愛を消したところにおいて恋愛が抽出・結晶化されている、と解釈できなくもないが、ならばやはり友愛と呼びうるところに、なぜか「恋愛」という意味的資源が滑り込んでいる、ということになる。これは、ふたつの症候として考えることができる。すなわち、瀬尾たちの議論においては性器的欲望・性器的行為を「性愛」と名指し、これを行為者の内面に帰属する(セクシュアリティ化する)作法が優位であり、他方で、広瀬たちの議論においては性器的行為も含めて、初恋から失恋、不倫、SMまで幅広く、およそ恋愛に関係しそうな事柄はすべて「恋愛」と名指し、これを普遍化・自然化する作法が優位である。いずれの作法もわれわれにとって馴れ親しまれたものであり、現実に両立しているといえる。恋愛という症候について述べておくと、たとえば広瀬は同対談で《原初的な詩の持ち味は恋愛観から派生するものだと思っています(略)恋愛は実際にはほとんど誰でもが経験する》(豊崎・広瀬[2020: 92])と――アセクシュアルやアロマンティックなど様々な「A-」たちへの――差別的とも受け取られかねない発言をしており、セクシュアリティについて生じた――三位一体神学!――のと同様の、排他的暴力が起きていることが分かる。マジョリティのふるまいを、自然で、歴史的に普遍的なことであると遠近法的に錯視する傾向は、恋愛という症候にかんしても生じる。だから再領土化は危険なことなのだ。ネイションについてベネディクト・アンダーソンたちが、同性愛者についてミシェル・フーコーたちが、言説以前のもの「として」想定される自然なセックス(生物学的性)についてジュディス・バトラーたちが、家族について多数の社会学者たちが、脱領土化された景色を見せてくれたように、恋愛についてもそうすることが必要だろう。それは政治的に正しい詩を書くためでもないし、道徳的であるためでもない。われわれの症候、錯視をこそ、権力は梃子にするのだし、そのため、われわれの言表や感情は容易に政治的に利用されてしまうからだ(それにしても、「政治的正しさ」とは、他者を歓待するという倫理が、たんに政治的に「のみ」正しい、といわんばかりであり、不快な響きをもつ言葉だ)。
社会学者ニクラス・ルーマン(Luhmann[1982=2005])は、愛(Liebe)を、17世紀に分出したコミュニケーション・メディアのうちのひとつであることを発見している(彼は「象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディア」とよぶ。なお、ここでルーマンが「愛」とよぶものは、われわれの文脈でいう「恋愛」のことである)。コミュニケーションの成功――すなわち他者の行為または体験に、自己の行為または体験を接続すること――は「ありそうもないこと」(Unwahrscheinlichkeit)である。なぜどこの馬の骨とも分からぬ者の書いた文章を読み・理解し・「恋愛を脱領土化せよ」なる提案にのらなければならないのか。このありそうもなさを前提とすることで、社会学が取り組むべき問題が浮かび上がる。成功する見込みがないはずなのに、実際には成功しているケースが少なくとも存在する、いい換えれば社会がいま現にあるということは、成功させるためのメカニズムがある(ないし、あった)はずであり、それはいかなる淘汰の過程を生き延びてきたのか、という問題である。たとえば貨幣は、売り手や買い手が互いに誰であるかに無関心でありながら、売買を成功させる、そうしたコミュニケーション・メディアである。愛も同様に社会進化上の獲得物である。愛というメディアが可能にするのは、他者の体験(愛される)に自己の行為(愛する)を接続する、という特殊なコミュニケーションである。他者の体験を、自己の行為の前提として受け入れる、というきわめてありそうもない事態が生じることになる。他者が自らの体験を語るとき、その特殊性ゆえに、聞き入れることはありそうもない。だが私は彼女の一風変わったものの見方を注意深く聴き、彼女のものの見方を前提として私の行為を企てるのだ。その理由は「彼女が彼女だから」である。その意味で、貨幣がインパーソナルな関係を拡大する(近代社会のコインの表といえる)ものであったのとは対照的に、愛はパーソナルな関係を「深める」(近代社会のコインの裏)。愛が社会進化上の獲得物であるならば、まさに進化の途上にある社会において、その意味内容・使用方法は変化する。現にわれわれが「愛のコミュニケーション」や「愛についてのコミュニケーション」を行うことを可能にし、行うことで再生産される意味的濃縮物の蓄積を社会構造とよぶとき、これに対応して、当該社会がその社会の自己記述を行う。これをゼマンティク(Semantik)とよぶ。ゼマンティクは主要にはテクストとして保持される。愛については、初期には恋愛小説が、近年では映画、テレビドラマ、漫画、ポップ・ミュージックなどがその役割を果たしている。詩もその役割を果たしてきたといえる(この歴史社会学的分析については、やはり豊崎・広瀬[2020]が役に立つ)。現にコミュニケーションを可能にし、条件付けている社会構造に対して、記述・描写の役割を担うゼマンティクはそれゆえ、遅れる。「時代遅れだ」と感じられることもあるだろう。しかし、社会構造がゼマンティクを一方的に規定するわけではない。ゼマンティクが新しい社会への変動を促し、方向づけ、刺激することもある(古いものでは宗教革命に出版物が果たした役割を、卑近な例では「ソーシャル・ディスタンス」なるキャッチフレーズを考えればよい)。
さて、現代詩から「恋愛が消えた」という事態は、何を表現しているのか(何のゼマンティクなのか)。豊崎・広瀬[2020]によれば、ポップス、サブカル、詩から分離した「ポエム」、短歌などが恋愛詩を継承した、とされているが、妥当だろうか。社会構造を事後的に記述する、というゼマンティクの役割のみを見るならば妥当であろう。しかしそれらにおいて表現されている「恋愛」は明らかに「時代遅れだ」と感じさせるものであるし、むしろそのレトロな雰囲気を楽しむものになってはいないか(ポップ・ミュージックの文脈で流行の「レトロ・フューチャー」でさえない)。むろん、たとえば短歌においては川野芽生『Lilith』(2020年)のように恋愛(という制度)を《奇習》とまでよび、《狂恋を逃れむがため》と歌い上げる「新しい」ポエジー(というか、現在的なポエジー)が生じてはいるが。現代詩について、言語との格闘を抜きにして考えることは難しい。8月号討議(瀬尾他[2020a])から9月号討議(瀬尾他[2020b])にいたるまで、頻出語ともなっている「読めなさ」は、そのまま現在の恋愛について、ひいてはコミュニケーションについて、生々しく、なにごとかを伝えようとしていると読めないだろうか(私は、8月号討議で、小笠原鳥類の作品が「線というより面」「読むというより見る」と評されているのを目にして、衝撃を受けた。私自身は新しい時代の落語の台本ででもあるかのように、昂揚感をもって「読む」を楽しんでいたからだ。この断絶は越えがたい。ことほどさように、コミュニケーションはありそうにないのだ)。私の仮説だが、現代詩から、恋愛も性愛も消えてなどいない。いや、そうよぶ必要のない、別の可能性が探られている。いまげんざい「恋愛」や「性愛」と習慣的によばれている社会的事実と、われわれの個別の経験が、どうしようもなく乖離している。スクリーンに映し出される映像と、観客席に座るものの尻の痛みほどに、離れている。新しい、別の社会構造が必要だ。それがいまげんざい「読めない」とされている現代詩において指し示されている。(社会)進化のつねとして、どれが淘汰され、どれが選択されるのかは、偶発的ではあるが。豊崎・広瀬[2020]において《エロス的恋愛詩》のひとつとして言及されている野村喜和夫「オルガスムス屋、かく語りき」(『デジャヴュ街道』より)は、たしかに目に見える文字で「読める」部分を頼りにするなら、ヘテロ男女の性愛を描いたものではあるのだが、これほどクイアな感触を与えるエクリチュールもそうそうないだろう。もちろん、「ヘテロもクイア」という短絡は、差し控えられるべきだ。マイノリティのもんだいが棚上げされてしまう危険をともなうからだ。せいぜい「ヘテロでもクイア」とよびうる領域が、切り開かれる可能性がある、というに留めておかなければならない。「クイア文学」なるカテゴリーはあり得ない。あるのは「クイアな読み」だけだ。必要なのは、新しい「読み」である。
【文献表】
Deleuze, Gill; Guattari, Félix, 1972, L'Anti-Œdipe, Paris: Les Éditions de Minuit. = 2006、宇野邦一訳『アンチ・オイディプス――資本主義と分裂症』河出文庫。
――――, 1980, Mille Plateaux, Paris: Les Éditions de Minuit. = 2010、宇野邦一他訳『千のプラトー――資本主義と分裂症』河出文庫。
榎本櫻湖、2020、「わたしはまたしてもなにも書かなかったことにされるんですか? 『現代詩アンソロジー2010-2019』に抵抗する」『現代詩手帖』vol.63, no.10: 148-150。
Luhmann, Niklas, 1982, Liebe als Passion: Zur Codierung von Intimität, Frankfurt: Suhrkamp. = 2005、村中知子・佐藤勉訳『情熱としての愛――親密さのコード化』木鐸社。
瀬尾育夫・野村喜和夫・小池昌代・蜂飼耳、2020a、「二〇〇〇年代、詩に何が起こったのか」『現代詩手帖』vol.63, no.8: 10-26。
――――、2020b、「10年代から現在へ――いま、詩は」『現代詩手帖』vol.63, no.9: 10-27。
豊崎由美・広瀬大志、2020、「『恋愛詩』が消えた!?」『現代詩手帖』vol.63, no.9: 92-108。
上野千鶴子、1997、「セックス/ジェンダー/セクシュアリティの三位一体神学の解体のあとで」『現代思想』vol.25, no.6: 88-93。











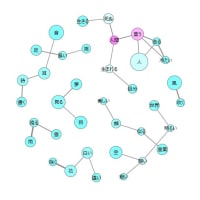


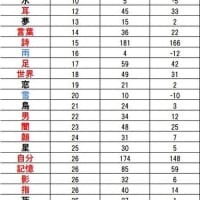
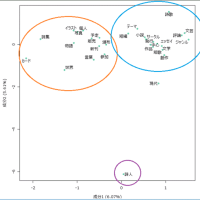
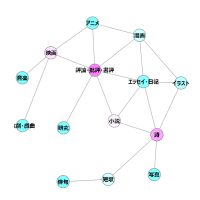
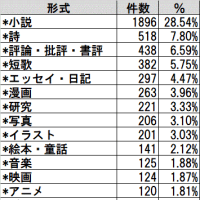
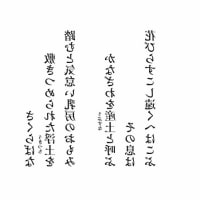
「いまげんざい「恋愛」や「性愛」と習慣的によばれている社会的事実と、われわれの個別の経験が、どうしようもなく乖離している。(…)新しい、別の社会構造が必要だ。それがいまげんざい「読めない」とされている現代詩において指し示されている。」
「別の社会構造」とはどういうものか、「読めない」詩をどう読むのか、今後の展開に期待しています。
はじめまして。大ファンの鳥類さんからコメントをいただき、びっくりです。先日の「懐紙シリーズ第一集」も、小島きみ子さんの個人誌『エウメニデス』掲載作品も読ませていただいています。
JugemブログもRSSフィードを登録して、更新されたらすかさず読んでいます。
榎本櫻湖さんも『詩手帖』10月号で「四人の選者が、ある傾向の作品群を(…)などとお手あげ状態なのは情けない」と書いていますが、まったくそのとおりだと思います。
そしてなぜか「読めない」「線でなく面で文字を見せる」代表格として、鳥類さんの名前があげられていて……ちょっとそれはないでしょう、と思いました(むしろ粒状の蜜が、どんどん次の蜜の粒を生んで、くっついていって、水飴のように糸をひいて、最終的に立体的な蜂蜜のかたまりみたいになる――ような感触をぼくは、小笠原作品に対して、抱いているのですが……いつも爆笑して読んでいるのですが……なので、いわゆる「読めない」と分類される作品では、ない、と思うのです)。
野村喜和夫さんにはまた、別の言い分があるのかもしれませんけれども。
ここで言っても詮無いことではありますが。
近々(来年)、もしかしたら、とあるところでご一緒するかもしれません。
そのときは、よろしくお願いいたします。
ここ(詩客の自由詩評)には、来年の2月に、もう一度書かせてもらえることになっています。