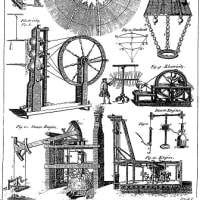以前、私がどうして工学部に所属していたのに、人文系の書物にのめりこんだかという経緯については『徹夜マージャンの果てに』に述べた。その後の私の取り組みについては以前も『セネカの本: De Vita Beata』で少し触れたが、さらに敷衍してみたい。
自分で決めた目標、つまり『人生の意義とは何か』について納得する答えをみつけるために、本を読むことにした。しかしそうは行っても、初めは何から読んでいいのか分からないので、とりあえず人生論と銘打った本を手当たり次第に読むことにした。今思い出すのは亀井勝一郎、河合栄治郎、三木清、倉田百三、阿部次郎などいわゆる大正デモクラシーの自由主義思想家達が多かったように思う。何冊か読むうちに、彼らの思想のバックボーンをなしているのがドイツ観念哲学だと分かった。
当時も、そして今もそうだが、私の本の読み方は、『主体的に読む』ということに尽きる。その意味は、世の中の評価とは無関係に自分の基準で本の価値を決めることである。これは孟子にある、『尽信書,則不如無書』(尽く書を信ずれば則ち書なきに如かず)の趣旨である。つまり『本を無批判的に信用するぐらいなら一層のこと、本は存在しない方がましだ』、という意味である。また字句にとらわれず、その大意を把握することに心がけた。それは荘子にある『筌蹄(せんてい)』の趣旨だ。(このことについては『得意而忘言』に述べた。)
上記の自由主義思想家が一様に挙げている人名の筆頭は近代ドイツ哲学のカント、ヘーゲルであったが、また必ずギリシャの哲人であるソクラテス、プラトン、アリストテレスにも遡及していた。その他、ショーペンハウアー、モンテーニュ、デカルトなどの名前もしばしば登場していた。これは当時の世界共通の現象であったことは、例えばNHK出版から出版されているブライアン・マギーの『哲学人』(上・下)を読むと、彼がオックスフォード大学で勉強した哲学も大体これらの人々のものであったことが書かれていることからも分かる。

さて、これらの本を読むうちに、興味がわいてきてここで挙げられている本を、当初は日本語で、その内にドイツ語で読むようになった。当時(1978年)はドイツ留学から戻ってきた直後でもあり、ドイツ語がよく読めたし、またドイツ語に上達したいとも願っていた。いろいろ読んでみて分かったのが、私の感覚に一番フィットするのがギリシャ・ローマ時代の哲学であるということだった。その理由はこれら古代ヨーロッパの哲学の中心テーマが『人はどのように生きるべきか』、とまさに私が求めていたものであったからだ。
とりわけ私が感銘を受けたのはプラトンとセネカであった。ついでに言うと、その後読んだモンテーニュのエッセーではこの二人と並んでプルタークが彼、モンテーニュのお気に入りの著者として挙げられている。そして、その影響をもろに受けた私もプラトンとセネカやモンテーニュと共にプルタークも愛読書となった。
しかしその中でもプラトンは私にとっては非常に大きなインパクトを与えた哲学者である。それは、内容というよりその語り口、いわゆるレトリックである。彼の対話篇とよばれる作品は私にとってはシェークスピア以上に素晴らしい戯曲であった。ビジネス書のベストセラーで最近ようやく邦訳が出版された『The Goal』でもプラトンは戯曲のように読むべしとの筆者(Goldratt氏)の意見があった。例えば、『プロタゴラス』においては、当時高名なソフィスト(遊説弁舌家)のプロタゴラスとソクラテスの語り口の違いがありありと分かるように書かれている。プロタゴラスは長文の演説で問題の核心をぼやかしながら、それでも人を知らず知らずの内に自分の土俵に引きずりこむやりかたであるのに対して、ソクラテスはまるで幾何学の証明問題を解くように、一問一答方式で緻密な論理展開をするやりかたであった。プラトンはその二人の特徴をあますところなく描写しているので、読んでいるとその二人を取り囲む数人の若者が熱心に聴いていて、思わず拍手をしたり、または相手方を冷やかしたりしている光景が眼前に彷彿とする。
ギリシャ人のゼノンが開祖であるストア学派(通常ストイックといわれている一派)はローマ時代に入ると人気沸騰し、ついにはローマ皇帝のマルクス・アウレリウスまでがストア学派の巨頭になった。ストア学派は本来ソクラテスの系統であるが、理性および強い意志の力を何よりも尊重するところにその特徴がある、と私は理解している。苦難、貧困は意志の力で克服できるものであって、貧乏で苦しくとも幸福であるにはなんらの障害にならない、と主張している。このような考えは仏教や儒教でも根本的には同じであるが、私が感心したのは、その説明のレトリックである。巧みな比喩を用いたり、または短い疑問文を幾つも重ねることで、相手に反論させる隙を見せずに説伏してしまう、そういった迫力はこのギリシャ・ローマのものに匹敵するものを私は知らない。
さて、その後私の興味は次第に『...であるべき』論が主体の哲学( Sollen哲学)から、『...であった』論が主体の歴史に変わった。それは、私の当初の疑問であった『人間はいかに生くべきか』という問いに対してこれら哲学者が述べていることに対して私自身で判断するには経験不足であったと、気がついたからだった。この点に気づいてからは、私の読書は次第に歴史、それも特に人物論主体の記述が多い歴史に興味が移っていったのであった。それについてはまたいづれ改めて述べたい。
自分で決めた目標、つまり『人生の意義とは何か』について納得する答えをみつけるために、本を読むことにした。しかしそうは行っても、初めは何から読んでいいのか分からないので、とりあえず人生論と銘打った本を手当たり次第に読むことにした。今思い出すのは亀井勝一郎、河合栄治郎、三木清、倉田百三、阿部次郎などいわゆる大正デモクラシーの自由主義思想家達が多かったように思う。何冊か読むうちに、彼らの思想のバックボーンをなしているのがドイツ観念哲学だと分かった。
当時も、そして今もそうだが、私の本の読み方は、『主体的に読む』ということに尽きる。その意味は、世の中の評価とは無関係に自分の基準で本の価値を決めることである。これは孟子にある、『尽信書,則不如無書』(尽く書を信ずれば則ち書なきに如かず)の趣旨である。つまり『本を無批判的に信用するぐらいなら一層のこと、本は存在しない方がましだ』、という意味である。また字句にとらわれず、その大意を把握することに心がけた。それは荘子にある『筌蹄(せんてい)』の趣旨だ。(このことについては『得意而忘言』に述べた。)
上記の自由主義思想家が一様に挙げている人名の筆頭は近代ドイツ哲学のカント、ヘーゲルであったが、また必ずギリシャの哲人であるソクラテス、プラトン、アリストテレスにも遡及していた。その他、ショーペンハウアー、モンテーニュ、デカルトなどの名前もしばしば登場していた。これは当時の世界共通の現象であったことは、例えばNHK出版から出版されているブライアン・マギーの『哲学人』(上・下)を読むと、彼がオックスフォード大学で勉強した哲学も大体これらの人々のものであったことが書かれていることからも分かる。

さて、これらの本を読むうちに、興味がわいてきてここで挙げられている本を、当初は日本語で、その内にドイツ語で読むようになった。当時(1978年)はドイツ留学から戻ってきた直後でもあり、ドイツ語がよく読めたし、またドイツ語に上達したいとも願っていた。いろいろ読んでみて分かったのが、私の感覚に一番フィットするのがギリシャ・ローマ時代の哲学であるということだった。その理由はこれら古代ヨーロッパの哲学の中心テーマが『人はどのように生きるべきか』、とまさに私が求めていたものであったからだ。
とりわけ私が感銘を受けたのはプラトンとセネカであった。ついでに言うと、その後読んだモンテーニュのエッセーではこの二人と並んでプルタークが彼、モンテーニュのお気に入りの著者として挙げられている。そして、その影響をもろに受けた私もプラトンとセネカやモンテーニュと共にプルタークも愛読書となった。
しかしその中でもプラトンは私にとっては非常に大きなインパクトを与えた哲学者である。それは、内容というよりその語り口、いわゆるレトリックである。彼の対話篇とよばれる作品は私にとってはシェークスピア以上に素晴らしい戯曲であった。ビジネス書のベストセラーで最近ようやく邦訳が出版された『The Goal』でもプラトンは戯曲のように読むべしとの筆者(Goldratt氏)の意見があった。例えば、『プロタゴラス』においては、当時高名なソフィスト(遊説弁舌家)のプロタゴラスとソクラテスの語り口の違いがありありと分かるように書かれている。プロタゴラスは長文の演説で問題の核心をぼやかしながら、それでも人を知らず知らずの内に自分の土俵に引きずりこむやりかたであるのに対して、ソクラテスはまるで幾何学の証明問題を解くように、一問一答方式で緻密な論理展開をするやりかたであった。プラトンはその二人の特徴をあますところなく描写しているので、読んでいるとその二人を取り囲む数人の若者が熱心に聴いていて、思わず拍手をしたり、または相手方を冷やかしたりしている光景が眼前に彷彿とする。
ギリシャ人のゼノンが開祖であるストア学派(通常ストイックといわれている一派)はローマ時代に入ると人気沸騰し、ついにはローマ皇帝のマルクス・アウレリウスまでがストア学派の巨頭になった。ストア学派は本来ソクラテスの系統であるが、理性および強い意志の力を何よりも尊重するところにその特徴がある、と私は理解している。苦難、貧困は意志の力で克服できるものであって、貧乏で苦しくとも幸福であるにはなんらの障害にならない、と主張している。このような考えは仏教や儒教でも根本的には同じであるが、私が感心したのは、その説明のレトリックである。巧みな比喩を用いたり、または短い疑問文を幾つも重ねることで、相手に反論させる隙を見せずに説伏してしまう、そういった迫力はこのギリシャ・ローマのものに匹敵するものを私は知らない。
さて、その後私の興味は次第に『...であるべき』論が主体の哲学( Sollen哲学)から、『...であった』論が主体の歴史に変わった。それは、私の当初の疑問であった『人間はいかに生くべきか』という問いに対してこれら哲学者が述べていることに対して私自身で判断するには経験不足であったと、気がついたからだった。この点に気づいてからは、私の読書は次第に歴史、それも特に人物論主体の記述が多い歴史に興味が移っていったのであった。それについてはまたいづれ改めて述べたい。