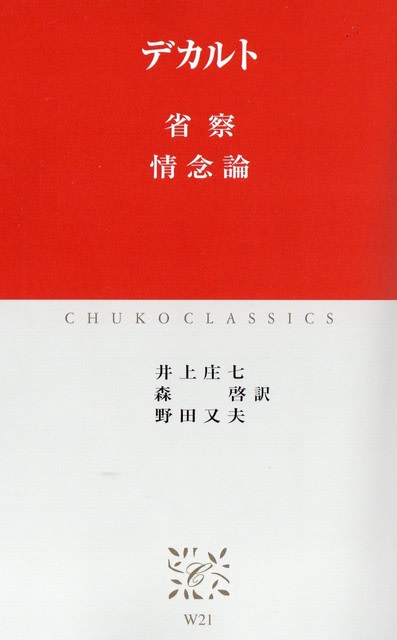デカルト著 省察・情念論(中公クラシック)
近代哲学・科学思想の祖 デカルトの道徳論 第2回
序(その2)
「デカルトの哲学体系」
哲学の根に相当する形而上学であるが、方法論的懐疑から「コギト・エルゴ・スム」という命題を見出し、神の存在証明に及んだ。そしてデカルト主義の二元論である心身合一の問題に一つの矛盾に突き当たるのである。方法的懐疑についてであるが、幼児の時から無批判に受け入れてきた先入観を排除し、真理に至るために、一旦全てのものをデカルトは疑う。この方法的懐疑の特徴として、2点挙げられる。1つ目は懐疑を抱くことに本人が意識的・仮定的であること、2つ目は一度でも惑いが生じたものならば、すなわち少しでも疑わしければ、それを完全に排除することである。つまり、方法的懐疑とは、積極的懐疑のことである。この強力な方法的懐疑は、もう何も確実であるといえるものはないと思えるところまで続けられる。まず、肉体の与える感覚(外部感覚)は、しばしば間違うので偽とされる。また、「痛い」「甘い」といった内部感覚や「自分が目覚めている」といった自覚すら、覚醒と睡眠を判断する指標は何もないことから偽とされる。この方法的懐疑の特徴は、当時の哲学者としてはほとんど初めて、「表象」と「外在」の不一致を疑ったことにある。方法的懐疑を経て、肉体を含む全ての外的事物が懐疑にかけられ、純化された精神だけが残り、デカルトは、「私がこのように“全ては偽である”と考えている間、その私自身はなにものかでなければならない」、これだけは真であるといえる絶対確実なことを発見する。これが「私は考える、ゆえに私はある」である。ラテン語ではコギト・エルゴ・スム と呼ばれる。コギト・エルゴ・スムは、方法的懐疑を経て「考える」たびに成立する。そして、「我思う、故に我あり」という命題が明晰かつ判明に知られるものであることから、その条件を真理を判定する一般規則として立てて、「自己の精神に明晰かつ判明に認知されるところのものは真である」と設定する(明晰判明の規則)。神の存在証明では、欺く神 ・ 悪い霊を否定し、誠実な神を見出すために、デカルトは神の存在証明を行う。
第一証明 - 意識の中における神の観念の無限な表現的実在性(観念の表現する実在性)は、対応する形相的実在性(現実的実在性)を必然的に導く。我々の知は常に有限であって間違いを犯すが、この「有限」であるということを知るためには、まさに「無限」の観念があらかじめ与えられていなければならない。
第二証明 - 継続して存在するためには、その存在を保持する力が必要であり、それは神をおいて他にない。
第三証明 - 完全な神の観念は、そのうちに存在を含む。(アンセルムス以来の証明)
このような「神」は、デカルトの思想にとってとりわけ都合のよいものである。ブレーズ・パスカルはこの事実を指摘し、『パンセ』の中で「デカルトの神は単に科学上の条件の一部であって、主体的に出会う信仰対象ではないと批判した。
物体の本質と存在の説明も、デカルト的な自然観を適用するための準備として不可欠である。三次元の空間の中で確保される性質(幅・奥行き・高さ)、すなわち「延長」こそ物体の本質であり、これは解析幾何学的手法によって把捉される。一方、物体に関わる感覚的条件(熱い、甘いetc.)は物体が感覚器官を触発することによって与えられる。なにものかが与えられるためには、与えるものがまずもって存在しなければならないから、物体は存在することが確認される。しかし、存在するからといって、方法的懐疑によって一旦退けられた感覚によってその本質を理解することはできない。純粋な数学・幾何学的な知のみが外在としての物体と対応する。このことから、後述する機械論的世界観が生まれる。1643年5月の公女エリーザベトからの書簡において、デカルトは、自身の哲学において実在的に区別される心(精神)と体(延長)が、どのようにして相互作用を起こしうるのか、という質問を受ける。この質問は、心身の厳格な区別を説くデカルトに対する、本質的な、核心をついた質問で「心身合一の問題」と呼ばれる。デカルトは情念はどのように生じ、どうすれば統御できるのか、というエリーザベトの問いに答える著作に取り組んだ。それは1649年の『情念論』として結実することになる。『情念論』において、デカルトは人間を精神と身体とが分かち難く結びついている存在として捉えた。心(精神)と身体を結ぶのは現医学では神経系であるが、デカルトは古い医学を採用し結び目は脳の奥の松果腺において顕著であり、その腺を精神が動かす(能動)、もしくは動物精気によって動かされる(受動)ことによって、精神と身体が相互作用を起こす、と考えた。デカルトが(能動としての)精神と(受動としての)身体との間に相互作用を認めたことと、一方で精神と身体の区別を立てていることは、論理の上で、矛盾を犯している。後の合理主義哲学者(スピノザ、ライプニッツ)らはこの二元論の難点を理論的に克服することを試みた。哲学の幹に相当するのが自然学である。デカルトは、物体の基本的な運動は、直線運動であること、動いている物体は、抵抗がない限り動き続けること(慣性の法則)、一定の運動量が宇宙全体で保存されること(運動量保存則)など、(神によって保持される)法則によって粒子の運動が確定されるとした。この考えは、精神に物体的な風や光を、宇宙に生命を見たルネサンス期の哲学者の感覚的・物活論的世界観とは全く違っており、力学的な法則の支配する客観的世界観を見出した点で重要である。更にデカルトは、見出した物理法則を『世界論』(宇宙論)において宇宙全体にも適用し、粒子の渦状の運動として宇宙の創生を説く渦動説を唱えた。ニュートンの万有引力にはまだ気が付いていないので、デカルトはガリレオとニュートmmを結ぶ科学史上の位置に置かれる。数学の分野では、2つの実数によって平面上の点の位置(座標)を表すという方法は、デカルトによって発明され、『方法序説』の中で初めて用いられた。この座標はデカルト座標と呼ばれ、デカルト座標の入った平面をデカルト平面という。デカルト座標、デカルト平面によって、後の解析幾何学の発展の基礎が築かれた。
(つづく)