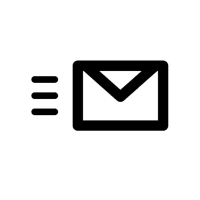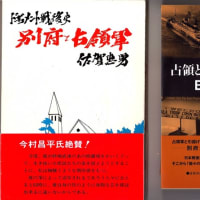誰も仮面を被りっぱなしでは生きられないわけで、人は生きづらさに耐えきれずに魔物を呼び寄せることもある。それは悪魔との契約なのか。
かなり以前に、ある病気と闘う人々を次々にインタビューした。実はテープ起こしのデータはなく、感熱紙にプリントアウトしたものしか残っていないものもあった。感熱紙の印字は時間とともに薄れ、やがて消えていく。その前に保存しておこうと再入力を行っている。入力していて心が震えた。その一部を読みもの的にアレンジした。まずはその前編。個人を特定できないよう若干枝葉を変えているが、語られる内容の幹は本当の話だ。まさに「事実は小説よりも奇なり」である。
ある男性の独白の記録
「何の因果でこんな病気になったのだろう。分かっているのは、変えられない病気が自分の中にあるということ。こんな病気にならないで、健康的に生きていたかったけど、それはできないことだった。何か十字架を背負っている感じ」
30代の男性は、自分の子ども時代から語り始めた。
小学生の頃
「何年生の頃だったでしょうか。父と母と僕と妹の4人で食事をしていました。父はお酒を飲んでいます。きっと日本酒だったと思います。母はお酒を飲ませたくないので、怒っています。とてもみんながピリピリしていました。会話はひと言もありません。みんな黙々とご飯を食べるのです。飲み過ぎた父がそのままうつぶせになって寝てしまったこともありました。ある日は、酒をもう一本という父を母が無視し、父が食卓をひっくり返すというアニメのようなこともありました。それが僕の家族でした。お酒をやめられない父とやめさせようとする母の、ぶつかり合いのなかにいつもいました」
今だから振り返ることができる温もりのない風景。
「夏休みになると友だちの家では家族旅行に行ったりする。それがわが家ではまったくありませんでした。今思うと健康的な家庭ではなかったのかもしれません。でも、それが自分では分かりませんでした」
実家は洋食屋を営んでいた。父親の記憶はモノトーン。
「父は朝から飲んでいました。母は落ち着かず、いつもイライラしていました。父の近所の行きつけの飲み屋さんから酔いつぶれたのでお金を持って来てと電話がよく掛かってきて……」
それは、母と子の関係にも影を落とす。
「僕も妹もかまってもらえませんでした。家業が忙しいこともあり、手を焼かせることをやるとすごく怒られました。とても母が怖かった」
宿題を忘れて、それが何度か重なって、学校から連絡があると母親は烈火の如く怒った。
「いまでも症状として残っていますが、対人恐怖症のような……、萎縮して、いつも何かに怯えているような感じでした」
子ども時代、多くの子がそうであったようにニンジンが嫌いだった。でも、嫌いだとは言えずランドセルに突っ込んだ。それが母親に見つかり物差しで叩かれた。
「叩かれた痛さより、母に捨てられる恐怖心から、何でも食べようと思いました」
母親のルールにさえ従っていれば問題は起こらない。「よい子」であることで、なんとか「ふつう」を維持できた。しかし、それ以上のふれあいの記憶ははない。
「母にほめられた記憶はありません。怒るときも、子どものためを思ってというのがよくあるじゃないですか。でも母はそれとは違っていたのではないかと思っています」
人から見捨てられたくない。それは体に刻印された叫びであった。
「失敗すると人に嫌われると何時も思っていました。今になって感じるんですけど、自分で自分をほめることができない。自分の長所を見つけ出すことができない。自分自身に厳しくなって、完璧主義の大人になりました」
中学生から高校生にかけて
「父は暴力こそ振るいませんでしたが、しらふの時間が少なくなりました。枕元で吐かれたこともありました。酒の量が増えるにつれて仕事がおろそかになり、その分母親は忙しくなって、家の中はいつも何かが張り詰めていました」
中学に入ると寝付かれないことが多くなっていった。
「夜、布団に入ると不安に取り囲まれるんです」
中学3年生のときアルコールを飲んだ。
「友だちから日本酒を勧められてコップに半分くらい。何かとても開放的な気分になりました。その感覚が忘れられず、寝る前に冷蔵庫から缶ビールを盗んできて飲んだら、朝までぐっすり眠れたんです」
酒は不安感を解き放ち、相対する人との関係に勇気を与えてくれた。
「高校1年で好きな女の子ができて、喫茶店で待ち合わせて、もうドキドキ。お酒を飲んだら落ち着きました」
飲酒の頻度は増えていったが酒量は少なく、運動部にも所属する若い体は健康だった。2年生になると毎晩飲むようになる。小遣いには限りがあり。アルコールをどう手に入れるかで頭がいっぱいになっていく。
「お金がなくなると、母の財布からお金を盗んだり、父の酒をくすねたり……。母が気づいて財布を隠すわけですが、今度は金庫から盗んだりもしました」
高校3年になると、酒量が一気に増え日本酒の900mlパックを空けるようになっていった。朝、「酒臭い」と友だちから言われることが多くなった。成績も下がり始めた。
「何かおかしい。お酒を控えなければ。 だが、そう思っても、夜になるとイライラしてきて、飲まずにはいられなくなってくるんです」
予備校時代
大学入試はすべて不合格。予備校に通うことになった。風邪で病院を受診したとき、医者は言った。
「君、酒臭いね」
「飲まないと眠れないんですよ」
「寝ないで死んだヤツはいない。酒はやめなさい。学生だろ。就職すればいくらでも飲める」
予備校生で学生ではないなどと説明しようかと思ったがやめた。「そうか、大学に入れば好きなだけ飲めるんだなあ」と勝手に解釈した。
「しばらく酒をやめようと真剣に思いました。徹夜をしました。本当に眠れなかったんです。いつのまにかお酒を飲まなければ眠れない体になっていた。いや、体ではなく、心がそういう状態になっていたのかもしれません」
3日目の徹夜明け、酒に手を出し、酒をやめることをやめた。
「予備校の授業料を使い込んだりもしました。昼はパチンコをしながら飲み、夜は安い焼鳥屋で飲むんです」
飲み方が人とは違っていると気づき始めたのはその頃だった。
「他の人は途中で切り上げることができるんです。でも僕にはそれができなかった。意識ができなくなるまで飲む。とにかくやめられないんです」
2年間の浪人の後、大学を諦めることになった。その頃父親の体調は著しく悪化、入退院を繰り返すようになっていく。
つづく
かなり以前に、ある病気と闘う人々を次々にインタビューした。実はテープ起こしのデータはなく、感熱紙にプリントアウトしたものしか残っていないものもあった。感熱紙の印字は時間とともに薄れ、やがて消えていく。その前に保存しておこうと再入力を行っている。入力していて心が震えた。その一部を読みもの的にアレンジした。まずはその前編。個人を特定できないよう若干枝葉を変えているが、語られる内容の幹は本当の話だ。まさに「事実は小説よりも奇なり」である。
ある男性の独白の記録
「何の因果でこんな病気になったのだろう。分かっているのは、変えられない病気が自分の中にあるということ。こんな病気にならないで、健康的に生きていたかったけど、それはできないことだった。何か十字架を背負っている感じ」
30代の男性は、自分の子ども時代から語り始めた。
小学生の頃
「何年生の頃だったでしょうか。父と母と僕と妹の4人で食事をしていました。父はお酒を飲んでいます。きっと日本酒だったと思います。母はお酒を飲ませたくないので、怒っています。とてもみんながピリピリしていました。会話はひと言もありません。みんな黙々とご飯を食べるのです。飲み過ぎた父がそのままうつぶせになって寝てしまったこともありました。ある日は、酒をもう一本という父を母が無視し、父が食卓をひっくり返すというアニメのようなこともありました。それが僕の家族でした。お酒をやめられない父とやめさせようとする母の、ぶつかり合いのなかにいつもいました」
今だから振り返ることができる温もりのない風景。
「夏休みになると友だちの家では家族旅行に行ったりする。それがわが家ではまったくありませんでした。今思うと健康的な家庭ではなかったのかもしれません。でも、それが自分では分かりませんでした」
実家は洋食屋を営んでいた。父親の記憶はモノトーン。
「父は朝から飲んでいました。母は落ち着かず、いつもイライラしていました。父の近所の行きつけの飲み屋さんから酔いつぶれたのでお金を持って来てと電話がよく掛かってきて……」
それは、母と子の関係にも影を落とす。
「僕も妹もかまってもらえませんでした。家業が忙しいこともあり、手を焼かせることをやるとすごく怒られました。とても母が怖かった」
宿題を忘れて、それが何度か重なって、学校から連絡があると母親は烈火の如く怒った。
「いまでも症状として残っていますが、対人恐怖症のような……、萎縮して、いつも何かに怯えているような感じでした」
子ども時代、多くの子がそうであったようにニンジンが嫌いだった。でも、嫌いだとは言えずランドセルに突っ込んだ。それが母親に見つかり物差しで叩かれた。
「叩かれた痛さより、母に捨てられる恐怖心から、何でも食べようと思いました」
母親のルールにさえ従っていれば問題は起こらない。「よい子」であることで、なんとか「ふつう」を維持できた。しかし、それ以上のふれあいの記憶ははない。
「母にほめられた記憶はありません。怒るときも、子どものためを思ってというのがよくあるじゃないですか。でも母はそれとは違っていたのではないかと思っています」
人から見捨てられたくない。それは体に刻印された叫びであった。
「失敗すると人に嫌われると何時も思っていました。今になって感じるんですけど、自分で自分をほめることができない。自分の長所を見つけ出すことができない。自分自身に厳しくなって、完璧主義の大人になりました」
中学生から高校生にかけて
「父は暴力こそ振るいませんでしたが、しらふの時間が少なくなりました。枕元で吐かれたこともありました。酒の量が増えるにつれて仕事がおろそかになり、その分母親は忙しくなって、家の中はいつも何かが張り詰めていました」
中学に入ると寝付かれないことが多くなっていった。
「夜、布団に入ると不安に取り囲まれるんです」
中学3年生のときアルコールを飲んだ。
「友だちから日本酒を勧められてコップに半分くらい。何かとても開放的な気分になりました。その感覚が忘れられず、寝る前に冷蔵庫から缶ビールを盗んできて飲んだら、朝までぐっすり眠れたんです」
酒は不安感を解き放ち、相対する人との関係に勇気を与えてくれた。
「高校1年で好きな女の子ができて、喫茶店で待ち合わせて、もうドキドキ。お酒を飲んだら落ち着きました」
飲酒の頻度は増えていったが酒量は少なく、運動部にも所属する若い体は健康だった。2年生になると毎晩飲むようになる。小遣いには限りがあり。アルコールをどう手に入れるかで頭がいっぱいになっていく。
「お金がなくなると、母の財布からお金を盗んだり、父の酒をくすねたり……。母が気づいて財布を隠すわけですが、今度は金庫から盗んだりもしました」
高校3年になると、酒量が一気に増え日本酒の900mlパックを空けるようになっていった。朝、「酒臭い」と友だちから言われることが多くなった。成績も下がり始めた。
「何かおかしい。お酒を控えなければ。 だが、そう思っても、夜になるとイライラしてきて、飲まずにはいられなくなってくるんです」
予備校時代
大学入試はすべて不合格。予備校に通うことになった。風邪で病院を受診したとき、医者は言った。
「君、酒臭いね」
「飲まないと眠れないんですよ」
「寝ないで死んだヤツはいない。酒はやめなさい。学生だろ。就職すればいくらでも飲める」
予備校生で学生ではないなどと説明しようかと思ったがやめた。「そうか、大学に入れば好きなだけ飲めるんだなあ」と勝手に解釈した。
「しばらく酒をやめようと真剣に思いました。徹夜をしました。本当に眠れなかったんです。いつのまにかお酒を飲まなければ眠れない体になっていた。いや、体ではなく、心がそういう状態になっていたのかもしれません」
3日目の徹夜明け、酒に手を出し、酒をやめることをやめた。
「予備校の授業料を使い込んだりもしました。昼はパチンコをしながら飲み、夜は安い焼鳥屋で飲むんです」
飲み方が人とは違っていると気づき始めたのはその頃だった。
「他の人は途中で切り上げることができるんです。でも僕にはそれができなかった。意識ができなくなるまで飲む。とにかくやめられないんです」
2年間の浪人の後、大学を諦めることになった。その頃父親の体調は著しく悪化、入退院を繰り返すようになっていく。
つづく