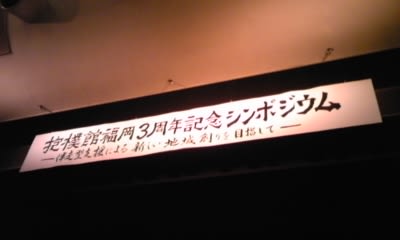抱樸館福岡が、われらがQ大のそばにあってよかったと本当に思う。自転車なら15分~20分。院生の研究においても、授業を介して学部学生にとっても、さまざまな出会いや学びをいただいている。信頼する若者たち太鼓集団「響」との出会いも共有させていただけた。大学で学び研究する人間にとって、誰の「隣人」であらんとして、その研究や授業がなされているのかは、とても大事なことだと思っている。さまざまな偏見や社会のひずみを一身に背負って地域や社会とのはざまで葛藤する抱樸館は、その思いを託しうる人々と実践だという思いが、時間を重ねるほどに深まっていく。
そんな抱樸館福岡の青木館長から、3周年記念シンポジウムの進行役をひきうけてほしいという依頼があった。もちろんありがたくひきうけさせていただいた。北九州ホームレス支援機構・奥田知志さんとの事前打ち合わせでは、本やら資料やら、どさっとおみやげをいただいた。そうだよな、これだけの蓄積に学びなおしてしか壇上にはたてない役目だ、と襟をただす思いでその資料の山をながめた。7月半ば以降、私は社会教育主事講習の運営に忙殺されているが、資料は常にかたわらにおき、ひまがあれば読み込む、というスタンスを当日まで続けた。
当日登壇者は、奥田さん・青木さんのほか、生活再生相談(家計相談)の実践で全国を牽引しているグリーンコープの行岡みち子さんや、厚労省の矢田地域福祉課長、福岡市の平田保護課長など、全員が全国一線級のデラックスな顔ぶれ。圧倒されるばかりだが、幸いほとんどの方と登壇前までにお人柄にふれる心安い関係を築かせていただいていた。そして話は刺激に満ちたものの連続で、たじろぐ思い以上に、お一人お一人の話やコメントの見事さにひきこまれるところのほうが大きかった。
不勉強な私にもわかったのは、国がいままさに可決にむけて尽力している新法「生活困窮者自立支援法案」が、単なるホームレス対策ではなく、高齢者むけ、障害者むけといった個別法でもない、非常に総合的な法であるということだ。「生活困窮者」とは、きっとこの社会の「わたしたち」のことだ。そしてここでの「生活困窮者対策」は、第1のネットとされる社会保険制度と、第3のネットとされる生活保護の「間」となる、求職者支援制度と生活困窮者対策を中心とする第2のネットとして構想されていた。…私も常々人間の自立は、即自的・対処療法的な対策ではなく、ジグザグしながら移行していく生身の人間をこそ支える「間」が必要だと思ってきたが、この新法はまさにその「移行」を支えるしくみをめざしていたのだ。(よほど根幹的な法なだけに、このしくみを動かす「人」と「経営的センス」がよほど必要だともおもったが…)
しかもその基本的な考え方と、具体的個別的政策である、住居喪失者へのシェルター、生活困窮者への家計相談(≒生活再生)、一般就労が困難な人への中間的就労などは、どれも抱樸館やそれと関連する北九州ホームレス支援機構・グリーンコープが、現場から先進的にたちあげてきたことだった。
制度のすきまにこぼれおちた問題の現実から「現場」が社会のしくみを動かそうとし、国の機関ががそれをうけて国会を動かそうとしている。その社会が熱く動くダイナミズムがこの壇上にはあった。きっとフロアにもその「熱」はとどいたに違いない。
そして何よりおもしろかったのは、よく教育や福祉にある、「それが大事なのはわかっている。でも財源がない」「国のパイの配分をかえねばならない」といった財源駆け引き論をこえた議論に展開していったことだ。
転機は福岡市の平田課長の「自治体も、国が予算を配分してくれなければ、厳しい」という正直な発言、そしてそれをうけた行岡さんのひとことだったと思う。「家計の破綻に至る前に生活できるように再生すれば、税金をおさめて国を支え、購買もして企業も支える。助け合いって、心の問題じゃなくて、経済効果までもちうるものですよね!」
そうなんだと思う。家庭が、地域が、企業が、行政が、きちんと再生してそのしくみをまわし、その付随物としてお金もまわるようになれば、おのずから社会も循環するのだろう。「地域」も「企業」も、この社会の人・機関のすべてが、この社会を再生するために誰一人欠かすことのできない大事な主体だ。そしてそれらすべての根幹にあるのは「人の再生」なのだろう。
それらを必然とするほどにゆがんだ社会・ゆがんだ時代だからこそ、人の再生にかかわる教育とりわけ社会教育が価値をみいだされず、お金もまわされない。「ホームレスの社会復帰って、そんなに復帰したい社会ですか?」とは奥田さんの言葉だ。そこからの逆転はきわめて厳しい道のりだけれど、でも、この「人の再生」を見つめ続ける領域を消してはいけない、いまの時代にみあったかたちに再生しなければ、とふるいたたされた。
自分の仕事の意味を再確認させてもらえたのは、このシンポが人間と社会の本質につきさす射程をもっていたからだろう。彼らの挑戦の「隣人」あるいは同志でありたい。この3周年シンポを経て、改めてそう思わされたのだった。
そんな抱樸館福岡の青木館長から、3周年記念シンポジウムの進行役をひきうけてほしいという依頼があった。もちろんありがたくひきうけさせていただいた。北九州ホームレス支援機構・奥田知志さんとの事前打ち合わせでは、本やら資料やら、どさっとおみやげをいただいた。そうだよな、これだけの蓄積に学びなおしてしか壇上にはたてない役目だ、と襟をただす思いでその資料の山をながめた。7月半ば以降、私は社会教育主事講習の運営に忙殺されているが、資料は常にかたわらにおき、ひまがあれば読み込む、というスタンスを当日まで続けた。
当日登壇者は、奥田さん・青木さんのほか、生活再生相談(家計相談)の実践で全国を牽引しているグリーンコープの行岡みち子さんや、厚労省の矢田地域福祉課長、福岡市の平田保護課長など、全員が全国一線級のデラックスな顔ぶれ。圧倒されるばかりだが、幸いほとんどの方と登壇前までにお人柄にふれる心安い関係を築かせていただいていた。そして話は刺激に満ちたものの連続で、たじろぐ思い以上に、お一人お一人の話やコメントの見事さにひきこまれるところのほうが大きかった。
不勉強な私にもわかったのは、国がいままさに可決にむけて尽力している新法「生活困窮者自立支援法案」が、単なるホームレス対策ではなく、高齢者むけ、障害者むけといった個別法でもない、非常に総合的な法であるということだ。「生活困窮者」とは、きっとこの社会の「わたしたち」のことだ。そしてここでの「生活困窮者対策」は、第1のネットとされる社会保険制度と、第3のネットとされる生活保護の「間」となる、求職者支援制度と生活困窮者対策を中心とする第2のネットとして構想されていた。…私も常々人間の自立は、即自的・対処療法的な対策ではなく、ジグザグしながら移行していく生身の人間をこそ支える「間」が必要だと思ってきたが、この新法はまさにその「移行」を支えるしくみをめざしていたのだ。(よほど根幹的な法なだけに、このしくみを動かす「人」と「経営的センス」がよほど必要だともおもったが…)
しかもその基本的な考え方と、具体的個別的政策である、住居喪失者へのシェルター、生活困窮者への家計相談(≒生活再生)、一般就労が困難な人への中間的就労などは、どれも抱樸館やそれと関連する北九州ホームレス支援機構・グリーンコープが、現場から先進的にたちあげてきたことだった。
制度のすきまにこぼれおちた問題の現実から「現場」が社会のしくみを動かそうとし、国の機関ががそれをうけて国会を動かそうとしている。その社会が熱く動くダイナミズムがこの壇上にはあった。きっとフロアにもその「熱」はとどいたに違いない。
そして何よりおもしろかったのは、よく教育や福祉にある、「それが大事なのはわかっている。でも財源がない」「国のパイの配分をかえねばならない」といった財源駆け引き論をこえた議論に展開していったことだ。
転機は福岡市の平田課長の「自治体も、国が予算を配分してくれなければ、厳しい」という正直な発言、そしてそれをうけた行岡さんのひとことだったと思う。「家計の破綻に至る前に生活できるように再生すれば、税金をおさめて国を支え、購買もして企業も支える。助け合いって、心の問題じゃなくて、経済効果までもちうるものですよね!」
そうなんだと思う。家庭が、地域が、企業が、行政が、きちんと再生してそのしくみをまわし、その付随物としてお金もまわるようになれば、おのずから社会も循環するのだろう。「地域」も「企業」も、この社会の人・機関のすべてが、この社会を再生するために誰一人欠かすことのできない大事な主体だ。そしてそれらすべての根幹にあるのは「人の再生」なのだろう。
それらを必然とするほどにゆがんだ社会・ゆがんだ時代だからこそ、人の再生にかかわる教育とりわけ社会教育が価値をみいだされず、お金もまわされない。「ホームレスの社会復帰って、そんなに復帰したい社会ですか?」とは奥田さんの言葉だ。そこからの逆転はきわめて厳しい道のりだけれど、でも、この「人の再生」を見つめ続ける領域を消してはいけない、いまの時代にみあったかたちに再生しなければ、とふるいたたされた。
自分の仕事の意味を再確認させてもらえたのは、このシンポが人間と社会の本質につきさす射程をもっていたからだろう。彼らの挑戦の「隣人」あるいは同志でありたい。この3周年シンポを経て、改めてそう思わされたのだった。