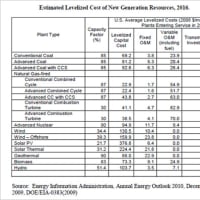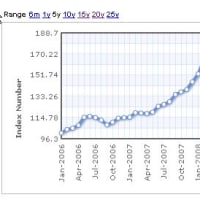「夢の超特急・新幹線の振動を防ぐ!
振動屋と呼ばれた男、松平精(まつだいら ただし)」
世界で初めて時速200km以上で走った夢の超特急『新幹線』。
このスピードでの運行を実現させたのは第2次世界大戦で人を死なせてしまったある男の、安全に対する執念でした。
昭和32年当時、鉄道の最高速度は特急こだまの時速110km 。
しかし、【東京ー大阪間をたった3時間、時速250km で移動する】という当時としては驚きの一大プロジェクトが、鉄道研究内で持ち上がりました。
そして、様々な分野の専門家が集められる中、鉄道の揺れに関するエキスパートも呼ばれました。
それが今回の主人公「振動屋」と呼ばれた松平精。
松平は戦時中にゼロ戦戦闘機の翼部分の振動研究で名を馳せ、戦後国鉄に迎えられたという異色の技術者。
一方、柴田技官からをはじめ、過去の経験に基づいて開発を進めていた鉄道専門の技術者たちは、耳慣れない振動屋の存在を快く思っていないよう・・・
そんな中でこの新幹線プロジェクトはスタートしたのです。
列車の速さを求める中、一番の問題だったのは、『蛇行動』。
『蛇行動』とは列車の車輪が”蛇がのたうつよう”が横方向に振動する現象を言います。
*もともと車輪とレールの間には、カーブを曲がるために作られたわずかな隙間があります。スピードを出しすぎるとその隙間のせいで、『蛇行動』が起きてしまい、限界を越えれば、脱線をする恐れがありました。
『蛇行動』を防ぐ手段を考えないことには、時速250km というとてつもないスピードを実現することはできない。
そこで松平は横振動を抑えるためのバネの開発に取り組みます。
しかし、寝食を忘れて日々研究を重ねる彼の姿は、松平と対立していた柴田技官でさえ、心配することでした。
松平がそこまで研究に力を入れていたのには、ある理由がありました。
戦時中、松平が責任者として開発していたゼロ戦戦闘機。
そのテスト飛行の時、翼が異常振動を起こして、戦闘機が墜落してしまったのでしたする。
不慮の事故だったにせよ、自分のせいでパイロットを亡くしてしまったことが、松平にとって大きなトラウマとなっていたのでした。
「もう誰も死なせたくない」
そんな思いで研究を重ねた末、松平がたどり着いたの『風船』。
風船=空気でバネをつくれば、あらゆる方向からの揺れを吸収できることを発見します。
新幹線の最終走行試験が迫る中、ついに『空気バネ』が完成したのです。
【昭和38年3月30日午前9時40分】・・・迎えた新幹線最終走行実験。
誰もが経験したことない約250キロを目指し、皆緊張の面持ちで列車に乗り込みます。
そこには松平とは対抗していた鉄道専門の技術者である柴田の姿もありました。
どんどんスピードを上げていく新幹線。
220キロ・・・240キロ・・・
『蛇行動』『脱線』という言葉が頭をよぎります。
そして、250キロ・・・とうとう目標速度を達成します。
喜ぶ傍ら、松平だけが視線を送るのは、水の入ったコップ。
「・・・揺れていない」
つまり、蛇行動も起きておらず、振動も問題ないということ。
ついに256キロ・・・世界最高速度達成。
コップの水は少しも揺れていませんでした。
そして、東京オリンピックを9日後に控えた【昭和39年10月1日午後6時】多くの人々の中の注目を浴びながら、新幹線は運行を開始することができ、鉄道の歴史の新たな1ページが幕を開けたのです。
☆★「零戦と新幹線を創った男」のあくなき執念と探究心に感動!☆★
創造のための「成功学」と「失敗学」
失敗学や成功学の観点から見ると、革新的な新製品を作り出すためには、
1,しっかりしたビジョンを持つこと
2,ビジョンを実現するためのコンセプトを獲得すること
3,コンセプトを新しいモデルに落とし込めること
4,そしてこのモデルをデザインして現実化すること
これらを順番に実行に移さなければならない。
私は、これを「創造のプロセス」と呼んでいる。このプロセスを実行するのが成功学である。プロセスの中では、何度も失敗を繰り返すことが常。失敗体験を解析して、コンセプトやモデルに修正を加えることは日常的な営みである。失敗学は成功学の基礎としてビルトインされているのだ。
私がIHIに在籍した当時、IHI技術研究所の所長は松平精さんである。松平さんは、軍の航空技術者から戦後は鉄道技術者に転身し、東海道新幹線のプロジェクトの「振動問題」を担当された方だ。たった7年間で革新的なプロジェクトを成功に導いたマネジメントは極めて質の高いものだった。
彼が軍の技術者だった頃、第2次世界大戦に向けて戦闘機の速力は急速に伸びて、時速500キロメートルを超えようとしていた。この時期、最も難しい技術課題の1つが戦闘機の機体に生じる振動だった。速く飛ぶには機体を軽くする必要がある。だが、軽量構造の機体は空気が作る渦の力によって振動しやすくなる。振動がひどくなると機体が空中分解してしまう悲惨な結果に至る可能性もある。当時の航空技術者は、たくさんの失敗を繰り返し、この極めて難しい技術課題を解決する力を獲得していった。
たくさんの失敗経験から、振動問題を解決する設計法を手中に収めるという「創造のプロセス」を実行したわけだ。戦後の新幹線開発プロジェクトに参画した松平さんは、この成功体験に裏打ちされた振動設計における創造のプロセスによって、安全な新幹線の開発に大きな貢献をした。
設計では、失敗を積み重ねる入門時代を経て、成功を学んでいく上達時代がある。だが、個人的な精進だけで、創造のプロセスの実行者となるには限界がある。人間には、時間にも、経験できる量にも限りがあるからだ。1人で創造のプロセスを生み出し、成功学を体現できる“カリスマ”や“天才”は少ない。
だからこそ、先達が編み出した創造のプロセスを科学的・論理的手法で解析し、なるべく多くの“凡人”が成功体験を共有し、利用できる仕組みが必要なのである。これが、創造のプロセスの実行者を増やすことにつながる。
振動屋と呼ばれた男、松平精(まつだいら ただし)」
世界で初めて時速200km以上で走った夢の超特急『新幹線』。
このスピードでの運行を実現させたのは第2次世界大戦で人を死なせてしまったある男の、安全に対する執念でした。
昭和32年当時、鉄道の最高速度は特急こだまの時速110km 。
しかし、【東京ー大阪間をたった3時間、時速250km で移動する】という当時としては驚きの一大プロジェクトが、鉄道研究内で持ち上がりました。
そして、様々な分野の専門家が集められる中、鉄道の揺れに関するエキスパートも呼ばれました。
それが今回の主人公「振動屋」と呼ばれた松平精。
松平は戦時中にゼロ戦戦闘機の翼部分の振動研究で名を馳せ、戦後国鉄に迎えられたという異色の技術者。
一方、柴田技官からをはじめ、過去の経験に基づいて開発を進めていた鉄道専門の技術者たちは、耳慣れない振動屋の存在を快く思っていないよう・・・
そんな中でこの新幹線プロジェクトはスタートしたのです。
列車の速さを求める中、一番の問題だったのは、『蛇行動』。
『蛇行動』とは列車の車輪が”蛇がのたうつよう”が横方向に振動する現象を言います。
*もともと車輪とレールの間には、カーブを曲がるために作られたわずかな隙間があります。スピードを出しすぎるとその隙間のせいで、『蛇行動』が起きてしまい、限界を越えれば、脱線をする恐れがありました。
『蛇行動』を防ぐ手段を考えないことには、時速250km というとてつもないスピードを実現することはできない。
そこで松平は横振動を抑えるためのバネの開発に取り組みます。
しかし、寝食を忘れて日々研究を重ねる彼の姿は、松平と対立していた柴田技官でさえ、心配することでした。
松平がそこまで研究に力を入れていたのには、ある理由がありました。
戦時中、松平が責任者として開発していたゼロ戦戦闘機。
そのテスト飛行の時、翼が異常振動を起こして、戦闘機が墜落してしまったのでしたする。
不慮の事故だったにせよ、自分のせいでパイロットを亡くしてしまったことが、松平にとって大きなトラウマとなっていたのでした。
「もう誰も死なせたくない」
そんな思いで研究を重ねた末、松平がたどり着いたの『風船』。
風船=空気でバネをつくれば、あらゆる方向からの揺れを吸収できることを発見します。
新幹線の最終走行試験が迫る中、ついに『空気バネ』が完成したのです。
【昭和38年3月30日午前9時40分】・・・迎えた新幹線最終走行実験。
誰もが経験したことない約250キロを目指し、皆緊張の面持ちで列車に乗り込みます。
そこには松平とは対抗していた鉄道専門の技術者である柴田の姿もありました。
どんどんスピードを上げていく新幹線。
220キロ・・・240キロ・・・
『蛇行動』『脱線』という言葉が頭をよぎります。
そして、250キロ・・・とうとう目標速度を達成します。
喜ぶ傍ら、松平だけが視線を送るのは、水の入ったコップ。
「・・・揺れていない」
つまり、蛇行動も起きておらず、振動も問題ないということ。
ついに256キロ・・・世界最高速度達成。
コップの水は少しも揺れていませんでした。
そして、東京オリンピックを9日後に控えた【昭和39年10月1日午後6時】多くの人々の中の注目を浴びながら、新幹線は運行を開始することができ、鉄道の歴史の新たな1ページが幕を開けたのです。
☆★「零戦と新幹線を創った男」のあくなき執念と探究心に感動!☆★
創造のための「成功学」と「失敗学」
失敗学や成功学の観点から見ると、革新的な新製品を作り出すためには、
1,しっかりしたビジョンを持つこと
2,ビジョンを実現するためのコンセプトを獲得すること
3,コンセプトを新しいモデルに落とし込めること
4,そしてこのモデルをデザインして現実化すること
これらを順番に実行に移さなければならない。
私は、これを「創造のプロセス」と呼んでいる。このプロセスを実行するのが成功学である。プロセスの中では、何度も失敗を繰り返すことが常。失敗体験を解析して、コンセプトやモデルに修正を加えることは日常的な営みである。失敗学は成功学の基礎としてビルトインされているのだ。
私がIHIに在籍した当時、IHI技術研究所の所長は松平精さんである。松平さんは、軍の航空技術者から戦後は鉄道技術者に転身し、東海道新幹線のプロジェクトの「振動問題」を担当された方だ。たった7年間で革新的なプロジェクトを成功に導いたマネジメントは極めて質の高いものだった。
彼が軍の技術者だった頃、第2次世界大戦に向けて戦闘機の速力は急速に伸びて、時速500キロメートルを超えようとしていた。この時期、最も難しい技術課題の1つが戦闘機の機体に生じる振動だった。速く飛ぶには機体を軽くする必要がある。だが、軽量構造の機体は空気が作る渦の力によって振動しやすくなる。振動がひどくなると機体が空中分解してしまう悲惨な結果に至る可能性もある。当時の航空技術者は、たくさんの失敗を繰り返し、この極めて難しい技術課題を解決する力を獲得していった。
たくさんの失敗経験から、振動問題を解決する設計法を手中に収めるという「創造のプロセス」を実行したわけだ。戦後の新幹線開発プロジェクトに参画した松平さんは、この成功体験に裏打ちされた振動設計における創造のプロセスによって、安全な新幹線の開発に大きな貢献をした。
設計では、失敗を積み重ねる入門時代を経て、成功を学んでいく上達時代がある。だが、個人的な精進だけで、創造のプロセスの実行者となるには限界がある。人間には、時間にも、経験できる量にも限りがあるからだ。1人で創造のプロセスを生み出し、成功学を体現できる“カリスマ”や“天才”は少ない。
だからこそ、先達が編み出した創造のプロセスを科学的・論理的手法で解析し、なるべく多くの“凡人”が成功体験を共有し、利用できる仕組みが必要なのである。これが、創造のプロセスの実行者を増やすことにつながる。