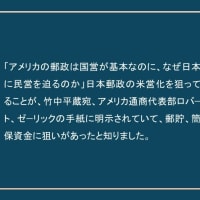千葉雅也「現代思想入門」のなかで、同一性の問題で、「派生物がオリジナルを超えることもある」・・・みたいな感じの文章があったと思うのですが良く見つけられません。このあたりの議論はどの辺の方面の議論なのでしょうか?
・・・
▶千葉雅也『現代思想入門』における「派生物がオリジナルを超える」議論の文脈
「派生物がオリジナルを超えることもある」という主張やその周辺の議論は、千葉雅也『現代思想入門』のなかで、同一性と差異、そして現代思想における「同一性」概念の再考に関わる部分に位置づけられます。
▶どのあたりの議論か
・千葉雅也は、デリダやドゥルーズ、フーコーといった現代フランス哲学を参照しつつ、「同一性/差異」の二項対立をめぐる議論を展開しています。
・特に、デリダの脱構築では「同一性」よりも「差異」に力点が置かれてきたが、千葉はそこからさらに一歩進め、「同一性」と「差異」のあいだをリズミカルに行き来する「仮固定的同一性」という概念を提唱しています。
・この「仮固定的同一性」は、固定的な本質やオリジナルに固執せず、むしろ派生や変化、ズレ(差異)を肯定的にとらえる態度を意味します。
▶「派生物がオリジナルを超える」発想の背景
・伝統的な西洋哲学では「同一性」=本質やオリジナルが価値を持ち、派生物や模倣は二次的・劣ったものとされてきました。
・しかし、ポスト構造主義以降の思想では、むしろ「差異」や「派生(ズレ)」が創造性や価値の源泉とみなされるようになります。
・千葉は、こうした文脈の中で「派生物がオリジナルを超える」現象――たとえば、模倣やリミックス、パロディがしばしば新たな価値や意味を生み出すこと――を肯定的にとらえています。
・これは、同一性が「元鞘に戻る」ような保守的なものではなく、むしろ差異や変化を受け入れつつ、仮に一時的に「同一性」をピン留めする(=仮固定)ことで、さらなる派生や変化を可能にするという発想です。
▶この議論の「方面」
・哲学的には、ポスト構造主義・脱構築(デリダ)や存在論的多様性(ドゥルーズ)、そして現代の同一性論(ポスト・ポスト構造主義)に位置づけられます。
・また、「同一性」と「差異」の関係、オリジナルと派生の価値転換は、現代アート論やカルチュラル・スタディーズ、ジェンダー論など多様な分野にも波及しています。
・千葉自身も、第6章や第7章で「現代思想をつくる四つの法則」や「ポスト・ポスト構造主義」として、こうした同一性の再考や複数性の肯定を論じています。
まとめると、「派生物がオリジナルを超える」という発想は、現代思想における「同一性/差異」論争、特にポスト構造主義以降の同一性の再考や脱構築の議論の流れに位置づけられます。千葉雅也は、同一性と差異の間をリズミカルに行き来する「仮固定的同一性」という概念を通じて、オリジナルと派生の価値転換や創造性の可能性を示しています。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆コピペ ここまで◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
ぴとてつのとっ散らかしメモ:
・青は藍より出でて藍より青し▶弟子が師よりも優れている、あるいは、教えを受けた人が教えた人よりも成長していることのたとえです。
(藍染の過程で、藍草から抽出された青色染料が、元の藍草よりも濃い青色になることから由来します。)
出典は『荀子』という、約二千三百年前の中国の書物のなかの「勧学篇」に、「青は藍より出でて藍より青し」の元となった文章が書かれています。
・安本美典(日本史研究家・日本語研究者)の日本語成立論▶西欧の系統樹派生ではなく、支流が流入しやがて大河となる日本語の成立過程
単一祖語からの分岐(例:インド・ヨーロッパ語族)あるいは生物進化論の影響の系統樹的進化(分化/派生)のモデルではなく
複数言語が順次流入し大河となる「流入混合論」のモデル:
日本語の基層に「古極東語」を想定し、インドネシア系言語、カンボジア系言語、ビルマ系言語、中国語など複数系統の言語が順次流入していったとする多重層説(混合/統合)のモデル(日本語成立論)
・「伝統とは火を守ることであり、灰を崇拝することではない」▶この言葉は、グスタフ・マーラーが語った言葉です。これは、過去の伝統を単に過去のものとしてありがたがるのではなく、それを活かし、未来へと繋げていくべきだということを意味します。すなわち、伝統をただ守るだけでなく、それを現代に活かし、発展させていくことが大切だと主張しているのです。
・「船は港にいる時、最も安全であるが、それは船が作られた目的ではない」▶パウロ・コエーリョ『星の巡礼』
・ジェーン・オースティン作品の現代版リメイク▶『ブリジット・ジョーンズの日記』(『高慢と偏見』のパロディ)が独自のカルト的人気を獲得。
・音楽におけるサンプリング文化▶ヒップホップのサンプリング:James BrownのドラムブレイクがPublic EnemyやKanye Westによって政治的主張の手段へ転換
・ボカロ文化▶初音ミクの音源をユーザーがリミックスし、オリジナル楽曲を超える二次創作文化が形成
・Meme(ミーム)文化▶海外の「Distracted Boyfriend」画像が日本で「浮気スナックパパ」としてローカライズされ新たな文脈を獲得
・TikTokの短編動画▶既存の楽曲やダンスをユーザーが再構成し、世界的流行を生む(例:FKA Twigsの動画編集技術が一般ユーザーに拡散)
・有田焼の超絶技巧▶江戸時代の磁器技術が現代アーティストにより「光透過磁器」という新ジャンルに進化
・組子細工×LED照明▶伝統的木工技術が現代インテリアデザインと融合し機能美を刷新
・進化的システム論▶生物進化の「水平伝播」(他種交配)が文化進化でも機能(例:和製英語のグローバル逆輸入)
・九龍ジェネリックロマンス▶「本物と偽物」の境界を問い直す葛藤が物語の核心的テーマとして多層的に描かれます。特に「偽物であること」を肯定的に再定義する描写が顕著です。(鯨井令子の存在意義をめぐる葛藤)
・葬送のフリーレンでヒンメルが勇者の剣を引き抜けなかった▶勇者の剣を持たずに世界を救ってみせたヒンメルを、フリーレンが「本物の勇者だよ」とたたえる感動のシーン:
フリーレンが「本物」と称賛する背景には、ヒンメルが剣の権威に依存せず、仲間との絆と自らの信念で魔王討伐を成し遂げた人間像への敬意が込められています。SNS上でも「偽物が本物を凌駕する展開」との評価が多く、伝統的な英雄像を刷新する物語構成が高く評価されました。