他者の言葉がわかるということには、日常での人付き合いということも含まれる。互いに違った家族や環境で育った者同士が理解し合うというのも、誰もが実感するように難しいものがある。ここでは、文学作品や思想に表れた他者の言葉の理解ということに限定して考えてみたい。
吉本さんの『遠い自註(連作詩篇)』(猫々堂)の最後の詩に「『さよなら』の椅子」(連作詩篇「野生時代」1984年3月号掲載)という詩があり、その中に次のような詩句がある。
さっきから黙ったまま
「さよなら」は 影絵みたいに
ひっそりと 主客の席にひかえてる
詩は 書くことがいっぱいあるから
書くんじゃない。
書くこと 感じること
なんにもないからこそ書くんだ
(「『さよなら』の椅子」『遠い自註(連作詩篇)』、『吉本隆明資料集57』猫々堂)
この部分の一連は、後にまとめられた『記号の森の伝説歌』の最終章「演歌」の末尾近くでは次のようになっている。行頭をそろえて示すと、
さっきから黙ったまま
「さよなら」は 影絵みたいに
ひっそりと 主賓の席にひかえてる
詩は 書くことがいっぱいあるから
書くんじゃない。
書くこと 感じること
なんにもないからこそ書くんさ
2つを比較すると、わたしがその意味を調べてみた「主客」が「主賓」となり、「書くんだ」が「演歌」という題を意識してか「書くんさ」となっている。これは、詩作品の中の詩というものを捉えた言葉であるが、吉本さんの詩に対する捉え方と見なしていいのではないだろうか。この言葉もまたよくわからないままにわたしの中に保留されてきた吉本さんの言葉である。この言葉に初めて出会ったとき、わたしにはよく分からないなあという感じが残った。もちろん、以下に述べるようなことは頭の隅に置いた上ではあるが。
まず、ある人が詩を書くことでいえば、次のような過程(段階)が考えられる。
1.読み味わう詩人の詩の影響もあり、ある言葉の蓄積とそこからの水圧のようなものの促しにより自然発生的に詩の言葉のようなものを書き付け始める。
2.詩を書くということを持続し、いろんなことを思い付いて、進んで(楽しんで)詩を書く。
3.何をどう書いたら良いかなど混迷して、詩を書くのが苦しくなったりしてくるが、それでも詩を書き続ける。
4.今までも自分のどこかに潜在していたとしても、本格的に問われることがなかったが、なぜ詩を書くのかという内省的な、詩への入口を再び反芻するような、還りがけの視線を内包しつつ、詩を書く。
吉本さんの上の詩句は、この4.の段階から放たれた言葉だと思われる。吉本さんは若い頃毎日のように持続的に詩を書いていた時期がある。「日時計篇」として膨大な詩篇が残されている。批評や思想に持続的な力を注いで、途中詩を書くことが間遠になったりする時期もあるが、この時期は再び持続的な詩の活動期に当たっている。雑誌「 野性時代」1975年10月号の詩「幻と鳥」から1984年3月号の詩「『さよなら』の椅子」にいたるまで、若い頃のように毎日のように詩を書くということではないとしても、持続的に連載された。それがこの『遠い自註(連作詩篇)』の詩であり、それらの連作詩篇をもとに作り上げられたのが、『記号の森の伝説歌』(1986年12月)である。吉本さんが批評や思想の表現に力を入れて詩を書いていない時期は、たぶん〈詩〉はそれらの批評や思想の言葉の奥深くに潜在しているか、あるいはそれらの表現された言葉と言葉のすき間に微かに散布されたように存在していたのではないかと思う。
この4つの段階のそれぞれに詩を書く者がいたとして、それは同一人物でも別人でもかまわない。1.の段階に居る者が、4.の段階に居る者からいくらていねいに説明してもらっても、実感として4.の段階のことは分からないと思う。このことは、段階の違いがある相互の間では言えることだと思う。
わたしは中断していた詩を再開しいくらか書き込んできたが、現在のわたしは、先の詩に関する吉本さんの詩句がなんとなくわかるようになってきた感じを持っている。この問題を比喩を用いてさらに以下に説明してみる。
わたしたちの日常的な生活実感に添うような比喩を使ってみる。
A:はじめての山登りの登り始め
B:はじめての山登りの中ほど
C:はじめての山登りの頂上到着
D:はじめての山登りの帰りがけ
B':何回もこの山に登った者の、山登りの中ほど
※ 個々人の固有性を退けた上での一般化として考えるから、A、B、C、D、B'は、すべて同一人物と見なしても、それぞれが別人と見なしても、いずれでもかまわない。
個々人の固有性を退けた上で一般化した場合、ほとんど山登りの経験のない者が、ある山にはじめて登ったとする。山に登る過程のA、B、C、D、それぞれの位置での人に湧き上がってくる感受や考えは違うはずである。しかしそれは、AからDの山の頂上に登る道程がひとつのまとまったものとして、ある波打つリズムのような曲線を描きながらたどる一連のものと見なせると思う。したがって、この場合の登る道程におけるA、B、C、D、という位置の違いによる感受や考えの違いは、心身の経験の量の違いではあるが、同一の経験の地平上での違いと見なせる。
次に、はじめてのこの山登りのBと何度もこの山に登っているB'の間の感受や考えの違いも明確にあるはずである。これもまた、BとB'の間には心身の経験の量の違いが明確にある。この場合は、B'はBと比べて一連の道程を何度も繰り返してきているから、B'には何層もの経験が積み重なっているということであり、心身の経験の量の違いが質的な違いとなっているはずである。したがって、BとB'は同一の風景をいっしょに眺めていたとしても、感受や考えの言葉の地平が位相の違ったものとしてBとB'には現象しているはずである。そのことを表すために、上の図ではB'は、同じ山であるが、右にずらした位置の表示をしている。このような相違は、おそらくそんなに事細かに説明しなくても日常に経験するものとして実感的ではないかと思う。
日常の経験でも、職人的な技でも、芸術の世界でも、同一人物であれ別人であれ、相互に違った段階にあるときは、そこから湧き上がって来る問題を風通しの良いものとして相互にわかり合うことは難しい。つまり、どんなに言葉を尽くしても互いがわかり合うことは難しい。ただ、未だ先の段階としてそれを経験していない者は、黙々と日々経験して先の段階に到達して、先の段階を経験している者のような実感を手にするほか互いがわかり合うことはできないように見える。この場合、両者は時間的に遅れて出会うことになる。親と子の関係もそれと同様なものとしてある。
因みに、吉本さんの『言語にとって美とはなにか』の「序」や『心的現象論序説』の「はしがき」や「あとがき」がある。これらは対象との取り組みをなんどもなんども繰り返されたB'の位置からの言葉であり、その道の初心者がその言葉に対して何が語られているのかわからないとか不審に思ったり違うんじゃないかなどと思うのは、上で述べたBとB'の関係からどうしようもないものである。もし、Bの位置にある者が言葉というものや人間の心や精神現象について根本から理解しようと願うなら、黙々と登攀(とうはん)を続けるほかないのである。そうして、いつか少しずつ靄(もや)が晴れ上がっていくのを目にすることになる。ただし、この場合、吉本さんの成した優れて深い考察が手助けやおくりもののように前にあるからずいぶんと軽減された登攀ということになる。
以上、日常生活世界では当たり前の実感について少し大袈裟に言葉を費やしてしまったが、人は日常生活世界の具体性の世界を抜け出して、文学や思想というある抽象性の世界に入り込むと日常世界の身体性や具体的なものにまつわる実感が消失してしまうことがある。そういうわけで、わたしの場合のわからなさということの自己確認の意味も込めて、言わずもがなのことを書き記してみた。
また、以上述べてきたことを覆したり大きく揺さぶるように見えるかもしれないが、最後にもうひとつ付け加えておきたい。人が対象に対し対象の有り様を捉える眼差しには、上に述べたように当然経験の差ということがある。しかし、日常わたしたちが経験するように、会社の管理職や学校の校長などが深い洞察力と見識を持っているとは限らない、ということも確かなことである。あるいはまた、研究する対象世界に長く触れ続けている学者でもエコノミストでも、それって根本から間違っていないか、という印象を持つ場合が多い。何が問題なのだろうか。
まず、上に述べてきたことは、確かなこととして言えることだと思う。しかし、その場合は、厳密にいえば、人が対象とする世界に対して自己の言葉を局所的に位置付けたり、イデオロギーを導入したりなどをしていないことを条件としている。つまり、人が対象とする世界に対して自己の言葉をできるだけ開ききるということを前提としている。現実には、そういう自己を世界に対して開いていない言葉が多いから、問題は複雑系になる。つまり、初心者でも年季の入った研究者に対する批判ということが「自己が世界に対して開かれた言葉」という人間的な地平において可能であるように思う。
付記 (上の最後の部分に関連して)
例えば、わたしは10年位前に、「専門的な修練を積んだまなざしからの言葉である。けれど、記憶を含めてあらゆる人間的な事象に素人も専門家も共通でありうるという地平も確かに存在するように思われる。そうした地平から言葉を繰り出してみるならば」として、精神科医の中井久夫の『徴候・記憶・外傷』の記憶というものの捉え方に少し異を唱えている。
記憶の初源から (過去の文章から、2008年)
http://blog.goo.ne.jp/okdream01/e/c5f9ec165f9fd10efbeeaad9ed6f8fa6
最新の画像[もっと見る]
-
 最近のツイートや覚書など2024年8月
1週間前
最近のツイートや覚書など2024年8月
1週間前
-
 最近のツイートや覚書など2024年8月
1週間前
最近のツイートや覚書など2024年8月
1週間前
-
 画像・詩シリーズ #15 田んぼの現在から
3週間前
画像・詩シリーズ #15 田んぼの現在から
3週間前
-
 水詩(みずし) #6
3週間前
水詩(みずし) #6
3週間前
-
 水詩(みずし) #5
2ヶ月前
水詩(みずし) #5
2ヶ月前
-
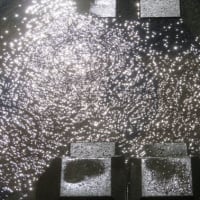 画像・詩シリーズ #14 はじまりの映像から
2ヶ月前
画像・詩シリーズ #14 はじまりの映像から
2ヶ月前
-
 農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26) 追記①、追記②
2ヶ月前
農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26) 追記①、追記②
2ヶ月前
-
 農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26) 追記①、追記②
2ヶ月前
農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26) 追記①、追記②
2ヶ月前
-
 農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26) 追記①、追記②
2ヶ月前
農事メモ ⑪ 今年のスイカ (2024.6.26) 追記①、追記②
2ヶ月前
-
 最近のツイートや覚書など2024年6月
3ヶ月前
最近のツイートや覚書など2024年6月
3ヶ月前










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます