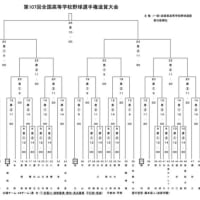滋賀県米原市のJR米原駅東口を出て右に曲がるとすぐ、舟のモニュメントがある。案内板には「米原湊跡」の文字。

駅から琵琶湖までは結構な距離があるし、新幹線が停車するなど米原市は「鉄道のまち」の印象が強い。なのに湊があったとは、どういうことなんだろう。水運から鉄道交通の要衝へと変貌したまちの経緯をたどった。

◇
「米原湊は、ここ米原駅付近にありました」から始まる案内板には、1603年(慶長8年)、北村源十郎が琵琶湖と入江内湖を結び、堀を開削して湊を開いた、とある。
美濃方面と大津湊の中継や、大阪と北陸を結ぶ湖上交通の中継の湊で、宿場として栄えたとも。駅と琵琶湖の間には、現在は田畑や住宅が広がっているが、かつては内湖があったのだ。

次に米原市文化財担当の高橋順之さんを頼った。高橋さんによると米原湊は彦根藩の命を受けた北村源十郎によりつくられ、彦根城下の松原湊、北国街道につながる長浜湊とともに「彦根三湊」と呼ばれたそうだ。
現存する最古の米原湊絵図(滋賀大経済学部付属史料館所蔵)には、六カ所の船着き場が見て取れる。
2013年に米原区が発刊した郷土誌「交通の要 まいはら」を見せてもらった。この中には米原に湊が開かれた理由について、「彦根藩の思惑が強かったと考えられる」とある。
米原湊の開削以前には琵琶湖に面する朝妻湊(米原市朝妻筑摩)が要港であったが、朝妻は彦根藩の勢力下になかったため「東国への重要なルートを他藩に抑えられているのを不都合と考え、東国への効率的な独自のルートを求めたのであろう」という。
1889年(明治22年)の鉄道の開通により、米原湊は役目を終えた。1944年(昭和19年)からは入江内湖の干拓事業が始まり、水運の拠点としての面影は消えていった。
◇
ではなぜ、入江内湖は干拓されたのか。米原市入江の市琵琶湖干拓資料館を訪問した。
展示資料によると入江内湖は広さ約300ヘクタール、周囲約8kmに及び、内湖としては当時2番目の広さ。琵琶湖との間に、長さ約2kmメートルの砂や小石の堆積による陸地で隔てられていた。干拓以前の地図を見ると、米原湊と琵琶湖の間に、広大な内湖があったのがよく分かる。
戦時中の食料難により、国営事業で干拓が始まった。延べ100万人ものが従事し、1949年(昭和24年)に完成した。こうして内湖は、256ヘクタールの水田に生まれ変わった。
◇
湊の開港と共に発展を遂げてきた歴史を、地元の人はどう感じているのだろう。「交通の要 まいはら」を編集した足立省一さんに話を聞きに行くと「寒村から交通の要衝地へ。源十郎なしに、米原の発展は語れない」と感慨深げ。 郷土誌を発刊した理由については「愛着がないとまちづくりはうまくいかないし、ええところを知らんと愛着を持てんやろ。若い人にも発展の歴史を知ってほしくて」と語ってくれた。
湊の開港を機に交通網が整備され、現在の鉄道の町へと発展を遂げた米原。駅前にひっそりとあるモニュメントは、駅を行き交う人々に、まちづくりの重要な分岐点を伝えていた。
<中日新聞・わたシガ名探偵!より>