日毎に緑濃くなるカラマツの芽吹き。
春が一度にくる信州。
花も一斉なら、山菜も一斉にスタート。
裏庭のコゴミも、畑のタラの芽も、ウドに椎茸に。
うれしいわねえ。
冷凍庫の「昨年」の蕗の煮物を大急ぎで食します。
日曜日の午後は、佐久市臼田文化センターの郷土史講座に夫と参加。
「龍岡城竣工図を見ながら巡る桜の散歩」
龍岡城は五稜郭なのです。
昨年、この竣工図の座学がありました。その続きで今回は五稜郭を外堀にそって歩きました。
時は桜が満開、お堀には散った花びらが浮かび・・・・・情緒いっぱい。

地元だけど合併前は隣の街で、遠足先にもならなかったから、歩いて一周なんていうのは初めての事。
ここ何年か歴史小説を読んでいた私には、とても興味深い。
頭の中でいろんなことが、繋がってくるのね。
集合場所が蕃松院というお寺、戦国時代のこの地域の歴史そのものね。
紋を見て納得だなあ~。我が家の紋と同じ、ルーツはここにあったか。
龍岡城が建設されたのは、幕末。
だから未完成なのね。
五稜郭のお堀も水をたたえているのは半分。
掘る工事は出来たけど、盛り土しなければならないところは、隣を流れる河川で代用することにしたのかも。
お堀の石垣も見えるとこは、切込ハギ平積石垣や亀甲積石垣で内側は野面積石垣なのが面白い。
この石垣は伊那の高遠の職人60人が3年かけて築いたものだという。
伊那の高遠の石工の話は、この地域の城廻りをすると度々耳にする。
たぶんその職人の手元をした方たちや、この地に残った石工が、その後この地で石屋さんになっていったのではないかと。
多いんです、この地域石屋さんが。
目の前の三分山の石を使ったのだそうですが、その石どうやって運搬したのでしょうね。
雪を利用したのだそうです・・・・・なるほど。
市はここを公園にしたいらしい。
しかし問題は、今は閉校になっているけれど、小学校の校舎があるのです。
これを片付けるには・・・・・お金かかるだろうな。
できた当時の建物で残っているのは「台所」だけです。
これは学校を建てる時に、引っ張って移動させてるのですね。
その昔は、音楽室や裁縫室として使っていたみたいです。

内部に入ってみてびっくり。
桁は、5間(10m)の長さで太さが元で2尺角(60cm)位。末は少し細くなっていましたが。
製材機もない時代、どうやって・・・・・・まあ人力ですわね。
まず、こんな太い丸太がどこにあったの。神社やお寺さんでしょうね。
財力と権力がなければできない芸当ですね。
もう1本その上にも桁として使われているのも10mで30cm角かな。
上がり框も10mの1枚板です。
もう感動・・・・・残す価値ありって思いましたね。
公園にするときは当初の場所へ移動させるようです。
地元の歴史は面白いです。
160年前のことを想像しながら。
たった160年ですよ・・・・・今の世を思います。
お読みいただきありがとうございました。
ブログランキングに参加しています。お帰りになる前に下の3つのうちの一つにポチッをしていただけると何よりもうれしいです、お願いします。
中島木材のホームページは こちら















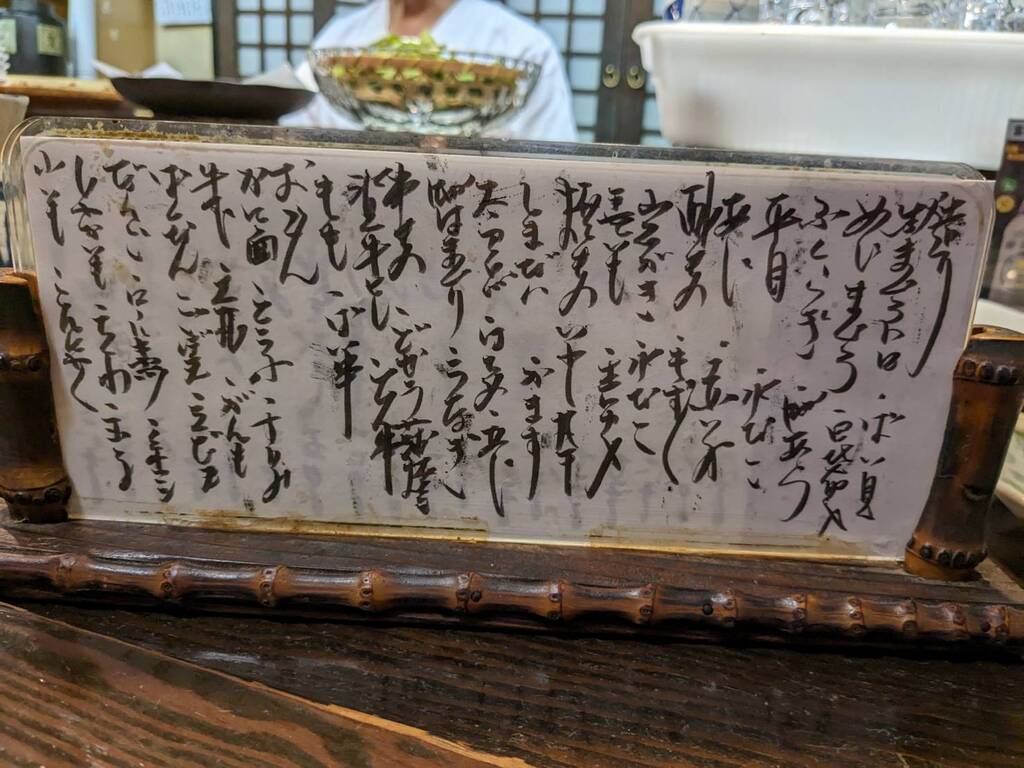













 諏訪大社
諏訪大社







