今日は六世中村歌右衛門丈のご命日なのだ。
それはピンクの衝撃:林家ぺー師匠ではなく(それはお誕生日)……森銑三先生に教えていただいたわけではなく、大成駒自身が思い起こせよ…と伝えてくださったことに違いなかった。
壇ノ浦の合戦があったのが、元暦二年三月二十四日…
(西暦でいえば1185年:近年、旧暦を新暦に変換して実際は…云々と解釈して別の暦日で記念日とする方がいらっしゃるが、月の暦において何月、ということはとても重要で…たとえば雛の日といえば三月三日に決まってるし、討入りは極月十四日でなくてはならぬので、逆からの翻訳で正しいというのは実は正しくないのだと感じます。
であるから、毎年微妙にズレた旧暦の暦日でアニバーサリーをそこはかとなく愉しむ、ということを実行し、真に季節感が知りたかった場合に、ユリウス暦やらグレゴリオ暦やらに換算して調べ、年どしの天候気象事情を反映させ個人的に想いを馳せればよいのではないかと、常々思っていたのでした)
…なので、三月の潮のよいときに、平家の芝居の話をしたいと思っていた。
旧暦と新暦の季節感がずれつつも微妙にマッチしている年に書きたいと思いつつ、この9年ほど、常に機を逸していたので、卅が微妙に並ぶ、今日この時を逃したら、もう書けないかもしれない、と、昨朝、とある歌舞伎の稿を起こしてみたのであるが……
東日本の震災の前だから、もう10年ほど以前になるだろうか…この時季になると不思議な日本の風物、花見…という行事のスケジューリングに心悩ませていた時のことであるのだが……実をいえば私は、細雪の三女・雪子と同じく、最終的には意に染まないことはできない性分だったので、狭い世間をますます狭くして暮らしてきたのだけれども、アラフィフを過ぎたころ、それでも年賀状のやり取りだけは続けてきて、何かというと声をかけてくれた(けれどもこちらから沙汰することは皆無であった自分の薄情さ加減を今となっては赤面するしかないのだけれども)高校時代からの友人Nさんが提唱する、三十年ぶりの再会を促す、上野の花見に誘われた。
それがきっかけとなって、震災の翌年はお休みとなったのだが、初手は三人だった年に一度の同窓会ともいえる美術鑑賞プラス花見の宴は、回を重ねるごとに1970年代末に女子高生だった漫画研究会の同級生メンバーが何人かずつ増えてゆき、皆がお互いの存在を確認することにより、自分自身が生きてこの世にあることを実感する、そしてまた、今は失われてしまったが、かつて存在したものが確かに存在していたのだと確信するあかし、安堵の機会となっていた。
しかしその花見も、4回を数えたのが、彼女と桜を観た最後になってしまった。
乃木坂の新美術館(何の展覧会だったか、もう失念してしまった)から、青山墓地へ桜狩した年だった。
畏れ多くて参ずることもなかった河村家の墓前へ差し掛かって、ここは大成駒のお墓よ、と耳打ちすると、カメラを常備している彼女が、いつの間にか素晴らしく整然として美しい、ひともとの桜を背景にした中村歌右衛門丈の墓影を、後日私に送ってくれたのだった。
その年の暮れに、検査入院をしている、という彼女からのメールが私への最後の便りとなった。
彼女の置き土産の花見の会は毎年続いていて、彼女の眼に映っていたあの時の青山墓地の写真を久しぶりに見たくなって…その写真は歌右衛門丈の追悼本に挟んであるので…それと同時に、本稿に取り上げたかった芝居のエピソードを確認するために、昨晩久しぶりに取り出してみて、大成駒のご命日が平成13年の3月31日だったことを想い出したのだった。
かつて存在した彼女の網膜がとらえた風景写真は、整然としていて端正で、完璧であった大成駒を偲ぶのにこれ以上のものはないように思われた。
空が青くて、桜が満開で、快晴で…文句のつけようのない一葉だった。
ご命日にこの本を手に取ったのが運命であるならば、再拝して読み返すのが勤めというものでありましょう。
…読経ならぬ再読をして、20年前に読んだ時とは違う印象がこの胸に宿った。
六世中村歌右衛門丈は、古典の本行を、とにかくとにかく、大切にして精進して勤めてほしい、と継ぐ者たちに訴えていたのだった。
伝統をほぼ完璧に完成させていた大先輩たちの作品を、新世代のものがいきなり、ご見物衆の気に入るように演じることなどできない。
生まれた時から何十年も丹精してきた仕手が、ようやっと描き演じだせる世界を、二十数年しか生きていない者に同じようにできるわけがない。
新しく継いだものが先輩たちと同じようにできるには、先輩たちが費やしたのと同じ時間と努力、労力が要る。
そして主役の意志と肉体だけでなく、舞台の世界全体を構築する脇役、衣装・結髪、小道具・大道具、音曲、照明、裏方諸々……etc.
江戸…いえ、物語の構築という点でいえば日本に文化が発祥したその時からの人智の積み重ねが、当初は中国文化をまねて更に自国のものとしてくふうし、平安、鎌倉、室町各時代の美意識を加味・踏襲し、集大成されて花開いたのが江戸時代。それから明治、大正、昭和と、鍛錬・丹精され、くふうされ続けてきたのが、歌舞伎です。
もとい、歌舞伎だけでなく、平成の世に伝わる日本文化なのです。
大成駒のその願いが叶ってほしい、あの時代、わたくしたちを魅了した舞台世界が、またいつの日か目前に展開してほしい…けれども、現在の日本国の経済観念からの発想しかない短絡的・短期間換算での文化測定・価値観の側面から慮るに、どうなることでしょうか……
歌舞伎界に例えず、わかりやすいように、落語のことについて申しましょうか。
いま、昭和に大成された古典落語を若い人たちが口演するのは、かわいそうだなと思う。
第一、日常に話している言葉が、もう昭和のころのそれと違うのだ。
語彙ばかりではない。イントネーション、言い回し、時代の雰囲気。日本語に対する感性。言葉に宿る魂。コトダマ自体がすでに20世紀のそれではない。
それを、かつての美意識、審美眼、判断基準にかけること自体が、酷、こちらの見当違い、狭量というものなのだ、と感じるようになってきた。いや、そう思わないと寛容できずにストレスが溜まって、娯楽と思えなくなってきた。
昭和の50年代後半、60年に入った頃だったでしょうか…映画・テレビドラマの時代劇に出てくる役者が、なんとなく、昭和のころよくあった特別番組・新春スターかくし芸大会、のために扮装している感じがして、私は新作の映像作品である時代劇に対する興味を失った。
時代の趨勢として、俳優の日常に、着物での生活がない、素養としての日本舞踊が失われた、ということがあったのだろう、とってつけたような仕草、所作・振る舞いは、いかに俳優たちが器用に演じても、不自然な作り物であるという、圧倒的な違和感を与えてしまうものだ。
十六年は一昔…それが二巡り、三囲ぐらいいたしますと、万事心得ていた裏方さんも代替わりしていって、教育係がいない現場というものは、いまや、知恵とくふう・美意識と価値観が集積された時代劇ではなく、フタッフ自身が未知なる世界である過去の時代に取材したSFになっているのである。
初めて寄席の空気に触れてしばらく入れ込むという状況にある受け手は、何年かごとに入れ替わるであろうし、そういった意味で客の感性も変わっていくから、寄席を構成しているすべての事柄…世界がすでに違うのだ。
新しい感性で、新しい若いお客さんにウケる、ということが今の伝統芸能界では使命のようになっているけれども、初めて伝統芸能に触れる方々は、自分の中にその芸能に関する他の演者の記憶がない。
つまり比較する対象、比べてみてどう、という判断基準を持たないから、彼らに支持されるに及び、人気者の仕手が裏付け・根拠のない自信を手にしてしまい、努力して鍛錬する…というあらゆる技術系のスペック涵養に不可欠な要素をないがしろにしてしまう結果となる。
(それは、半年ぶりにふらっと寄席に立ち寄り、こんな下手な:上っ面、口跡は整っているのに笑いどころで全然笑えない、面白さのかけらもない壺算、聞いたことがない…!しかも真打なのに…!!と、怒りまくった自分自身へ、かつまた昨夏、母を連れてふらっと入った新宿の老舗寄席で重鎮の落語家に、九月に目黒のサンマ聴かされた…ぁぁもう腹立たしい、そんな当たり前の噺を聞くために寄席まで来たわけじゃない…!!と怒り狂った自分自身への窘めの記述になるのかもしれないのだけれども)
志ん朝師匠のカッコよかったことと言ったら…!!(愛宕山の爽快感ときたら譬えようもなく、私は大好きだったのですが)もう早世した生き方自体が、噺家として完璧です。
リアルタイムで私は談志の追っかけをしていたが(もちろん定席の普通の寄席にも通っていて、お気に入りは先代小南師匠でしたが)、私の中の落語世界が喪失した21世紀以降に、主に繰り返し聞いていた落語のCDは、三世金馬と志ん朝であった。
年に二回ほど1か月弱の期間を持って興行される、人形浄瑠璃文楽の鑑賞教室@東京三宅坂国立劇場公演。
数年前まで欠かさず伺っていたのだけれども、観劇の前に、あらすじと人間関係のレクチャーが1時間ほど行われる。
この時点で、もはや、ムリ、な感じになっていないかなぁ、気の毒に…と学校単位で鑑賞教室に参加する若人たちの興味の行く先を案じていた。
日常、テレビをつけたら時代劇をやっている、昭和の子供たちには義経やら弁慶やら、富士山の麓の巻狩り、仇討がどうしたこうした、細かいことは分からなくとも、大筋が血肉として集積された下地があるから、前置きはいらないのだ。
翻ってワンピースやナルトを読んだことがない昭和の子供たちには、同じ漫画といえどもちんぷんかんぷんで、観たくないなぁ…と思っちゃうのと同じことである。
世間を知らぬ若者は、自分が初めて接する偉大なる文化の、その時点で完璧で手の届かないものを応援するのに気がひける。
だから自分たちのヒーローが欲しい。
いま寄席に行って、自分の記憶の中の昭和の名人たちの高座以上の噺を、現代の古典落語に求めるのは無理というものなのだ。
日常に、あの時代の空気、言葉遣いがあってこその、その下地があってこその鍛錬で、あの落語世界が創れるのである。
それはないものねだりであって、レストア版古典を無理に演じてもらうよりも…話し手自身が自分の言葉でもって語り構築した新作に…換骨奪胎・パロディ化した元ネタが共通認識として分かっているので尚更、カタストロフィーやらエクスタシーを感じるのは当然のことなのであった。
それと同時に、やはりもう30年以前のことになるが、とあるホール落語会で新作落語を聴いた時のこと。
その噺の筋・展開の面白さに心を奪われた私は気がつかなかったのだが、一緒にいた友人が、
「こんなガサツな落語、聞いたことがない」
と、言ったのである。
洋楽理論に則った現代邦楽はきちんと演奏できるのに、古典作品をやると形無し…という演奏をよく耳にするのだが、楽譜が基準でそれを見て弾ける程度でよしとする理解力では、本人たちは気がつかないのかもしれないが、厚みを持つ古典作品は弾ききれないのである。
新作落語はまず、アイデア勝負なので、その時の友人の、昭和の洗練された古典落語を聞いていた耳には荒く映ったのであろう。
古典は、現代に残っているということ自体が既に錬成されているわけで、そこそこの技術しかない仕手であってもそれなりに、ある程度鑑賞に堪えるようなつくりになっている、有難い作品なのである。
それは作品自体の魅力なのであって、古典を面白く聞かせられないのは、錬成しきれていない落語家の怠慢なのである。
このところの落語ブームとか言われている現象で、持ち上げられている本人が気づいていないのが一番困ったもので、うっかり入ってしまった寄席で、鼻持ちならない、ガサツで聞くに堪えない古典落語を、本人の勢いだけで、力業のごとく聞かされる目には遇いたくないものである。
そしてまた、雰囲気だけの、ルーティンワークのような上っ面だけの噺を聴くのもつらい。
熱量換算で、おあしに足る、いやそれ以上にスゴイ!と感じることのできる落語が、古典と新作の別なく、私は好きなんである。
それはピンクの衝撃:林家ぺー師匠ではなく(それはお誕生日)……森銑三先生に教えていただいたわけではなく、大成駒自身が思い起こせよ…と伝えてくださったことに違いなかった。
壇ノ浦の合戦があったのが、元暦二年三月二十四日…
(西暦でいえば1185年:近年、旧暦を新暦に変換して実際は…云々と解釈して別の暦日で記念日とする方がいらっしゃるが、月の暦において何月、ということはとても重要で…たとえば雛の日といえば三月三日に決まってるし、討入りは極月十四日でなくてはならぬので、逆からの翻訳で正しいというのは実は正しくないのだと感じます。
であるから、毎年微妙にズレた旧暦の暦日でアニバーサリーをそこはかとなく愉しむ、ということを実行し、真に季節感が知りたかった場合に、ユリウス暦やらグレゴリオ暦やらに換算して調べ、年どしの天候気象事情を反映させ個人的に想いを馳せればよいのではないかと、常々思っていたのでした)
…なので、三月の潮のよいときに、平家の芝居の話をしたいと思っていた。
旧暦と新暦の季節感がずれつつも微妙にマッチしている年に書きたいと思いつつ、この9年ほど、常に機を逸していたので、卅が微妙に並ぶ、今日この時を逃したら、もう書けないかもしれない、と、昨朝、とある歌舞伎の稿を起こしてみたのであるが……
東日本の震災の前だから、もう10年ほど以前になるだろうか…この時季になると不思議な日本の風物、花見…という行事のスケジューリングに心悩ませていた時のことであるのだが……実をいえば私は、細雪の三女・雪子と同じく、最終的には意に染まないことはできない性分だったので、狭い世間をますます狭くして暮らしてきたのだけれども、アラフィフを過ぎたころ、それでも年賀状のやり取りだけは続けてきて、何かというと声をかけてくれた(けれどもこちらから沙汰することは皆無であった自分の薄情さ加減を今となっては赤面するしかないのだけれども)高校時代からの友人Nさんが提唱する、三十年ぶりの再会を促す、上野の花見に誘われた。
それがきっかけとなって、震災の翌年はお休みとなったのだが、初手は三人だった年に一度の同窓会ともいえる美術鑑賞プラス花見の宴は、回を重ねるごとに1970年代末に女子高生だった漫画研究会の同級生メンバーが何人かずつ増えてゆき、皆がお互いの存在を確認することにより、自分自身が生きてこの世にあることを実感する、そしてまた、今は失われてしまったが、かつて存在したものが確かに存在していたのだと確信するあかし、安堵の機会となっていた。
しかしその花見も、4回を数えたのが、彼女と桜を観た最後になってしまった。
乃木坂の新美術館(何の展覧会だったか、もう失念してしまった)から、青山墓地へ桜狩した年だった。
畏れ多くて参ずることもなかった河村家の墓前へ差し掛かって、ここは大成駒のお墓よ、と耳打ちすると、カメラを常備している彼女が、いつの間にか素晴らしく整然として美しい、ひともとの桜を背景にした中村歌右衛門丈の墓影を、後日私に送ってくれたのだった。
その年の暮れに、検査入院をしている、という彼女からのメールが私への最後の便りとなった。
彼女の置き土産の花見の会は毎年続いていて、彼女の眼に映っていたあの時の青山墓地の写真を久しぶりに見たくなって…その写真は歌右衛門丈の追悼本に挟んであるので…それと同時に、本稿に取り上げたかった芝居のエピソードを確認するために、昨晩久しぶりに取り出してみて、大成駒のご命日が平成13年の3月31日だったことを想い出したのだった。
かつて存在した彼女の網膜がとらえた風景写真は、整然としていて端正で、完璧であった大成駒を偲ぶのにこれ以上のものはないように思われた。
空が青くて、桜が満開で、快晴で…文句のつけようのない一葉だった。
ご命日にこの本を手に取ったのが運命であるならば、再拝して読み返すのが勤めというものでありましょう。
…読経ならぬ再読をして、20年前に読んだ時とは違う印象がこの胸に宿った。
六世中村歌右衛門丈は、古典の本行を、とにかくとにかく、大切にして精進して勤めてほしい、と継ぐ者たちに訴えていたのだった。
伝統をほぼ完璧に完成させていた大先輩たちの作品を、新世代のものがいきなり、ご見物衆の気に入るように演じることなどできない。
生まれた時から何十年も丹精してきた仕手が、ようやっと描き演じだせる世界を、二十数年しか生きていない者に同じようにできるわけがない。
新しく継いだものが先輩たちと同じようにできるには、先輩たちが費やしたのと同じ時間と努力、労力が要る。
そして主役の意志と肉体だけでなく、舞台の世界全体を構築する脇役、衣装・結髪、小道具・大道具、音曲、照明、裏方諸々……etc.
江戸…いえ、物語の構築という点でいえば日本に文化が発祥したその時からの人智の積み重ねが、当初は中国文化をまねて更に自国のものとしてくふうし、平安、鎌倉、室町各時代の美意識を加味・踏襲し、集大成されて花開いたのが江戸時代。それから明治、大正、昭和と、鍛錬・丹精され、くふうされ続けてきたのが、歌舞伎です。
もとい、歌舞伎だけでなく、平成の世に伝わる日本文化なのです。
大成駒のその願いが叶ってほしい、あの時代、わたくしたちを魅了した舞台世界が、またいつの日か目前に展開してほしい…けれども、現在の日本国の経済観念からの発想しかない短絡的・短期間換算での文化測定・価値観の側面から慮るに、どうなることでしょうか……
歌舞伎界に例えず、わかりやすいように、落語のことについて申しましょうか。
いま、昭和に大成された古典落語を若い人たちが口演するのは、かわいそうだなと思う。
第一、日常に話している言葉が、もう昭和のころのそれと違うのだ。
語彙ばかりではない。イントネーション、言い回し、時代の雰囲気。日本語に対する感性。言葉に宿る魂。コトダマ自体がすでに20世紀のそれではない。
それを、かつての美意識、審美眼、判断基準にかけること自体が、酷、こちらの見当違い、狭量というものなのだ、と感じるようになってきた。いや、そう思わないと寛容できずにストレスが溜まって、娯楽と思えなくなってきた。
昭和の50年代後半、60年に入った頃だったでしょうか…映画・テレビドラマの時代劇に出てくる役者が、なんとなく、昭和のころよくあった特別番組・新春スターかくし芸大会、のために扮装している感じがして、私は新作の映像作品である時代劇に対する興味を失った。
時代の趨勢として、俳優の日常に、着物での生活がない、素養としての日本舞踊が失われた、ということがあったのだろう、とってつけたような仕草、所作・振る舞いは、いかに俳優たちが器用に演じても、不自然な作り物であるという、圧倒的な違和感を与えてしまうものだ。
十六年は一昔…それが二巡り、三囲ぐらいいたしますと、万事心得ていた裏方さんも代替わりしていって、教育係がいない現場というものは、いまや、知恵とくふう・美意識と価値観が集積された時代劇ではなく、フタッフ自身が未知なる世界である過去の時代に取材したSFになっているのである。
初めて寄席の空気に触れてしばらく入れ込むという状況にある受け手は、何年かごとに入れ替わるであろうし、そういった意味で客の感性も変わっていくから、寄席を構成しているすべての事柄…世界がすでに違うのだ。
新しい感性で、新しい若いお客さんにウケる、ということが今の伝統芸能界では使命のようになっているけれども、初めて伝統芸能に触れる方々は、自分の中にその芸能に関する他の演者の記憶がない。
つまり比較する対象、比べてみてどう、という判断基準を持たないから、彼らに支持されるに及び、人気者の仕手が裏付け・根拠のない自信を手にしてしまい、努力して鍛錬する…というあらゆる技術系のスペック涵養に不可欠な要素をないがしろにしてしまう結果となる。
(それは、半年ぶりにふらっと寄席に立ち寄り、こんな下手な:上っ面、口跡は整っているのに笑いどころで全然笑えない、面白さのかけらもない壺算、聞いたことがない…!しかも真打なのに…!!と、怒りまくった自分自身へ、かつまた昨夏、母を連れてふらっと入った新宿の老舗寄席で重鎮の落語家に、九月に目黒のサンマ聴かされた…ぁぁもう腹立たしい、そんな当たり前の噺を聞くために寄席まで来たわけじゃない…!!と怒り狂った自分自身への窘めの記述になるのかもしれないのだけれども)
志ん朝師匠のカッコよかったことと言ったら…!!(愛宕山の爽快感ときたら譬えようもなく、私は大好きだったのですが)もう早世した生き方自体が、噺家として完璧です。
リアルタイムで私は談志の追っかけをしていたが(もちろん定席の普通の寄席にも通っていて、お気に入りは先代小南師匠でしたが)、私の中の落語世界が喪失した21世紀以降に、主に繰り返し聞いていた落語のCDは、三世金馬と志ん朝であった。
年に二回ほど1か月弱の期間を持って興行される、人形浄瑠璃文楽の鑑賞教室@東京三宅坂国立劇場公演。
数年前まで欠かさず伺っていたのだけれども、観劇の前に、あらすじと人間関係のレクチャーが1時間ほど行われる。
この時点で、もはや、ムリ、な感じになっていないかなぁ、気の毒に…と学校単位で鑑賞教室に参加する若人たちの興味の行く先を案じていた。
日常、テレビをつけたら時代劇をやっている、昭和の子供たちには義経やら弁慶やら、富士山の麓の巻狩り、仇討がどうしたこうした、細かいことは分からなくとも、大筋が血肉として集積された下地があるから、前置きはいらないのだ。
翻ってワンピースやナルトを読んだことがない昭和の子供たちには、同じ漫画といえどもちんぷんかんぷんで、観たくないなぁ…と思っちゃうのと同じことである。
世間を知らぬ若者は、自分が初めて接する偉大なる文化の、その時点で完璧で手の届かないものを応援するのに気がひける。
だから自分たちのヒーローが欲しい。
いま寄席に行って、自分の記憶の中の昭和の名人たちの高座以上の噺を、現代の古典落語に求めるのは無理というものなのだ。
日常に、あの時代の空気、言葉遣いがあってこその、その下地があってこその鍛錬で、あの落語世界が創れるのである。
それはないものねだりであって、レストア版古典を無理に演じてもらうよりも…話し手自身が自分の言葉でもって語り構築した新作に…換骨奪胎・パロディ化した元ネタが共通認識として分かっているので尚更、カタストロフィーやらエクスタシーを感じるのは当然のことなのであった。
それと同時に、やはりもう30年以前のことになるが、とあるホール落語会で新作落語を聴いた時のこと。
その噺の筋・展開の面白さに心を奪われた私は気がつかなかったのだが、一緒にいた友人が、
「こんなガサツな落語、聞いたことがない」
と、言ったのである。
洋楽理論に則った現代邦楽はきちんと演奏できるのに、古典作品をやると形無し…という演奏をよく耳にするのだが、楽譜が基準でそれを見て弾ける程度でよしとする理解力では、本人たちは気がつかないのかもしれないが、厚みを持つ古典作品は弾ききれないのである。
新作落語はまず、アイデア勝負なので、その時の友人の、昭和の洗練された古典落語を聞いていた耳には荒く映ったのであろう。
古典は、現代に残っているということ自体が既に錬成されているわけで、そこそこの技術しかない仕手であってもそれなりに、ある程度鑑賞に堪えるようなつくりになっている、有難い作品なのである。
それは作品自体の魅力なのであって、古典を面白く聞かせられないのは、錬成しきれていない落語家の怠慢なのである。
このところの落語ブームとか言われている現象で、持ち上げられている本人が気づいていないのが一番困ったもので、うっかり入ってしまった寄席で、鼻持ちならない、ガサツで聞くに堪えない古典落語を、本人の勢いだけで、力業のごとく聞かされる目には遇いたくないものである。
そしてまた、雰囲気だけの、ルーティンワークのような上っ面だけの噺を聴くのもつらい。
熱量換算で、おあしに足る、いやそれ以上にスゴイ!と感じることのできる落語が、古典と新作の別なく、私は好きなんである。










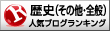


















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます