(スタッフの起承転結その4のつづき)
けれど、作ってる時はそうは思っていなかった。自分の手によって、少女漫画を「アニメーション映画」に育ててやろうと思っていた。
たとえば、主人公のハルは長身に見えるけれど、内股で肩をすぼめているポーズが印象的だったので、「無意識に自分を小さく見せようとしてしまう子」「背は高いけど腰は低い」という設定にして、落ち着きのないちょこまかした動きを肉付けした。ただし、これは柊さんのラフ画をもとにしているので、完成された少女漫画では、少しニュアンスが変わったように思える。完成した漫画では、もう少しハルが自信に満ちているように見える点が興味深い。キャラクターデザインの森川聡子さんの描いたアニメーションのハルは、柊さんの下描きの絵にすごく忠実である点は強調しておきたい。
一方のバロンは、優しい笑顔のキャラクターだったけれど、猫のくせにいつも蝶ネクタイをビシッと締めている様子から逆算して、堅すぎるんじゃないかというぐらいストイックな性格に変えた。リアルな絵が得意な森川さんのバロンは首が太いので、ネクタイで首周りが締まる印象になるから、いつも背筋を伸ばして、決してキョロキョロしない。いつもまっすぐ前を見ているその顔からは表情を消した。仮面ライダーやウルトラマンなど、仮面ヒーローものの無表情の魅力をヒントにして肉付けした。
トトやムタ、猫王は原作とさほど変わらない。けれど、猫王の家臣のナトルやナトリ、SP猫には、シナリオ構成上必要な役割から逆算して新たな性格を与えた。このあたりのアイディア出しは楽しく、ナトルが濱田マリさんの声で人気者になったり、SP猫の受けがよかったのは仕事としてとてもおいしかった。
これらのキャラクターが活躍する舞台構成もアニメーション化に向けて工夫した。もっとも苦労したのは、現実世界から猫の事務所へ行き、そこからさらに猫の国へ行くという、二重ファンタジー構造をどう処理するか。ファンタジーの扉が二回開き、現実離れが過ぎるのを心配した。そこで、猫の事務所をできるだけ、現時世界と地続きに感じられるように演出した。原作のショウウインドウの煌めきをくぐるという幻想的なアイディアは消した。
私は柊さんの、こうしたファンタジックな表現に、映画に通用する「深み」を感じなかったのである。他にも動く迷路をくぐり抜けると、また王様の宮殿に戻ってしまうという、まるで不思議の国のアリスの現代版のようなアイディアも、「ゲーム感覚」のように思えてしまったので、猫王の手による「塔の爆破」という、スペクタクルに変えた。
このような私のアプローチが、ある程度スタッフにも評判がよかったのは、その場の思いつきで猫の国へ旅立つハルのキャラクター性の中に、「刹那的な生き方の肯定」という確固としたテーマを見つけ出せていたからだという自負が私にはあった。前回書いたように、もともと柊さんの原作に活劇的な要素が含まれていたとは言え、「承」だけでなく「転」の半分ぐらいは担わせてもらっているような気持ちはあったのである。しかし、こうした私の「図に乗った気分」を打ち砕いたのが、鈴木敏夫プロデューサーだった。
これは暴露話でもなんでもない。映画公開時のキャンペーンで札幌を訪れた時。いくつかの雑誌の合同取材の場で、私は鈴木さんと肩を並べて気持ちよく自分の演出意図について話していた。少女漫画のテイストには忠実だったと、私がこのキャンペーンで何度も話している内容にさしかかった時、鈴木さんが腹を立てて反論を始めたのである。記者さんの前で語られたこの時の鈴木さんの言葉は、批判されたというショックを通り越して、感銘を覚えた。こうした教えは私にとって宝である。
「でも、少女漫画だとしたら恋愛でしょう? それにしてはバロンの描き方がおざなりだよね。ムタの面白さに比べたらさあ。全然かっこよくないもん」
「あと原作で猫の国は死の国っていう設定でしょう? 人間が死を意識するのは年をとってからではなくて思春期なんだよね。ハルはそこを通過して大人になる、それをバロンが手助けするっていう、原作はそういう話じゃない?」
「いや、森田君はすごく現実的にしたんだよね。少女漫画だったら、もっと幻想だもの。猫の国なんかさあ、原作だともっと、ばーっとすごいもん」
「いや、オレはどっちがいいとか言ってないよ。ただ、森田君はそういう風にしたんだよね」
最後のところ、気を遣ってくれているのは、鈴木さんが私の演出意図をちゃんと理解した上での換言だからだ。それが証拠に鈴木さんは、私が原作の中から自分なりに発見した、「刹那的な生き方の肯定」というテーマの気分をすくい上げて、「猫になってもいんじゃない?!」というコピーを宣伝ポスターに採用してくれている。
けれど、私が原作の奥に隠されていた深みのあるテーマを読み落としたことは、もはや取り返しがつかない。私は原作の「猫の国で、ハルが死に別れた飼い猫と再会する」という話を「ペットロスト症候群を慰める話」としか解釈しなかったのだ。私はこうした感傷的な話が好きじゃなく、映画を底支えするテーマとして弱いと考えたのだ。けれど、これが鈴木さんの言う解釈だと話が違ってくる。「死を意識した時少女は大人になる」というテーマなら、映画のテーマとして充分な力があるからだ。
それに気づかずに、私が映画に与えたテーマは、所詮映画を成立させる手管(テクニック)の延長にあるに過ぎず、企画のスケールを縮めてしまっている以上、私の仕事は「転」には足りず「承」である。そして何より、そうした企画の枠組みに関わるような問題に無自覚に図に乗った監督の態度というものを許せないのが、いわゆるプロデューサーという人種なのだなということを、私はこの時学んだ。(つづく)
けれど、作ってる時はそうは思っていなかった。自分の手によって、少女漫画を「アニメーション映画」に育ててやろうと思っていた。
たとえば、主人公のハルは長身に見えるけれど、内股で肩をすぼめているポーズが印象的だったので、「無意識に自分を小さく見せようとしてしまう子」「背は高いけど腰は低い」という設定にして、落ち着きのないちょこまかした動きを肉付けした。ただし、これは柊さんのラフ画をもとにしているので、完成された少女漫画では、少しニュアンスが変わったように思える。完成した漫画では、もう少しハルが自信に満ちているように見える点が興味深い。キャラクターデザインの森川聡子さんの描いたアニメーションのハルは、柊さんの下描きの絵にすごく忠実である点は強調しておきたい。
一方のバロンは、優しい笑顔のキャラクターだったけれど、猫のくせにいつも蝶ネクタイをビシッと締めている様子から逆算して、堅すぎるんじゃないかというぐらいストイックな性格に変えた。リアルな絵が得意な森川さんのバロンは首が太いので、ネクタイで首周りが締まる印象になるから、いつも背筋を伸ばして、決してキョロキョロしない。いつもまっすぐ前を見ているその顔からは表情を消した。仮面ライダーやウルトラマンなど、仮面ヒーローものの無表情の魅力をヒントにして肉付けした。
トトやムタ、猫王は原作とさほど変わらない。けれど、猫王の家臣のナトルやナトリ、SP猫には、シナリオ構成上必要な役割から逆算して新たな性格を与えた。このあたりのアイディア出しは楽しく、ナトルが濱田マリさんの声で人気者になったり、SP猫の受けがよかったのは仕事としてとてもおいしかった。
これらのキャラクターが活躍する舞台構成もアニメーション化に向けて工夫した。もっとも苦労したのは、現実世界から猫の事務所へ行き、そこからさらに猫の国へ行くという、二重ファンタジー構造をどう処理するか。ファンタジーの扉が二回開き、現実離れが過ぎるのを心配した。そこで、猫の事務所をできるだけ、現時世界と地続きに感じられるように演出した。原作のショウウインドウの煌めきをくぐるという幻想的なアイディアは消した。
私は柊さんの、こうしたファンタジックな表現に、映画に通用する「深み」を感じなかったのである。他にも動く迷路をくぐり抜けると、また王様の宮殿に戻ってしまうという、まるで不思議の国のアリスの現代版のようなアイディアも、「ゲーム感覚」のように思えてしまったので、猫王の手による「塔の爆破」という、スペクタクルに変えた。
このような私のアプローチが、ある程度スタッフにも評判がよかったのは、その場の思いつきで猫の国へ旅立つハルのキャラクター性の中に、「刹那的な生き方の肯定」という確固としたテーマを見つけ出せていたからだという自負が私にはあった。前回書いたように、もともと柊さんの原作に活劇的な要素が含まれていたとは言え、「承」だけでなく「転」の半分ぐらいは担わせてもらっているような気持ちはあったのである。しかし、こうした私の「図に乗った気分」を打ち砕いたのが、鈴木敏夫プロデューサーだった。
これは暴露話でもなんでもない。映画公開時のキャンペーンで札幌を訪れた時。いくつかの雑誌の合同取材の場で、私は鈴木さんと肩を並べて気持ちよく自分の演出意図について話していた。少女漫画のテイストには忠実だったと、私がこのキャンペーンで何度も話している内容にさしかかった時、鈴木さんが腹を立てて反論を始めたのである。記者さんの前で語られたこの時の鈴木さんの言葉は、批判されたというショックを通り越して、感銘を覚えた。こうした教えは私にとって宝である。
「でも、少女漫画だとしたら恋愛でしょう? それにしてはバロンの描き方がおざなりだよね。ムタの面白さに比べたらさあ。全然かっこよくないもん」
「あと原作で猫の国は死の国っていう設定でしょう? 人間が死を意識するのは年をとってからではなくて思春期なんだよね。ハルはそこを通過して大人になる、それをバロンが手助けするっていう、原作はそういう話じゃない?」
「いや、森田君はすごく現実的にしたんだよね。少女漫画だったら、もっと幻想だもの。猫の国なんかさあ、原作だともっと、ばーっとすごいもん」
「いや、オレはどっちがいいとか言ってないよ。ただ、森田君はそういう風にしたんだよね」
最後のところ、気を遣ってくれているのは、鈴木さんが私の演出意図をちゃんと理解した上での換言だからだ。それが証拠に鈴木さんは、私が原作の中から自分なりに発見した、「刹那的な生き方の肯定」というテーマの気分をすくい上げて、「猫になってもいんじゃない?!」というコピーを宣伝ポスターに採用してくれている。
けれど、私が原作の奥に隠されていた深みのあるテーマを読み落としたことは、もはや取り返しがつかない。私は原作の「猫の国で、ハルが死に別れた飼い猫と再会する」という話を「ペットロスト症候群を慰める話」としか解釈しなかったのだ。私はこうした感傷的な話が好きじゃなく、映画を底支えするテーマとして弱いと考えたのだ。けれど、これが鈴木さんの言う解釈だと話が違ってくる。「死を意識した時少女は大人になる」というテーマなら、映画のテーマとして充分な力があるからだ。
それに気づかずに、私が映画に与えたテーマは、所詮映画を成立させる手管(テクニック)の延長にあるに過ぎず、企画のスケールを縮めてしまっている以上、私の仕事は「転」には足りず「承」である。そして何より、そうした企画の枠組みに関わるような問題に無自覚に図に乗った監督の態度というものを許せないのが、いわゆるプロデューサーという人種なのだなということを、私はこの時学んだ。(つづく)











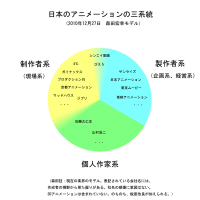















私は、どちらかというと映画派です。
実は死の国だったというのはどうも話が重い気がしまして・・・
「猫の恩返し」大好きです。
これからも頑張ってください。
こんな経緯でも、試写を見た柊さんが喜んでくれたのには
救われました。