晩秋の日曜日、ミモロは、伏見にある寝具メーカーの「大東寝具工業」のねむりを研究し、よい睡眠をアドバイスするショールーム「ねむりの蔵」で行われる「京ざぶとんワークショップ」に参加しました。


「大東寝具工業」は、大正14年の創業。寝具をはじめ、枕、座布団などを生産、京都の家庭をはじめ、旅館、そして料理屋さん、神社仏閣などで使われています。
ショールームである2階には、快適な眠りをもたらすさまざまな品が揃っています。


ここのスタッフの多くは、睡眠健康指導士の資格を有していて、お客様にアドバイスをしてくれます。
まず、大東社長の会社に関する説明とご挨拶でワークショップが始まりました。

そして今日行うワークショップの説明と「京ざぶとん」に関する歴史的な説明などが、スタッフの柳さんから行われます。

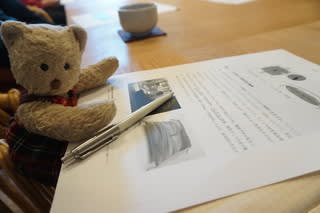
現在の座布団の歴史は、平安時代の寝具「褥(しとね)」から始まったそう。その時代は、枯れ草などで編んだ薄いもの。「昔って、住まいはフローリングで、畳じゃないんだよね。寝るところだけ、畳みたいの敷かれてたんでしょ」とミモロ。
「源氏物語絵巻」などを見ても、座ったり、眠ったりする部分だけ、畳のようなものが敷かれています。
「きっとすごく寒かっただろうね~。それに硬いから眠りにくかったと思うよ~」と、ベッドに寝ているミモロ。
綿花の栽培が普及する江戸時代になって、やっと中綿がはいった布団が、人々の間に登場します。でも一般に座布団が普及するのは、明治時代になってからだそう。
「え?時代劇で長屋に住む人も、座布団してるよ~」とミモロ。
そして座布団が、もっとも普及したのは、昭和です。「サザエさんのお家もちゃぶ台に座布団だよね~」
でも、次第に住まいが西洋化し、茶の間はダイニングルームに代わり、今や和室のない家も増え、座布団の家庭での需要は激減しているそう。
「うちにも座布団ない~」とミモロ。それで今回、座布団づくりのワークショップに参加したのです。
「座布団といっても、京ざぶとんを今回つくります」「え?座布団にも種類があるんだ~」とミモロ。
「京ざぶとん」というのは、座布団の中央部を締める糸が、三方に綴じらるという特徴をもっています。

また、かまぼこ型で、座布団の上下がすぐにわかるそう。
「座布団にも前後と裏表があるんだね~」お客様には、きちんとお出ししたいもの。
ミモロたち参加者は、事前に座布団の皮を選び、また当日、綴じる糸の色を選びました。
 「どれにしようかな~ミモロのは、赤いから、糸も赤にしよう~」
「どれにしようかな~ミモロのは、赤いから、糸も赤にしよう~」さて、いよいよショールームの奥にある工房へ移動します。

まずは、中綿を座布団の皮に入れる作業から…



座布団の幅より、皮よりちょっと小さめに綿をカットし、長方形の綿を、縦、横各2枚、十文字に組み合わせ、正方形に整えます。そして、抑えて空気を抜いて、皮に入れやすいようにします。皮をかぶせて、空いている部分から皮を返しながら綿を入れてゆくのです。
ミモロの前には、すでに三方を縫った座布団の皮と、それに合うように整えられた中綿が置かれています。

それにビニールをかぶせ、皮に入れやすいように、抑えて空気を抜きます。
 「エーイ、ヨイショ」
「エーイ、ヨイショ」
力がないミモロは、全身で中綿を抑えます。
座布団の皮を表に返しながら、空いている部分から中綿を押しこみます。


「う~、なかなか入らない~。ギュ~」
ここが、技術のいるポイント。職人さんたちは、クルンと皮を返すと、中綿もしっかり納まるのですが、ミモロの場合は、ほとんどがはみ出してしまい、後から、押しこむことに・・・。
フワフワの綿を抑えながら、座布団に皮にいれる作業は、なかなか難しく、四隅まで綿がなかなか届きません。
「もう少し~グ~」

「フ~やっと入った~」格闘の末、なんとか中綿を皮に押しこんだミモロです。

「どうですか?できましたか?」とスタッフの方がミモロの作業をチェックしてくれます。
 「う~もう少し、奥に入れてください~」
「う~もう少し、奥に入れてください~」「もっと押しこまなくちゃ~」
 「こんな感じかな?」
「こんな感じかな?」
「はい、いいですね~」最後にビニールを抜いて、この作業は終了です。

「では、次は、空いている部分を縫ってゆく作業です。テーブルの方に移動してください~」
ミモロの京ざぶとんづくりは、まだまだ続きます。
ブログを見たら 金魚をクリックしてね ミモロより
 人気ブログランキング
人気ブログランキングミモロへのお問い合わせ・ご要望は、mimmoro@piano.ocn.ne.jpまで
ミモロの通販ショップ「ミモロショップ」はこちら


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます