またもや前回の投稿からずいぶん時間が経ってしまいましたが、「場所」と「場」をめぐる話題をどのように受けとめてくださったでしょうか。「校舎が人をつくる」。近年では伝統的な校舎を解体して建てかえる計画が持ち上がったときなどに、このことばをよく耳にします。改修・保存を求めるひとたちは、その建築がはぐくんできた学びの伝統と校風を大切にし、それを引き継いできた先輩たちの営みを継承すべきだと主張しますが、たいていの場合、その主張は退けられ、「時代の要請に応える」として、効率的に利用でき、学生のニーズに合った(とされる)新たな建物に建てかえられていきます。校舎だけでなく校地や周囲の環境などをふくむ学校という場所が学生や教師の意識と行動にどのようなインパクトを与え、その人生をどのように左右する契機となってきたか。そんな不確定要素が多くて計量的な分析になじみにくい基準は省みられずに、短期的なスパンで学習活動を活性化し教育効果を高めることが優先されます。これは学校建築にかぎらず最近の教育施策全般にみられる傾向のようです。しかし、学校を単に効率的な人材養成機関ととらえるのではなく、子どもの生涯にわたる学びの基盤を形成する場所だという認識に立てば、長期的な展望をもって学校という場所と子どもの人間的成熟との関わりを考えておくべきなのは当然でしょう。わたしは学校の施設のなかでも、とりわけ学校図書館に注目して「子どもの生涯にわたる学びの基盤を形成するために学校図書館はどんな場所であるべきか」というテーマにとりくんでいます。その一環として今日は「居場所としての学校図書館」について考えることにします。
学校図書館という場所がもつ機能について、最近は「読書センター」「学習情報センター」に「心の居場所」を加えて三つの側面から語られることが多い。学校図書館というひとつの場所が利用者との関わり方によってさまざまな様相を示すというのは、その通りだと思う。だとすれば、三つの機能の相互の関係を明らかにする必要があるだろう。子どものなかで読書と学習はどのようにつながっていて、それらの活動に場所はどのように関わるのか。「居場所としての図書館」とは、単に「落ち着いて読書や学習ができる場所」「読書をとおして自分を取り戻す場所」といった意味でとらえるだけでいいのだろうか・・・。でも、どうして「心の居場所」なのか。居場所を語るときに、あえて身体的な関わりを捨象して心的過程に特定あるいは限定する必要があるのだろうか。「心のオアシス」といった表現も含めて、ポエムに入り込んでしまっては議論を深められないのではないか。
他方で、学校図書館が居場所としての機能を果たすことが期待されている背景のひとつに、何らかの理由で学校生活にストレスを感じて、馴染めないでいる子どもたちをケアする受け皿が必要だという事情がある。だとすれば、肝心なのは、そういった子どもたちを担いきれない学校の教育システムそのものを問い直し、改善していくことであって、その過程で学校図書館が受け皿となることは、あくまでも緊急避難的なものと考えるべきだろう。
では、学校図書館本来のあり方としての居場所は、どのようにとらえるべきか。
「居場所」とは、文字どおり「(自分が)存在する(ことを実感できる)場所」「身のおきどころ」である。その場所にいることでホッとしたり、生きた心地がしたり、自分の力を存分に発揮できると感じるとき、わたしたちは、こころとからだが統合された全体として場所につつまれている。場所には自然があり、事物(artifact)があり、人(他者と自分)がいる。居場所は、それらすべてが自分のありのままを受け入れてくれる場所であり、そこを起点として社会的・創造的な活動が営まれる場所でもある。そうした場所で営まれる活動をとおして、わたしたちは自らのアイデンティティを摸索し、コミュニティへの帰属意識を高め、自らの存在を確認できるのである。つまり、居場所は自分を知る場所でもある。
学校図書館が、そのような居場所として十全に機能するには、どのような条件が必要だろうか。その手がかりは、当然のことながら、図書館で積み重ねられてきた活動の中にある。たとえば、かつて図書館のビジネス支援に関して「人生を応援する施設」(『図書館雑誌』2006.3)という短い文章に記された豊田恭子さんのことばが、いまも記憶に残っている。
書棚の間を徘徊しながら、図書館員と会話を交わしながら、人は自分だけの「解」探しをす る。孤独なはずの作業が、図書館という空気に包まれることで、悲壮感から免れる。
図書館によるビジネス支援の第一の意味は、誰かに教えてもらえるような「解」のない問題を抱えて、ひとり悩み、苦しみぬいて結論を出さなければならない孤独な戦いを強いられている世の仕事人たちに、貴方たちは一人じゃない、というメッセージを送ることにある。
ここから読み取れるのは、場所と利用者と図書館員との有機的なかかわり(相互作用)から生みだされる図書館の「空気」である。その空気を肌で感じた利用者はきっと、自分の存在を実感できるかけがえのない場所として「ここが自分の居場所だ」と感じるにちがいない。もちろん、学校図書館にも同じような活動の蓄積があり、経験から得られた叡智がある。
学校図書館の目的(それは、もちろん学校教育の目的でもある)は、子どもたちが責任ある市民社会の担い手として成熟するプロセスに寄り添い、これからの人生で遭遇するであろう、さまざまな正解のない課題に立ち向かって生き抜く力を高めることにある。そのためには、何よりも子どもたちが安心して自分を開き、勇気をもって自らの疑問や違和感にチャレンジし、もてる力を存分に発揮して探究に打ち込むことができる場所が必要である。だからこそ、学校図書館における場所と利用者と図書館員との相互作用による居場所づくりの経験が、もっと語られ、共有されるべきである。
だが、一般的に大人が何らかの教育的意図をもって関わってくる場所は、子どもの居場所感覚を失わせることが多い。その一方で、子どもたちが大人の干渉を避けて自発的につくった居場所は、同質性の高い「たまり場」になりやすい。それも居場所の一つにはちがいないが、異質な存在が排除されることによって創造的な活動の源泉にはなりにくいということもある。このジレンマをどう克服するか。子どもと大人が同じ場所を共有しながら、それぞれの意図をもって自分を生きるなかで、試行錯誤を重ねて社会や世界へと広がる新たな関係性を築いていく。その営みをとおして、それぞれの居場所感が醸成されるのを待つほかないだろう。
そんな居場所としての学校図書館でおこなわれる活動は、苦手を克服するとか、自分にないものや不足しているものを自分のものにするといった「訓練」にはなじまない。いま、ここに存在しない自分になることに意識を集中することによって居場所感が失われる可能性が高いからだ。場所に触れ、場所を感じ、場所と関わることによってもたらされるのは「気づき」(awareness)である。子どもたちは成長の過程で生きていくために必要なさまざまな知識や能力を身につけているにもかかわらず、そのことに気づいていなかったり、過小評価していたりすることが多い。それには、現在の学校の価値観や成績評価のあり方が、不足していたり、欠落していたり、他者より劣っていたりする、特定の知識や技能、資質などに子どもの意識を向けていることが大きく影響しているのだろう。
気づきが子どもの学びにもたらすものは大きい。たとえば、いま自分が利用できる多様な資源(知識や技能、直接・間接の人のつながり、身近な情報源を利用する能力など)に気づいて、それを創造や課題解決のために活用すること(いざというときに、あらゆる手立てをつくして手もちの資源を使いこなすこと)。自分の思考や行動を限定してきた無意識の前提や価値観に気づいて視野を広げ、さまざまな事象に対して相対的な見方ができるようになること。人々の多様さやユニークさに気づいて、同調圧力に流されないで他者や自分のありのままを受けいれられるようになること。ことばにならない自分の内的欲求や直感に気づいて、それを新たな発想や探究につなげること・・・
場所を構成する自然や事物や人に触れて、さまざまなことに気づき、発見することから、受容と変容という学びのプロセスがはじまる。そのような居場所としての学校図書館を実現するには、自らも探究者であり、豊かな感性をもつ大人の存在が不可欠である。子どもと共に歩み、同じ月を見ることで「貴方は一人じゃない」という無言のメッセージを送る。そんな学校図書館における教師や学校司書の営みが居場所づくりの一つのモデルとなって学校全体に、そして地域社会にも広がっていけばいいのだが。
参考文献
田中治彦・萩原建次郎編著『若者の居場所と参加:ユースワークが築く新たな社会』(東洋館出版社、2012)
 |
若者の居場所と参加 |
| 東洋館出版社、2012 | |
| 東洋館出版社 |










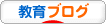


















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます